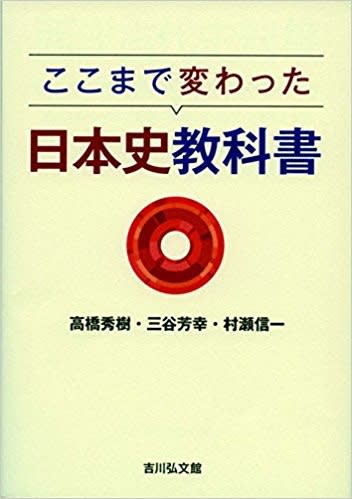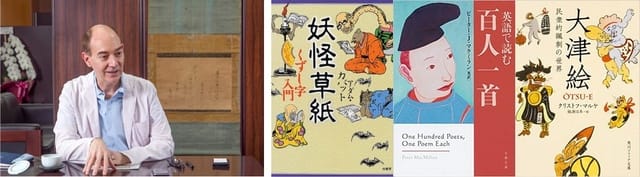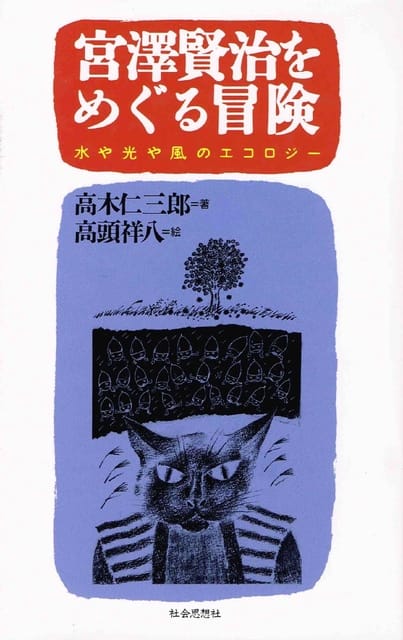テレビが白黒だった一時期,時間つぶしにこのビデオ (当時は映画だったかも) がしょっちゅう放映されていたように記憶している.
むかしラジオで誰かが「彼はジャズ・プレイヤーだったが,病気で余命いくばくもないと知って,家族のためにポピュラーシンガーに転向した」と言っていたが,嘘だろう.モナ・リザのヒットが 1950,肺がんで亡くなったのは1965 年,45 歳だった.
かってはジャズとポピュラーの垣根は低かった.
1955 年のレスター・ヤング,バディ・リッチのトリオにピアニストとして参加したときの録音がいくつか Youtube にアップされていた.例えば https://www.youtube.com/watch?v=dxZ3r1LGA4Q
オスカー・ピーターソンは彼をアイドルとしていのだそうで,"With Respect to Nat" https://youtu.be/r6vDPo0wixsというアルバムがある. 2曲目の Paper Moon はレイ・ブラウン,ハーブ・エリスとのトリオ.