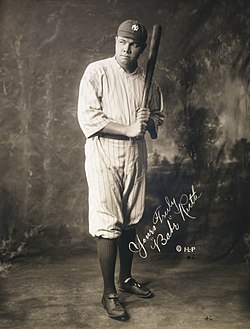【HUNTER】:入管法改正案の危うさ
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【HUNTER】:入管法改正案の危うさ
回数制限なしの難民申請による送還停止を2回までに制限し、拒否した場合は罰則を科すなどの内容を盛り込んだ「出入国管理及び難民認定法」(入管法)改正案の審議が今月、国会で始まった。難民排除と人権侵害につながる法改正だとして反対の声も上がっているが、新型コロナウイルスの感染拡大に揺れる中、この問題に対する国民の関心は薄れがちだ。改めて、難民問題について考えた。
■簡単にできる「帰化」
国会議員の事務所には、外国人による日本への滞在申請に関する陳情がたくさん舞い込んでくる。中には難民申請など難しい案件を持ち込んでくる人もいる。
政治家に相談に来るケースは大部分が難しい案件で、そもそも、普通の申請でスムーズに通るようであるなら、わざわざ相談に来るはずがない。つまり「筋の悪い案件」が集中するわけで、多くは不法滞在者の滞在延長や再入国の相談。ほとんど許可されることはない。一方で、安易に許可されているのが帰化申請である。
法務省のが公表している「帰化許可申請者数等の推移」の国籍別帰化許可者数によると、2019年に日本国籍を取った人8,453人のうち、韓国・朝鮮が4,360人 中国が2,374人などと、中国・韓国・北朝鮮に集中していることが分かる。
20歳以上で、日本に5年以上継続して居住し、素行が善良であり、自ら生計を営むことができる人間は、大部分が帰化できる。つまり、5年間だけ日本で問題を起こさなければ日本人になれることになる。
「日本を愛して、日本が好きになり、だから日本に帰化した」という点が要求されるわけではないので、ひどい場合は「日本は大嫌いだが、帰化した方が便利だから帰化してやる」という外国人もいる。
試しに検索エンジンで調べてみると、「永住申請報酬4万円 不許可0件! 相談件数年1000件超」、「当事務所では、帰化申請許可率99.9%の帰化専門の行政書士が事前にお客様の状況をヒアリングをして、帰化可能か診断いたします」、「 一流の行政書士による最高品質のサービスをどこよりも安い費用で在日韓国人の方々に対してご提供致します。【会社員の方:100,000円 自営業の方:150,000円】」などという広告が大量に出てくる。
行政書士に10万円程度で帰化申請を代行してもらえるほど、日本の帰化制度は緩い制度なのだ。そこに問題はないのか?
立憲民主党所属の蓮舫氏(日本名・齋藤蓮舫、中華民国名・謝蓮舫)は1995年、雑誌『ジョイフル』第22巻第8号で下記のように語っている。
《今、日本人でいるのは、それが都合がいいからです。日本のパスポートは、あくまでも外国に行きやすいからというだけのもの。私には、それ以上の意味がありません。いずれ台湾籍に戻そうと思っています。》
この方が日本の国会議員だというのも驚きだが、支持する有権者が多いことも確か。多くの人は国籍に関心がないのだろう。
■稚拙な難民政策
かたや、人道的な問題を抱えながら解決されないのが難民問題だ。出入国在留管理庁の資料によると、「難民認定申請を行った外国人(以下「申請者」という。)は10,375人。難民認定手続の結果,我が国での在留を認めた者は81人。そのうち,難民と認定した者は44人(一次審査での認定者43人と不服申立てで「理由あり」とされた者(認定者)1人の合計)であり,難民とは認定しなかったものの人道的な 配慮を理由に在留を認めた者は37人」(令和2年3月27日)となっている。つまり難民と認定されるのは、0.4%ほどという極めて狭き門なのだ。
理由は就労目的での偽装難民が多いことによる。短期滞在は容易な手続きで日本に入国することができるので、在留が有効な期間が終了した後も偽りながら日本に居座り続ける外国人が多い。令和2年7月1日現在における不法残留者数は8万2,616人。観光ビザなどで入国した外国人が就労目的でそのまま日本に滞在し続けるケースが典型例だ。
難民申請をすると、一定期間経過後に「特定活動」の在留資格で、就労が可能になる。難民認定されるまでには1年~2年かかり、難民認定が不許可になると、次に不服申立手続きを取ることが可能となる。この難民認定制度を悪用し、就労目的で難民申請をする偽装難民が急増したため、警察がこのようなコンサルティングを行っていた業者や偽装難民申請をした外国人を逮捕するという事例もでてきた。
そうした中、30代のスリランカ人女性が名古屋出入国在留管理局で収容中の3月6日に死亡するという事件が起きた。このスリランカ人女性は不法滞在のため2020年8月に名古屋入管に収容された。今年1月下旬から嘔吐などの症状があり、施設内外で診察を受け「食道炎のような症状」があるとの診断が出ていた。死の3日前に面会した支援者は、生命の危険があるとして即時入院を入管側に申し入れていたが、女性は3月6日午後に居室内で倒れているのが発見され、病院に緊急搬送されたが、死亡が確認された。
収容期間が半年を超える収容者は、20年6月末で527人中232人で4割を超える。3年を超えて収容されている人も47人。長期収容の中で肉体的、精神的な健康問題を抱える人も少なくない。国連人権理事会の恣意的拘禁作業部会は20年秋に、日本の現状は「人権侵害で国際法違反」と指摘している。
その他に「仮放免」としてアパートなどで暮らしている外国人も数多く存在する。仮放免中は仕事に就くことができないために、支援者からの支援だけで生活しなければならず、子供が公立学校に通うことも許可されず、健康保険にも加入できないという過酷な状況がある。
国会審議が始まった入管難民法改正案は、不法滞在対策のためという大義名分はあるものの、助けるべき人々を追い詰める法案と言えるだろう。これまで難民申請中の人は強制送還が保留されていたが、政府が2月19日に国会提出した入管法の改正案では、難民申請が3回以上の人は送還が可能となる。
2019年に日本が難民と認定した人は世界的にみても極端に少ない。日本の認定率が0.4%であるのに対し、ドイツは25.9%、フランスは18.5%である。この状態で強制送還を認めると、迫害を受ける人々の生命を日本政府が積極的に奪うことに加担しかねない状況となる。
現在多くの相談が寄せられているのはクルド人だ。シリア内戦やクルド人難民というと遠い世界の出来事のようだが、日本にも中東から難民が逃げてきており、その多くが埼玉県の川口市や蕨市に住んでいる。クルド人への迫害が激しいトルコ出身の難民申請者を日本では認めていないが、同国出身のクルド人は、米国やカナダでは8割以上が難民認定されている。それだけ緊迫した状況があるのだ。
強制退去命令を受けても様々な事情から帰国できない外国人に対して刑事罰を課すこともできるようにする改正案。これが現実になれば、難民は犯罪者として扱われ、強制送還されることになってしまう。支援団体からは「難民申請者を迫害の危険のある国へ送り返すことになる」と批判が相次いでいる。「先進国」としては、あまりにも稚拙な難民政策ではないだろうか。(国会議員秘書)
元稿:HUNTER 主要ニュース 政治・行政 【政策・国会・「出入国管理及び難民認定法」(入管法)改正案】 2021年04月28日 08:30:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。