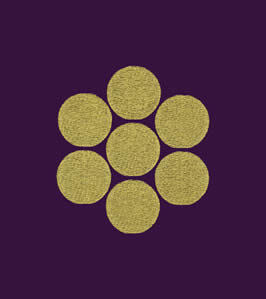△チェルノブイリ・ハート(2003年 アメリカ 61分)
原題 Chernobyl Heart
staff 監督/マリアン・デレオ
編集/ジョン・クストディオ 協力/アディ・ロッシュ
△1986年4月26日、チェルノブイリ原発事故
アカデミー賞の短編ドキュメンタリー部門で受賞したってこともあって、
ともかく、観た。
とてもよくできた映画だった。
けど、なんだか『コーヴ』と同じ匂いを感じた。
チェルノブイリの事故はたしかに大変なものだった。
大変というのは、周囲に対する放射能の影響のことだ。
言葉では言いあらわせないほど悲惨だし、
この映画の描いているとおりの状況ならば、
どれだけ恐ろしい事故が引き起こされたのか、想像を絶するし、
ぼくたちの棲んでいるこの国の将来について非常に懸念されるわけだけれど、
ちょっと、違和感を持ったところがないでもない。
チェルノブイリ・ハートというのは、
チェルノブイリの事故により放射能が漏れ、その放射能による影響で、
生まれついて心臓に重度の疾患をもってしまうことなんだけど、
そうした子どもたち、あるいは放射能障害の人達の実数や正確なデータ、
さらには病院関係者の数値をもってする証言や奇形や疾患の原因などが、
この映画を観ているだけだと、いまひとつ、よく見えてこないってところだ。
制作者側は、なるほど、明確な意思と意義をもって撮影している。
それは、わかる。
ただ、たとえば、この作品に併映されてた『ホワイト・ホース』もそうなんだけど、
チェルノブイリで放射能を浴びてしまったとおもわれる主人公が、
27歳の若さで他界したttことを知らされたとき、
その原因が原発事故による放射能障害であるとは明確に断定されてないんだよね。
こういうふうに映画を完成させてしまうのは、
なんとなく「惜しいな~」とおもっちゃう。
感情に訴えるんじゃなくて、
もっと具体的な分析データみたいなものを、
冷静に提示することが必要なんじゃないのかな~と。
たとえば、チェルノブイリから放出された放射能について、
広島の600倍だとかいうけど、それはどこまで信憑性があるのかとか、
被災者は900万人で、移住を余儀なくされた人は40万人で、
隣国ベラルーシの方が放射能の被害は大きく、
そこで生まれてくる子どもの小児甲状腺ガンの発生率は、
0.9%だったのが26%に跳ね上がったとかいうのは、
たしかに数値ではあるんだけど、
どこで誰がどのようにして調べて、どれだけ確実性のあるものなのかということを、
いったいどれくらい検証されたかが、語られていない。
だから、惜しいな~とおもうんだよね。
「汚染地域の新生児の85パーセントがなんらかの障害を持って生まれてくる」
とかいわれると、そりゃあエライことじゃんっておもうし、
チェルノブイリ・ハートの子どもを持った両親とかの証言は、
たしかに身につまされるものはあるんだろうけど、
病院に収容されてる新生児や幼児たちの全員が、
放射能障害による患者なのかどうかも明確にされてないんだよね。
ドキュメンタリは、膨大な量のフィルムを回した上で、
撮影されたものに従って脚本を書き、編集していくものだ。
当然、そこには制作者の主観は入れられるし、
ほんのちょっとした編集で、意味合いは大きく変わる。
そうしたことを踏まえた上で、自分なりの鑑賞眼をもって観ないといけない。
だから、
この作品は人道的な怒りをもった良心的な人達によって撮られたんだろうけど、
そうであれば、なおさら、観客がぐうの音も出ないような数値が必要になる。
そんなふうにおもってしまう僕は、
ほんと、物事を斜めに見ちゃう性質なんだろか…。