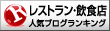(月のピラミッド)
テオティワカンとは「神々の都」という意味なのだそうです。
ここには「太陽のピラミッド」と「月のピラミッド」があります。
紀元一世紀頃造られた太陽のピラミッド、高さは65m、基底は224m。
エジプトのクフ王・カフラー王のピラミッドにつぐ世界3位の大きさということですが
去年行ったばかりのクフ王のピラミッドの半分位の高さなので
正直、そんなにたいしたことないじゃんと思っていたのです。

ところがこちらは、その周りが凄かった。
上の写真は月のピラミッドの上から見た死者の大通りと、その途中にある「太陽のピラミッド」。
「死者の大通り」はここから3キロ先のケツァルコアトルの神殿まで一直線に伸び、
その途中に無数の基壇・神殿が並んでいます。
しかもこれらの建物の配置は、実に緻密に計画的に行われているというのです。
「太陽のピラミッド」は夏至の日に太陽が正面に沈むことで有名ですが、
そのために「死者の大通り」は真北から東に15度25分ずらして造られている。
また、ここでは83㎝を一単位としていて、建物の大きさや建物間の距離を
83㎝で割ると、すべてメソアメリカの暦に関連する数字になるのだそうです。

(太陽のピラミッド)
アステカ文明侮れない!
ところが、それについての本を読み齧ると、残酷な事実が次々に。
ピラミッドの四隅には子供たちの生贄が埋められ、
このピラミッドのための生贄の遺骸が、神殿内外から150体以上見つかっているというのです。
生贄は、ピラミッドの上で4人の神官に手足を押さえられ、生きながら心臓を取り出されたのですって。
子どもの頃、少年漫画で恐る恐る見た生贄の儀式、本当にあったのね。
生贄については、マヤ・アステカ文明には切っても切れないものらしく、
その後行った博物館や他の遺跡でも必ず出て来たので、後にまた書きます。

エジプトのピラミッドは登ることができませんでしたが、こちらは大丈夫。
石の階段はかなりの急勾配、高さもまちまちでかなり登りにくいのですが
これくらいへっちゃら!と元気に登って行ったら、一瞬、目の周りが真っ白になりました。
慌てて休んだものの、心臓はバクバク、気分悪く脂汗がタラタラ。
軽い貧血を起こしたようでした。
そういえばここは標高2300mだった…前日ろくに寝てなかったし。
メキシコのピラミッド、やはり侮れません。
参考文献 「古代マヤ・アステカ不可思議大全」 芝崎みゆき
「アステカ文明の謎」 高山智博