車海老 紹興酒に 跳ね踊り 喉越し通る バブルの一夜
■
【緑茶が世界を救う?】 辻村みちよ
「翠翔」のカウンターでベゴニアは廻りの喧噪を
楽しむかのように、アルティメディアと話してい
る(『柳葉魚とソフト知財の育成』のつづき)。
「文明と病気は切り離せないけれど、食文化とも
切り離せない。俄然、こここにきて和食が注目さ
れるようになってきたし、ここら辺の情報を整理、
整頓しなきゃね」とグラスに残るビールを飲み干
す。「例えば、お茶文化ね」と空かさずティンカ
ーベルが話しに割り込でくる。「シルクロード周
辺は食道癌が多いしな」とコキノダイモナも参戦。
眼鏡のつるを指で軽くつまむ仕草をしながら「熱
いお茶は粘膜を刺激し、細胞を傷つけやすいかさ
」と突然、スパタロもカウンタに割り込んできた。
それもそのはず、スパタロはコキノダイモナの後
をつけてきたのだ。
「ところで、お茶との付き合い方は?」とベゴニ
アが続けると「20数年前ごろからお茶の産地で胃
がんの死亡率が低いことから研究が始まったが、
熱いお茶でなく温めか冷えたお茶を3~4時間ごと
に呑むのが良い。血中カテキン量は約90分でピー
クに、10~12時間でほぼ消えるからね。日本では
緑茶の成分や機能が古くから研究され、カテキン
が抽出され、1929年に辻村みちよが化学構造を突
き止めた。いまは、抗酸化作用や生活習慣病の予
防効果、抗菌、抗ウィルス作用など世界をリード
する発見に脈々とつながっているんだ」とアルテ
ィメディアつづけた。

「茶カテキンは緑茶を普段飲むように熱湯抽出し
て、水を飛ばしてカフェインなどを取り除いてと
れる。それをポリフェノンといい、カテキンの含
有量によっていろいろなグレードに分け精製した
純粋なものがカテキン類で、メインの物質が4種
類、エピガロカテキンガレート(EGCg)、エピガ
ロカテキン、エピカテキンガレート、エピカテキ
ンだ」と一息つき、眼鏡を外し右手で顔を拭い、
再び眼鏡を掛けた。
※特許:P2001-114687A「抗癌剤」
【課題】
優れた効果を有し、かつ副作用が少ない抗癌剤を
提供すること。
【解決手段】
一般式Iで表わされるカテキン類と一般式IIで表
わされるイソフラボン類を有効成分とする抗癌剤。


「米国では、百兆円にも上るといわれる医療費の
削減のため、副作用の少ない天然物を予防薬に活
用しようと大きな期待されているよ。この中で注
目されているのが、マウスを使った実験でエピガ
ロカテキンガレードをあたえるとマウス胃内での
発ガン物質の変異活性を抑制するという結果が出
ている緑茶カテキン抽出物『ポリフェノンE』(エ
ピガロカテキンガレートを60%、カテキンを90%含
有、カフェインは0.5%程度)というわけだ。日本
語にするとき、エピガロカテキンガラートとか没
食子酸エピガロカテキンとするが、英語風にガレ
ートと書くこともある。Gallic acid (没食子酸)と
は、3,4,5-トリヒドロキシ安息香酸ではあるが」。
「統計的手法だけでの応用展開は中途半端じゃな
いかしら」とティンカーベルが空かさず突っ込ん
でくる。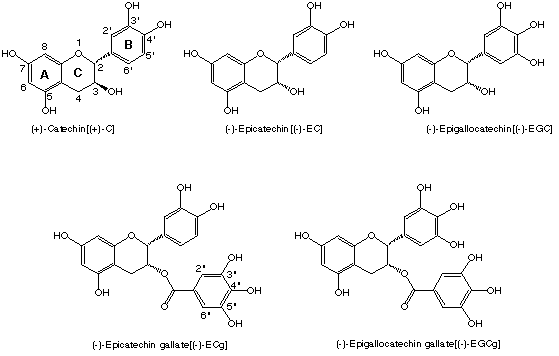
「緑茶から抽出したカテキンのホルムアルデヒド
捕捉能力が非常に高い。ホルムアルデヒドと緑茶
カテキンの求電子置換反応の高い反応性を持つが、
それは、フロログルシノール様の構造持ち、カテ
キンの反応性を分子軌道法で理論的な解析をやっ
ているように、茶カテキンの反応振幅を増大させ
るπ系官能基の働きをさらに解明することや」と
関西弁でコキノダイモナスが難しいことを言うと、
アルティメディアは「なるほど、先を越されまし
たね」と頭を搔くと「こういった知財はいち早く
発信することで、実証期間が短縮できますよね」
とベゴニアが言うと「その肝が美味い」とスパタ
ロは砂肝をパクつきながら叫んだので期せずして
一同が失笑することとなった。
■
【コキノダイモナスのアバター】
■
【車海老と養殖】
「エビでタイを釣る」「クラゲは海老を目とす」
「蝦おどれども川を出ず」「蝦は跳ねても一代、
鰻はのめっても一代」「ハモも一期、海老も一期」
「海老と名の付く家老殿」「海老の鯛まじり」と
海老に纏わる箴言や例えが多い。さて、クルマエ
ビ(車海老、Marsupenaeus japonicus)は、クルマエ
ビ科に分類されるエビの一種。内湾の砂泥底に生
息する大型のエビで、重要な食用種である。かつ
ては多くの近縁種と共に Penaeus 属に分類され、
学名を Penaeus japonicus として記載した文献や図
鑑も多い。研究が進んだ結果クルマエビ科の分類
は細分化され、Penaeus はウシエビ、クマエビな
どに限定された「ウシエビ属」となり、クルマエ
ビの属名には Marsupenaeus が充てられた。
図 漁獲量
図 養殖量
クルマエビの稚エビは海岸のごく浅いところにい
て、夏から秋にかけて潮の引いた干潟などで見る
こともできるが、成長するにつれ深場に移動し冬
眠する。寿命は2~3年とみられる。ほぼ1年を通
して漁獲されるが、特に夏の漁獲が多い。重要な
漁業資源だけに発生の研究も進んでいる。明治38
年に熊本県天草諸島の維和島で、海水池を利用し
た天然稚エビの蓄養が開始され、以来天草地方は
クルマエビ蓄養の本場になった。その後1960年代
初めにエビ類では最も早く養殖技術が確立され、
クルマエビの養殖は全世界に広がった。死ぬと急
速に傷んで臭みも出るが、オガクズの中に詰め、
湿度を保っておくと長時間生かしておけるので、
この状態で出荷・流通が行われる。 活け車海老の紹興酒漬け
活け車海老の紹興酒漬け
従来なら、養殖中の汚れ堆積→腐敗→病気等の発
生の原因→池底の清掃や天日干しをおこなって病
気の発生を防止(化学薬品投入し殺菌)している
が、二酸化塩素発生器や水中ロボット等の設備が
必要であり、多大な費用がかかり、天日干しだけ
では、池底内のウイルス等の駆除が困難でだ。特
許:P2009-225762A「養殖池の池底改良工法」では
ラクトバチルスファーメンタムとエンテラコッカ
とが混合された二種混合乳酸菌を30倍に希釈した
二種混合乳酸菌液を、魚の養殖池に投入すること
で、車海老の急性ウイルス血病やビブリオ病が抑
制でき収量が上がったという。
わたしなら、初期投資に経費を掛けても(→実は、
こののところへの政府支援が大切)、先端技術を
投入するだろう。例えば、養殖池は二重構造とし
て堆積物は底から自動排出させる。投餌の管理は
微粒子濃度計で制御、投餌の栄養及び免疫力向上
剤及び抗菌・殺菌剤は天然系有機化合物やオゾン
使用を徹底する。用水は、真水加えるミネラル分
濃度を自動制御管理し、養殖池の槽表面塗装、備
品・什器・容器間仕切り材は、養殖場と並行し緑
茶栽培し、緑茶から抽出したカテキンを、養殖地
の餌及び抗菌、免疫力向上剤として使用し、養殖
池の排出堆積物を有機堆肥化し緑茶園に還元使用
するようなシステムを新規考案。手前味噌だが医
療と食糧の双方に貢献でき、このモデルを販売・
消費・指導ノウハウをつけて商品販売すれば良い
と思うのだが如何に。
■
















