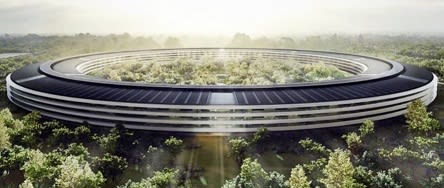今日は土曜日だ。賃労働していときは、土日祭日は待ち遠しく、特別な日だった。それは年を重ね
てでも変わらなかった。ところが、書斎がスモール・オフィース化してからは気分変化の増幅は小
さくなるにつれ、鬱状態が反対に大きくなることを体験する。解決方法は分かっているので、これ
は詰まるな!?と思うと、とりあえずハンドルを握り、ドライブへ出かける。そんなことを考えな
がら、クルーグマンの本を読み進める。まず、「第五章 10年後の世界はこう変わる」の金融危
機で表出した『恐慌型経済』 」の節っだが、ケインズ主義を経ているクルーグマンの本領発揮とい
うわけだが、「懲りないウォール街の住人たち」の節などのように、『デジタルケインズと共生・
贈与』『校舎の桜にケインズ』あるいは『新たな飛躍に向けて-新自由主義からデジタル・ケイ
ジアンへの道-』(環境工学研究所WEEF)などで掲載したものは削除し、めぼしいところを抜
粋掲載する。また、この章の「中国のボトルネックは環境破壊」 の節に絡み、岡本隆司 著『内藤
湖南「支邦論」の凄さ』(文藝春秋、2013年12月号)を加筆掲載する。

金融危機で表出した『恐慌型経済』
二〇〇八年に金融危機が起こったあと、私は『世界大不況からの脱出』(早川書房)で、世
界経済は恐慌に陥ったというわけではないが、恐慌そのものの復活はないにしても、そこで「
恐慌型経済」のかたちが現われ、一九三〇年代以降はみられなくなった問題が表出している、
と述べた。
恐慌型経済とは、この数十年間で初めて、経済の需要サイドにおける欠陥、つまり利用可能
な生産能力に見合うほどの十分な個人消費が存在しないことが、世界経済の足かせになってい
る、ということである。本から一部を引用しよう。
「世界は今、一つの経済危機から次の経済危機へと綱渡りをしている状態である。それらは
すべて、需要が十分でないというきわめて重大な問題をはらんでいる。一九九〇年代初頭以降
の日本、九五年のメキシコ、九七年のメキシコ、タイ、マレーシア、インドネシア、韓国、二
〇〇二年のアルゼンチン。そして二〇〇八年では世界のほとんどの国が次々と景気後退を余儀
なくされ、何年にも及ぶ経済成長を一時的であれ台無しにせざるを得なくなった。
しかも従来の政策対応では、まったく効果がないといえるのだ。再び経済の生産能力を活用
するために、いかに需要を十分に刺激するかが決定的な問題となった。これこそ恐慌型経済の
再来である」
そこで私はケインズ政策の重要性を説いた。これまで以上にケインズの考え方が妥当性を増
していたのである。
景気を回復させるためにできることは何でも行なう、という精神で、危機に対応しなければ
ならない。そこで行なったことがもし十分ではなかったなら、信用が拡大しはじめ、経済全体
にその拡大が広がるまでさらに多くを実行し、それとは違う施策も打つべきである、と述べた
のだ。
そして、われわれが産業革命以降、百五十年以上の歴史から学んだことは、残念ながら危機を放
っておくと、さらなる大きな苦痛を生み出す可能性がある、ということだ。一つの金融機開か傾け
ば、それが他の金融機関にも伝播していく。悪影響が伝染するのである。一九三〇年代に起こった金融
危機は、ニューヨークのきわめて小さな銀行から始まった。そこからスタートしたドミノ現象はき
わめてリアルなもので、取り付け騒ぎへと発展する。その取り付け騒ぎのなかでみなが同じ資産を
売り、資産価値は崩壊した。そこでは財政難に陥っていない金融機関さえも突然、同様の状態に陥
ってしまったのだと述べるていう。これをわたしたちは、"信用恐慌の連鎖反応"と呼ぶ。そして、
次の節では、米国の景気はまだ本調子ではないと指摘する。

アメリカはまだ地盤を取り戻せてない
『世界大不況からの脱出』を著した時期に比較すると、世界経済は大きな変化の局面を迎え
ているようにみえる。
リーマンでンョックによって発生した金融危機は、まさに急性危機とでも呼べるものだった。
世界経済のリセッションは二〇〇八年初頭から始まったが、二〇〇九年には終焉を迎えた。し
かしそれ以来、慢性的な不振状態が続いている。アメリカはいささかマシだろう。最悪なのは
ヨーロッパである。ときには成長もみられたが、リセッションに後戻りするような状況もある。
長引く標準以下の経済状態を、「不況」という名前で呼んでもよい。一九三○年代も経済成
長がなかったわけではなく、最初にかなりひどい落ち込みがあり、その後、少し回復し、再び
落ち込んだ。それと同じことが起こっているが、その規模は当時に比べれば小さい。しかし、
それにしてもひどい状況だ。
アメリカでは金融危機以前の二〇〇七年、失業率は四パーセント台だったが、二〇一三年七
月は七・四パーセント。状況は好転していない。そこではさまざまな「合併症」が生じている、
といってもよいだろう。人口動態に合わせて数字を修正するとわずかな向上がみられるが、失
われた地盤を取り戻せているわけではない。
ヨーロッパの失業率は上昇する一方で、新記録を更新しつづけている。二〇一三年六月のユ
ーロ圏の失業率は一二・一パーセント。前月から横ばいになったものの、引き続き、過去最高
水準で推移している。
懲りないウォール街の住人たち
金融についてはどうだろうか。リーマン・ショックとその後の金融危機を引き起こしたウオ
ール街は、自浄したのだろうか。二〇〇九年にスタートしたオバマ政権は、金融危機を教訓と
してドッド・フランク法(ウオール街改革および消費者保護法)を制定した。この法律は二〇
〇九年六月、政権が議会に提示し、その翌月には法律案として下院に提出された。同年十二月
二日には、修正版がバーニー・フランク下院金融サービス委員会委員長によって下院に、クリ
ストファー・ドッド上院銀行委員会委員長によって同委員会へと示された。
法律案に対する彼らの修正を踏まえ、二〇一〇年年六月に報告を行なった協議委員会は、こ
の二人の議員の名前にちなみ、法律案の命名を決議した。そして翌月、ドッド・フランク法は
無事、制定された。(中略)
第一に、消費者を保護すること。この法律によって消費者金融保護局がうまく機能すれば消
費者を被害から守ることができる。
第二に、清算権限。これは問題が起こった金融機関を差し押さえ、その運営を代わりに続け
る、というものだ。バンカーを救済せずにアメリカの金融システムを運営しつづけるには、ど
うしたらよいのか。これが金融危機当時の喫緊の課題だった。銀行は必要だが、株主は助けた
くない。そこでは曖昧ではなく、明確な法的権限が必要とされた。
第三に、健全な規制を課する権限。金融機関に対して、より高い資本基準を課す権限のこと
だ。この三つはいずれも非常に重要だ。しかし一方で、その結果は自由裁量によって左右され
る。言い換えるなら、それは当局の統治体質に大いに依存する、ということだ。この法案を制
定したオバマ政権のもとですら、どれくらいうまく機能するかはわからない。
オバマの次の大統領が誰になるかによって、状況は変わってくるだろう。たとえば民主党の
ヒラリー・クリントンが大統領になり、消費者金融保護局の創設に携わったエリザベス・ウォ
ーレンが財務長官に指名されれば、かなり効果的な金融規制が期待できる。
逆に、共和党のランド.ポールが大統領になり、自分の父親であり、共和党の大統領予備選
に何度も出馬した元下院議員のロン・ボールを財務長官に指名するような事態が起これば、そ
の規制はけっして実現しない。
当のウォール街の住人たちは、まったく懲りている様子がない。ほんとうにうまく逃げおお
せたのだ。私にいわせれば、当時よりも状況はむしろ悪くなっている。彼らから何か知恵を学
ぼうとしても、ただ失望させられるだけだろう。それほどまでにウォール街は変わっていない
のだ。
オパマはなぜ「チェンジ」できなかったか
オバマについては、「少々、あきらめムードになっているのではないか」と感じるときがあ
る。彼は慎重な人で、大胆なことをしたがらない。対立も好まない。それが裏目に出ているよ
うに思う。
理不尽な敵のいる政治的環境で、合理的な同意を得ようとして多くの時間を費やしたが、結
局のところ、そのほとんどがムダになった。そして、複数の最悪ともいえる事態が引き起こさ
れた。オバマが敵に正面切って立ち向かっていれば、そのなかのいくつかは回避できたかもし
れない。
もちろん、彼はとても頭がよい。チーム・オバマも非常に優秀で、オバマと議会の民主党議
員は決定的に重要な二つの法案を成立させた。その一つは先に述べた金融制度改革、もう一つ
は第4章で触れた医療制度改革である。
医療制度改革だけを取り上げても、それは第三六代アメリカ大統領であり、高齢者医療保険
制度制定、学校に対する補助金の支給、失業者への職業斡旋の強化、貧困家庭の児童に対する
就学前教育の拡充などを実現したリンドン・ジョンソン以来、いかなる大統領が成し遂げた功
績よりも大きい。
一方で、オバマにひどく失望している人がいることも確かだ。彼らはオバマを「チェンジが
できる指導者」だと考えていたからである。
私はそうした考えに賛同しなかったが、まるで彼が共和党に妥協したかのようにみえたとき
には怒りを覚え、落胆した。しかし私がもっとも期待した医療制度改革をみごとに勝ち取った
ことは当然だが評価されるべきである。
共和党がつくったアメリカの借金
他の文脈でアメリカに失望し、批判を続けている人もいる。一九八一年から八五年までレー
ガン政権下でOMB(行政管理予算局)の局長を務めたデヴイッド・ストックマンという元政
治家が、二〇一三年四月、“The Great Deformation"というタイトルの本を出版した。アメリ
カ経済は借金と縁故資本主義、政府介入によって腐敗している、というのがその中身だ。
縁故資本主義とは、ビジネスの成功が大企業のビジネスマンと政府官僚との密接な関係によ
って決定づけられるというもので、税制優遇措置、政府認可の配分において、それが表出する
ことが多い。政府介入のもっともわかりやすい例は、リーマン・ショック後にアメリカの金融
がクラッシュしたとき、大々的に行なわれた救済措置である。
タイトルだけをみるとこの本は注目に値するように思えるが、中身は羊頭狗肉で大したこと
はない。具体的な数字も出てくるが、ごまかされてはいけない。ストックマンはアメリカの借
金は八兆ドルもあり、途方もない額だ、と吹聴するが、アメリカ経済のGDPは年間一六兆ド
ル。八兆ドルという金額は、一年間のGDPのわずか半分にすぎないのだ。海外投資からのキ
ャピタルゲインを加味すれば、その数字はさらに取るに足らないものになる。
そもそも、その借金は誰がつくったのか。一九八〇年までアメリカ経済は借金に悩まされて
いなかった。レーガン政権、ブッシュ・シニア政権の時代に負債が膨らみはじめ、クリントン
政権で軽減されたが、ブッシュ・ジュニア政権でまた悪化した。
もちろん金融危機の余波も少なくはなかったが、歴史的な事実をみるかぎり、アメリカの借
金は金融危機までは一党、つまり、共和党が引き起こした問題だったのである。
銀行を破綻させれば経済は悪化する
自動車産業についてもストックマンは、金融危機のとき、政府は四万人の職を救済したが、
そこで救済を行なわなくとも南部にある日産自動車などのメーカーに人びとは移動しただろう、
と述べている。しかし、自動車産業は結局破綻しなかったわけだから、いまは何とでもいえる
状況だ。当然のこと、実際にGMを破綻させていたら、その四万人が南部に行ったかは定かで
はない。
縁故資本主義の解決策はあるのだろうか。不況をもたらして、すべてを破綻させ、ウォール
街の裕福なバンカーたちを救済しなければよい、という考え方もあるが、それではけっして経
済はうまく回らない。ベストな手はバンカーを規制しながら、同時に労働者を救済することだ。
ストックマンはFRBも痛烈に非難している。長期間にわたり金利を低く抑えて金融危機を
引き起こし、住宅バブルを膨張させたという趣旨だ。彼の論理は低金利がウォール街の狂乱投
機を煽ったというものだが、たとえば一九四〇年代から五〇年にかけての低金利時代において、
狂乱投機が発生しただろうか。
当時と現在の違いは何か。経済が悪化しているときにFRBが金利を下げるのは、諸悪の根
源ではない。金利を下げることはFRBの仕事である。問題は金融システムの悪用を防ぐセー
フガードが取り払われてしまったことだ。金融システムの悪用は、たとえ金利がゼロに近くな
くとも蔓延している。
経済が悪化したのはバブルが発生し、待ち逃げしたバンカーたちが世に溢れたからだ、とい
われるが、経済学とは道徳劇ではなく、一つの学問であることを忘れてはならない。政府が緊
縮政策に走らないという条件つきだが、危機が何も起きなければ、経済はいずれ自然に回復す
るものなのだ。
中国のボトルネックは環境破壊
アメリカとともにG2と呼ばれた中国経済の状況はどうか。政情安定の条件ともいわれたG
DP成長率八パーセントの達成は困難だ。二〇一三年七月十五日に中国国家統計局が発表した
二〇一三年度四~六月期GDPは、物価変動の影響を除いた実質ペースで前年同期比七・五パ
ーセント増にとどまった。一~三月期の七・七パーセントを下回り、二期続けての鈍化である。
八パーセントは当然のこと、これからの中国は五パーセント成長ができれば十分、という人
もいる。
二〇一五年には人口減少社会に突入するなかで、短期的な中国経済の将来を予測することは
難しい。中国政府の発表するデータをどのように解釈すればよいか、まったくわからないから
だ。中国がこれからリセッションに陥るのかどうか、私には判断材料がない。
長期的にみれば、中国経済はこれまでの理論に当てはまるかたちで推移するだろう。つまり
農民人口が過剰であったとき、その過剰人口を吸収できるかぎりにおいて、経済成長は遠くな
る。しかし、それが吸収され切ったときに賃金は上昇しはじめ、成長スピードも減速する。い
まや中国経済は、その段階に到達したようにみえる。
もちろん、これから賃金の上昇がみられることは、中国にとって本質的にはよいことだ。
しかし、さらに懸念すべきは環境破壊である。
今日の先進国の経済は、まずは成長そのものが目的とされ、ほとんど環境保護に気が配られ
ることなく、それが耐えられないレベルにまで達してから環境保護の改善要求が出てくる、と
いう段階を通過している。
中国もそうした先進国と同じ道をたどっているが、その変化はまさに超スピーディだった。
経済後進国からあっという間にGDPでは世界第二位の経済大国へと変貌し、その結果、北京
ではPM2・5という大気汚染問題が起こり、快晴の日でもつねに視界がさえぎられる日々が
続いた。
中国医師協会などがまとめた報告書によれば、中国の都市住民の七七パーセントが呼吸器系
に異常を抱えているという。専門家は、PM2・5が主因であると指摘している。
中国の国民は、こうした環境問題を懸念している。あまりに規模の大きな環境破壊が、彼ら
が解決すべき問題の最優先事項になっている、ということだ。いくら裕福になったところで、
息ができない状態が続くなら、クオリティ・オブ・ライフ(生活の質)も何もあったものでは
ない、ということだろう。
第5章 「10年後の世界経済はこう変わる」
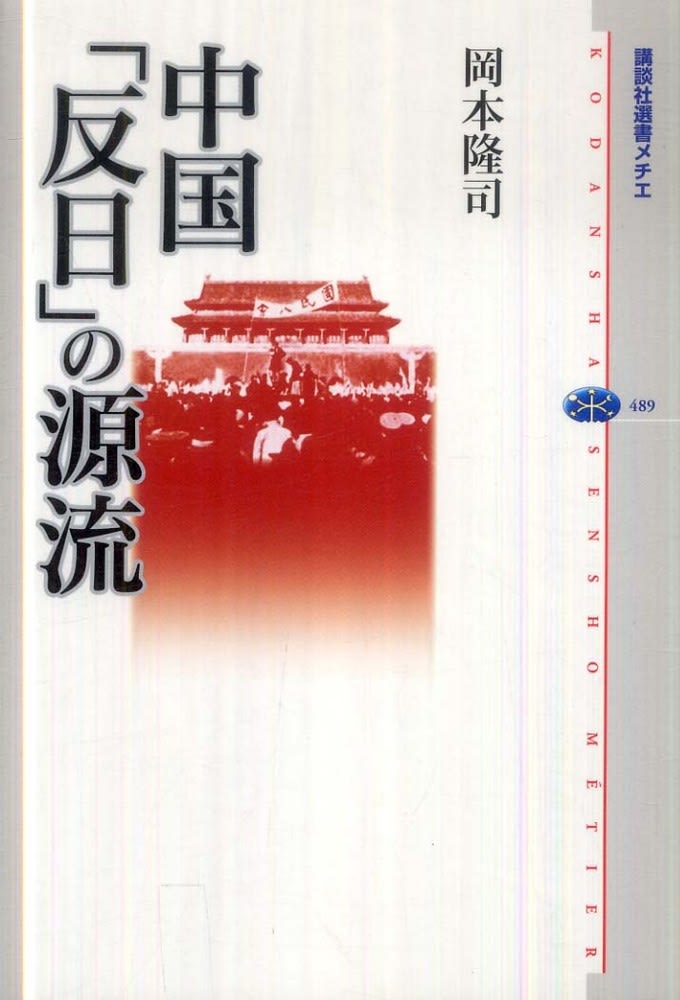
この最後の節の注評に関して、「環境破壊時代に突入した中国」(『デジタル革命粛々』2011.09.
08)でもブログ掲載しているが、この対応に失敗することで内政混乱から世界経済の混乱と連鎖す
るシナリオもあり得るだろう。そこで、岡本隆司著『内藤湖南「支邦論」の凄さ』の抜粋し特別に
追加掲載した。
当今、中国と無縁の日常生活は考えにくい。モノ・ヒト・情報、善かれ悪しかれ、意識する
とせざるとにかかわらず、どこかで必ず中国と遭遇する。中国製の機械・食品・雑貨はあふれ、
中国人の観光客・留学生もおびただしい。中国に関わる日々の報道事件はいわずもがな。そこ
でどうしても、中国を知る必要が生じる。
ところがその中国は、どうもよくわからない。目前の事象について、ひととおり説明を聴く
と、いったんは納得した気になる。それでも、そもそもなぜ、いつからそうなのか。根本的な
事情は俯に落ちないことが多い。
そんなとき、少し見方を変えてやればどうだろう。中国を知るには、内藤湘南を読みなおす。
これが筆者おすすめの方法であり、自ら実践してきたことでもある。
内藤湘南は明治維新の前々年に生まれたジャーナリスト、二十世紀に入って京都帝大の東洋
史学の教授になり、日中戦争が始まる直前に生涯を終えた、という人物。われわれ東洋史の学
徒にとっては、斯学(しがく)の草分けにして泰斗だが、そんなスケールで収まりきらない巨人
である。
一般にはむしろ、日本学者としてのほうが、名は通っているかもしれない。たとえば、二十
世紀の日本を知るには、「われわれの真の身体骨肉に直接触れた歴史」の「応仁の乱」以後を
研究すれば十分、ほかはいらない、と断じたことなど、よく知られるエピソードではなかろう
か。
『清朝衰亡論』が清朝三百年にとどまったのに対し、『支那論』は中国の歴史全体を相手どっ
て、その把握を試みた。そこに独創的、体系的な中国史観が生まれる。唐宋変革論はその中核
をなす所説だった。唐と宋のあいだ、十世紀を境に「貴族制」が崩潰する。それに代わり、「
君主独裁」の政体がおこって、「平民」の勃興した社会に移行した。この政体は以後、官僚機
構を組織して社会を統治したけれども、それは今日いうところの行政はおこなわない。人民よ
り税を搾取するにすぎず、いわば社会から遊離した存在である。社会の実体は父老、ないし郷
紳など、地域の名望家の指導する「郷団」組織、「自治団体」にあった。人々の生活にふれる
行政は、すべてそうした団体が担っていることを、湖南は強調する。すなわち当時・辛亥革命
直後の中国の社会状態は、宋代にはじまり、そこから継続してできあがったものである。中国
の唐宋変革はその意味で、あたかも日本の「応仁の乱」に相当するといってよい。「平民」社
会の勢力が興起し、独裁君主・官僚機構がそこから浮き上がっていった趨勢のすえ、清朝・皇
帝制度は崩潰した。そうである以上、もはや皇帝制・独裁制の復活はありえず、辛亥革命以降
の政体は必然的に、「平民」を主体とする共和制でなければならない。そうした政治社会構造
とその推移を考慮しない、形式的な近代化の無意味さをも説いたうえで、袁世凱のやり方が時
代に逆行していると指摘。
湖南の高足・宮崎市定は『新支那論』を「第一次世界大戦直後に、日本がなめさせられた苦悩
の表情だと見るべきである」と評して、断言する。アメリカの日本に対する干渉が次第に露骨
になってきて、当時の日本は在華権益を守るに汲々としていた。このころから次第に盛り上が
っアメリカの日本に対する干渉が次第に露骨になってきて、当時の日本は在華権益を守るに汲
々としていた。このころから次第に盛り上がってきた中国のナショナリズムは、実は日本から
の圧迫と、アメリカからの、今から見ればおかしいほどヒステリックな干渉とが育成したもの
である。アメリカのアジアヘの干渉はもともと中国が自ら招いたもので、中国はそれなりに
利益を得ているが、一銭の得にもならず、日本がなくなったらアジアがどうなるかも考えず、
ひたすら干渉し続けたアメリカが一番バカだ、というふうに読むのが『新支那論』の本当の読
み方だろう。『新支那論』を圧縮蒸溜して、宮嶋じしんにはあたりまえの中国学・東洋学的な
論述を除き去ったら、おそらくこのような骨格・設計図が残るのだろう。学識の浅いわれわれ
は、『新支那論』の述べる具体的な史実や解釈につい目を奪われてしまうので、とてもこうは
いかない。とまれ、東洋の時局全体を中国史と日米との関係で描こうとした『新支那論』のね
らいも、これではっきりする。
-中 略-
湖南はそこで、文化の発展とその中心移動を基軸として歴史と現状を架橋し、あるべき指針
を示そうとした。時局に対する苦悩、ひいては絶望をそこにみるのも可能だろう。湘南の歿後
三年にして、日中は全面戦争状態に入って破局をむかえた。かれの時局論はそのなかで、むし
ろ日本の中国侵略を支持する方向で利用され、湘南じしんも対外強硬派、中国侵略論者とみな
され、『支那論』『新支那論』もその種の著述に分類される。日本の敗戦により’それはいよ
いよ牢乎として抜きがたく定まった。
現状をみる目の甘さに対する指弾。新たな勢力「ヤング・チャイナ」が視野に入っていない、
「中国のナショナリズム」を直視しなかった、との断罪。時論家としての湘南の評価は、数々
だった。『支那論』『新支那論』も、忘却の彼方に消え去ってゆく。
-中 略-
マルクス史学は生産様式にもとづく発展段階論を中軸とする。奴隷制↓農奴制↓資本制とい
う段階発展であり、発展のゆきつくゴールが社会主義であり、共産主義であった。もっともこ
のプロセスは、ヨーロッパにおこったものであって、アジアは古来一貫して、発展が始動する
以前の段階にとどまっているとみなされる。いわゆる「アジア的生産様式」「アジア停滞論」
であり、かつてはこれが列強のアジア侵略を正当化する論理ともなっていた。
日本も同じである。中国は進歩、近代化の契機をもたない停滞した社会であり、なればこそ
近代化し資本主義化した日本が、その契機を与えてやらねばならない。こうした考え方が戦前
の中国侵略・アジア主義の一面をなしている。
戦後日本のマルクス史学は、その反省からはじまった。「中国停滞論」の克服である。資本
主義より進んだ社会主義に達した中国が「停滞」していたはずはないから、その発展のありよ
うを歴史から説明しなくてはならない。そこで恰好の足がかりとなったのが、湘南の唐宋変革
論である。
-中 略-
ところが、中国の民族主義を支持する立場は、これを中国蔑視の錯誤だと決めつけた。論拠
をなすのは、中国の歴史そのものの展開よりも、ナショナリズムやマルクス史学といった西洋
の理論や価値観であり、湖南が批判した「ヤング・チャイナ」の思考・論法とも重なる。それ
を信奉した毛沢東らの統一中国という現実が、その論拠に抗えない説得力を与えていた。湖南
を評価して唐宋変革論を基軸とした中国史の研究でさえ、社会内部の階級支配・階級闘争に大
きく比重をかけ、国家・社会の全体構造や社会そのものの性格や位置づけを考えようとはしな
くなった。
しかし現状はどうだろうか。もはやマルクス主義の権威は、色裾せて久しい。ナショナリズ
ムはじめ、西洋の政治理論も多様化している。歴史を考えるにせよ、現状を見るにせよ、既成
理論にもとづいて説明するだけでは、もはや十分とはいえまい。かたや「改革開放」をへて大
国化した眼前の中国は、社会主義でありながら市場経済を運営し、国民国家といいながら民族
紛争がたえず、法治を布きながら不法が横行し、統計がそなわりながら数値は信用ならない。
謎は枚拳にいとまがないのである。とてもわれわれの欧米本位の理論・思考では、理解しきれ
ない存在になった。
それでも目を凝らせば、いくつかの事象がみえてくる。日本と不可分の経済関係にあっても、
いっこうに収束しない「反日」・尖閣の問題、「党高民低」「国進民退」など、途方もない官
民格差、政府の意向に副いつつ、実はまったく顧慮していない民意の奔流なればこそ対内的に
は思想統制を、対外的には強硬路線を強めざるをえない国家権力。いずれもかつて湖南が描き
出した国家と社会の乖離というリアルタイムの中国像にみまがう。『支那論』『新支那論』が
今、みなおされているゆえんである。
唐宋変革以来、エリート層と庶民とがはるかに隔たった二重社会。そんな方厖大な社会を掌
握、制御しきれない微弱な独裁国家。そのはざまに介在し、大きな勢力を有して根を張る中間
団体。日本や欧米という国民国家の常識ではかりしれない中国の言動は、こうした全体構造に
由来する。国家と社会それぞれの外貌は、辛亥革命以後、たび重なる革命を通じて、たしかに
変わった。しかし構造そのものは、歴史的になお存続している、といってあながち誤りではな
いだろう。
したがって、「現代の中国を知るには、目前の現象だけでなく、歴史の事実からみなくてはならな
い。では、長い歴史のどこをみればよいのか。迷ったときに繙(ひもと)くべきが内藤湖南の東洋
史学、『支那論』『新支那論』ばかりにかぎらない。歴史と現状を架橋せんとする姿勢、千年を見
通そうとする洞察、それに応じて選び抜かれた史実。否応なく中国を知らなくてはならない われ
われが今、そこから学べるものは、決して少なくあるまいと結ぶが、わたし(たち)の立場は、湖
南の歴史・文明観(中国美学・中国学、日本文化史)を踏まえつつ、マルクスの考えを発展させた、
デヴィッド・ハーヴェイ(『新自由主義-その歴史的展開と現在』)の階級社会戦略論・運動論に
依拠しつつ国家間紛争の解決を模索する以外に道はないだろうと考えている。
尚、岡本隆明が用いる中国が社会主義とマルクスの社会主義は、"国家を開く"という点で、全く
異なり、現在の中国の社会体制は国家縁故資本主義、あるいは、国家赤色官僚専制主義とでも呼ぶ
べきものだと考える。