都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「新・北斎展」 森アーツセンターギャラリー
森アーツセンターギャラリー
「新・北斎展 HOKUSAI UPDATED」
1/17~3/24

森アーツセンターギャラリーで開催中の「新・北斎展 HOKUSAI UPDATED」を見てきました。
2000件以上も北斎と北斎派の作品を有し、北斎の研究者でもあった永田生慈氏の北斎コレクションが、東京・六本木の森アーツセンターギャラリーへまとめてやって来ました。
それが「新・北斎展 HOKUSAI UPDATED」で、永田コレクションのみならず、日本浮世絵博物館、中右コレクション、それに太田記念博物館のほか、シンシナティ美術館、ギメ美術館、メトロポリタン美術館などの海外の作品、約480件(展示替えあり)にて、北斎の画業の変遷を辿っていました。

「四代目岩井半四郎 かしく」 安永8(1779)年 島根県立美術館 (永田コレクション) 展示期間:1月17日(木)~1月28日(月)
はじまりは最初期の作品で、北斎は19歳にして勝川春章に入門し、春朗を名乗っては、役者絵や挿絵本などを制作していました。「四代目岩井半四郎 かしく」はデビュー作の1つで、人気の女形であった岩井半四郎の演じたかしくを、のびやかな筆致で描いていました。北斎は、結果的に15年も春章の元で過ごし、子供絵や名所絵、武者絵のほか、黄表紙や芝居絵本の挿絵までも幅広く手がけました。
「鎌倉勝景図巻」は、鎌倉から江ノ島へ至る道中を、9メートル近くの絵巻に仕立てた作品で、七里ガ浜などの景観を、柔らかく細かな筆で表していました。余白を用いた空間も特徴的で、全体的に穏やかな調子でまとめられていました。一方で力強いのは「鍾馗図」で、太く鋭い線を用い、剣を振り下ろす鍾馗の勇ましい姿を捉えていました。春朗の落款を持った、現存する唯一の肉筆画として知られています。
勝川派を離れ、琳派の俵屋宗理の名を継いだ北斎は、これまでの浮世絵とは一線を画し、摺物や肉筆画を多く手がけるようになりました。また西洋画を意識した銅版画も描いていて、のちの浮世絵の風景版画にも影響を与えました。肉筆では、後ろを振り向く女性の立ち姿の美しい「夜鷹図」が印象に深かったかもしれません。

「津和野藩伝来摺物」 寛政元~12 (1789~1800)年 島根県立美術館(永田コレクション) 通期展示(4期に分けて全点を展示)
宗理期のうち、特に貴重であるのが、「津和野藩伝来摺物」と題した作品で、長らく江戸時代に津和野藩主を務めた亀井家に伝来しました。大小暦や正月に配られた摺物とされていて、永田氏が118点を入手し、初めて全点が公開されました。(ただし展示替えあり。)総じて状態の良く、とりわけ淡い、紙から滲み出るような色彩の美しさに目を奪われました。
1805年、葛飾北斎と号した北斎は、当時、江戸で流行していた読本の挿絵を多く制作するようになりました。また中国絵画の影響も受けていて、優美な宗理時代とは異なり、豪胆でかつ大胆な画風の肉筆画を描きました。「円窓の美人図」は、町家の娘が冊子を見やる様子を表していて、頭髪の生え際など、細部までを丹念に写していました。女性の若々しい雰囲気も良く伝わっているかもしれません。
「竹に昼顔図」は、斜めに配した竹に絡む昼顔を描いたもので、素早い筆を動かしつつ、白く、うっすらピンク色を帯びた花を、驚くほど写実的に表していました。また「蛸図」も面白い作品で、正面から蛸を見据えつつも、何やら擬人化とも呼べうる、人懐っこい姿で描いていました。
50歳を過ぎると、北斎は戴斗と号し、門人を多く抱え、絵の手本を与えるべく、「北斎漫画」を含んだ絵手本を多く制作しました。また肉筆や錦絵でもさらなる変化を見せていて、まさに「UPDATED」のごとく、同じ地点に留まることはありませんでした。
「生首図」と「なまこ図」に目を引かれました。ともに生首となまこのみを扇面に描いていて、とりわけ歯を食いしばっては、上目遣いで白目を剥く生首には、著しいほどに迫真性がありました。また「鶏図」は、番いの鶏を、線ではなく面で表していて、鶏冠の色の面のグラデーションも巧みに示していました。即興的に描いたのかもしれませんが、鶏の様態を見事に写しているのではないでしょうか。

「冨嶽三十六景 凱風快晴」 天保初期 (1830~34)頃 島根県立美術館 (新庄コレクション) 展示期間:1月17日 (木)~2月18日 (月)
北斎画でも特に有名な「富嶽三十六景」が制作されたのは、北斎が為一と名乗った、60歳を過ぎてからのことでした。またこの時期は、一連の風景画だけでなく、花鳥画や古典画、それに武者絵なども精力的に描きました。中でも骸骨と化した小平二が蚊帳を覗き込む「百物語 こはだ小平二」などは、よく知られた作品と言えるかもしれません。

「向日葵図」 弘化4(1847)年 シンシナティ美術館 通期展示
70歳を超えた北斎は、なお旺盛に創作活動を続け、画狂老人卍を名乗っては、主に動物や植物、ないし宗教的なモチーフの肉筆画を描きました。学問を司る神で、北斗七星の第一星である文昌星を、まるでサイボーグのように表した「文昌星図」や、何やら嬉しそうに月を眺める虎を描いた「月みる虎図」などが印象に深いのではないでしょうか。また北斎が88歳に手がけた「向日葵図」も珍しい一枚で、竹に支えられた向日葵を、思いがけないほど細かに写していました。初公開の作品でもあります。

「弘法大師修法図」 弘化年間 (1844~47) 西新井大師總持寺 通期展示
ラストを飾るのは、北斎の最晩年でかつ最大級の作品である「弘法大師修法図」で、病魔を示す鬼が襲う中、大師が祈祷を続ける光景を描いていました。漆黒の闇の中、巨大な鬼と大師が対峙する姿からしても、異様な迫力を見せていましたが、鬼気迫る感で吠え続ける犬の描写も、また劇的と言えるかもしれません。西新井大師に伝わる作品で、1983年に永田氏の研究により、同寺の物置より発見されました。
2005年に東京国立博物館で開催された「北斎展」以来、東京では十数年ぶりとなる大規模な回顧展です。初公開作品も少なくない上、あまり見知らない希少作も網羅していました。作品自体こそ見ることの多い北斎ですが、画業の全体に改めて接する良い機会と言えそうです。

「しん板くミあけとうろふゆやしんミセのづ」パネル撮影コーナー
なお本展の監修も担った永田氏は、2017年、コレクションを一括して、故郷の島根県立美術館へ寄贈しました。そしてこの展覧会への準備を進めてきましたが、昨年2月、病のため、66歳にして亡くなられました。
その寄贈に際し、永田氏は自身のコレクションを、島根県内のみで公開することを希望されたそうです。よって、永田コレクションが東京で公開されるのは、今回が最後となります。
展示替えの情報です。出展総数は約480件にも及びますが、前後期で相当数の入れ替えがある上、各会期においてもAとBに分かれています。実質、4会期制の展覧会です。一度に見られるのは約120点ほどでした。
「新・北斎展 HOKUSAI UPDATED」出展リスト(PDF)
前期:1月17日(木)~2月18日(月)
A:1月17日(木)~1月28日(月)、B:1月30日(水)~2月18日(月)
後期:2月21日(木)~3月24日(日)
A:2月21日(木)~3月4日(月)、3月6日(水)~3月24日(日)
最後に館内の状況です。会期の早々、1月19日の土曜日に見てきました。

六本木へは昼過ぎに到着しましたが、入口に5分待ちの表記があったものの、実際に列はなく、待ち時間なしでスムーズに入館出来ました。
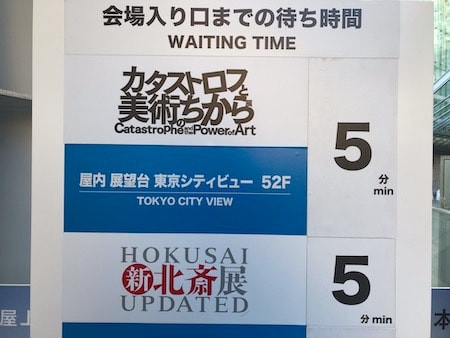
展示室内も、最初の春朗期、宗理期あたりは賑わっていたもの、途中からは特に並ぶこともなく、最前列でじっくり鑑賞出来ました。現在のところ、規制がかかるほどは混雑していません。

しかし北斎の知名度は絶大です。繰り返しになりますが、東京では久しぶりの大規模な北斎展でもあり、会期中盤以降は列が出来ることも予想されます。また森アーツの会場自体も広くはありません。
3月24日まで開催されています。早めの観覧をおすすめします。
「新・北斎展 HOKUSAI UPDATED」(@HOKUSAI_UPDATED) 森アーツセンターギャラリー
会期:2019年1月17日(木)~3月24日(日)
休館:1月29日(火)、2月19日(火)、2月20日(水)、3月5日(火)。
時間:10:00~20:00
*火曜日のみ17時閉館。
*入館は閉館の30分前まで。
料金:一般1600(1400)円、大学生1300(1100)円、高校・中学・小学生800(600)円。未就学児無料。
*( )内は15名以上の団体料金
住所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階
交通:東京メトロ日比谷線六本木駅1C出口徒歩5分(コンコースにて直結)。都営地下鉄大江戸線六本木駅3出口徒歩7分。
「新・北斎展 HOKUSAI UPDATED」
1/17~3/24

森アーツセンターギャラリーで開催中の「新・北斎展 HOKUSAI UPDATED」を見てきました。
2000件以上も北斎と北斎派の作品を有し、北斎の研究者でもあった永田生慈氏の北斎コレクションが、東京・六本木の森アーツセンターギャラリーへまとめてやって来ました。
それが「新・北斎展 HOKUSAI UPDATED」で、永田コレクションのみならず、日本浮世絵博物館、中右コレクション、それに太田記念博物館のほか、シンシナティ美術館、ギメ美術館、メトロポリタン美術館などの海外の作品、約480件(展示替えあり)にて、北斎の画業の変遷を辿っていました。

「四代目岩井半四郎 かしく」 安永8(1779)年 島根県立美術館 (永田コレクション) 展示期間:1月17日(木)~1月28日(月)
はじまりは最初期の作品で、北斎は19歳にして勝川春章に入門し、春朗を名乗っては、役者絵や挿絵本などを制作していました。「四代目岩井半四郎 かしく」はデビュー作の1つで、人気の女形であった岩井半四郎の演じたかしくを、のびやかな筆致で描いていました。北斎は、結果的に15年も春章の元で過ごし、子供絵や名所絵、武者絵のほか、黄表紙や芝居絵本の挿絵までも幅広く手がけました。
「鎌倉勝景図巻」は、鎌倉から江ノ島へ至る道中を、9メートル近くの絵巻に仕立てた作品で、七里ガ浜などの景観を、柔らかく細かな筆で表していました。余白を用いた空間も特徴的で、全体的に穏やかな調子でまとめられていました。一方で力強いのは「鍾馗図」で、太く鋭い線を用い、剣を振り下ろす鍾馗の勇ましい姿を捉えていました。春朗の落款を持った、現存する唯一の肉筆画として知られています。
勝川派を離れ、琳派の俵屋宗理の名を継いだ北斎は、これまでの浮世絵とは一線を画し、摺物や肉筆画を多く手がけるようになりました。また西洋画を意識した銅版画も描いていて、のちの浮世絵の風景版画にも影響を与えました。肉筆では、後ろを振り向く女性の立ち姿の美しい「夜鷹図」が印象に深かったかもしれません。

「津和野藩伝来摺物」 寛政元~12 (1789~1800)年 島根県立美術館(永田コレクション) 通期展示(4期に分けて全点を展示)
宗理期のうち、特に貴重であるのが、「津和野藩伝来摺物」と題した作品で、長らく江戸時代に津和野藩主を務めた亀井家に伝来しました。大小暦や正月に配られた摺物とされていて、永田氏が118点を入手し、初めて全点が公開されました。(ただし展示替えあり。)総じて状態の良く、とりわけ淡い、紙から滲み出るような色彩の美しさに目を奪われました。
1805年、葛飾北斎と号した北斎は、当時、江戸で流行していた読本の挿絵を多く制作するようになりました。また中国絵画の影響も受けていて、優美な宗理時代とは異なり、豪胆でかつ大胆な画風の肉筆画を描きました。「円窓の美人図」は、町家の娘が冊子を見やる様子を表していて、頭髪の生え際など、細部までを丹念に写していました。女性の若々しい雰囲気も良く伝わっているかもしれません。
「竹に昼顔図」は、斜めに配した竹に絡む昼顔を描いたもので、素早い筆を動かしつつ、白く、うっすらピンク色を帯びた花を、驚くほど写実的に表していました。また「蛸図」も面白い作品で、正面から蛸を見据えつつも、何やら擬人化とも呼べうる、人懐っこい姿で描いていました。
50歳を過ぎると、北斎は戴斗と号し、門人を多く抱え、絵の手本を与えるべく、「北斎漫画」を含んだ絵手本を多く制作しました。また肉筆や錦絵でもさらなる変化を見せていて、まさに「UPDATED」のごとく、同じ地点に留まることはありませんでした。
「生首図」と「なまこ図」に目を引かれました。ともに生首となまこのみを扇面に描いていて、とりわけ歯を食いしばっては、上目遣いで白目を剥く生首には、著しいほどに迫真性がありました。また「鶏図」は、番いの鶏を、線ではなく面で表していて、鶏冠の色の面のグラデーションも巧みに示していました。即興的に描いたのかもしれませんが、鶏の様態を見事に写しているのではないでしょうか。

「冨嶽三十六景 凱風快晴」 天保初期 (1830~34)頃 島根県立美術館 (新庄コレクション) 展示期間:1月17日 (木)~2月18日 (月)
北斎画でも特に有名な「富嶽三十六景」が制作されたのは、北斎が為一と名乗った、60歳を過ぎてからのことでした。またこの時期は、一連の風景画だけでなく、花鳥画や古典画、それに武者絵なども精力的に描きました。中でも骸骨と化した小平二が蚊帳を覗き込む「百物語 こはだ小平二」などは、よく知られた作品と言えるかもしれません。

「向日葵図」 弘化4(1847)年 シンシナティ美術館 通期展示
70歳を超えた北斎は、なお旺盛に創作活動を続け、画狂老人卍を名乗っては、主に動物や植物、ないし宗教的なモチーフの肉筆画を描きました。学問を司る神で、北斗七星の第一星である文昌星を、まるでサイボーグのように表した「文昌星図」や、何やら嬉しそうに月を眺める虎を描いた「月みる虎図」などが印象に深いのではないでしょうか。また北斎が88歳に手がけた「向日葵図」も珍しい一枚で、竹に支えられた向日葵を、思いがけないほど細かに写していました。初公開の作品でもあります。

「弘法大師修法図」 弘化年間 (1844~47) 西新井大師總持寺 通期展示
ラストを飾るのは、北斎の最晩年でかつ最大級の作品である「弘法大師修法図」で、病魔を示す鬼が襲う中、大師が祈祷を続ける光景を描いていました。漆黒の闇の中、巨大な鬼と大師が対峙する姿からしても、異様な迫力を見せていましたが、鬼気迫る感で吠え続ける犬の描写も、また劇的と言えるかもしれません。西新井大師に伝わる作品で、1983年に永田氏の研究により、同寺の物置より発見されました。
2005年に東京国立博物館で開催された「北斎展」以来、東京では十数年ぶりとなる大規模な回顧展です。初公開作品も少なくない上、あまり見知らない希少作も網羅していました。作品自体こそ見ることの多い北斎ですが、画業の全体に改めて接する良い機会と言えそうです。

「しん板くミあけとうろふゆやしんミセのづ」パネル撮影コーナー
なお本展の監修も担った永田氏は、2017年、コレクションを一括して、故郷の島根県立美術館へ寄贈しました。そしてこの展覧会への準備を進めてきましたが、昨年2月、病のため、66歳にして亡くなられました。
新・北斎展 みどころ③ 永田コレクション、最後の東京公開本展監修者、故・永田生慈氏のコレクションは本展に出品された後は、島根県のみで公開されることとなりました。本展は永田コレクションを東京で見ることができる最後の機会となります。#新北斎展 pic.twitter.com/kmtqXFOGFi
— 新・北斎展 HOKUSAI UPDATED (@HOKUSAI_UPDATED) 2018年12月12日
その寄贈に際し、永田氏は自身のコレクションを、島根県内のみで公開することを希望されたそうです。よって、永田コレクションが東京で公開されるのは、今回が最後となります。
展示替えの情報です。出展総数は約480件にも及びますが、前後期で相当数の入れ替えがある上、各会期においてもAとBに分かれています。実質、4会期制の展覧会です。一度に見られるのは約120点ほどでした。
「新・北斎展 HOKUSAI UPDATED」出展リスト(PDF)
前期:1月17日(木)~2月18日(月)
A:1月17日(木)~1月28日(月)、B:1月30日(水)~2月18日(月)
後期:2月21日(木)~3月24日(日)
A:2月21日(木)~3月4日(月)、3月6日(水)~3月24日(日)
最後に館内の状況です。会期の早々、1月19日の土曜日に見てきました。

六本木へは昼過ぎに到着しましたが、入口に5分待ちの表記があったものの、実際に列はなく、待ち時間なしでスムーズに入館出来ました。
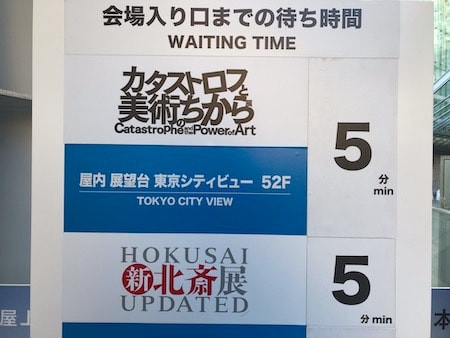
展示室内も、最初の春朗期、宗理期あたりは賑わっていたもの、途中からは特に並ぶこともなく、最前列でじっくり鑑賞出来ました。現在のところ、規制がかかるほどは混雑していません。

しかし北斎の知名度は絶大です。繰り返しになりますが、東京では久しぶりの大規模な北斎展でもあり、会期中盤以降は列が出来ることも予想されます。また森アーツの会場自体も広くはありません。
3月24日まで開催されています。早めの観覧をおすすめします。
「新・北斎展 HOKUSAI UPDATED」(@HOKUSAI_UPDATED) 森アーツセンターギャラリー
会期:2019年1月17日(木)~3月24日(日)
休館:1月29日(火)、2月19日(火)、2月20日(水)、3月5日(火)。
時間:10:00~20:00
*火曜日のみ17時閉館。
*入館は閉館の30分前まで。
料金:一般1600(1400)円、大学生1300(1100)円、高校・中学・小学生800(600)円。未就学児無料。
*( )内は15名以上の団体料金
住所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階
交通:東京メトロ日比谷線六本木駅1C出口徒歩5分(コンコースにて直結)。都営地下鉄大江戸線六本木駅3出口徒歩7分。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )










