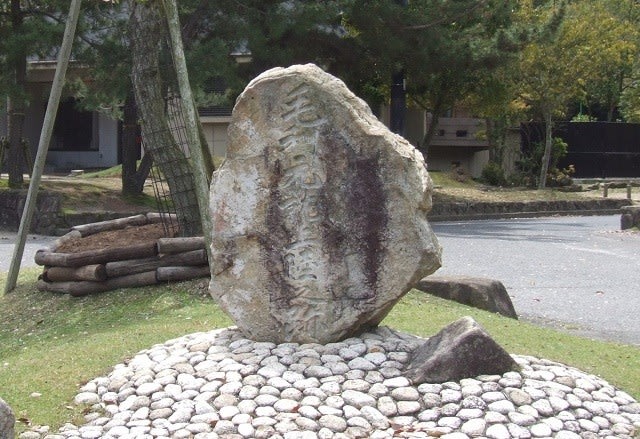昨日紹介したみかどホテルは明治44年(1911)12月に組織・名称を変更して宮島ホテルとなり、みかどホテル時の洋館部を主に使用していたが大正4年(1915)に焼失した。原爆ドームを設計したヤン・レツルが大正6年(1917)に擬和風の木造4階建洋館を設計し建築されている。戦後宮島ホテルはBCOF(英連邦占領軍)に接収(下画像-呉の歩みⅡより)されていたが昭和28年(1953)に焼失した。
当ブログ主が小学生の頃、遠足で大元公園へ訪れた際に現在の「みやじま 杜の宿」がある地に宮島ホテルの焼失残骸があったのを記憶しているのである。