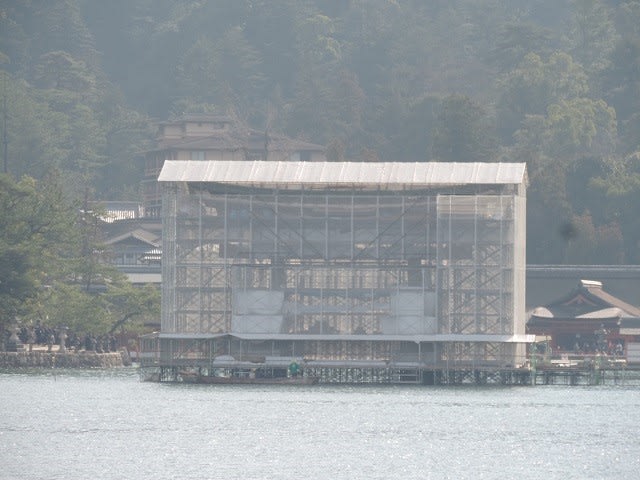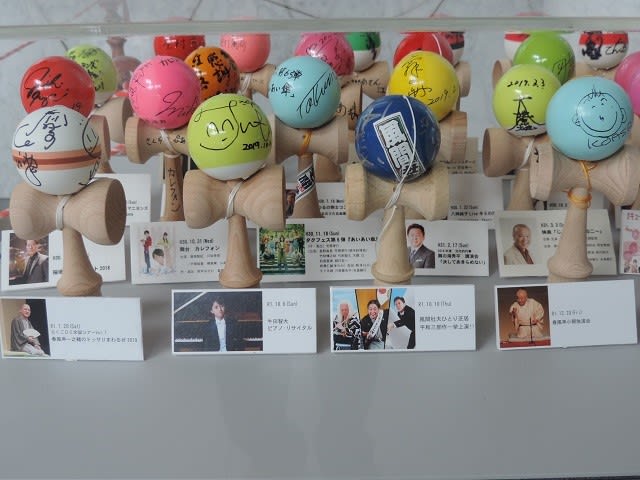厳島大鳥居之図は享和元年(1801)3月に上棟した大鳥居の各部の寸法などが記されている。中画像は千畳閣に架けられている尺杖で表示によると明治8年(1875)に再建された現在の大鳥居の高さと同じ16mの現場用の物差しとのことである。上画像をみると惣高6丈3尺余とあり、当時の大鳥居は現在のものより約3mも高い19.09m(63尺)であったようである。下画像は宝物館前に展示してある大鳥居の根元材で、昭和26年(1951)の大修理の際取り換えた楠の根元材のようである。(根元材取換えの顛末については宮島町史特論編・建築に詳述されている)