〇藤木久志『新版 雑兵たちの戦場:中世の傭兵と奴隷狩り』(朝日選書) 朝日新聞出版 2005.6
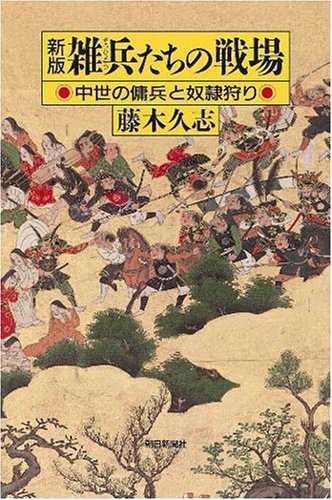 いつか読もうと思っていた本書をようやく読む機会を得た。素人の私が言うのもナンだが、たぶん日本中世史研究における記念碑的な名著である。華やかな戦国群雄論や合戦物語の裏側で、実は飢えた雑兵たちが生きるため食うための戦争を戦い、人と物の略奪を繰り広げていたことを明らかにする。いま読んでも十分面白いが、原著出版当時(1995年)の衝撃は、さらに大きかっただろうと思う。現在では、たとえば大河ドラマに描かれる中世の社会も、かなり本書の見解に沿ったものになっているので、あらためて出発点を確認するような気持ちで読んだ。
いつか読もうと思っていた本書をようやく読む機会を得た。素人の私が言うのもナンだが、たぶん日本中世史研究における記念碑的な名著である。華やかな戦国群雄論や合戦物語の裏側で、実は飢えた雑兵たちが生きるため食うための戦争を戦い、人と物の略奪を繰り広げていたことを明らかにする。いま読んでも十分面白いが、原著出版当時(1995年)の衝撃は、さらに大きかっただろうと思う。現在では、たとえば大河ドラマに描かれる中世の社会も、かなり本書の見解に沿ったものになっているので、あらためて出発点を確認するような気持ちで読んだ。
雑兵とは身分の低い兵卒のこと。上級武士以外の、悴者(かせもの)・若党・足軽(以上が侍)、中間・小者・あしらこ(以上が下人)、夫(ぶ)・夫丸(以上は百姓)をいう。彼らには御恩も奉公も武士道もなく、たとえ懸命に戦っても恩賞があるわけでもなく、ただ作戦の合間の乱取りと、落城後の掠奪を目当てに戦闘に参加していた。
そもそも農業の未発達な中世の暮らしは飢えと隣り合わせだった。中世の関東の過去帳の調査から、早春から初夏にかけての端境期に死亡者が集中することが分かっている(中国は二毛作のため春と秋にピークあるとのこと)。戦場は春に飢える村人たちの稼ぎ場であり、口減らしの意味もあった(一方で、農繁期に百姓を徴発するのは容易でなかったという指摘も面白い)。
乱取りされた人々は、大名の国元に連れていかれる者もあり、身代金で買い戻される者もあり、また人買い商人に売り払われる者もあった。その一部は、ポルトガルの商船に転売されていたというのが、なかなか衝撃だった。一部どころではなく、傭兵、奴隷、労働者などとして、16世紀末から海を渡った日本人の総数はおそらく10万人以上、その1割ほどが東南アジアに住み着いたという推定もあるそうだ。キリシタン史料から見えてくる中世日本の姿、もっと一般的に知られてほしい。
先を急いではいけない。秀吉の天下統一によって国内から戦場が消滅すると、掠奪・暴行のエネルギーは朝鮮に向けられた。著者は、かつて朝鮮侵略における日本軍の激しい掠奪行為を「外国の戦場ゆえの逸脱、侵略戦争ゆえの退廃、近代に先行する強制連行の史実」と見ていたが、「実は日本国内の戦場の人取り習俗の持ち出しであったなどとは、当時はとても信じられなかった」と告白しており、感慨深い。人間、外国だからとか非日常だからといって、そんなに本質が変わるものではないのかもしれない。
本格的に国内に戦場がなくなると、食えない村人たちは都市の普請場や金銀山に向かうようになる。相次ぐ築城は、戦場を閉鎖し平和を保ち続けるために、新たな稼ぎ場を用意する公共事業だったと見ることもできる。
本書は、文書類に拠るだけでなく、狂言(召使う者が一人しかいない武士=一僕者)を引いたり、絵画資料(大坂夏の陣屏風)を例に挙げたり、目配りが広い。傭兵たち≒かぶき者の風体についての考察を読みながら、岩佐又兵衛など、桃山・江戸初期の風俗屏風を思い浮かべていた。戦いのときは、ただ無力に蹂躙されるのではなく、城籠り・山上がり、寺社に逃げ籠る、半手・半納など、さまざまな手立てで身を守ろうとする村のありかたも興味深かった。「誰にでもいい、強い者につく」というのが、武士と異なる、百姓の生き方だったという。
豊富な参考文献には、興味深い先行研究がたくさん目についた。とりあえず本書を含む著者の朝日選書三部作『戦国の村を行く』と『飢饉と戦争の戦国を行く』を読もう。あとは折口信夫の「ごろつきの話」が読みたい。

























