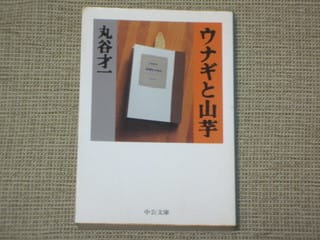丸谷才一 1995年 中公文庫版
とにかく何か読んでみたくて、ことしの2月ころだったかな、出先の古本屋で買った、丸谷才一の文庫本。
もともとは1984年に刊行された『遊び時間3』というタイトルの単行本だったらしい。まちがえて古本屋で単行本買わないようにせねば。(買ってもいいんだけど。)
エッセイ集というよりは、評論集という感じに近い気がする、ボリューム的には書評が多くを占めてるし。
著者あとがきにいわく、「書評あり、随筆あり、日本語論あり、一風変つた角度からの憲法擁護の講演あり、洋服屋さんの広告まであるといふ、にぎやかな(雑然たる?)本」ってんだけど、まあ、そういうことか。
書評は72篇あって、1970年代後半から80年代前半にかけて週刊朝日に載ったものらしい。
書評って、新聞に週1回日曜にあるのを読んだり、週刊誌のなかに2頁くらいあるのを読んだりするんなら、ちょうどよくて興味もてるんだけど、それだけを集めてギュッと詰まってるのをまとめて読むとなると、私にはそれほど得意なものとはいえない。
ところが、著者は、
>わたしは、出来のいい書評を読むことと、ある程度以上の古本屋の目録を読むことは、それぞれが人生の快楽の一つに数へていいと思つてゐる。(p.335「縦横ななめ」)
というくらいだから恐れ入る。読んでるうちに飽きてきちゃう私はその境地までは遠い。
それよりも、やっぱ日本語論みたいなほうがおもしろい。
たとえば、日本国憲法がもたもたした読みにくい文章なのをとりあげて、
>(略)明治憲法が書かれた明治期において、いや現行憲法が翻訳された昭和二十年代においてすらも、日本語の散文といふものが確立されてゐなかつた。
>(略)和文脈系漢文脈系の双方とも、国民の大多数が、自分の意思を他人に対してはつきりとそして詳しく表明するための道具にはなつてゐなかつた。さういふものではなくて、極めて特殊な個人の使ふ、極めて特殊なものにすぎなかつたのです。(p.277「文章論的憲法論」)
と日本語の散文の未発達、日本語は和歌を中心として表現を磨いてきたって説いたりするのを読むと、とても刺激的である。
ほかにも、国語教科書のひどさ、国語教育がなっちゃいないことについて、
>第一に、それはろくでもない文体で書いてあつた。どの教科書のどの巻を取つても、半分以上はがらくた同然の文章だつた。全巻駄文だけといふ代物もあつた。(p.297「日本語ばやり」)
と手厳しいとこなんかも、強く迫るものがある。
あと、
>聞くところによると、暮しの手帖社は男であらうと女であらうと、新入社員にはまづ料理記事を担当させるんださうですね。(略)新入社員をしかるべき板前ないしコックのところに行かせる。目の前で作つてもらひながら教はる。帰つて来て作り方を文章にする。その記事を別の社員に渡す。その社員は記事を読みながら料理を作る。作りながらわからないところは一々チェックして新入社員につきつける。そこの文章を新入社員は直す。(p.285「文章論的憲法論」)
なんてエピソードの紹介はおもしろい。ちゃんと言いたいことの伝わる散文の訓練とはそういうものだと。
章立ては以下のとおり。
I パロディの練習
II 書評の楽しみ
III 文章そして日本語
IV 序文の形式を借りて
V 文学と文明についての閑談
VI 推薦文十五篇
VII 大岡昇平との往復書簡
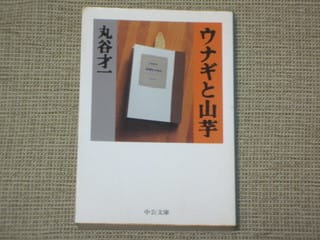
とにかく何か読んでみたくて、ことしの2月ころだったかな、出先の古本屋で買った、丸谷才一の文庫本。
もともとは1984年に刊行された『遊び時間3』というタイトルの単行本だったらしい。まちがえて古本屋で単行本買わないようにせねば。(買ってもいいんだけど。)
エッセイ集というよりは、評論集という感じに近い気がする、ボリューム的には書評が多くを占めてるし。
著者あとがきにいわく、「書評あり、随筆あり、日本語論あり、一風変つた角度からの憲法擁護の講演あり、洋服屋さんの広告まであるといふ、にぎやかな(雑然たる?)本」ってんだけど、まあ、そういうことか。
書評は72篇あって、1970年代後半から80年代前半にかけて週刊朝日に載ったものらしい。
書評って、新聞に週1回日曜にあるのを読んだり、週刊誌のなかに2頁くらいあるのを読んだりするんなら、ちょうどよくて興味もてるんだけど、それだけを集めてギュッと詰まってるのをまとめて読むとなると、私にはそれほど得意なものとはいえない。
ところが、著者は、
>わたしは、出来のいい書評を読むことと、ある程度以上の古本屋の目録を読むことは、それぞれが人生の快楽の一つに数へていいと思つてゐる。(p.335「縦横ななめ」)
というくらいだから恐れ入る。読んでるうちに飽きてきちゃう私はその境地までは遠い。
それよりも、やっぱ日本語論みたいなほうがおもしろい。
たとえば、日本国憲法がもたもたした読みにくい文章なのをとりあげて、
>(略)明治憲法が書かれた明治期において、いや現行憲法が翻訳された昭和二十年代においてすらも、日本語の散文といふものが確立されてゐなかつた。
>(略)和文脈系漢文脈系の双方とも、国民の大多数が、自分の意思を他人に対してはつきりとそして詳しく表明するための道具にはなつてゐなかつた。さういふものではなくて、極めて特殊な個人の使ふ、極めて特殊なものにすぎなかつたのです。(p.277「文章論的憲法論」)
と日本語の散文の未発達、日本語は和歌を中心として表現を磨いてきたって説いたりするのを読むと、とても刺激的である。
ほかにも、国語教科書のひどさ、国語教育がなっちゃいないことについて、
>第一に、それはろくでもない文体で書いてあつた。どの教科書のどの巻を取つても、半分以上はがらくた同然の文章だつた。全巻駄文だけといふ代物もあつた。(p.297「日本語ばやり」)
と手厳しいとこなんかも、強く迫るものがある。
あと、
>聞くところによると、暮しの手帖社は男であらうと女であらうと、新入社員にはまづ料理記事を担当させるんださうですね。(略)新入社員をしかるべき板前ないしコックのところに行かせる。目の前で作つてもらひながら教はる。帰つて来て作り方を文章にする。その記事を別の社員に渡す。その社員は記事を読みながら料理を作る。作りながらわからないところは一々チェックして新入社員につきつける。そこの文章を新入社員は直す。(p.285「文章論的憲法論」)
なんてエピソードの紹介はおもしろい。ちゃんと言いたいことの伝わる散文の訓練とはそういうものだと。
章立ては以下のとおり。
I パロディの練習
II 書評の楽しみ
III 文章そして日本語
IV 序文の形式を借りて
V 文学と文明についての閑談
VI 推薦文十五篇
VII 大岡昇平との往復書簡