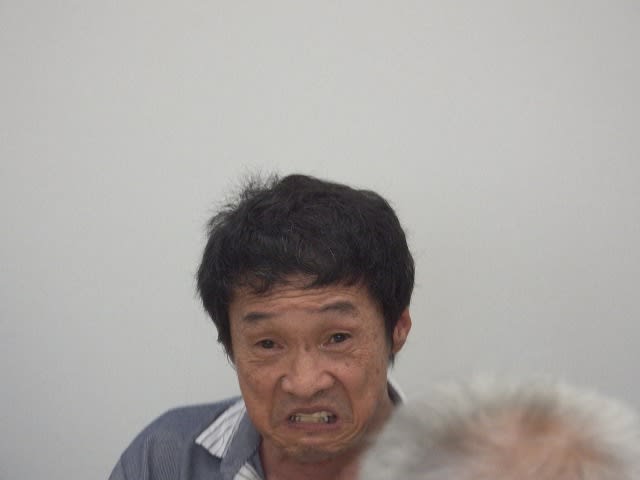浅田訴訟の裁判意義を再確認いたします。
裁判の意義については原告訴訟代理人、柿崎弘行弁護士による意見陳述書(平成25年11月17日)に書かれています。
その要約版より引用します。(再掲載)
裁判の第一の意義ー障害福祉の実態を明らかにすることー
1.障害福祉と介護保険は、目的も内容も違う制度です。年齢だけを見て介護保険に切り替えろというのは不適切です。自己負担についても大きな違いがあります。障害者を年齢で区別し、高齢の障害者により大きな経済的負担を負わせるのは、どう考えてもおかしいのです。
2.障害者自立支援法7条(現在の障害者総合支援法7条)は、「介護保険でカバーできる範囲は、障害者サービスを提供しない」としています。これが、年齢だけを見て機械的に介護保険の利用を強制するという意味であれば、憲法14条と憲法25条に違反します。
3.むしろ、障害者自立支援法22条は、障害者の特性や生活状況など様々な事情を考えることを求めています。障害福祉と全く同じ条件で介護保険を利用できる場合だけ介護保険にするというのが、この法律の本当の意味ではないでしょうか。今回の岡山市の取り扱いは憲法違反です。仮に、憲法の話は脇に置くとしても、行政機関としてきちんと考えていなかったこと自体が違法です。
裁判の第二の意義ー岡山市の非人道的態度を問うことー
1.当初の決定はサービスの全面打ち切りでしたが、何度も取り消しや変更がなされ、最終的には相当の部分が支給されました。岡山市は、なぜ最初から一部支給の決定をしなかったのでしょうか。
2.浅田さんは、サービスを全面的に打ち切られたために、床に倒れて起き上がれなくなり、下痢で大便を漏らしたり、たいへん苦しみました。後から取り消しや変更がされても、時間を遡ってサービスを受けることはできません。浅田さんの苦しみがなかったことにはならないのです。
3.岡山市は、障害福祉より介護保険の方が市町村の財政的負担が軽いために、65歳を迎えた障害者に介護保険への切り替えを求めているのです。浅田さんは、見せしめのように、サービスを打ち切られました。岡山市だけでなく、全国各地で同じような問題が起こりつつあります。全国の障害者が、今後二度と、浅田さんと同じような苦しみをあじわうことのないようにしなければなりません。
終わりに
2010年、障害者自立支援法違憲訴訟訴訟原告団・弁護団と国(厚生労働省)との間で基本合意が成立しました。その中で、障害者自立支援法7条の問題点が指摘されています。岡山市がこの基本合意を十分に理解していれば、今回の事件は起こらなかったはずです。裁判所では、厳格な審理が行われるよう、強く要望します。
以上引用しました。
以下はこのブログの管理人の現在の思いを書きました。
裁判が長引くというのはよくいわれることです。
今まで他の裁判も何度か傍聴していいますがテレビドラマのように原告側弁護士と被告側弁護士が丁々発止とやりあうということはなかったです。
行政訴訟では法廷の場で劇的に進行するということはないといっていいのでしょう。
双方が裁判所や相手側から求められる書面を期日までに提出し、その書面をもとにさらに検討を重ね不明な点を絞っていくという地道な作業のように思えます。
裁判官は両者の意見や釈明を聞きながら方向性を模索し、両者にその方向性に従った書面を提出してもらうことで審議の意味や内容を明らかにするよう努めているように思えます。
そのため両者の提出書面は、相手方への反論や自己の主張が明確となり裁判官にもその主張が理解出来やすいように作成される必要があると感じました。
今回の裁判は2つの法律が係るため、細かな法律的な論争が中心になりがちです。
しかしそれでは一部の人にしか理解できない裁判になってしまう可能性があります。
それは原告側の求めることではありません。
この争点は、違憲とも言える法律の不備であるとともに 裁量権を持つ自治体(介護保険保険者=岡山市)の市民への不適切な対応であり決定です。
原告が裁判に訴えなければならなかったこの原点に絶えず戻りながら、現在の法廷での論争との距離を計らなければならないのでしょう。
裁判の論点や主張を誰の目にも明らかにすることは予想以上に困難が伴うように思います。
しかしそのことをなんとか成し遂げるのが原告側の役目だと思います。
浅田さんを支援する会合に友人に誘われたのは去年の4月でした。
すでに1年3ヶ月が経過しました。
そして、今いよいよこの裁判の山場を迎えようとしてると感じています。
全国でこの裁判が注目されています。
かつて岡山では、朝日訴訟という社会福祉史上に残る裁判が行われました。
その裁判は その後の日本の社会福祉に大きな影響を与えました。
浅田訴訟も そのような歴史的役割を果たすことが期待されています。
これからの口頭弁論を注目していただきたいと思います。
今まで記事は、このブログのカテゴリー「障がい者を65歳で差別するな浅田訴訟」に書いています。
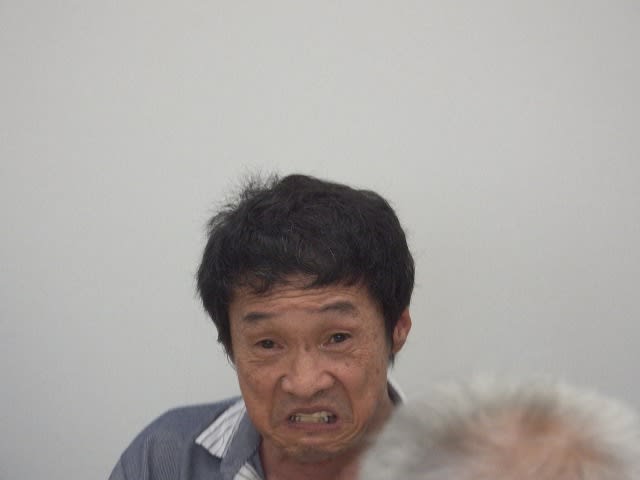
裁判の意義については原告訴訟代理人、柿崎弘行弁護士による意見陳述書(平成25年11月17日)に書かれています。
その要約版より引用します。(再掲載)
裁判の第一の意義ー障害福祉の実態を明らかにすることー
1.障害福祉と介護保険は、目的も内容も違う制度です。年齢だけを見て介護保険に切り替えろというのは不適切です。自己負担についても大きな違いがあります。障害者を年齢で区別し、高齢の障害者により大きな経済的負担を負わせるのは、どう考えてもおかしいのです。
2.障害者自立支援法7条(現在の障害者総合支援法7条)は、「介護保険でカバーできる範囲は、障害者サービスを提供しない」としています。これが、年齢だけを見て機械的に介護保険の利用を強制するという意味であれば、憲法14条と憲法25条に違反します。
3.むしろ、障害者自立支援法22条は、障害者の特性や生活状況など様々な事情を考えることを求めています。障害福祉と全く同じ条件で介護保険を利用できる場合だけ介護保険にするというのが、この法律の本当の意味ではないでしょうか。今回の岡山市の取り扱いは憲法違反です。仮に、憲法の話は脇に置くとしても、行政機関としてきちんと考えていなかったこと自体が違法です。
裁判の第二の意義ー岡山市の非人道的態度を問うことー
1.当初の決定はサービスの全面打ち切りでしたが、何度も取り消しや変更がなされ、最終的には相当の部分が支給されました。岡山市は、なぜ最初から一部支給の決定をしなかったのでしょうか。
2.浅田さんは、サービスを全面的に打ち切られたために、床に倒れて起き上がれなくなり、下痢で大便を漏らしたり、たいへん苦しみました。後から取り消しや変更がされても、時間を遡ってサービスを受けることはできません。浅田さんの苦しみがなかったことにはならないのです。
3.岡山市は、障害福祉より介護保険の方が市町村の財政的負担が軽いために、65歳を迎えた障害者に介護保険への切り替えを求めているのです。浅田さんは、見せしめのように、サービスを打ち切られました。岡山市だけでなく、全国各地で同じような問題が起こりつつあります。全国の障害者が、今後二度と、浅田さんと同じような苦しみをあじわうことのないようにしなければなりません。
終わりに
2010年、障害者自立支援法違憲訴訟訴訟原告団・弁護団と国(厚生労働省)との間で基本合意が成立しました。その中で、障害者自立支援法7条の問題点が指摘されています。岡山市がこの基本合意を十分に理解していれば、今回の事件は起こらなかったはずです。裁判所では、厳格な審理が行われるよう、強く要望します。
以上引用しました。
以下はこのブログの管理人の現在の思いを書きました。
裁判が長引くというのはよくいわれることです。
今まで他の裁判も何度か傍聴していいますがテレビドラマのように原告側弁護士と被告側弁護士が丁々発止とやりあうということはなかったです。
行政訴訟では法廷の場で劇的に進行するということはないといっていいのでしょう。
双方が裁判所や相手側から求められる書面を期日までに提出し、その書面をもとにさらに検討を重ね不明な点を絞っていくという地道な作業のように思えます。
裁判官は両者の意見や釈明を聞きながら方向性を模索し、両者にその方向性に従った書面を提出してもらうことで審議の意味や内容を明らかにするよう努めているように思えます。
そのため両者の提出書面は、相手方への反論や自己の主張が明確となり裁判官にもその主張が理解出来やすいように作成される必要があると感じました。
今回の裁判は2つの法律が係るため、細かな法律的な論争が中心になりがちです。
しかしそれでは一部の人にしか理解できない裁判になってしまう可能性があります。
それは原告側の求めることではありません。
この争点は、違憲とも言える法律の不備であるとともに 裁量権を持つ自治体(介護保険保険者=岡山市)の市民への不適切な対応であり決定です。
原告が裁判に訴えなければならなかったこの原点に絶えず戻りながら、現在の法廷での論争との距離を計らなければならないのでしょう。
裁判の論点や主張を誰の目にも明らかにすることは予想以上に困難が伴うように思います。
しかしそのことをなんとか成し遂げるのが原告側の役目だと思います。
浅田さんを支援する会合に友人に誘われたのは去年の4月でした。
すでに1年3ヶ月が経過しました。
そして、今いよいよこの裁判の山場を迎えようとしてると感じています。
全国でこの裁判が注目されています。
かつて岡山では、朝日訴訟という社会福祉史上に残る裁判が行われました。
その裁判は その後の日本の社会福祉に大きな影響を与えました。
浅田訴訟も そのような歴史的役割を果たすことが期待されています。
これからの口頭弁論を注目していただきたいと思います。
今まで記事は、このブログのカテゴリー「障がい者を65歳で差別するな浅田訴訟」に書いています。