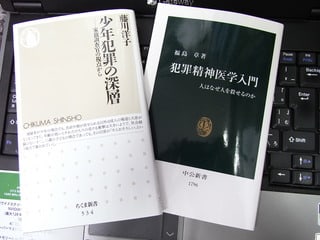歴史館の応接室に続いて旧園長室がある。20畳くらいはありそうだ。
大きな机があり、壁には歴代の園長の写真が掲示されている。
この事務本館に入所者が立ち入ることは厳しく制限されていた。
いわば聖域だった。
園長といえば、保育園や幼稚園の園長を連想してしまうが、
実態は想像を絶した(歴史館のどこにも書かれてはいないが)。
その権限というのは、「専制君主」といっていい。
行政権、警察権、司法権を一手 . . . 本文を読む
簡単に。
厚生労働省が、やっとサンプリング調査を始めたと思ったら、
すぐに大きな問題が出てきた。
厚生年金の支払いが過少になっているという。
給与の申告が少なくなっているケースもあるという。
数十年前の給与額など、わかるはずがない。
少なくとも私にはわからない。
この「消えた年金」、いまだに底が見えぬ。
そして、もっとも頭に来たのが、枡添発言。
「国民の皆様と一緒に、社会保険庁から年金を取り戻し . . . 本文を読む
長島をほぼ横断した時、小さな橋が現れ、その先の入り江に建物が並んでいた。
入り江の先には教会もあった。
青空と澄んだ海、美しい風景だ。
橋を渡り、一番手前の駐車場に車を停めた。
多くの車が停まっている。職員の方の車だろうか。
海岸の道を頻繁に走っているのは工事関係の車だ。
この日も工事関係の方を多く見た。
入り江の中央部分に小高い丘がある。その中腹に古い2階建の建物がある。
外壁を蔦におおわれて . . . 本文を読む
私は岡山の町で18歳まで暮らした。
その間に、ハンセン病について聞いた話はわずかだった。
高校時代に保健体育の教師に長島を訪れたときの話を聞いた。
一緒にスポーツを楽しんだ話だった。
若い患者さんの顔が汗のため化粧が落ちていくシーンにはショックを受けた。
心に重く沈んでいった。
そして、再び生活の大半を岡山で過ごそうと決めたときに、
ようやく少年時代からの心のわだかまりに向き合おうと思った。
. . . 本文を読む
1945年6月29日夜、140機のB29が岡山の街を襲った。
岡山市の中心部は文字通り焦土と化し、死者は1700名余りに上った。
その時代の写真や遺留品が駅前で展示されていた。
入り口正面には、天井に届かんばかりの大きな写真が2枚並んで展示されていた。
米軍が、空爆前と空爆後の写真である。
その写真の精密さには驚く。まるでグーグルの写真と同じだ。
米軍には、専門の写真部隊がいたという。
この写真 . . . 本文を読む
手元に2冊の本がある。
とても刺激的な本である。裁判員になる可能性がある私たちには必読の本かもしれない。
裁判員は重大な犯罪にも関わることになっている。
例えば、秋葉原事件のようなケースも関わるかもしれないのだ。
被害者感情を考えれば極刑という判決が当然と考えてしまいがちだが、
ことはそう簡単ではない。
そのことを根拠を持って教えてくれる本である。
1.「犯罪精神医学入門」 福島 章 中公新 . . . 本文を読む
他者を傷つけるということに関しても考えなくてはならない。
このことは、もちろん許されないことである。
それでも、人は他者を傷つける。
そして、そのことが正当化されることはまずない。
他者を傷つけたものの多く(一部例外はある)は、意識,無意識の違いはあるが
悔やむ日々を送っている。
当然、自己正当化はできるものではない。
では他者を傷つけるということを正当化されることがあるのか。
ご存知のように数 . . . 本文を読む
1885年、第1回ハワイ官民移民945名がハワイに向け横浜港を出発した。
国策移民の始まりである。
移民の背景には国内の経済事情の悪さもあるが、国が海外移民が新しい楽土作り
だという幻想を持たせたことは確かだ。なによりそのことを証明するのが移住者の
出身県の多くが西日本であったこと。当時最も経済の厳しかった東北からの移民は
少ないことがある。
ハワイに続いて、米国本土にも移民は渡ったが、米国への移 . . . 本文を読む
2005年4月25日に起こったJR福知山線脱線転覆事故の被害者と家族の
2年間を追ったドキュメンタリーを観た。
私はこの事故の瞬間は自宅のテレビの前にいた。
第1報は、線路に車が入って衝突事故が起こったという程度だった。
しかし、時間が経過するに従い、とんでもない大事故が起こっていることが
わかってきた。JRの説明は二転三転し、事故の全容の把握ができなかったことを
覚えている。
このドキュメン . . . 本文を読む
NHK BS でドキュメンタリーの優秀賞を放映していた。
上映3本のうち、2本は民放の番組である。
これって、画期的なことではないだろうか。
2作とも、見逃せない内容だった。
「裁判長のお弁当」東海テレビ制作
「私は生きる~JR福知山線事故から2年」毎日放送
「裁判長のお弁当」は、裁判長の職場に初めてテレビが入ったということが
「売り」のドキュメンタリーだ。
何がそこで(裁判所)で行われて . . . 本文を読む
このふたつの言葉が、この事件のキーワードであることは確かなように思える。
わたしたちは、このふたつの言葉の差異を意識しているだろうか。
国語辞典(小学館)によれば、
孤独=ひとりぼっちでさみしいこと。
孤立=ひとりだけで、仲間や助けがないこと。
わたしたちの感覚でも、このふたつの言葉を使いわけているのではないだろうか。
孤独には、さみしさという精神面が強く感じられることに対して、
孤立は、仲間や . . . 本文を読む
テレビのコメンテーターが秋葉原事件の特集の中で、ぽつりと
話したことばが、心に残った。
加害者の成育歴と職歴を放映した後である。
「彼はわれわれがつくった社会で育ったのだね」。
その番組では、加害者と同年代の若者にも取材をしている。
彼らは、「書き込み」については理解できる(50%)という。
そして、年をとることへの不安があるという。
(キャリアアップが出来ない中、年齢を重ねることは自らの市場 . . . 本文を読む
現代の社会関係性の主役は家族ではなく高度に発達したマス情報環境で
ある(「福祉哲学」加藤博史著)。
であるとすれば、「高度に発達したマス情報環境とは、どのようなものか」、
考えていかなくてはならない。
「秋葉原事件」の加害者がどのようなマス情報環境であったのかは、
断片にしか聞こえてこない。
この断片から思考を進めていくことは、推論を重ねることになるので
あまり意味がないと思われる。
「ゲーム脳」 . . . 本文を読む
2008年6月8日(日)、秋葉原で起こった事件について、
考えてみたいと思います。
まず被害を遭われた方々。そしてその家族や友人の方々に
哀悼の意を表したいと思います。
なぜ、あの人が被害にあったのか。なぜ私ではなかったのか。
そして、
加害者が彼であって、なぜ私ではなかったのか。
被害者も加害者も、私自身でありえないとは決していえないのです。
昨日の毎日新聞に(この事件と直接には関係のない記事 . . . 本文を読む
日本社会福祉士会全国大会の初日、阿部志郎先生の基調講演を、
聞かせていただきました。
私は初めてお聞きしました。ゆえに先生のお話がどのようなかたちを
とられるのか、予備知識はありませんでした。
壇上に上がられた先生は、少し間を置いた後に
前置きなしに話し始めました。
「半分こ」の話です。
ふたりの子どもが、ひとつしかないせんべいをどのように分けるか。
「この一枚のおせんべいを二つに割る。これ . . . 本文を読む