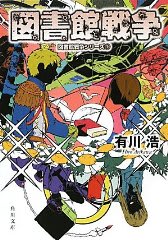京都での2件の歩行者への衝突事故、長距離ツアーバスの高速道路事故。
いずれも多数の死傷者が出てしまった。
車社会が発達し現代生活に欠かせないからといって「仕方がない」で済むことではない。
車は人間が運転する限り、「走る凶器」に変わりはない。
「走る凶器」からいかに身を守るか。
「凶器」は走らないようにすることが一番。
鉄道や路面電車が安全や資源面から交通の中心にすべく研究や運動をしている人々 . . . 本文を読む
『アンデルセン、福祉を語る―女性、子ども、高齢者』 G・エスピンーアンデルセン NTT出版
『子どもの貧困ー日本の不公平を考える』 阿部彩 岩波新書
どちらも2008年発行です。
キーワードは、子どもと女性だと思います。
もう一冊は、『脱原発の市民戦略』上岡直見、岡将男共著 緑風出版
この本はとても重要な資料だと思います。
脱原発の理論武装的な本ですね。
きちんと読むことができれば . . . 本文を読む
認知症を発症している要介護4の父は午前2時頃から覚醒しているのことが多い。
尿漏れで衣服が濡れてしまうので目が覚めるようです。
起きてから窓の開け閉めを繰り返します。いつまでも。
冬でも行います。
着替えを介助しベッドに入ってもらうのですが、父は「寝ぼけた」状態でとても怖い顔です。
私がなにものかわかっていないようです。
本人にとっては、突然暗闇から知らない男が現れて身体を触るわけですから、怒 . . . 本文を読む
主治医のいる総合病院はいつも混んでいます。
もちろん高齢者の方が中心です。
見るとはなしに見ていると足の悪い方が多い。
杖を使っている人も多い。
そして足が細いという印象です。
若い時は、歩くことは当たり前のことと思うけど、
歩行ということは実は大変な動作なのですね。
筋力はもちろんバランスも必要。
歩行には一人一人癖があって、年を重ねれば重ねるほどその癖が目立つようになります。
私が通っ . . . 本文を読む
若年性認知症の当事者・佐藤雅彦さんが支援者前田隆行さんへのメール2通を連載してきました。この回で終了です。
最終回は私たちへのプレゼントといえるものです。
原文のママです。
________________________
不幸にして、認知症になった時のために、どんな準備をすればよいか
1)まず、記憶力に障害を受けるかつ漢字が書けなくなり、昨日どのように過ごしたか思いだせなく、記憶の連続 . . . 本文を読む
2006年4月25日から7年が経過しました。
事故の発生時、テレビ報道が混乱し全容の把握に時間がかかったことを思い出します。
当ブログでも、事故当日から書き始めた79のメモを、「JR西日本福知山線脱線転覆事故」というカテゴリーで分類しています。
このブログは「石井十次」とこの「JR西日本福知山線脱線転覆事故」の二つのカテゴリーが長期にわたる覚えとなっています。
107名が死亡、562名が負傷し . . . 本文を読む
中西麻耶さんのセミヌードカレンダーが評判になっています。
中西さんは、陸上障害クラスT44/F44 100m13秒84(日本記録)、200m28秒52(アジア記録)、走り幅跳び4M96(アジア記録)を持っているアスリートです。購入はこちらのサイトから。
. . . 本文を読む
若年性認知症の当事者である佐藤雅彦さんから介護者へのメッセージです。
原文のママです。
___________________________
介護職にしてもらいたくないこと
1)ごまかしたり、うそをついたりすること
たとえば、奥さんが入院して、施設に預けられているある男性は、夕方になると妻が心配するから「家に帰る」とそわそわする時、奥さんはすでに病院で亡くなられでこられなくなったとき、 . . . 本文を読む
「認知症の人」という表現がどうかと思われている方もいらっしゃると思います。
当ブログでは、著者である佐藤雅彦さんの記述をそのまま掲載させていただきます。
原文ママです。
_________________________
認知症の人とどう接するか
・認知症の人を社会のお荷物とかんがえるたり人間的に劣ると考えなくまた、認知症と言う病気の人とみるのではなく、一人の人格のあるりっぱな大人として接し . . . 本文を読む
狐の日記帳さんのブログでこの本のことを知りました。
全く知らない分野の本なので恐る恐る読み始めました。
設定は荒唐無稽です。
図書館が武装するというのです。
なぜ武装するか。
もちろん、財産である書籍を守るためです。
その書籍を守るとはどういうことか。
著者は実在の図書館で以下の文章が掲示されていることを見つけます。
実際は夫の手柄だそうですが。
_____________
図書館の自由に関 . . . 本文を読む
連載は7回になりました
原文のままです。
この連載は佐藤様彦さんご本人と支援者前田隆行さんの了解を得て実名にて紹介させていただいています。
___________________________
認知症本人をサポートする上の注意点。
1.本人の選択権を奪わないでください。
食べもとでも、本人に2つ示して、本人に選んでもらい、本人に考えてもらうことが、脳のリハビリになり、いつ本人の意向 . . . 本文を読む
人がいきいきと生きていくことの大切さを佐藤さんが書いています。
メール第1信より転載します。
原文のままです。
_________________________
人がいきいきと生きていくためには
いきいきと生きるためには、衣食住が足りているだけでは十分ではありません。
社会の一員として、何かの役割をもちたい。
社会の一員と認められたく、仕事がしたい。
認知症になっても、仕事を持って働き . . . 本文を読む
佐藤雅彦さんは、若年性認知症を発症されてから後も、人生の意味について深く考察されています。
美しいものを愛することがあることの意味が書かれています。
自然や芸術そして宗教が私たちに与えるものについて改めて考えさせられます。
原文のままです。
___________________________________
生きている意味
私は配送途中で地図を見て、配送先商品を届けナの地、車に戻る道 . . . 本文を読む
津波が来る。釜石小の子どもたちはこうして逃げた。
そして、助かった。
子どもたちは自分で考え、臨機応変に対応し、危機を脱した。
朝日新聞4月17日付記事より考える。
この記事は防災教育がいかに大切なものが端的に教えてくれる。
津波が襲来した場合、生き残るためには「津波でんでんこ」を実践するしかない。
「津波でんでんこ」は、一人ひとりがてんでんばらばらに逃げること。
バラバラに逃げるためには、一 . . . 本文を読む
2005年10月に若年性認知症の診断告知を受けた佐藤雅彦さんのその後の日々をメール第2信より転載します。
原文のままです。
____________________________________
退職と将来の不安の中で
診断告知後、すぐに病気休暇に入った私は、認知症に関する本を買ったり、図書館で探して読みふけったりしました。
そこで「多くの場合、6年から10年で全介護状態になる」と言う記 . . . 本文を読む