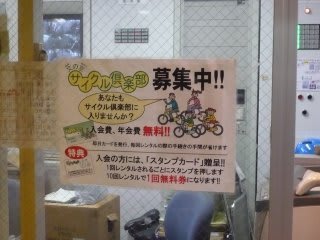今日も快晴で涼しい一日。まさに絶好の行楽日和です。今日も東京自転車巡りにお付き合いください。
私の自転車の旅は、ぎりぎりまで行く先を決めません。貸し自転車場へ向かう地下鉄の中で、なんとなく東西南北の方向性だけを決めて、適当に出発し、途中で気が向いたり縁が導くままに神社やお寺を巡るという旅なのです。
今日は自転車を借りる前は、隅田川を越えて東へ向かおうと決めたはずだったのに、突然五色不動の一つである目白不動を先に見に行こうと思い立って、全く逆の西へと向かいました。
目白不動は、宿坂という坂の途中にある金乗院慈眼寺(こんじょういん・じげんじ)というお寺の中に鎮座しています。このお寺の墓地には、槍術の創始者といわれる丸橋忠弥のお墓もありました。探せば有名人はどこにでもいるようです。
これで、目赤、目黄、目白と三つの不動さんを見て歩きました。残りは二つです。


※ ※ ※ ※
続いては坂を下って氷川神社へちょっとご挨拶。江戸も含まれる武蔵の国の一宮は大宮市にある氷川神社。そのため東京にはそこかしこに氷川神社を分霊した神社があるのですが、これはその中でも歴史のある神社です。
もっとも、東京大空襲で焼けてしまったので今の社殿は昭和29年に再建されたものだそうです。

さて、ここでお参りが終わったところ、近くで地図を見ていたお爺さんに声をかけられました。写真の左の狛犬の陰にちらっと見えている方です。
「すみません、ここからだとJRは高田馬場と目白とどちらが近いでしょうかね?駅が持っている地図からはみ出ちゃって分からなくなっちゃって」「ちょうど地図を持っているから見てみましょう。うーん、高田馬場の方が少し近いみたいですよ」
「そうですか、すみません」
「お寺を巡ってらっしゃるのですか?」
「ええ、今度地区の老人会をつれてこようと思って、トイレだとか駅を下見するのに歩いていたら疲れちゃいました」
聞けば、もう82歳になるこの方は、50歳を過ぎたときから思い立って、歴史や絵の勉強を続けてきたのだそう。絵などは、東京都展覧会で参議院議長賞まで取ってしまったのだそう。
「へえ、きっかけは何だったのですか?」
「きっかけはねえ、伊能忠敬ですよ。彼が測量を始めたのが50歳からでしょ?それを知ってから、よーし、50歳になったらいろいろなことを始めようと思いましてね。絵も随分書いたんだけど、都展で賞を取ったところで眼をやられましてね、視力が落ちちゃった。それからは今度は歴史的なものを見て歩くようになりました」
「私も神社を巡ったり、富士講の富士塚を見て歩いています」
「富士塚?それじゃ庚申塚は見て歩くのはどうですか」
「庚申塚も見ますが、あまり詳しくはありません」
「庚申塚はね、感心なことに作ったときの年号と日付、それにどこの誰が作ったか、ということを石に刻むんですよ。それにお金をかける作り方とお金をかけずに作った様子が見ていると分かってくるので、それを作った庚申講がお金持ちか貧乏かも分かるんですよ」
「そうですか、じゃ今度から気をつけてみてみることにします」
「それがいいよ。あなたはまだ若いから、これから一生懸命見ると眼力がつきますよ」
『眼力』という単語を久々に聞きました。しかもなんとこの方、最近前立腺ガンが分かって調べてみると骨に転移までしてしまっているのだとか。
「だから家になんているとしょぼけっちゃうし、歩いている方がいいと思ってね。あと5年くらいは生きてやろうと思ってますよ、はっはっは…」
この方から見ると私などはまさに若造に過ぎませんが、いつ初めても何かを見続ける、やり続けることが大事なのですね。
神社の境内で出会うなんて、これも神様の導きなのでしょうか。
私の自転車の旅は、ぎりぎりまで行く先を決めません。貸し自転車場へ向かう地下鉄の中で、なんとなく東西南北の方向性だけを決めて、適当に出発し、途中で気が向いたり縁が導くままに神社やお寺を巡るという旅なのです。
今日は自転車を借りる前は、隅田川を越えて東へ向かおうと決めたはずだったのに、突然五色不動の一つである目白不動を先に見に行こうと思い立って、全く逆の西へと向かいました。
目白不動は、宿坂という坂の途中にある金乗院慈眼寺(こんじょういん・じげんじ)というお寺の中に鎮座しています。このお寺の墓地には、槍術の創始者といわれる丸橋忠弥のお墓もありました。探せば有名人はどこにでもいるようです。
これで、目赤、目黄、目白と三つの不動さんを見て歩きました。残りは二つです。


※ ※ ※ ※
続いては坂を下って氷川神社へちょっとご挨拶。江戸も含まれる武蔵の国の一宮は大宮市にある氷川神社。そのため東京にはそこかしこに氷川神社を分霊した神社があるのですが、これはその中でも歴史のある神社です。
もっとも、東京大空襲で焼けてしまったので今の社殿は昭和29年に再建されたものだそうです。

さて、ここでお参りが終わったところ、近くで地図を見ていたお爺さんに声をかけられました。写真の左の狛犬の陰にちらっと見えている方です。
「すみません、ここからだとJRは高田馬場と目白とどちらが近いでしょうかね?駅が持っている地図からはみ出ちゃって分からなくなっちゃって」「ちょうど地図を持っているから見てみましょう。うーん、高田馬場の方が少し近いみたいですよ」
「そうですか、すみません」
「お寺を巡ってらっしゃるのですか?」
「ええ、今度地区の老人会をつれてこようと思って、トイレだとか駅を下見するのに歩いていたら疲れちゃいました」
聞けば、もう82歳になるこの方は、50歳を過ぎたときから思い立って、歴史や絵の勉強を続けてきたのだそう。絵などは、東京都展覧会で参議院議長賞まで取ってしまったのだそう。
「へえ、きっかけは何だったのですか?」
「きっかけはねえ、伊能忠敬ですよ。彼が測量を始めたのが50歳からでしょ?それを知ってから、よーし、50歳になったらいろいろなことを始めようと思いましてね。絵も随分書いたんだけど、都展で賞を取ったところで眼をやられましてね、視力が落ちちゃった。それからは今度は歴史的なものを見て歩くようになりました」
「私も神社を巡ったり、富士講の富士塚を見て歩いています」
「富士塚?それじゃ庚申塚は見て歩くのはどうですか」
「庚申塚も見ますが、あまり詳しくはありません」
「庚申塚はね、感心なことに作ったときの年号と日付、それにどこの誰が作ったか、ということを石に刻むんですよ。それにお金をかける作り方とお金をかけずに作った様子が見ていると分かってくるので、それを作った庚申講がお金持ちか貧乏かも分かるんですよ」
「そうですか、じゃ今度から気をつけてみてみることにします」
「それがいいよ。あなたはまだ若いから、これから一生懸命見ると眼力がつきますよ」
『眼力』という単語を久々に聞きました。しかもなんとこの方、最近前立腺ガンが分かって調べてみると骨に転移までしてしまっているのだとか。
「だから家になんているとしょぼけっちゃうし、歩いている方がいいと思ってね。あと5年くらいは生きてやろうと思ってますよ、はっはっは…」
この方から見ると私などはまさに若造に過ぎませんが、いつ初めても何かを見続ける、やり続けることが大事なのですね。
神社の境内で出会うなんて、これも神様の導きなのでしょうか。