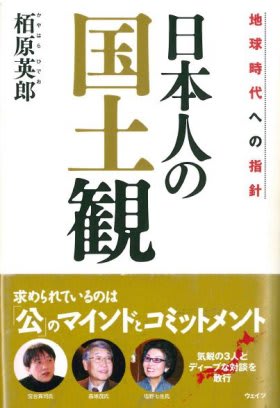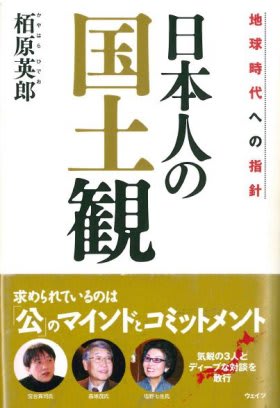
旧国土庁で、四全総をはじめとする国土計画に携わられた栢原英郎さんが、日本人の国土に対する考え方について考察された「日本人の国土観」という本を読みました。
前段はこれまでの国土計画の歴史と、国土観からくる地域の発展モデルなどの紹介がありましたが、興味深かったのは、国土観についての三名の方との対談の部分。
国土計画分野に指導的な立場で各種審議会や委員会でご活躍されている森地茂先生、「ローマ人の物語」のなかでローマ人が作り上げた国づくりとインフラについて暖かいまなざしをもって現代のわれわれに伝えてくれた小説家の塩野七海さん、そして現代の若者の生態を鋭い視点で切り取る社会学者の宮台慎司さんの三人です。
切り口の異なるお三方と栢原さんとの対談には興味深い対話が多くありました。
◆
まずは森地先生から。
森地先生は、カナダ人が作った一風変わった洛星中学・高校へ通われて非常に印象的な教育を受けたと述懐されています。
なかでも修学旅行は一般的に皆東京へ行ったときに、専用列車で二十九時間かけて北海道まで行ったそうです。そしてあまりに違う風景、美しさ、スケールの違いなどにショックを受けて、それいら地域というものに興味が湧き、全国を旅して結果としてご自身の国土観が醸成されたとおっしゃいます。
森地「…ところで、北海道は不思議で、京都も北海道も両方とも全体的に良いイメージがものすごく高い。少なくとも全国的に、誰もが好きといっていいでしょう。つまり、京都とか北海道というと、あるイメージが湧く。それを最初から持っているのはものすごいメリットです。
あと国内では瀬戸内海とか、富士山とかありますが、北海道と京都は、特別にそういう意味で有利な位置にいます。
ところが不思議なことに、京都のイメージはたかだか六キロ四方の中で、東山と嵯峨野が違うだの、春と冬は違うだの、漬け物はどっちがうまいだの、ものすごく多重にイメージを作ろうとしてきました。
ところが北海道は不思議なところで、南北の距離が東京から明石くらいある。納沙布から積丹、襟裳岬から納沙布、稚内、それくらいの距離のところなのに、どこへ行っても同じイメージです。どこへ行ってもイカとホタテと広大な農地で、多様性を売ろうという意識があまり感じられません。どこへ行っても『うちは北海道』(笑)。これはとても不思議なことです。要するに、道内の地域間が醸成されていないように見える。これをなんとかしないと、地域が色々な意味で頑張っていかないだろうと思います」
栢原「自分たちの地域をどう見るのか、どう評価するかという地域の国土観や地域観は、国土計画や地域計画づくりのみならず、個別のインフラの整備に当たっても益々重要な要素になると考えています。例えば北海道で政策をまとめると必ず『フロンティア』という言葉が入ります。内容を突き詰めると結局は『未利用の土地がいっぱいあります』ということだったりする。空き地を売り出す不動産屋の広告の印象があります。他人のイメージで自らの土地を見ており、自分たちの地域を自分の目できちんと見ていないのではないかと感じます。これでは良い地域計画が出来るとは思えません」
森地「…大学の先生も財界の人も、北海道とは近いからナホトカとか樺太との関係で地域づくりをしようとおっしゃるんです。地政学の問題を距離だけで捉えるなんて明らかに間違っている。つまり、台湾の人がなぜ北海道にたくさん来るか。自分たちの住んでいるところと違うから来るのです。地域戦略は『近い』ということ以外にたくさんあるのに、北海道のほとんどの人は『近い』ということだけに着目した戦略を言うのですが、これは不思議です」
◆
続いて塩野七海さん。多くの歴史家が、いつ何がつくられたか、ということを記述するのに対して、塩野さんは「なぜそれが作られたのか」ということに強く興味をもったと言います。
栢野「一般の市民もインフラの大切さを理解していたのですか」
塩野「ローマ法では私有軒が非常に重視されたけれど、インフラのための用地について何か問題が起こったという記録はありません。そうでなければあんなに真っ直ぐに道が通り、あんなに真っ直ぐに水道橋が通るはずがない。こういうのを公共心と言うのですね」
栢原「市民の公共心が高かったということですか」
塩野「インフラの目的がはっきりしていたことも、理由の一つでしょうね。道路や水道は絶対に必要だから作ったのであって、決して政治家のために作ったものじゃないということがはっきりしているからです。現代の指導者よりはるかに強大な権力を持っていたにもかかわらず、古代ローマ帝国で『自分の別荘の近くに街道を通せ』なんて言った人は一人もいない(笑)。
それからもう一つ、整備の考え方が公平なのです。水道の場合には、自分の家に挽くときは金を払う。甕(かめ)を下げて街角の水汲み場から汲んでくる場合は無料です。さらにすごいのは、水道の優先順位です。渇水期に何を優先させるかというと、街角の公共水道口です。その次に優先されるのが公衆浴場。工程の宮殿なんぞは後回しです」
◆
最後は社会学者の宮台慎司さん。
栢原「国土計画などをつくるときに感じるのは、地域に入ってよく聞くと、この地域は遅れているからもっと手当てが必要だ、と思っているのは県庁や役場、商工会議所の人だけで、住民は日ごろの生活で満足している。そういう傾向が強くなっている中で、身近ではない国土観だとか国土計画を作ることの難しさを感じます」
宮台「悪循環ですね。かつて丸山眞男が『日本人には作為の契機が乏しい』と言いました。『社会とは然るべく作り出されたものだから、ちゃんとメンテナンスしないと駄目になる』という感覚がなく、山や川のように在るものだと思っていることです。『自覚的に選択して維持しないと社会が回らない』という感覚が日本人に乏しいのは事実です」
栢原「属している社会に対するコミットメント(=関わっていくこと)がほとんどないということが問題です」
宮台「日本で『公共に貢献して行こう』と言うと、『何をやってもこの国はダメ。多少崩壊速度が遅くなる程度。そんな無駄なことをやってどうするんだ』という揶揄が必ず出てきます。でもそれが一体どうしたというのでしょうか。
『どうせ崩壊するのに何やってんだよ』と言う揶揄は合理的に見えますが、それは『お前どうせ死ぬのに何やってんだよ』と言う揶揄と同じです。そうした揶揄をするヤツ自体がのうのうと生きているのですから、あまり大きな口を叩くべきではないんです」
◆
もちろん対談はもっと長いもので、目からウロコの表現も多々あるのですが、国土計画に関わって興味深いところだけを抜き出してみました。
普段あまり考えない国土のあり様や国土観ということですが、もう一度私たちの国の国土というものについて考えてみてはいかがでしょうか。
誰かエライ人に任せてしまって自分は考えないというのではいろいろなものが見えなくなってしまいそうですよ。