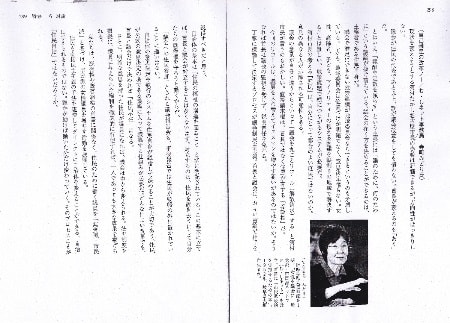秋晴れの昨日、9月19日。
東京の明治公園で「さようなら原発5万人集会」が開催されました。
東京の集会と連動して、全国でも反原発集会やデモなどのイベントがあり、
名古屋でも2000人が集まったそうです。
【youtube】9・19「さようなら原発集会」~6万人が参加
名古屋の集会には、わが家から宣伝カーのみ参加(笑)、
集会アピールを友人の坂東弘美さんが読み上げた、とのこと。
坂東さんのブログに乗っている集会アピールを転載させていただきます。
「さよなら原発1000万人アクション」HP
応援クリック してね
してね 


本文中の写真をクリックすると拡大します。
今朝の新聞各紙には、脱原発集会の様子が、大小の記事で掲載されました。
最後まで読んでくださってありがとう
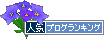
 クリックを
クリックを
 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね

東京の明治公園で「さようなら原発5万人集会」が開催されました。
東京の集会と連動して、全国でも反原発集会やデモなどのイベントがあり、
名古屋でも2000人が集まったそうです。
【youtube】9・19「さようなら原発集会」~6万人が参加
| 脱原発集会:「さよなら原発」訴え行進 3県から名古屋に2000人集結 /愛知 ◇東京の大規模集会に協調 東日本大震災から半年が過ぎたのを機に、速やかな脱原発を訴えようと、名古屋市中区栄の白川公園で19日、「さよなら原発1000万人アクションinあいち」が開かれた。この日、東京都新宿区で大規模な脱原発集会が開かれるのに合わせ、東海3県で環境問題や平和運動、子育て支援などに取り組む団体・個人による実行委員会が主催し、約2000人が集まった。 集会では、静岡県や福井県、福島県で脱原発運動に関わる人々のメッセージを読み上げた後、「次の世代に命をつなげるために原発のない未来をみんなでつくろう」とのアピールを採択した。 続いて横断幕やプラカードを持った参加者が約1時間、周辺をデモ行進し「すべての原発を止めよう」「人を犠牲にするエネルギーはもうやめよう」と呼び掛けた。 参加した名古屋市西区の二上巌さん(70)は「子孫のためにこの世代で原発を停止させなければと、いてもたってもいられなくなった。多くの人が声を上げてほしい」。同市北区の学童保育指導員の女性(50)は「人間がつくった原発は人間の手でなくすしかない。名古屋から自然エネルギーへの転換を訴えたい」と話した。 実行委員の一人、安楽知子さん(49)は「福島第1原発事故をきっかけに脱原発への関心が確実に広がっている。原発は速やかにやめよう、とみんなで新政権に求めたい」と話した。【高木香奈】 毎日新聞 2011年9月20日 |
名古屋の集会には、わが家から宣伝カーのみ参加(笑)、
集会アピールを友人の坂東弘美さんが読み上げた、とのこと。
坂東さんのブログに乗っている集会アピールを転載させていただきます。
| 名古屋2000人、東京6万人デモ(2011年09月19日 がま口塾) さよなら原発パレード」集会&パレードin愛知は2000人で問題なく終了。猛暑。東京は6万人で福島からも約500人が訪れたそうですが、NHKの夜7時のニュースでは1ミリも報道しませんでした。6時台でやったのかしら? こちらのローカル局では2局ほどチラッと放送したようです。2000人のデモや6万人のデモが大々的に報道されないのは、不思議でたまりません。(後記:さすがにNHKもTV朝日、TBSも全国報道した) 東京で経産省ハンスト中の関口詩織さんからの電話アピールもあって、迫力満点。私は実行委員ではないのだけど、「集会アピール文」を読めと言われて、大きな声で頑張りました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(中略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ <9.19さよなら原発1000万人アクションinあいち> 集会アピール 3月11日の東北地方太平洋沖地震の発生から半年余りが経ちました。被災地では、今も4千人を超える方の行方が分からないままですが、一方で復興に向けた取り組みも少しずつ始まっています。 しかし、大事故を起こした福島第一原子力発電所では、今なお数千人の作業員の方が、日々被ばくを強いられながら、事故の収束作業にあたっています。原発事故は、まだ終わってはいません。 環境にまきちらされた放射能は、放射性セシウムだけで広島原爆168個分と言われ、福島の大地や海だけでなく、日本全土に降り注ぎました。チェルノブイリ原発事故の時に強制移住の対象となった1平方メートル当り55万5千ベクレルを超えた地域の面積は、琵琶湖の1.2倍にも達し、現在も数十万人の住民が、何の避難の手だても与えられずに留めおかれています。更に、下水汚泥やガレキ、腐葉土やリサイクル堆肥など、既に二次汚染、三次汚染の問題が深刻になっています。私たちはこれから、終わりのない放射能汚染の時代を生きていかねばならなくなったのです。 この「原発震災」は決して天災などではありません。国策の名の下で、原発に対する国民の批判や懸念をお金と力で押さえ込み、利益追求のために地震列島に54基もの原発を建設してきた国と電力会社、原子力産業の責任であることは明らかです。 この半年の間、東京電力をはじめ国や御用学者の楽観的な判断はことごとく裏切られ、その無力さ、無能さを国民の前にさらけ出しました。にも関わらず、その責任をとることも、それを恥じることもなく、いまだに原子力行政を取りしきり、福島原発事故の真の原因を隠蔽しようとしています。そして、地元の不安を解消できず既に8割が停止している全国の原発に対して、再び根拠のないストレステストで安全のお墨付きを与え、運転再開を急ごうとしているのです。 原発事故の被害の広大さ、深刻さを目の当たりにし、放射能でふるさとを捨てざるをえなくなった人びとの痛みに触れてもなお、原発に固執する国は、本当に国民を守る気があるのでしょうか。 この夏、あれだけ大仰な電力危機キャンペーンが展開されたにも関わらず、結局、どこにも停電は起きませんでした。原発がなくてもやって行けることが明らかになったのです。過剰な電気のために原発が必要だと言いつのることは、もはや無意味です。 原発のウソは、もうたくさんです。 原発がなくても、私たちは豊かに暮らせる知恵をもっています。 子どもたちにこれ以上被ばくの危険と原子力の負の遺産を押し付けたくはありません。 次の世代にいのちをつなげていくために、「原発のない未来」を皆で選びとりましょう。 私たちは今日ここに集い、野田新総理に対して速やかな脱原発政策への転換を求めるとともに、改めて「原発はいらない」という思いを共有し、ここに原発との決別を宣言します。 「さよなら、原発!」 2011年9月19日 9.19さよなら原発1000万人アクションinあいち 参加者一同 |
「さよなら原発1000万人アクション」HP
応援クリック



本文中の写真をクリックすると拡大します。
今朝の新聞各紙には、脱原発集会の様子が、大小の記事で掲載されました。
| 2011年9月20日(火)付「天声人語」 朝日新聞 41年前のイタリア映画「ひまわり」が再上映されると聞いて試写を見た。ご存じ、戦争から還(かえ)らぬ夫を捜し、若妻が旧ソ連を訪ねる悲話である。切ない調べが流れるタイトルバック。風にそよぐヒマワリ畑を、カメラはゆっくり左に動いていく▼地平線に至る黄色の海は、ウクライナで撮影されたという。花は500年前、北米から欧州に渡り、油の原料として広まった。最大の産地が旧ソ連で、映画には異郷を語る景色として登場する▼チェルノブイリ原発事故の汚染域にも、菜種と共に植えられた。土壌の放射能が油に移りにくいためだ。ただ除染の力は定かでなく、福島で実験した農水省の判定は「ほぼ効果なし」。根を深く張るので、地表近くの放射性物質は吸収しづらいらしい▼除染の早道は表土の除去だ。4センチまで削ると、セシウムの75%が除かれたという。森口祐一東大教授の試算では、除染対象の面積は最大で福島県の7分の1にもなる。気が遠くなる労力と費用に、改めて原発事故の罪深さを思う▼昨日、東京での「さようなら原発」の集会と行進には、大江健三郎さんらの呼びかけで大勢が参加した。壇上から作家の落合恵子さんが訴えたように、平仮名しか読めぬ子が「ほうしゃのうこないで」とおびえる現実、捨て置けない▼孫の将来を案じてか、敬老の日を脱原発にあてたお年寄りも多かった。大切な誰かを本気で守ろうと思えば、人は街に繰り出す。黄色を身につけた群衆が、波打つヒマワリ畑に重なった。 |
| 大江健三郎さんら脱原発訴え 都心で6万人参加デモ 毎日新聞 2011年9月20日 朝日新聞 脱原発を訴える「さようなら原発集会」が19日、東京・明治公園で開かれた。ノーベル賞作家の大江健三郎さんらが呼びかけた。主催者側によると、全国から約6万人が参加し、東京電力福島第一原発の事故に関連した集会では、最大規模になったという。 集会では大江さんのほか、経済評論家の内橋克人さんや作家の落合恵子さんらが登壇。大江さんは「原子力は荒廃と犠牲を伴う。私らは原発に抵抗する意志を持っているということを政党の幹部に知らせる必要がある」と呼びかけた。 参加者は集会後、のぼりやプラカードを手に渋谷や新宿の繁華街を3コースに分かれてデモ行進。7歳の娘と初参加したという都内の女性(49)は「原発に無関心で無知だったことを反省した。子どもの世代に、原発に依存しない社会を残したい」と話した。 集会は脱原発への政策転換を求める署名運動「さようなら原発1000万人アクション」の一環。原水爆禁止日本国民会議(原水禁)などが支え、これまでに100万人を超える署名を集めたという。 ◇ 名古屋市中心部でも19日、「脱原発」を訴える集会とデモがあり、約2千人(主催者発表)が参加した。 東日本大震災後半年にあわせ、ノーベル賞作家の大江健三郎さんらが全国で呼びかける「さよなら原発1千万人アクション」の一環として、東海地方の実行委員会が同市でも企画した。参加者らは「原発さようなら」などと声を合わせ、中区の白川公園から東区の中部電力本店まで歩いた。 インターネットで開催を知った北区の会社員田中秀之さん(47)はデモ初参加。「最初は少し怖かったが、いろいろな人が参加していて心強かった。デモだけで終わらず、考え続けたい」と話した。(畑宗太郎) ◇ 九州各地でも連帯の声を上げようと、集会やデモがあった。 福岡市博多区の公園で開かれた集会には、主催者によると、労組や市民グループを中心に約千人が参加した。福島市から福岡県福津市に娘と避難している主婦宇野朗子(さえこ)さん(39)もマイクを握った。 原発事故から半年。影響を過小評価する政府などの発表から、福島から避難できずにいる人もおり、「コミュニティーが引き裂かれている」と訴えた。さらに「除染して復興を」という掛け声のもとで「被曝(ひばく)の危険を伴う除染作業に留め置かれた住民が駆り出されようとしている」と指摘。「福島の現実を見つめ、二度と繰り返してはならないと決意しましょう」と呼びかけた。参加者は集会後、繁華街の中洲から天神を経て福岡市中央区の九州電力本社まで約2キロを「原発はいらない」などと声を上げながら歩いた。 長崎市でも集会があり、主催者によると約600人が集まった。脱原発を願う歌を歌い、被爆者団体や労組の代表が思いを述べた。 |
さようなら原発5万人集会(毎日新聞,写真特集) 東京電力福島第1原発事故を受け、原発依存からの脱却を訴える「さようなら原発5万人集会」が19日、東京都新宿区の明治公園で開かれた。集会やパレードには主催者発表で約6万人が参加。原発事故後では、最大規模とみられる。 原水爆禁止日本国民会議(原水禁)や有識者らで構成する「さようなら原発1000万人アクション」主催。呼びかけ人の一人で作家の大江健三郎さん(76)は「原子力のエネルギーは必ず荒廃と犠牲を伴う」と語った。 参加した俳優の山本太郎さん(36)は「今の日本の政治は一人の命や安全を無視している」と脱原発を訴え、参加者とともに「原発反対、子供を守れ」とシュプレヒコールを上げた。その後、参加者はプラカードや旗を掲げながら、明治公園から新宿や原宿など3コースに分かれて約2~4キロをパレードした。 警視庁によると、集会やパレードには約3万人が参加した。【長野宏美、山田奈緒】 2011年9月19日 毎日新聞 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 脱原発:東京で大規模集会 避難者も叫び ◇日本全体で考えて/まだ隠しているのでは/「安全」うそだった 東京都内で19日午後開かれた原発依存からの脱却を求める「さようなら原発5万人集会」やパレードには多くの市民が参加した。故郷の福島を離れて避難している人や、事故をきっかけに初めて問題意識を持った人も目立った。【長野宏美、山田奈緒】 福島県南相馬市を離れ、川崎市に妻と娘、孫の4人で避難している元教師の山崎健一さん(65)は「福島に暮らしている人以外にも、原発問題にもっともっと関心を持ってほしい。原発政策、脱原発を日本全体で考えてほしい」との思いで集会に参加した。南相馬に戻りたいが「1歳の孫を思うと、除染が完全に終わらない限り安心して暮らせないので戻れない」と訴える。 福島に残っている消防士の娘婿の内部被ばくも心配という。「この年で故郷を追われて暮らすなんて考えたこともなかった。不安だらけで悲しいが何か行動しなければ何も変わらない」と話し、パレードに出発した。 同県飯舘村から避難し、福島市の借り上げ住宅で暮らす女性(40)もバスで東京に駆け付け、パレードに参加。飯舘村で生まれ育ったが、第1原発のことは「小学生か中学生のころに社会科見学で行ったことがあるが、その後の日常生活で意識することは全然なかった」と振り返る。 原発事故後、夫と一緒に勤めていた村内の会社を「100%安全と言い切れない場所では働けない」と夫婦そろって退社。「原発に無関心だった自分への戒めの意味もあってデモに参加した。悔しさをぶつける場所はどこにもないが、せめて今日は大声で『原発はもういらない』と叫びたい」と話した。 同県郡山市から近所の主婦仲間と訪れた女性(72)は「街から子供の姿が消えた。公園や校庭に子供の元気な声が響く街に戻ってほしい」と参加。「国も東電も信じられない。都合の悪い情報をまだ隠しているのではないかと思える。こんなにも大勢の人が集まったのは、不信感の表れだと思う」と話した。 一方、東京都練馬区のパート、小川美樹さん(40)は「行動しないのが一番悪い」と思い、初めて参加。実家は静岡県富士市で浜岡原発は身近な問題。3月11日以降「原発は安全というのはうそだった」と不信感を募らせた。 埼玉県戸田市に住む妹が6月に女児を出産したが、外で遊ばせることにも不安を感じている。「子供の将来を考えると、原発を止めてほしい。同じ思いの人がたくさんいるのを見て、止められるんじゃないかと思った」と話した。 毎日新聞 2011年9月20日 |
| 脱原発6万人集会 2011年9月20日 東京新聞 脱原発を目指して作家の大江健三郎さんらが呼び掛けた「さようなら原発五万人集会」が十九日、東京・明治公園で開かれ、参加した約六万人(主催者発表)が原発依存社会からの脱却を訴えた。集会で、大江さんが「私らには民主主義の集会や市民のデモしかない。しっかりやりましょう」と呼び掛けると、会場からは地鳴りのような拍手が湧き起こった。 作家の落合恵子さんは参加者に「あなたたちに会えたきっかけを考えると腹立たしくてならない」と語り掛けた。その上で「放射性廃棄物の処理能力もない人間が、原発を持つべきでない」と原発不要論を唱えた。 ゲスト参加した俳優の山本太郎さんがあいさつで「すごい…すごい人ですね」と切り出すなど、会場に入りきらないほどの人が集まった。集会後は福島県民らを先頭に「再稼働させるな」「子どもたちを守ろう」とシュプレヒコールを上げ、都心を練り歩いた。 大江さんらは東京電力福島第一原発事故を受け、来年三月までに脱原発を求める一千万人分の署名を政府と国会に提出する計画。主催者によると、署名は現在約百万人に達しているという。 集会は原水爆禁止日本国民会議(原水禁)が中心となって開催。警視庁は参加者を三万人弱としている。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- できることから行動を 福島からの参加者「訴え継続必要」 2011年9月20日 東京新聞 作家大江健三郎さんらの呼び掛けで十九日、東京・明治公園で開かれた「さようなら原発五万人集会」。東京電力福島第一原発事故の影響に苦しむ福島の人たちも加わり、集まった人々は「原発はいらない」と大きな声を上げた。次世代を思い、子連れで都内をデモする人も。「脱原発」の思いは大きなうねりとなって広がった。 集会には、福島県からも多くの人が駆けつけた。 福島市でパン店を経営しながら市民運動をしている橋本敬子さん(42)は、福島の地名が入った旗を持ち会場入りすると拍手で迎えられた。「私たちだけが闘っているんじゃないんだ」と感じ入った様子。これまで県内でデモをする機会は少なかったという。 また、飯舘村の会社員小暮俊和さん(55)は「東京で集会をするのは全国へのアピールになる。大勢集まるのはいい」。一方で、「村の人は五年、十年では忘れることができないが、十年後にこれだけ人が集まるかなとも思う。続けていくことが必要」と訴えた。 新地町の会社員菅原政紀さん(41)は「子どもたちのためにも声を上げ、私たちの世代で原発を止めることが役目」と、次女(3つ)を連れて初めてデモに参加した。「広島、長崎を経験した日本は原発を持つべきでなかった。同じことを思う人がこれほどいて心強い」と会場を見渡しながら、しみじみと語った。 自治労福島県本部県南総支部の村越晴也事務局長(55)は「今は脱原発の流れだけど、大停電などが起きて風が変わってしまうこともあるんじゃないかな」と危ぶんだ。 |
最後まで読んでくださってありがとう

 クリックを
クリックを 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。明日もまた見に来てね