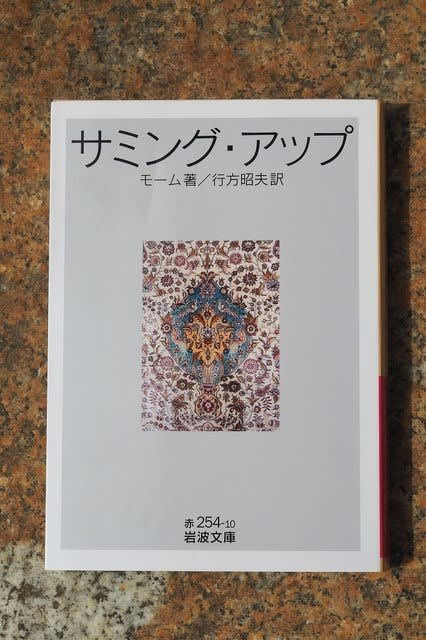
「月と六ペンス」のモームによる、自伝。いや、よく読んでみると、自伝的な要素もあるが、人生論、文学論、随筆といったおもむきを備えている。自由闊達な筆運びともいえるし、乱雑な書き散らしともいえる。わたしは兼好法師の「徒然草」やモンテーニュの「エセー」を、しばしば連想しながら、読み飛ばしせず、356ページの最後まで読みおえた´0`*)
全部で77章の断章からなっていて、それぞれが完結したり、次章へつながったり、気分のおもむくまま。
話題がワンセンテンスの途中で変わったりするから、見方によっては、口述筆記、あるいは速記録を編集したのでは? と感じられるところもあった。
モームというと、どうしてもシニカルなペシミストのイメージが強いが、“見えすぎる眼”を持っているのかもしれない。父にも母にも若くして死に別れ、親戚の手で育てられた。そこから自然と人がしゃべっていることと、やっていることの矛盾を見抜く子供になったのだろう。
甘味より、渋みが持ち味。しかも、ときおりそこにブラックコーヒーの苦みが加わる。
つまり女子ども向けというより、成熟した男のまなざしが、しばしばギラリと光る。
巻末の年譜によると、本書を書いたとき64歳。
いまのわたしくらいの年齢だが、こういう年になると、どうしても回顧的になるし、いやでも人生の裏表が見えてしまっている(。・_・)
モームは哲学書をずいぶん読んでいる。しかし、そこから得られたものは、ほんのわずかしかなかったといっている。
比較的若いころに劇作家として成功し、裕福な作家となった。英国の情報活動に従事したり、結核のため、サナトリウムに入院したり、世界を旅してまわったり。
その旅先でも、大勢の人と接触し、創作の材料を仕込んだ。つまりほとんどすべてのモームの作品は、ストーリーは彼自身のつくりだしたものだろうが、登場人物には「モデル」がいた・・・と考えた方がよい。そこにモームならではの“リアリズム”の根拠が存在している。
そのうえ、彼は基本的に「人間嫌い」ときている。だから、偽善者にはきわめてデリケートなリアクションを示す。人の欠点に寛大である場合もあるが、たいていは暴きたてずにはいられない。そこからモーム流の苦い味わいが迸る。だけど、彼は他人にきびしく、自分に甘かった小説家ではない。
《実在の人はあまりに捉えがたく、あまりに漠然としていて、丸写しにするのは不可能である。あまりにも支離滅裂、矛盾だらけである。》(本書250ページ)
《人は友人をその長所ではなく短所によって覚えているのである。》(252ページ)
《作家の多重人格に最初に気付いたのはおそらくゲーテであり、彼はそのことで一生悩んだ。》(268ページ)
《人生には理由などなく、人生には意味などない。これが答えである。》(319ページ)
《デカルトを読むのは、底が透けて見えるくらい澄んだ湖で泳ぐのに似ていた。あの水晶のような水は驚くほどさわやかだった。スピノザをはじめて読んだときは、生涯で最も記念すべき経験だった。何だか高い山脈を目のしたときのような高揚した気分で満たされた。》(280ページ)
《自分はたくさん本を読み、たくさんの絵画を観たからというので、他の人より偉いと思っているのだ。現実から逃避するために芸術を盾にし、人間の生活に必要な活動を否定するために平凡なものには何であれ愚かしい軽蔑の目を向ける。》(348ページ)
・・・長くなるからやめておくが、この種のいわば“箴言”はいくらでも拾いだすことができる。
「わたしはペシミストではない」といいながら自殺を肯定しているので、わたしには十分ペシミストに見える。
できれば作家ではなく、農民としておだやかな一生をまっとうするのが理想だとも書いている。この本の中ですら、モームは矛盾したことを述べ、二つか三つの道を、逡巡しながらいったりきたり。
そこが本書の持ち味となっている。つまり、「サミング・アップ」にはモームの作品世界が、そのまま反映されているのだし、彼はここでも“モーム節”をうなっているわけだ。
彼は文学やその方法を、「オチ」のないチェーホフではなく、「オチ」をむしろ武器としているモーパッサンから学んだといっているが、彼の世界観、人生観はチェーホフの方にむしろ似ている。
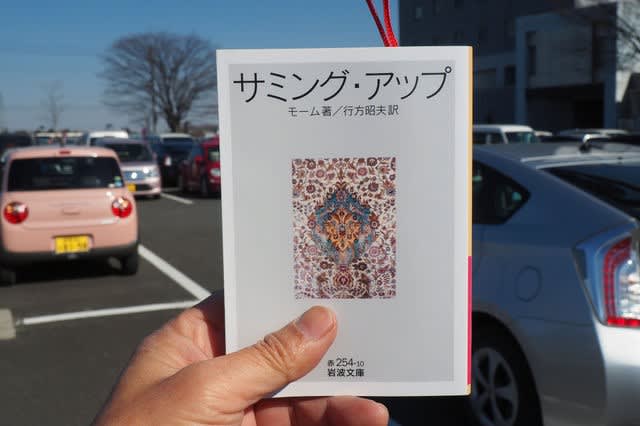
苦みばしった香り豊かな極上のカクテルの味わい、それがモームのファンを捉えてはなさない。本書と出会って、60歳半ばをすぎたわたしには、新しい親友が出来たようなうれしさがある(^^♪
というわけで本は文庫本等でそろえたが、次からつぎ読むかどうか?
しかし、おそらくモームとは死ぬまでの、あるいは老いて本が読めなくなるまでの、長いつきあいになるだろう。
訳者行方昭夫さんの日本語も十分こなれ、中野好夫さんあたりと較べれば、現代的な風味をそえている。
モーム本人と訳者の両方に、読者として感謝を捧げたい。
訳者による、充実した丁寧な解説、詳細な年譜があるのもありがたい。おかげでいい本とめぐりあうことができたのだ。
評価:☆☆☆☆☆
全部で77章の断章からなっていて、それぞれが完結したり、次章へつながったり、気分のおもむくまま。
話題がワンセンテンスの途中で変わったりするから、見方によっては、口述筆記、あるいは速記録を編集したのでは? と感じられるところもあった。
モームというと、どうしてもシニカルなペシミストのイメージが強いが、“見えすぎる眼”を持っているのかもしれない。父にも母にも若くして死に別れ、親戚の手で育てられた。そこから自然と人がしゃべっていることと、やっていることの矛盾を見抜く子供になったのだろう。
甘味より、渋みが持ち味。しかも、ときおりそこにブラックコーヒーの苦みが加わる。
つまり女子ども向けというより、成熟した男のまなざしが、しばしばギラリと光る。
巻末の年譜によると、本書を書いたとき64歳。
いまのわたしくらいの年齢だが、こういう年になると、どうしても回顧的になるし、いやでも人生の裏表が見えてしまっている(。・_・)
モームは哲学書をずいぶん読んでいる。しかし、そこから得られたものは、ほんのわずかしかなかったといっている。
比較的若いころに劇作家として成功し、裕福な作家となった。英国の情報活動に従事したり、結核のため、サナトリウムに入院したり、世界を旅してまわったり。
その旅先でも、大勢の人と接触し、創作の材料を仕込んだ。つまりほとんどすべてのモームの作品は、ストーリーは彼自身のつくりだしたものだろうが、登場人物には「モデル」がいた・・・と考えた方がよい。そこにモームならではの“リアリズム”の根拠が存在している。
そのうえ、彼は基本的に「人間嫌い」ときている。だから、偽善者にはきわめてデリケートなリアクションを示す。人の欠点に寛大である場合もあるが、たいていは暴きたてずにはいられない。そこからモーム流の苦い味わいが迸る。だけど、彼は他人にきびしく、自分に甘かった小説家ではない。
《実在の人はあまりに捉えがたく、あまりに漠然としていて、丸写しにするのは不可能である。あまりにも支離滅裂、矛盾だらけである。》(本書250ページ)
《人は友人をその長所ではなく短所によって覚えているのである。》(252ページ)
《作家の多重人格に最初に気付いたのはおそらくゲーテであり、彼はそのことで一生悩んだ。》(268ページ)
《人生には理由などなく、人生には意味などない。これが答えである。》(319ページ)
《デカルトを読むのは、底が透けて見えるくらい澄んだ湖で泳ぐのに似ていた。あの水晶のような水は驚くほどさわやかだった。スピノザをはじめて読んだときは、生涯で最も記念すべき経験だった。何だか高い山脈を目のしたときのような高揚した気分で満たされた。》(280ページ)
《自分はたくさん本を読み、たくさんの絵画を観たからというので、他の人より偉いと思っているのだ。現実から逃避するために芸術を盾にし、人間の生活に必要な活動を否定するために平凡なものには何であれ愚かしい軽蔑の目を向ける。》(348ページ)
・・・長くなるからやめておくが、この種のいわば“箴言”はいくらでも拾いだすことができる。
「わたしはペシミストではない」といいながら自殺を肯定しているので、わたしには十分ペシミストに見える。
できれば作家ではなく、農民としておだやかな一生をまっとうするのが理想だとも書いている。この本の中ですら、モームは矛盾したことを述べ、二つか三つの道を、逡巡しながらいったりきたり。
そこが本書の持ち味となっている。つまり、「サミング・アップ」にはモームの作品世界が、そのまま反映されているのだし、彼はここでも“モーム節”をうなっているわけだ。
彼は文学やその方法を、「オチ」のないチェーホフではなく、「オチ」をむしろ武器としているモーパッサンから学んだといっているが、彼の世界観、人生観はチェーホフの方にむしろ似ている。
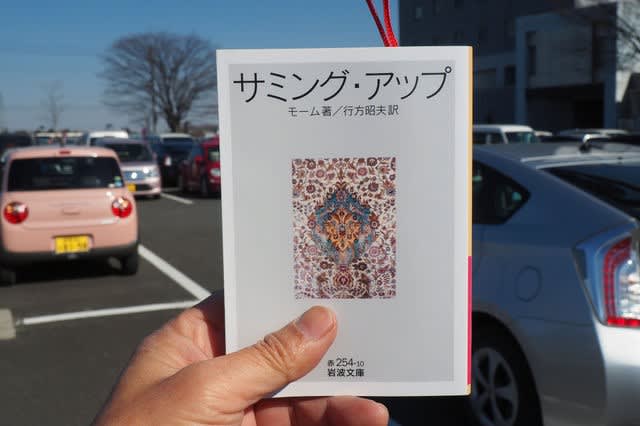
苦みばしった香り豊かな極上のカクテルの味わい、それがモームのファンを捉えてはなさない。本書と出会って、60歳半ばをすぎたわたしには、新しい親友が出来たようなうれしさがある(^^♪
というわけで本は文庫本等でそろえたが、次からつぎ読むかどうか?
しかし、おそらくモームとは死ぬまでの、あるいは老いて本が読めなくなるまでの、長いつきあいになるだろう。
訳者行方昭夫さんの日本語も十分こなれ、中野好夫さんあたりと較べれば、現代的な風味をそえている。
モーム本人と訳者の両方に、読者として感謝を捧げたい。
訳者による、充実した丁寧な解説、詳細な年譜があるのもありがたい。おかげでいい本とめぐりあうことができたのだ。
評価:☆☆☆☆☆


























