
11月2日(月)曇り
もうずいぶん昔の話。
娘を出産して、育児に悪戦苦闘してた頃、伊藤比呂美さんのエッセイを読んだ。
本職というか、スタートは詩人の方だが、「良いおっぱい悪いおっぱい」や
「おなかほっぺおしり」や「コドモより親が大事」など、
育児エッセイの開拓者だ。
コドモのことを愛して愛して、死んじゃったんじゃないかと意味なく心配するほど愛しているけど、
でも、自分のことも大事っていうとこが、当時のワタクシにとっては、ホッと息をつける感じだった。
我が家の近所の図書館には、リサイクルコーナーがあり、
本の入れ替えによって生じた古い本を「どうぞご自由に」持って帰れる。
そこで、久しぶりに伊藤比呂美という名を目にし、彼女のエッセイ「またたび」を
大喜びで持って帰る。
その中で、彼女が、娘二人を連れてユダヤ系イギリス人と再婚し、アメリカに住んでいることを知る。
彼女は、若い頃摂食障害で苦しんだ時期もあり、食べ物への関心は人一倍。
このエッセイ自体、食べ物のエッセイで、とてもおもしろいのだが、
特に好きな話が二話。
一つは、タイトルが「居ながらレストラン」
料理を作ることに疲れた妻を思いやり、このイギリス人の夫が一週間を、You-Me-You-Me-You-チックス(テイクアウトのお店らしい・・・)-子供というふうに
料理作りをシェアしようと提案。
毎週日曜日は夫が子供たちに指導しながらの料理。
彼女は「パスタ料理を食べたいわ」とリクエストする。
炒めたタマネギとにんにくに、トマトの水煮缶をがーっ・・・って簡単なものから
スタートするだろうと思いきや
この夫「古典的イタリア料理の本質」というかなりな専門書を使ってフェットチーネ、ピンクのエビのクリームソースを子供達と作る。
夫の担当日が週二日、子供の監修まで含めると週に三日も豪華なおまつり食。
「うちに居ながらレストラン」と喜んでも居られず、経済的な心配、体重増加も心配。
でも良かったことが、この夫と娘達との関係。
ただでさえ難しい関係なうえに、言葉の壁もあり、ぎこちなかった彼らが、
この料理を始めてから壁が薄くなってきたようだと喜ぶ。
ただ、その関係は、シェフとその助手という関係ができつつあるような・・・というオチもおもしろい。
ワタクシ達が再婚した時、娘は小学五年生だった。
「新しいパパができた。わぁ~い!」と喜ぶほど子供でもなく、
「ママが幸せなら、ワタシもうれしいわ」っていうほど大人でもないビミョーなお年頃。
数回会っただけの夫と、東京で暮らすことになったわけだ。
東京で、まず食べたのが「もんじゃ」だった。
もちろん、娘もワタクシも初めてである。
まず、夫が具材で土手を作って、その中に汁を流し入れて、しばらく待って、グチャグチャに混ぜ、
へらでガチャガチャと少し刻んでからべろ~~んと広げる。
で、少し待ってから、小さなへらで引きずるようにして焦してから食べる。
儀式のようにおごそかに執り行う夫、それを食い入るように見つめる娘。
美味しいというより、面白いという感覚。
「次はワタシが作るっ!」と、娘意気込んでへらを手にする。
「もういい?」
「まだまだ!」
「もうまぜていい?」
「よしっ!いいぞ!」
ってな感じで焼いては食べ、食べては焼き・・・
娘はすっかりもんじゃのとりこ。
しばらくは外食といえば「もんじゃ」の日々であった。
今思えば、このもんじゃ焼きは、かなり家族の関係強化に役立ったなあ~
今でも、九州の友人が遊びに来たら、必ず案内コースには『月島でもんじゃ』が入り、
一番弟子の娘が焼いて見せることになっている。
オーバーだが、我が家のソウルフードはもんじゃかなあ~なんてことを思いながら
このエッセイを読んだのだった。
今日の一枚は、食べ物つながりってことで、
先日の我が家の休日のブランチ。
スーパーの駅弁フェアで、夫は押し寿司、ワタクシは海鮮丼、娘はかしわめしをチョイス。
もうずいぶん昔の話。
娘を出産して、育児に悪戦苦闘してた頃、伊藤比呂美さんのエッセイを読んだ。
本職というか、スタートは詩人の方だが、「良いおっぱい悪いおっぱい」や
「おなかほっぺおしり」や「コドモより親が大事」など、
育児エッセイの開拓者だ。
コドモのことを愛して愛して、死んじゃったんじゃないかと意味なく心配するほど愛しているけど、
でも、自分のことも大事っていうとこが、当時のワタクシにとっては、ホッと息をつける感じだった。
我が家の近所の図書館には、リサイクルコーナーがあり、
本の入れ替えによって生じた古い本を「どうぞご自由に」持って帰れる。
そこで、久しぶりに伊藤比呂美という名を目にし、彼女のエッセイ「またたび」を
大喜びで持って帰る。
その中で、彼女が、娘二人を連れてユダヤ系イギリス人と再婚し、アメリカに住んでいることを知る。
彼女は、若い頃摂食障害で苦しんだ時期もあり、食べ物への関心は人一倍。
このエッセイ自体、食べ物のエッセイで、とてもおもしろいのだが、
特に好きな話が二話。
一つは、タイトルが「居ながらレストラン」
料理を作ることに疲れた妻を思いやり、このイギリス人の夫が一週間を、You-Me-You-Me-You-チックス(テイクアウトのお店らしい・・・)-子供というふうに
料理作りをシェアしようと提案。
毎週日曜日は夫が子供たちに指導しながらの料理。
彼女は「パスタ料理を食べたいわ」とリクエストする。
炒めたタマネギとにんにくに、トマトの水煮缶をがーっ・・・って簡単なものから
スタートするだろうと思いきや
この夫「古典的イタリア料理の本質」というかなりな専門書を使ってフェットチーネ、ピンクのエビのクリームソースを子供達と作る。
夫の担当日が週二日、子供の監修まで含めると週に三日も豪華なおまつり食。
「うちに居ながらレストラン」と喜んでも居られず、経済的な心配、体重増加も心配。
でも良かったことが、この夫と娘達との関係。
ただでさえ難しい関係なうえに、言葉の壁もあり、ぎこちなかった彼らが、
この料理を始めてから壁が薄くなってきたようだと喜ぶ。
ただ、その関係は、シェフとその助手という関係ができつつあるような・・・というオチもおもしろい。
ワタクシ達が再婚した時、娘は小学五年生だった。
「新しいパパができた。わぁ~い!」と喜ぶほど子供でもなく、
「ママが幸せなら、ワタシもうれしいわ」っていうほど大人でもないビミョーなお年頃。
数回会っただけの夫と、東京で暮らすことになったわけだ。
東京で、まず食べたのが「もんじゃ」だった。
もちろん、娘もワタクシも初めてである。
まず、夫が具材で土手を作って、その中に汁を流し入れて、しばらく待って、グチャグチャに混ぜ、
へらでガチャガチャと少し刻んでからべろ~~んと広げる。
で、少し待ってから、小さなへらで引きずるようにして焦してから食べる。
儀式のようにおごそかに執り行う夫、それを食い入るように見つめる娘。
美味しいというより、面白いという感覚。
「次はワタシが作るっ!」と、娘意気込んでへらを手にする。
「もういい?」
「まだまだ!」
「もうまぜていい?」
「よしっ!いいぞ!」
ってな感じで焼いては食べ、食べては焼き・・・
娘はすっかりもんじゃのとりこ。
しばらくは外食といえば「もんじゃ」の日々であった。
今思えば、このもんじゃ焼きは、かなり家族の関係強化に役立ったなあ~
今でも、九州の友人が遊びに来たら、必ず案内コースには『月島でもんじゃ』が入り、
一番弟子の娘が焼いて見せることになっている。
オーバーだが、我が家のソウルフードはもんじゃかなあ~なんてことを思いながら
このエッセイを読んだのだった。
今日の一枚は、食べ物つながりってことで、
先日の我が家の休日のブランチ。
スーパーの駅弁フェアで、夫は押し寿司、ワタクシは海鮮丼、娘はかしわめしをチョイス。





















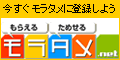





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます