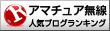アンテナは電波を出す周波数でベストに調整されているべきですね。
それは正しい。
でも電波を出す周波数より少し違う周波数で、アンテナチューナーでSWRを落とした場合の飛びってどうなんでしょう。
チューナー無し状態の高いSWRの時と同じ程度しか飛ばないのでしょうか。
バンドが違うくらいかけ離れた周波数だと、はい、飛びません、が正解です。
受信しても感度がからっきし低いです。
でもでも、バンド内に同調点がしっかりあるアンテナで、そこからずれてSWRが3~5程度の位置なら、チューナーで1に落とせばアンテナを調整して1にした時とそう差が無いくらいは飛びます。
受信感度もしっかり確保されます。
まずは、3.573MHzに同調を取ったアンテナのスコープ画像です。3.573辺りの感度が高いですね。右のほうが明るくなっています。
アンテナは電動コイルが作動するSD330です。自在に同調点が変えられます。

次に、3.509MHzに同調を取ったアンテナのスコープ画像です。左のほうが感度が高いので明るくなっています。

最後に、3.573MHzで同調をとりつつ、3.507MHz辺りで外付けアンテナチューナーを動作させてSWRを落としたときのスコープ画像です。
右が明るかったのに左が明るく、に変化しました。

本当は1枚目の状態なのにチューナーで2枚目の状態そっくりになりました。
アンテナ自身のSWRが高くても、かなり実用的なアンテナとして動作することがわかると思います。
ちなみに内蔵チューナーではどうなの?という話ですが、SWRが落ちればそれなりに期待できますが、あまり高いとSWRが落とせないことが多いので、外付けチューナーのほうが期待出来ると思います。
チューナーは、アンテナから反射して戻ってきた電流を再びアンテナに戻す、という動作をするそうで、結果殆ど電波になって出ていく、飛びもそこそこ実現されるそうです。戻ってきた電流は熱になるばかりではない、ということです。
というわけで、先日購入した9バンドホイップですが、バンドのど真ん中辺りに同調点を持って来させすれば、外付けアンテナチューナーと併用でいちいち調整し直さなくてもかなり実用になる、ということです。
LDG社のチューナーは安価で汎用性が高いのでおすすめですよ。車にはZ-11Proを積んでます。
今話題の信越総合通信局の親切なお手紙。
要約すると
あなたの局は旧スプリアス基準のままの無線機があります。
旧スプリアス基準の無線機はそのままだと令和4年11月30日で使えなくなっちゃいます。
スプリアス保証とか手続きすれば今後も使えるかも知れないので手続きしてくださいね。
という内容。
当局がうっかり失効によりすべてをパーにしてしまったあの手続きのおすすめです。
正式には スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書 と言うやつを出す手続きですが、個人では証明が難しいのでさらにスプリアス保証というサービスを利用して行う手続きです。
これ、やったんですけどね。手間もお金もかけて。
書類結構大変でしたね。いろいろ略せないんです。過去の申請書類とか取扱説明書とか全部見てみないと書けないことがたくさんありました。
私はパーにしてしまったので、開局からやり直し。
再開局の後、保証認定で追加申請、目下審査中で復活中。
保証認定だとスプリアス保証を飛ばすことができちゃいます。なぜなら(平成18年以降は既に)新スプリアス基準で保証認定しているから。
そこで気づいたのが、スプリアス保証より保証認定のほうが安いんでねぇかい?ってこと。どこでやるかにもよるけど。
使用している無線機なら、同じ機種で取替手続きを保証認定で行えばいいのです。
嘘っぽいのや嫌な方は、一旦そのリグを廃止して、手続きが終わったら今度はそのリグを増設、これを保証認定で行えばOKです。
ハムログの使い方はあちらこちらで散々やっているので今さらなのですが・・・
届いたQSLカードのチェック、届いたマークの付け方ってどうしてます?。
実はかなり素早く入力する方法があります。
表示 メニューから
QSL未着コール一覧 を開いてください。
すると下の方に サフィックス ってありますね。
少し右に サフィックス検索 にチェックが入っていると思います。(取るとプリフィックスからの検索になります。)
左下の入力欄に サフィックス を打ち込んでみると・・・
打ち込んでいる最中にもどんどん抽出作業がされて、あっという間に探していたコールサインのデータが見えてきます。
さてここからです。
上下キーやマウスで、このデータだ!というやつを選択してください。
続いて Enterキー
さらに、Insertキー
たったこれだけでチェック完了です。QSL欄の右端に*が入ります。どんなもんだい!って感じです。
次のカードをチェックする時は、ここからちょっと面倒ですが、
Escキー BSキー3回(3桁入れていたら) ←これはもう機械的にやってください
で、次のサフィックスを入れます。
この一連の作業ものの数秒で終わります。
もう少し丁寧なやり方。
上下キーやマウスで、このデータだ!というやつを選択したら
Enterキー
もう一度
Enterキー ここで窓が開きます
すかさず
Insertキー
あとは開いた窓の内容をジロジロチェックして、名前とかQTHとかグリッドロケーターとか備考とか、カードを見ながら追記したりしながらEnterキーを連打して終了
そしてまた
Escキー BSキー3連打
で次のカード。
お試しください。

UHV-9、コイルフル装備で9バンド運用できるアンテナ


旧スプリアス機については現在工事設計書に載っていても、そのままでは令和4年の秋に使えなくなります。
それを救済する措置として、旧スプリアス時代の無線機でも新スプリアス基準を満たしている機種に限って引き続き更新していけるようスプリアス保証という制度が出来ました。
手続きは一つ必要でしたが、古い設備が全滅しなくても済んだのは助かりましたね。
でも私、せっかくこの手続きしたのにうっかり失効していまい。すべての努力が泡となってしまったのです。
次の手はあるのか無いのか。無かったらもう古い無線機は使えません。
手はありました。
普通に保証認定で増設(開局)すればよいのです。
保証認定ではスプリアス保証出来る機種も保証してくれます。
ポイントその1 申請の方法は簡略化無し
昔のままの方法です。技適ナンバーを書くだけでかなりの部分を略することが出来るという恩恵はありません。
こつこつと必要な項目を埋めていかなければなりません。
HF~430に出られるオールバンド、オールモード機でさらにパソコンでFT8などやろうとすれば結構な労力です。
送信機ごと、一台一台、全部入力です。
ポイントその2 添付書類が必要
送信機毎に送信機系統図が必要です。
ノーマルのままでも必要ですし、附属装置があればそれも盛り込みます。
必ず書かないといけないのが、機種名があれば機種名、旧技適番号かJARL登録番号、終段の名称です。
この送信機系統図が保証の肝で、番号があるものはその資料、自作機ならば終段の性能、フィルターの有無で保証審査されるようです。
10台保証を受けるなら10枚必要です。
ポイントその3 電子申請のシステムは使うけど送信はしない
電子申請のシステムで申請書を作りますが、まだ申請しないで保存。送信してはいけません。(総通から「保証が必要です。取り下げてください。」という通知が届いてしまう)
その保存したファイルで保証手続きを進めていきます。
何度か補正したりしながらTSSとやりとりし、問題が無くなったところで最終バージョンをこちらに保存。
数日後保証書がメールで届くので、電子申請のシステムに最終バージョンを読み込みさらに保証書を添付して完全バージョンにして、それを初めて「送信」します。

青い送信ボタンは保証を受けるまで押さないこと!
では添付書類、画像で補足します。
電子申請で入力した、届出内容の画面です。たくさんのモードを手入力した成果です。


嫌というほど打ち込むのですが、これでもまだ1台分です。
13台分徹夜で打ち込みました。
送信機系統図です。
今回の申請では第1,13~25送信機、全14台分徹夜で書き上げました。Hi
今思えば周波数帯ごとの終段の名前、数、電圧、出力も盛り込んだ方が良かったかも。
新スプ対応の技適機です。+附属装置+リニアアンプです。リニアアンプのために保証を受けています。
リニアを使おう、という目的の無い方はまだこの申請はしない方がいいです。(パソコン追加だけなら後日もっと楽な方法が始まりますので)

旧スプ技適機の例です。

旧JARL登録機の例です。(昔々、JARL保証っていうのがあったんですよ)

旧技適機にパソコンをつないだ例です。
増設で保証が必要だったので一緒に盛り込みました。
(新技適機にパソコンをつなぐ場合、マイク端子等につなぐのなら保証不要です)
RTTYをFSKでも運用したいのでRTTY端子への接続も盛り込んでいます。

メーカーによる50W措置改造を受けた機種の例です。パソコンもつないでいます。
IC7400はなぜか50W機が発売されませんでした。
なかなか良いリグでダイヤルのフライホイールが効いていて、IC7610よりも気持ちよく回ります。
もう一台、FT847も50W改造機で申請しました。新発売当時は50W機が無くてメーカー改造で使いました。
FT847の100W機はスプリアス保証が受けられないようですが、50W機は通るので申請しました。
機種名だけで可否は判断できませんね。

KX3の例です。海外製のリグなので保証を受けなければ使えない無線機です。
海外製のリグは最初の一台の保証を受けるのは苦労するでしょうが、前例があればなんとかなります。
これにはリニアもパソコンもつながっています。
KX3は以前、リグ内蔵のRTTYやPSKがAFSK方式では、と指摘されたことがありましたが、外部から何も入れていないのでFSKだろう、ということで今回FSK方式と書かせていただきました(リグのモードもRTTYやPSK)。パソコンから運用する場合はAFSK方式になります。(リグはDATAモード)

メーカーさんの系統図は右から左に流れるのでわざわざ書き起こしました。
話題になる分周率の一覧も盛り込んであります。
(このデータはこれから申請しようとお考えの方には提供しますのでご一報ください)
他にTR-1902というFBな50MHz帯AM3mWトランシーバーを申請しました。この図は作者の方のホームページから起こさせていただきました。
私にはわからない部分もあり、なにか指摘されたらどうしようと思いながら申請しました。

附属装置の諸元表です。実際に使うものに絞りました。(今後はモード追加の変更の必要は無くなる方向なので、一旦出しておけばOKです。)

1.9MHz帯でのRTTYは帯域を狭めたものでないと駄目で、普通のRTTYでは送信できないのでやめました。
F1Bモードを書いていないのはそのせいです。
というわけで無事復帰が果たせそうです。
ん?これで保証料4000円、変更申請無料。
スプリアス保証受けるより、無線機の取替申請を保証認定で行ったほうが安いってことかな。