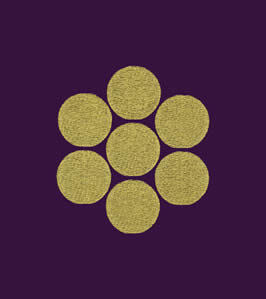◇PEACE BED アメリカ vs ジョン・レノン(2006年 アメリカ 99分)
原題 The U.S. vs. John Lennon
staff 監督・脚本/デヴィッド・リーフ ジョン・シャインフェルド 監修/オノ・ヨーコ
撮影/ジェームズ・マザーズ 音楽/ジョン・レノン 編集/ピーター・S・2世
cast オノ・ヨーコ ジョン・ウィーナー ロン・コーヴィック アンジェラ・デイヴィス タリク・アリ
◇WAR IS OVER IF YOU WANT IT
ぼくは、いまだにビートルズの全曲を聴き終わっていない、とおもう。
それだけ、音楽が身近な存在じゃないからだ。
中学3年のときだったか、生まれて初めてビートルズを聴いた。
その頃のぼくは、映画にようやく目覚め始めた頃で、
『小さな恋のメロディ』があったから、ビージーズを、
『卒業』があったから、サイモン&ガーファンクルを聴いていたくらいで、
『イエロー・サブマリン』を観たところで、ビートルズには向かなかったろう。
それくらい、ぼくは音楽に疎かった。
もちろん、威張れた話じゃないけど、いまも疎い。
その疎さをごまかすようにして、
高校の頃は、誰も買わないような映画のサントラばかり買ってた。
だから、ほかの音楽、ことに洋楽はなかなか手が出なかった。
なぜって?
英語がちんぷんかんぷんだったからだ。
ぼくはおもうんだけど、
世の中の人達は、洋楽を聴いたり歌ったりしてるのは、
みんな、歌の意味をちゃんと聴きとれてるからなんだろうか?
曲調ていうか旋律が、あるいは雰囲気が好いから、
好きだわ、これ~とかいって聴いてるんだろうか?
もしも、世の中の人達がみんなぼくくらいな英語の読解力しかなくて、
単純に「あ、この曲、かっこいいじゃん」とかいって、
歌詞の意味とかまるでわかんないまま聴いてるんだったら、
たぶん、外国の歌手は「なんだよ、わかんねーのかよ」って残念がるだろう。
当時のジョン・レノンなら、特にそうだ。
かれは、平和を心の底から愛していた。
と同時に、戦争や暴力を心の底から毛嫌いしていた。
それが、かれに歌を作らせる原動力となり、メッセージもまた歌に込められた。
もちろん、ジョン・レノンだけじゃない。
当時、ことにアメリカの、少なくない歌手が戦争を反対し、歌にした。
英語のわからないぼくは、そのメッセージがよくわからなかった。
訳詞くらい読めばいいのに、それすらめんどくさがるような、あほたれだったけど、
日本でもジョン・レノンのメッセージを受け止め、
かつ、自分なりに歌に託して、若者に支持された歌手が登場するようになった。
思想が歌を作らせ、歌によって思想の語られる時代の到来だ。
ジョン・レノンは、その先頭で旗をふる役割に立たされてしまった。
若者たちはそんなかれを支持し、かれの行動はさらに突き抜けた。
1969年、オノ・ヨーコと結婚したとき、新婚旅行先のアムステルダムで、
「戦争をする代わりにベッドで過ごそう、髪を伸ばそう、平和になるまで」
といってベッドの上で日々を送ることを宣言し、マスコミも殺到した。
ここでいう戦争は、泥沼と化したベトナム戦争で、大統領はニクソン。
レノンとヨーコの静かにして過激な行為は、ニクソンの目の上のたんこぶになった。
新婚旅行が終わり、
ニューヨークでふたたび「peace bed」の暮らしをはじめたかれらに待っていたのは、
かれらを戦争反対の御輿に据えようとする運動家と、
かれらを戦争反対の象徴と捉えて排除したいとおもいはじめた米国家そのものだった。
監視、盗聴、永住権の申請拒否、国外退去の勧告…。
よくもまあ、超大国をあいてどって、たったふたりで戦う気になったもんだけど、
「ぼくは戦争は嫌なんだ、人を殺したくないんだ、歌を歌っていたいだけなんだ」
という若者に対して、こうも本気になって国家が挑みかかるという事実にも驚く。
時代ってやつかもしれない。
あまりに安易なまとめ方だから恥ずかしいんだけど、それ以外にいいようがない。
ベトナム戦争が泥沼化していったのも時代なら、
戦争反対を唱えて、歌に託していった若者の象徴に、
かれらが押し上げられたのもまた時代だろう。
純粋といえば純粋、知的といえば知的、過激といえば過激、
そして、まちがいなく誰もが真剣、
真剣に人生を語り、歌を語り、国を語り、戦争を語り、地球を語り、
戦争するくらいならベッドの上で愛し合っていようと真剣に主張した。
そういう時代だ。
この映画は、そうした時代をぼくらに語り、
そしてポスターにあるように、
『もし変えようと思うなら
ほんとうに変えようと思うなら
世界は変えられる』
という主題を伝えようとしていること以外にないんだよね。
ただ、1980年12月8日、かれは凶弾に倒れた。
とうに過ぎ去ってしまったはずの時代の亡霊が、かれを殺したのか、
それとも、単純に、愛されすぎてしまったために殺されたのか、
どっちなのか、ぼくにはわからない。