
ニューヨーク・タイムズの辛口な劇評で知られるフランク・リッチは、「ショウボート」があったからこそ、「オクラホマ!」も「ポギーとベス」も、そして「ウェスト・サイド物語」も生まれたと書いている。スタンダード・ナンバーの多くはミュージカルに書かれた曲だが、「サウンド・オブ・ミュージック」や「マイ・フェア・レディ」のような有名なものは知っていても、曲以上にその内容を語れることはない。
さてリッチがミュージカルを変えたという「ショウボート」とは、どんなストーリーなのだろう。白人と黒人の結婚を軸に人種問題を浮き彫りにした作品で、1927年の初演当時、白人と黒人の結婚は法律で禁止されていたという時代背景を考慮すると、この内容はかなり勇気が必要だったといえる。ボーイ・ミーツ・ガール・ストリーを主軸にした音楽付きレビューが一般的なミュージカルに一石を投じた意味では歴史に残る作品だ。音楽を担当したのはジェローム・カーンとオスカー・ハマースタイン2世で、「オール・マン・リヴァー」をはじめ多くの曲がこのミュージカルから生まれた。
なかでも多くのジャズマンが取り上げるのが、「ノーバディ・エルス・バット・ミー」だ。45年にリバイバルの際に追加された曲でカーンの最後の曲でもある。ケニー・ドーハムは丸ごとこの作品の曲ばかりを集めたアルバムを作っていて、端整で原曲を生かした丁寧な演奏はシリアスな内容に相応しい。録音されたのは60年で、まだ人種差別の壁が厚い時代である。ドーハムが公民権運動に参加した話は聞かないが、盟友のマックス・ローチが同じ年に「ウィ・インシスト」を録音していることから少なからずその思想に影響を受けていたことは考えられる。「ショウボート」というアルバムを作ったのは、穏やかなドーハムが示した静かな運動だったのかもしれない。
「ショウボート」は何度か映画化されているが、MGMで51年に制作するときレナ・ホーンを起用する予定だった。30年代のハリウッドでは白人の黒塗りが伝統だったので、画期的な配役だったが、制作直前に奴隷制が根強く残る南部での上映を憂慮しエヴァ・ガードナーを抜擢したという。同じく白人と黒人の結婚を真正面から見据えた問題作に「招かれざる客」がある。67年の作品だ。ハリウッドが人種の壁に風穴を開けるには相当な時間が必要だったといえよう。
さてリッチがミュージカルを変えたという「ショウボート」とは、どんなストーリーなのだろう。白人と黒人の結婚を軸に人種問題を浮き彫りにした作品で、1927年の初演当時、白人と黒人の結婚は法律で禁止されていたという時代背景を考慮すると、この内容はかなり勇気が必要だったといえる。ボーイ・ミーツ・ガール・ストリーを主軸にした音楽付きレビューが一般的なミュージカルに一石を投じた意味では歴史に残る作品だ。音楽を担当したのはジェローム・カーンとオスカー・ハマースタイン2世で、「オール・マン・リヴァー」をはじめ多くの曲がこのミュージカルから生まれた。
なかでも多くのジャズマンが取り上げるのが、「ノーバディ・エルス・バット・ミー」だ。45年にリバイバルの際に追加された曲でカーンの最後の曲でもある。ケニー・ドーハムは丸ごとこの作品の曲ばかりを集めたアルバムを作っていて、端整で原曲を生かした丁寧な演奏はシリアスな内容に相応しい。録音されたのは60年で、まだ人種差別の壁が厚い時代である。ドーハムが公民権運動に参加した話は聞かないが、盟友のマックス・ローチが同じ年に「ウィ・インシスト」を録音していることから少なからずその思想に影響を受けていたことは考えられる。「ショウボート」というアルバムを作ったのは、穏やかなドーハムが示した静かな運動だったのかもしれない。
「ショウボート」は何度か映画化されているが、MGMで51年に制作するときレナ・ホーンを起用する予定だった。30年代のハリウッドでは白人の黒塗りが伝統だったので、画期的な配役だったが、制作直前に奴隷制が根強く残る南部での上映を憂慮しエヴァ・ガードナーを抜擢したという。同じく白人と黒人の結婚を真正面から見据えた問題作に「招かれざる客」がある。67年の作品だ。ハリウッドが人種の壁に風穴を開けるには相当な時間が必要だったといえよう。











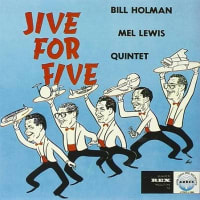














ミュージカルの「ショウボート」からは多くの名曲が生まれております。今週は「ノーバディ・エルス・バット・ミー」のお気に入りの演奏をお寄せください。ヴォーカルは機を改めて話題にします。
管理人 Nobody Else But Me Best 3
Kenny Dorham / Show Boat (Time)
Sonny Rollins / Don't Stop the Carnival (Milestone)
Brad Mehldau / The Art Of The Trio Vol.1 (Warner Bros)
他にもゲッツ、マリガン、エヴァンス等、多くのプレイヤーが取り上げております。
今週もベストにかかわらず皆様のコメントをお待ちしております。
今週は、 Nobody Else But Me ですか。
ドーハムとロリンズは、外せないですね。
大賛成です。
3枚目は、店で考えます。
あっ!仕事に行かなくちゃ!(汗)
ドーハムは全盛期の作品ですので絶好調です。ジミー・ヒースとドリューのソロはキレがありますし、タイム感覚というのでしょうか、「間」が上手いですね。それでレーベルはタイム。(笑)
ロリンズは後期の録音ながらアドリブ発展は50年代を彷彿させます。
まだまだ名演がありますので、じっくり3枚目をお探しください。
と身構えていたら、まともに来ましたね。
しかし、上がっている盤以外に、あまり手持ちがありません。
「Signs of Life / Peter Bernstein」のヴァージョン、
なかなかブルージーでよかったです。
ブラッド・メルドー参加ですが、
この人サイドに回ると余り捻ったバッキングはしない印象です。
この曲のヴォーカルといいますとアルバムタイトルにもなっているベティ・ベネットを思い出しますが、ここはまともなベストにしました。恋多きベネットも話題にしたいですね。
ピーター・バーンスタインもありましたか。一度聴いたきりで取り出しておりませんが、良い内容だったように思います。メルドーとは、ストレンジャー・イン・パラダイスでも共演しておりますが、リーダーを立てるタイプなのでしょう。54
2、Kenny Dorham / Show Boat (Time)
3、Stan Getz /Not But Else Me
(Verve)
という順でしょうか。
しかし、ズンリロのドントストップは懐かしですなぁ・・。
高校生の時でしたな、ロリンズが沈黙を破ってついに再登場と、そこで出てきたのが、「橋」と「ドントストップ・・」長年、橋の上で修行をしてきたと聞き及んで、いかように変わってきたかと仲間内で話題になったのでありやした。
頭が坊主頭だとか・・奏法が変わっただとか・・・。
しかし、その後ロリンズは革新的な変化を遂げたのでありました。証拠品は「Our Man In Jazz」であります。
ロリンズはドンチェリーをお共にガツーンとモヒカン刈できました。かっこよかった!
一方でコルトレーンはドロフィーをお供に「ビレッジ・バンガード」でありんす。
これぞ、巨頭が相並んだ図式でありんす。
当時はよかった「its been a long long time」でありんす。
メルドーもありますが、あのガキは自己中で他人を立てることを知らないのではないかと・・まあ管楽器と共演は苦しいでしょうな。
彼の場合は右手と左手の共演で精一杯なのではと思うのでありんす。
ああああ、疲れた、昨今の温度差にやられておりやす。
ドン・チェリーを伴って来日したロリンズの目撃者の SHIN さんにとって、ロリンズは身近でありながら神のような存在なのかもしれません。62年に「橋」でカンバックしたときの様子は当時のジャズ雑誌で知ることができますが、衝撃は大きかったようですね。
ドントストップは78年ですのでリアルタイムで聴いておりますが、派手なジャケとともに印象深いアルバムでした。
メルドーに否定的なようですが、所謂新世代のピアニストですので、ジャムセッションという場を知らないのでしょう。いみじくも 25-25 さんが、サイドに回ると余り捻ったバッキングはしない印象、と仰っておりますが、リーダーを立てる反面、殻から抜け出せないのかもしれません。ベーシストのジーン・ラミーは、ジャムセッションは殺気だった場だと言っておりますが、この修羅場で経験を積むと管楽器と良い共演ができるでしょう。
ゲッツはこの曲が好きなようでして、52年のヴァーヴ・セッションやクール・サウンズでも取り上げておりましたね。曲調はゲッツ向きです。
赤松さんから以下の提案があり。
面白いと思うのですが、如何でしょう?
↓
25-25プレゼンツの特別プログラムとして以下のような事を提案します。
二部の最初辺りで予定するのですが、
題して『トランペットがいないのにココでマイルス!』。
マイルス・デイビスが逝ってから早い物で今年で没後二十年になります。
彼の残した影響はトランペット奏者に留まらず、僕らの脳裏にもしっかりと刻みこまれています。
数ある彼のいろんなタイプの演奏の中から、今回は1964年2月のリンカーン・センター
(後のエイブリーフィッシャー・ホール)で記録された二枚のアルバムにスポットを当てて、
25-25プレゼンツらしいアプローチを行いたいと思います。
1964年を選んだ理由は多々ありますが、飛び抜けて大きな理由は
この年の7月に初来日している事から、最も最初に日本との接点が生れた年として
メモリアルと考えるからです。
(マイルス・イン・トーキョーでもいいじゃないか、と思われるかもしれませんが、
サム・リバースの臨時参加によってバンドとしてのまとまりはコチラに一歩譲る為)
この時期の最重要レパートリーは“Stella by starlight”なのでこれは外せません。
(この曲を使って当日いろいろお楽しみを考えています)
この企画は三曲の構成で考えていますが、他に演奏する二曲を事前に
参加する皆さんに選んでいただこうというもの。
『トランペットがいないのにココでマイルス!』候補曲
・ My Funny Valentine
・All Of You
・All Blues
・I Thought About You
・So What
・Walkin'
・Joshua
・ Four
・Seven Steps To Heaven
・There Is No Greater Love
Vib+P+B+Dsで聴いてみたい『トランペットがいないのにココでマイルス!』コーナーで
リクエストの上位二曲を先の“Stella By Starlight”と組み合わせて演奏。
ハクエイ君のピアノを聴いていて、ふとこの企画を思い浮かべました。
太郎君とはアルバム(「Focus Lights」)で“Seven Steps To Heaven
”を演奏しているし、僕の最新盤にはヴォーカル入りで“I Thought About You”
が入っているし、、何かと今でも繋がりのあるものなので。
http://www.morimoto-clinic.org
ラシッド・アリという、大道芸人のようなヤツでペットを吹く時に、左の頬しか膨らまない変な奴でした。そして音楽的にも変なヤツで、前衛らしいのですが、意味不明なフレーズでドン・チェリーとは似ても似つかない奴でした。
そして、来日公演の途中でロリンズにビーク(首)になり、強制送還になってしまいました。
これが当時目の前で見てきた歴史的事実でありやす。
私は東京から大阪、京都まで追っかけて行きましたが、突然アリが居なくなってしまったのです。後日確認すると、以上のようなことでありやした。なお、加えますと、当時のロリンズの演奏スタイルは空中高くテナーを掲げ水平にして吹くというまるでレスターヤングみたいなスタイルであったことを付け加えさせて頂きます。これ以上の当時の奏法上の新発見は有料でお話をさせていただきたく候う。以上、ご報告申し上げます。ジャンジャン。