(麻生太郎・新潮新書)
「とてつもない日本」というタイトルは、祖父・吉田茂の口跡からのようだ。養老孟司『バカの壁』で当てて以来、好調な新潮聞き書きシリーズの一冊だから、読みやすい。何10年も他人の原稿を書き直ししているから、たいていの編集者は読みやすい文章を書くという点では、たいていの筆者を上回る。小説は読者に読ませないのが勘所の場合があるが、小説一筋で担当作家の著作を徹底的に読み込んでいる編集者なら、やはり書き直せる。ネット時代になって、ライターは激増したが、優れた編集者は少ないまま。そうした非対称がネットのテキストの天井かもしれないと思う。
かつて竹中労の「聞書アラカン一代 鞍馬天狗のおじさんは」という傑作があったように、語り手と波長が合い、聞き手に練達の技術がある場合、聞き書きそのものが優れた作品と成り得る。芸能人や政治家の本を「どうせ本人は書いていない」と切り捨てるには惜しい本も稀にある。
虚実皮膜というが、語り手聞き手の双方が、虚に実に勇敢に踏み込んでいく「共犯関係」が成り立っている場合、読者はその場に居合わせたようなスリルとサスペンスを味わうことができる。誰の話を誰に聞かせるかという企画を立てるのが、また編集者であり、彼もその虚と実に踏み込んでいくのだ。まだ、読みはじめたばかりだが、聞き手(たぶん編集者)が嬉しがっている様子に好感が持てる。
「とてつもない日本」というタイトルは、祖父・吉田茂の口跡からのようだ。養老孟司『バカの壁』で当てて以来、好調な新潮聞き書きシリーズの一冊だから、読みやすい。何10年も他人の原稿を書き直ししているから、たいていの編集者は読みやすい文章を書くという点では、たいていの筆者を上回る。小説は読者に読ませないのが勘所の場合があるが、小説一筋で担当作家の著作を徹底的に読み込んでいる編集者なら、やはり書き直せる。ネット時代になって、ライターは激増したが、優れた編集者は少ないまま。そうした非対称がネットのテキストの天井かもしれないと思う。
かつて竹中労の「聞書アラカン一代 鞍馬天狗のおじさんは」という傑作があったように、語り手と波長が合い、聞き手に練達の技術がある場合、聞き書きそのものが優れた作品と成り得る。芸能人や政治家の本を「どうせ本人は書いていない」と切り捨てるには惜しい本も稀にある。
虚実皮膜というが、語り手聞き手の双方が、虚に実に勇敢に踏み込んでいく「共犯関係」が成り立っている場合、読者はその場に居合わせたようなスリルとサスペンスを味わうことができる。誰の話を誰に聞かせるかという企画を立てるのが、また編集者であり、彼もその虚と実に踏み込んでいくのだ。まだ、読みはじめたばかりだが、聞き手(たぶん編集者)が嬉しがっている様子に好感が持てる。










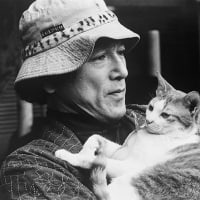

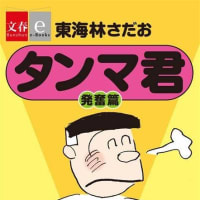







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます