 「「世界の大富豪」成功の法則」の購入はコチラ
「「世界の大富豪」成功の法則」の購入はコチラ
「「世界の大富豪」成功の法則」という本は、「フォーブス」誌の「世界長者番付」にランキングされたビル・ゲイツらのトップ・ビリオネラや、いまや伝説となったロックフェラーを中心とした名門ビリオネラがどうやって巨富を手に入れその人生がどんなであったか、そして彼らの格言等を紹介し、そのほか成功各国のロイヤルファミリー、IT長者、遺産相続、アジア圏の長者についても書かれ、彼らから学べる点についてもまとめられています。
特にビリオネラの格言は勉強になりますね♪
ちなみにフォーブス世界長者番付の歴代トップは以下の通りとのことです。
バブルの頃は日本人がずっとトップだったのですね♪
またマイクロソフト創業者のビル・ゲイツが長年トップを守り続けているのはすごいと思います^_^)
1987年~90年 堤義明(西武鉄道グループ元オーナー)
1991年~92年 森泰吉郎(森ビル創業者)
1993年~94年 堤義明
1995年~07年 ビル・ゲイツ(マイクロソフト創業者)
2008年 ウォーレン・バフェット(投資持株会社バークシャー・ハサウェイ 会長兼CEO)
2009年 ビル・ゲイツ
2010年~13年 カルロス・スリム(通信会社テルメックス オーナー)
2014年~15年 ビル・ゲイツ
また、フォーブス誌が発表した2015年の「ビリオネア国別人数」は、IT長者がひしめき合うアメリカが他国を圧し、以下の順位は次のようになっています。
アメリカや中国、ドイツが多いんですね。
1位 アメリカ536人(人口3億2260万人)
2位 中国 213人(人口13億9380万人)
3位 ドイツ 103人(人口8270万人)
4位 インド 90人(12億8740万人)
5位 ロシア 88人(人口1億4260万人)
6位 イギリス 53人(人口6350万人)
7位 フランス 47人(人口6460万人)
8位 台湾 33人(人口2330万人)
9位 韓国 30人(人口4950万人)
10位 日本 24人(人口1億2700万人)
なお、対10万人でのビリオネア人数は以下となり、台湾がかなり健闘していることがわかります。
1位 アメリカ 16人
2位 台湾 14人
3位 ドイツ 12人
4位 イギリス 8人
5位 フランス 7人
6位 ロシア、韓国 6人
8位 中国、日本 2人
10位 インド 1人未満
「「世界の大富豪」成功の法則」という本は、現在や過去のビリオネラがどうやって巨富を手に入れその人生がどんなであったか、そして彼らの格言等を学べ、とてもオススメです!
以下はこの本のポイント等です。
・ビル・ゲイツの「大富豪への12の成功方程式」
①人生は公平じゃないという処世訓を頭にたたき込んでおくことだ。
②貧しく生まれるのは君のせいじゃないが、貧しく死ぬようなら君のせいだ。
③直感を信じることが、しばしば必要になる。
④成功体験は困った教師のようなものだ。抜け目のない者を失敗するわけがないと信じ込ませてしまう。
⑤人と比較してはいけない。そんなことをすれば、自尊心を傷つけるだけだ。
⑥成功に酔うのは結構だが、失敗から学ぶ方がもっと有意義である。
⑦うまくできないなら、せめてよく見えるようにせよ。
⑧手元に金があると我を忘れてしまうが、金がなければ世間から忘れ去られる。それが人生というもの。
⑨ほとんどの人は、1年でやれたことは過大評価し、10年でできることを過小評価しがちだ。
⑩最も得るところが大きい顧客は誰かといえば、一番不満を持っている顧客ということになる。
⑪どれだけ忍耐できるか。それが成功の鍵を握っている。
⑫大きく勝とうとすれば、大きなリスクが付随することを覚悟しなければならない。
・カリロス・スリムの「大富豪への10カ条の成功方程式」
①危機は誰にも訪れる。問題は、その危機をバネにして強くなれるかどうかだ。
②失敗は誰にもある。人間的なことなのだ。失敗は小さくし、素直に受け入れ、修正せよ。そして、忘れるのだ。
③どんなビジネスにも誤りはつきものだ。大きな誤りをどうやって避けるのかが成功の鍵となる。
④精神状態を左右するネガティブな感覚・感情を抑制しないといけない。傷心は他人のせいで生じるのではなく、自分自身から生まれ、大きく膨らむのだ。
⑤人は、誰かと競い合うことで、いつも、いつだって、大きくなれる。たとえ競争相手が勝ってもだ。
⑥現実を直視し、達成可能な明確な目標を持て!
⑦楽観的であれ。おびえてはいけない。
⑧何でもかんでも自分でやろうとするな。むしろ、他人と連携し、共同でやるべし。
⑨競争を楽しむこと。そうすれば健康になり、自分自身やビジネスをもっと強くする方法を掴むことだ。
⑩ローカル発のグローバルを目指すのだ。
・「ウォーレン流投資戦略」が、誰にもわかる単純明快な正攻法である点も共感を得ている。コカ・コーラとかIBMといった「優良株」を、株価が安いときに買って長期間”塩漬け”にしておく。目先の動きには絶対に左右されないこと。それだけだ。
①信頼できる企業、10年20年経ってもみんながほしいと思う商品を作っている会社にしか投資しないこと。
②ルール1「絶対に損をしないこと」。
ルール2「そのことを絶対に忘れないこと」。
・ウォーレン・バフェットの「大富豪への15カ条の成功方程式」
地道に確実に資産増やすための心得は、誰もが明日から実戦に応用できるので、少し多めにリストアップし、小見出しをつけてみた。
①興奮せず、欲張らず、身の丈で戦え
投資家の大敵は、「興奮」と「資金」だと知っておいて損はない。
②あせらず、好機の到来を待て
株式市場は見逃しのストライクがないゲームだ。すべての球を打つ必要はない-好球を待っていればいいのである。
③人を見る目を養うべし
ウォール街というところは、ロールスロイスに乗る人が地下鉄に乗る人からアドバイスを受ける唯一の場所だ。
④無駄なことは聞くな
散髪を必要とするかどうかを床屋に尋ねるような愚かな言動は決してしてはならない。
⑤頭がよくても、株で成功するとは限らない
投資というのは、IQ160の男がIQ130の男を負かすゲームではないんだよ。
⑥ビジネス現場の生きた情報を活かせ
ビジネスマンだからいい投資家でいられるし、投資家であるからいいビジネスマンといえる。
⑦コツコツ築いた評判を一瞬で崩すな
評価を勝ち取るには20年もかかるが、その評価を失うには5分もあれば十分だ。そう考えることができたら、それまでと違ったやり方をするはずだ。
⑧先達への感謝の気持ちを忘れるな
今、誰かが木陰に座って憩えるのは、昔、誰かがその木を植えたからだ。
⑨無謀なチャレンジは禁物だ
私は7フィートのバーを飛び越すような真似はしない。周囲を見回し、簡単にまたげる1フィートの高さのバーを捜すだけだ。
⑩狭い視野に陥るなかれ
ビジネス界の動きに敏感であろうとするなら、いつでも、フロントガラスから見るよりバックミラーの方から見るべきだ
⑪株は5年間のスパンで考えること
私は、「株式市場が、明日閉鎖され、その後5年間、再開のめどが立たない」と想定して株式を買っている。
⑫間違った判断を減らす努力をせよ
人生で心がけることは、正しくないことをできるだけ避け、正しいことを少しだけするようにすればいいのである。
⑬自分は自分、人は人
他の人たちが熱くなっているときは、その雰囲気に呑まれないようにしなければならない。
⑭いかなる場面でもクールであれ
「自分を見失うと危険」という警句を胸に刻んでおくことだ。
⑮物事を複雑に考えない習慣をつけるべし
簡単なことを難しく考えてしまうのが、人間の弱さではないだろうか。
・ラリー・エリソンは、若い頃、日本で働いた経験がある。大学を中退したラリー・エリソンは、1973年、シリコンバレーのアムダールに就職。同社は、IBMをスピンアウトしたジーン・アムダールがその3年前に設立し、1年前から富士通と資本提携していた。そんな関係で、ラリー・エリソンは日本へ出張したのだ。だがアムダールは、技術的な問題をクリアできずに経営を悪化させ、ラリー・エリソンは解雇。プロ用ビデオ機器などをつくるアンペックスに転職した。同社は、1956年に世界で最初にVTRを商品化した企業である。人生、何が幸いするかわからない。ラリー・エリソンは、そこで知り合った気の合う仲間二人と語らって、1977年6月16日に起業。自己資金は1400ドル(約38万円)だった。同社は2度、社名変更し、1983年に「神託」を意味する「オラクル」という現在の社名となり、今日に至るのである。2015年4月上旬、ラリー・エリソンは来日、オラクルが開催したイベントで、こう話した。「日本企業での経験で経営者としての働き方を身につけた気がする。長時間努力を惜しまないトレーニングになった」ラリー・エリソンは、日本流のがむしゃらな仕事っぷりで成功したが、それほど稼ぎがない時分からスケールのでっかい目立つ遊び方をしてきた。「とことん働き、とことん遊ぶ」「オンとオフの切り替えが抜群にうまい」のがラリー・エリソンの特徴であり、そういうこともビリオネアになるために必要な条件といえるようだ。
・オラクルのラリー・エリソンの「大富豪への9カ条の成功方程式」
①人生は旅だ。自分の限界を見つける旅なのだ。
②人は夢を追う生き物だと信じて疑わない。私はそうしてきたのだ。
③望みを達成するためには、自分のやることを信じなければならない。
④ビジネス戦線では、ほかの人のまねをしていたら勝つことなどできない。人より先んじられる唯一の方法は、人とは違っているということだ。
⑤「金儲けより」も重要なもの。それは、ずっと一番であり続けることだ。
⑥革新的なことをやりたかったら、世間から変人呼ばわりされることを覚悟しないといけない。
⑦働いて働きぬかなければならないときは、今を置いてないと思え。
⑧ソーシャル・ネットワークは、現代のサービスアプリケーションのパラダイムである。
⑨大業へと人を駆り立てるものは何かといえば、成功を追い求める気持ちはさほどなく、失敗することへの恐怖の方が強い。
・ウォルマート創業者のサム・ウォルトンの「大富豪への10カ条の成功方程式」
①いつも仕事に忠実であること
②利益はすべての仲間(従業員)と分かち合い、彼らをパートナーとして遇すること。
③パートナーのやる気(モチベーション)を引き出すようにすること。
④パートナーにはできるだけ隠しごとなど一切せず、互いの気持ちが通い合うようにすること。
⑤仲間がした仕事は、どんな小さなことでも感謝する気持ちを忘れないこと。
⑥成功したら、思いっきり自分を褒めるようにすること。
⑦どんな社員の声にも耳を傾けるように心がけること。
⑧お客様の期待以上のことをしようとする心がけを持つこと。
⑨競合相手よりも節約する工夫を心がけること。
⑩チャンスの目は人がやろうとしないところにある、と考えること。
・カジノ王のシェルドン・アデルソンの「大富豪への6カ条の成功方程式」
①確実であることが何よりも重要だ。ビジョンを描き、間違いないと確信したら、実行せよ。
②あらゆるビジネスに共通することは、どれくらい継続させられるか。どうすれば現状を変えられるかということだ。
③人と違うようにするだけだ。ほかの人がやらない方法で人生に関わることをせよ。
④起業家に必要なのは、リスクとは報酬であり、報酬とはリスクであるとする考え方だ。
⑤誰も私を助けてくれなかった。すべて自力でやるしかなかったのだ。
⑥見本市には成長商品の種が転がっている。
・ロックフェラーが92歳だった昭和7年(1932年)の人気少年雑誌「キング」は、新年号付録「偉人はかく教える」のロックフェラーの項の冒頭に次の言葉を太字で記した。
「殖やさなければ減るのが金の性質である。」
その後の文章も紹介しよう。
「現代で一番よく到富の術を心得ている人の一人はロックフェラーである。もっとも彼は単なる金貯め機械ではない。
「うんと稼ぎ、うんと貯め、うんと寄付せよ」
それが彼の一生のモットーであった。だから月給25円の番頭時代から、彼は月々きちんきちんと貯金すると同時に、毎週2銭ずつ、教会に寄付することを忘れなかった。彼が一生のうちに稼いだ50億円のうち、30億円は寄付して、今の財産は20億円と言われる。
・ロスチャイルドの「大富豪への10カ条の成功方程式」
①人生の競争にあたって勇敢なれ
②ことに臨んで機敏になれ
③十分に考え、しかして速やかに決断せよ。
④進むに大胆なれ。
⑤巧みに時を使用せよ。
⑥自己の人物を実際以上に装うべからず。
⑦強き酒を飲むな。
⑧忍耐よく困難に耐えよ
⑨決して失意することなかれ
⑩ぎょうこうを頼みとするな
かくして精励すれば成功は期せずして得られるべし。
・ベンジャミン・フランクリンの「徳目」13カ条
①節制 頭の回転が鈍るまで食べるな。ぐでんぐでんになるまで飲むな。
②沈黙 自分にも他人にも無益なことを口にするな。くだらない会話を避けよ。
③規律 持ち物は場所を決めておけ。仕事は時間配分を決めてからかかれ。
④決断 やるべきことを実行する決意をせよ。決意したら、しくじずに行え。
⑤節約 自分にも人にも役立たないことに金を使うな。つまり、浪費はするな。
⑥勤勉 時間を無駄にするな。つねに有益なことをせよ。不必要な行動は控えよ。
⑦誠実 策略で人を傷つけるな。良心に恥じないよう公正に判断し、口を開くときは話す内容にふさわしい話し方をせよ。
⑧正義 他人の利益を邪魔したり、与えるべき利益を与えないなどして他人に損害をもたらすな。
⑨中庸 極端に走るな。不当に傷つけられ、憤って当然のときもじっと耐えろ。
⑩清潔 体、服、住まいを不潔にするな。
⑪平静 ささいなこと、ありふれた、避けがたい自己で取り乱すな。
⑫純潔 性の交わりは、健康のためか子づくりのためにだけ行え。むやみにふけって、頭脳を鈍らせ、心身を弱らせ、自分や伴侶の平和ないしは信用を損なわないようにせよ。
⑬謙譲 イエスおよびソクラテスを見習え
・アンドリュー・カーネギーの「大富豪への成功方程式」10カ条
①富を得るには、すべての卵をひとつのかごに積めて、大切に見守ることだ。
②やるべきことだけをするのではなく、少しでもいいからそれ以上のことをすることだ。そうすれば、未来はその人に微笑むだろう。
③他人をリッチにできない者に、リッチになる資格はない。
④幸せになりたいなら、まず目標を定め、全力を投入して、望みに燃え、自らを鼓舞せよ。
⑤笑顔を忘れるな。笑う門には福来る、だ。
⑥どんな素晴らしい才能があったとしても、やる気のない人間は、つまらない人生に満足するしかない。
⑦たったひとりで仕事をするよりも、他人の助力を得る方が一段と素晴らしい仕事ができると悟ったとき、人は大きな進歩を遂げるものなのだ。
⑧成功する秘訣は、自分の仕事に求めるのではなく、その仕事にふさわしい適材を見つけることにある。
⑨努力しない者を助けようとしても無駄である。はしごを上ろうとする意志がない者を誰かが押し上げることなど到底できっこないのだ。
・”アメリカのロイヤルファミリー”とまでいわれる名門ケネディ家の先祖は1849年にアイルランドからボストンへ渡ったパトリック・ケネディから始まる。だが、彼や長男はコレラで死に、次男パトリック・ジョセフが14歳から港湾労働者となって母と3人の姉を養いながら金を貯め、バーを開業すると、これが大当たり。店は上流階級の集まる社交場となり、20代でマサチューセッツ州議会の下院議員に出世する。洋酒輸入会社の買収、石炭会社の株式保有など事業・投資にも触手を伸ばした。これが、ケネディ家のルーツである。大富豪に成り上がるのは、パトリックの息子ジョセフの代だ。ハーバード大学を卒業すると実業界に飛び込み、弱冠25歳でコロンビア・トラスト銀行の頭取になる。子は父の背中を見て育つというが、ジョセフはその典型。酒や投資に目をつけ、今日ならインサイダーになる強引な手口で大儲けし、禁酒法時代にはマフィアと結託して密造酒で巨万の富を得た。相場勘も鋭く、1929年の大暴落直前に所有株を売り払っている。政治的野心も半端ではなく、ひそかに大統領の椅子をねらっていた。ジョセフは強引な手口で資産を増やし続け、ルーズベルトを資金面でバックアップして大統領に2度当選させた見返りとして、駐英大使のポストを手に入れるが、親ナチス・反ユダヤ的な発言を繰り返して失脚。野望の実現を長男ジョセフ・ケネディJrに託していたが、Jrは第二次世界大戦で戦死。次男ジョンの出番となり、見事、大統領になったのである。
・モナコは王国ではなく公国である。王や王女が統治する君主国家を王国と呼び、立憲君主制と絶対君主制があるのに対し、公爵などの貴族が君主として統治する国家を公国といっている。
立憲君主制の王国・・・英国、オランダ、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、ベルギー、タイ、カンボジア、マレーシア、モロッコ。
絶対君主制の王国・・・サウジアラビア、ブルネイ。
公国・・・モナコ、リヒテンシュタイン
・2位のコーク一族にしろ、3位のマース一族にしろ、4位のカーギルにしろ、長く生き残るビリオネア・ファミリーには、共通する「成功方程式」が存在する。親子兄弟姉妹の仲がよく、遺産をめぐる争いを起こさないという点だ。「結束が固い一族」は、繁栄するのである。「ベスト20」の顔ぶれを創業時期の違いで分けると、次のようになる。
19世紀前半 デュポン、メロン、ジョンソン
19世紀後半 ブッシュ、ハースト、カーギル、コックス、SCジョンソン、ブラウン、ドランス。
20世紀前半 マース、コーク、ジフ、ハント、ニューハウス、プリッカー、ローダー、チャールズ&ルパート・ジョンソン。
20世紀後半 ウォルトン、ダンカン。
良かった本まとめ(2016年上半期)
<今日の独り言>
Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします。
















 「ぼくたちに、もうモノは必要ない。」の購入はコチラ
「ぼくたちに、もうモノは必要ない。」の購入はコチラ 











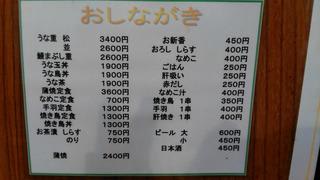

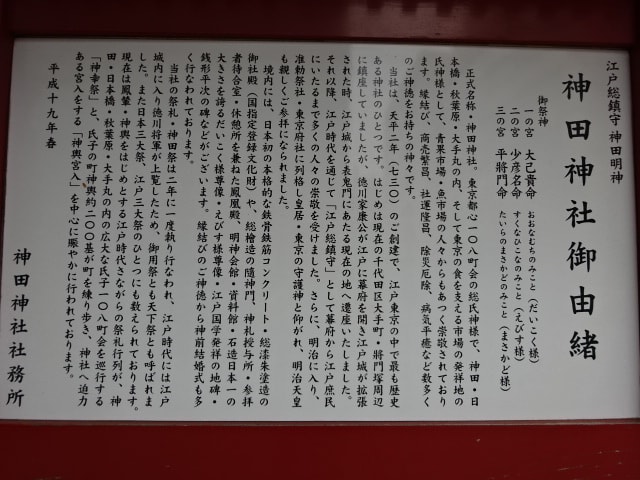




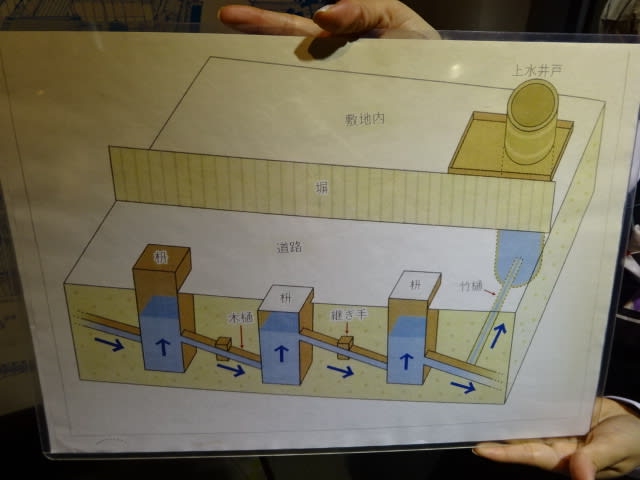




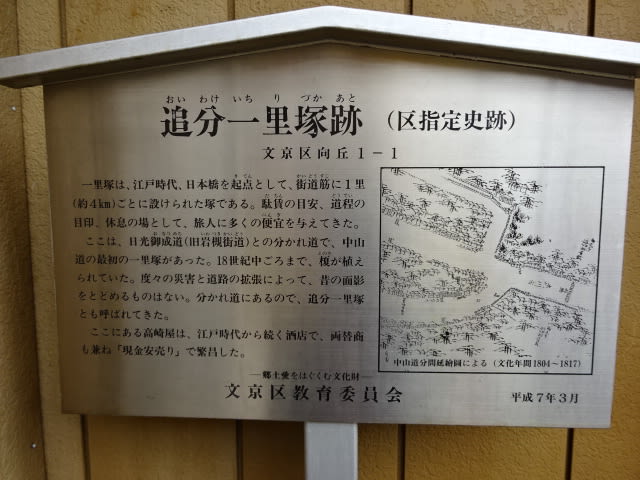

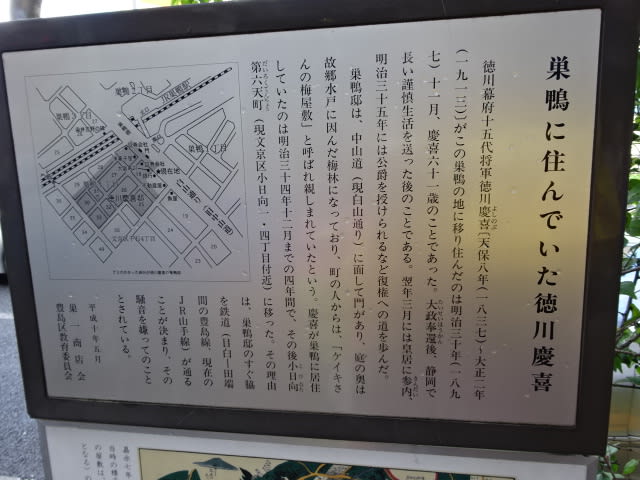
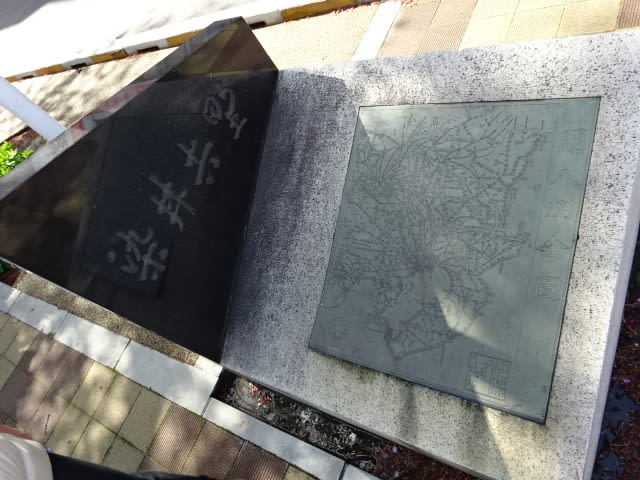


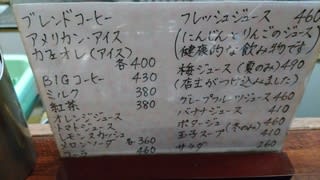









 「103歳になってわかったこと」の購入はコチラ
「103歳になってわかったこと」の購入はコチラ 







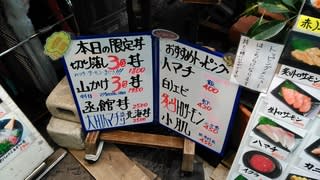











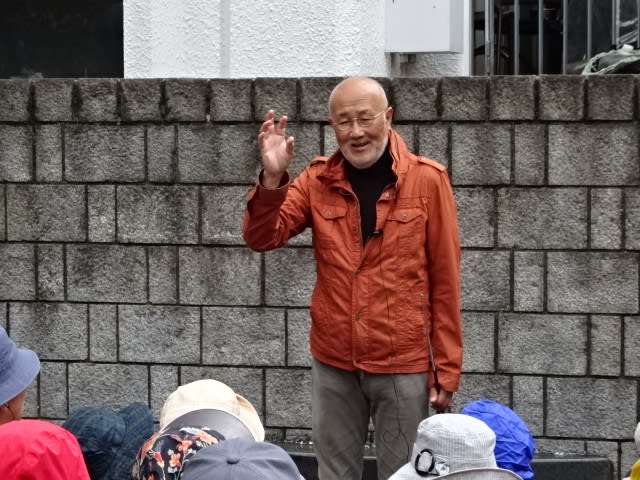


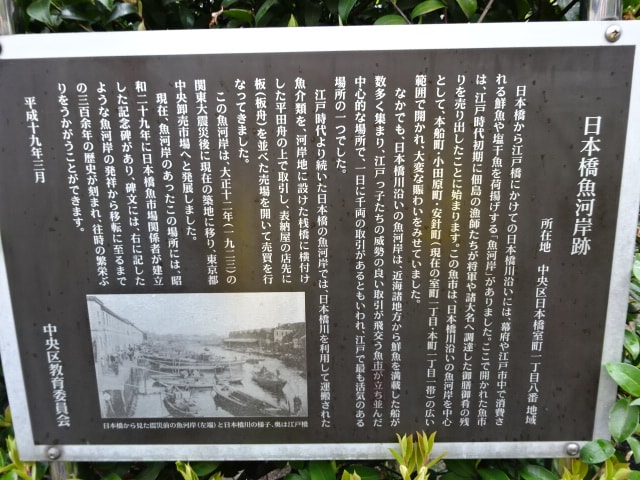
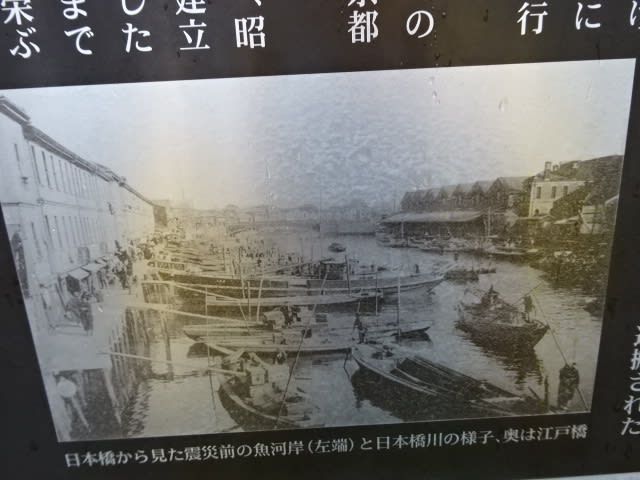



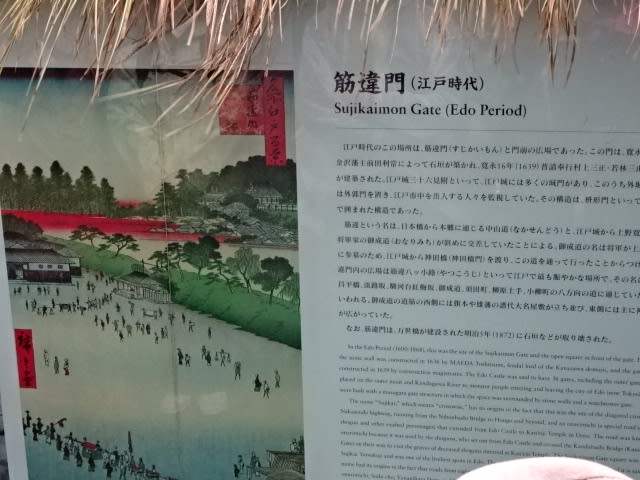
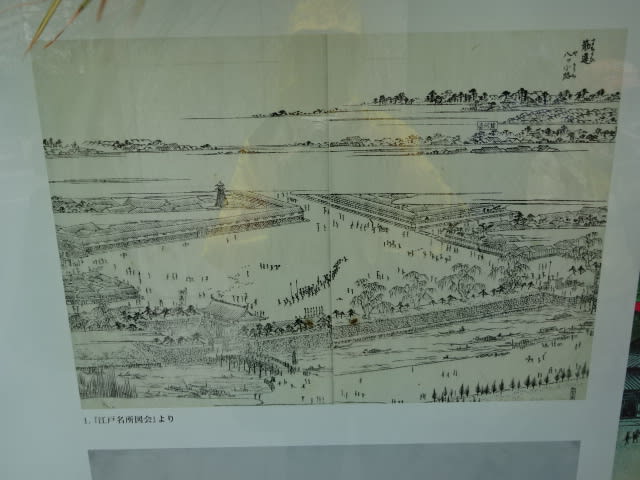
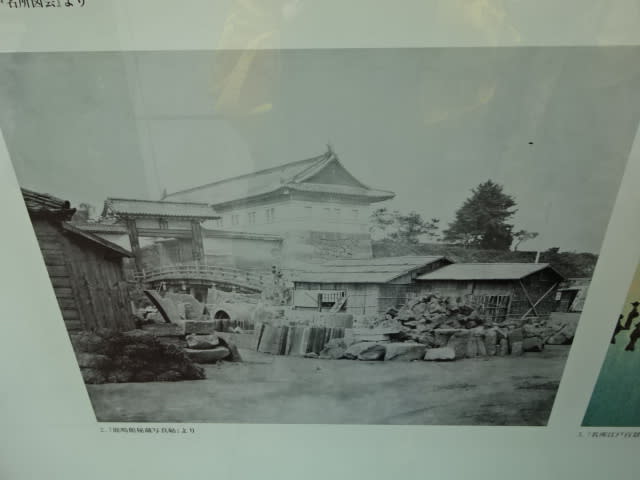
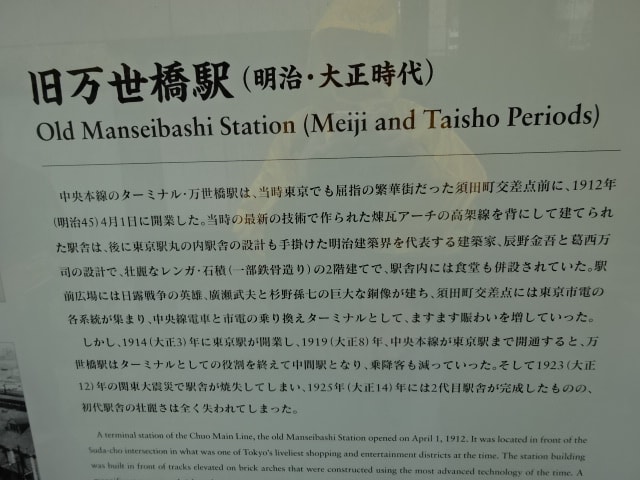

 「「世界の大富豪」成功の法則」の購入はコチラ
「「世界の大富豪」成功の法則」の購入はコチラ 




