友人に教えてもらい、東京大丸ミュージアムで10月25日まで開催されている「古代カルタゴとローマ展」を観に行ってきました。かつてその巧みな航海術と交易で地中海に君臨したフェニキア人の通商国家「カルタゴ」。戦史上に燦然と輝く名将ハンニバルを生み、「地中海の女王」と称えられたカルタゴが歴史の彼方に消えていった経緯には多くの教訓があると以前から感じていました。
今日は『興亡の世界史03 通商国家カルタゴ』(栗田伸子、佐藤育子:講談社)より、カルタゴ滅亡までの経緯を追ってみたいと思います。
第二次ポエニ戦争(前219年~前201年)の緒戦、戦史上名高いカンナエの戦い(前216年)でローマ軍を完膚なきまでに殲滅し、南イタリアを完全に制圧したかに見えたハンニバルでしたが、そこから何故か戦局は長い膠着状態に陥ります。「戦争は他の手段をもってする政策の延長に過ぎない」と喝破したのは19世紀、プロイセンの軍学者クラウゼビッツでしたが、そもそもローマとの軍事的勝利によって達成する政治目的が何であるのか、ハンニバルにとってもカルタゴ政府にとっても不明確であったようです。つまり「政策の延長としての戦争」になっていなかった事が、現在でも会戦の金字塔として、軍事学の教書に必ず取上げられるほどの大勝利であったカンナエの戦いを活かしきることができず、そればかりかカルタゴの滅亡を招いた最大の要因であったように思います。
ハンニバルはイタリア本土を攻撃することによって、ローマの支配体制そのものを崩壊させることができると期待したようですが、実際にはそうはならず、カルタゴは自国が有利な局面での戦争の早期終結の機会を逸してしまいました。
「政治目的の欠如」はその後もカルタゴのちぐはぐな対応となって、至るところに表れます。まず、南部イタリアにおけるハンニバルの決定的大勝利、またハンニバルの再三にわたる要請にもかかわらず、カルタゴ政府は南イタリアに援軍を送りませんでした。ローマという大敵を目前にしながら、本国内部の政争にあけくれた結果でした。ハンニバル自身が「ハンニバルを打ち負かしたのはローマ人ではなくカルタゴ元老院の悪意と中傷だ」と言ったように、自国の内部にいる者が進んで国を滅亡に追いやった例は、歴史上枚挙に暇がないのです。
一方、西方のイベリア半島戦線においても、前211年にローマのスピキオ兄弟を破り壊滅状態に追い込んだにもかかわらず、今度はカルタゴ軍内部の内紛によって決定的な勝機を逸してしまいます。その後、カルタゴはイタリア、スペイン、アフリカ全ての方面において敗走の一途を辿ることになります。
前202年、北アフリカのザマにおいてハンニバルは大スキピオに敗れ(ザマの戦い)、第二次ポエニ戦争は終わりを告げます。ローマの講和条件を受諾した結果、カルタゴは10隻を除く全軍船の引渡し、戦象の引渡し、アフリカの外のいかなる民族に対しても戦争をしないこと、アフリカ内部でもローマの承認なしには戦争をしないこと、賠償金として50年賦で銀10,000タラントを支払うこと、などの過酷な条件が課せられました。
ところが第二次ポエニ戦争の後、わずか50年の間にカルタゴは再び奇跡的な復興を遂げます。商品作物の生産や商工業が再び発展し、特に仇敵ローマとの盛んな貿易によって巨富を築きました。戦後課せられた50年賦10,000タラントもの賠償金を敗戦後わずか10年で一括払いしようと申し出たという逸話はカルタゴの戦後復興と繁栄振りを窺わせます。
第三次ポエニ戦争(前149年~前146年)が何故起こったのか、大カトーの有名な言葉を借りれば、何故「カルタゴは滅ぼされなければならなかった」のかについては諸説がありますが、カルタゴの繁栄がローマに危機感を与えたことと、第二次ポエニ戦争を契機としてローマが明確に地中海世界の覇権国家としての道を歩み始めたことが関係していることは確かなようです。
とはいえ、昔も今も大義名分がなければ戦争はなかなか起こせません。ローマにつけいる隙を与えさせたのは、カルタゴの隣国ヌミディアとの交戦でした。第二次ポエニ戦争の後、カルタゴの隣国ヌミディアはカルタゴのアフリカ領を自国に併呑する野心を抱き、カルタゴの属領に侵攻しました。カルタゴはローマに調停を求めますが、ローマは態度を明らかにせず、結果としてこの属領はヌミディアに併呑されることとなってしまいました。この時、カルタゴ政界には「ヌミディアに領土問題で譲歩してもローマとの開戦を回避しよう」という親ヌミディア派が存在していました。しかし、ヌミディアが次にカルタゴのアフリカ領中枢部の領有を主張し始めると、カルタゴ内の対ヌミディア強硬派は親ヌミディア派を追放してしまいます。追放された親ヌミディア派はヌミディアに開戦を勧め、ヌミディア軍はカルタゴの都市を包囲しました。またしてもカルタゴは内部の造反者によって国難を迎えることになったのでした。
ローマとの講和条件を堅持してきたカルタゴでしたが、国の中枢部が侵されるにあたってついに前150年、ヌミディアとの戦争状態に入りました。そしてこれが、ローマに開戦の口実を与えることになったのです。ローマの開戦準備を知ったカルタゴは狼狽し、戦争を回避するためローマとの交渉に入りますが、ローマは応じません。その後も交渉の過程で人質としてカルタゴ貴族の子弟300人を差し出す、あらゆる武器を引き渡すなど、無理難題を耐えローマの寛容に期待しましたが、ローマは武器引渡しが済むやカルタゴへの侵攻を開始したのです。ここでも政治目的の欠如したカルタゴと、明確な政治目的をもって臨むローマとの差は歴然でした。目的のない国家は歴史の必然として消え行く運命にあるのかもしれません。カルタゴはその後3年に及ぶ包囲戦を持ちこたえましたが、ついに前146年力尽き滅亡しました。市街は二度と復興できないよう、7日間に渡り完膚なきまでに破壊しつくされたといいます。
カルタゴはその後、滅亡より102年後にローマの初代皇帝アウグストゥスによって再建され、やがて首都ローマ、アレクサンドリアと並ぶ帝国内で最も繁栄した都市の一つとなりました。「古代カルタゴとローマ展」ではその時の繁栄振りを物語るモザイクなどが展示されています。しかしそれらはあくまで「ローマのカルタゴ」であって、恐らくその当時のカルタゴ市民は、自分たちがポエニのカルタゴ人の子孫であるという自覚すらなかったことでしょう。やはり「地中海の女王」カルタゴは前146年で地上から消滅し、わずかに博物館や遺跡でその痕跡をとどめるのみとなったのです。
繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした
よろしければクリックおねがいします!
↓
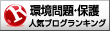
今日は『興亡の世界史03 通商国家カルタゴ』(栗田伸子、佐藤育子:講談社)より、カルタゴ滅亡までの経緯を追ってみたいと思います。
第二次ポエニ戦争(前219年~前201年)の緒戦、戦史上名高いカンナエの戦い(前216年)でローマ軍を完膚なきまでに殲滅し、南イタリアを完全に制圧したかに見えたハンニバルでしたが、そこから何故か戦局は長い膠着状態に陥ります。「戦争は他の手段をもってする政策の延長に過ぎない」と喝破したのは19世紀、プロイセンの軍学者クラウゼビッツでしたが、そもそもローマとの軍事的勝利によって達成する政治目的が何であるのか、ハンニバルにとってもカルタゴ政府にとっても不明確であったようです。つまり「政策の延長としての戦争」になっていなかった事が、現在でも会戦の金字塔として、軍事学の教書に必ず取上げられるほどの大勝利であったカンナエの戦いを活かしきることができず、そればかりかカルタゴの滅亡を招いた最大の要因であったように思います。
ハンニバルはイタリア本土を攻撃することによって、ローマの支配体制そのものを崩壊させることができると期待したようですが、実際にはそうはならず、カルタゴは自国が有利な局面での戦争の早期終結の機会を逸してしまいました。
「政治目的の欠如」はその後もカルタゴのちぐはぐな対応となって、至るところに表れます。まず、南部イタリアにおけるハンニバルの決定的大勝利、またハンニバルの再三にわたる要請にもかかわらず、カルタゴ政府は南イタリアに援軍を送りませんでした。ローマという大敵を目前にしながら、本国内部の政争にあけくれた結果でした。ハンニバル自身が「ハンニバルを打ち負かしたのはローマ人ではなくカルタゴ元老院の悪意と中傷だ」と言ったように、自国の内部にいる者が進んで国を滅亡に追いやった例は、歴史上枚挙に暇がないのです。
一方、西方のイベリア半島戦線においても、前211年にローマのスピキオ兄弟を破り壊滅状態に追い込んだにもかかわらず、今度はカルタゴ軍内部の内紛によって決定的な勝機を逸してしまいます。その後、カルタゴはイタリア、スペイン、アフリカ全ての方面において敗走の一途を辿ることになります。
前202年、北アフリカのザマにおいてハンニバルは大スキピオに敗れ(ザマの戦い)、第二次ポエニ戦争は終わりを告げます。ローマの講和条件を受諾した結果、カルタゴは10隻を除く全軍船の引渡し、戦象の引渡し、アフリカの外のいかなる民族に対しても戦争をしないこと、アフリカ内部でもローマの承認なしには戦争をしないこと、賠償金として50年賦で銀10,000タラントを支払うこと、などの過酷な条件が課せられました。
ところが第二次ポエニ戦争の後、わずか50年の間にカルタゴは再び奇跡的な復興を遂げます。商品作物の生産や商工業が再び発展し、特に仇敵ローマとの盛んな貿易によって巨富を築きました。戦後課せられた50年賦10,000タラントもの賠償金を敗戦後わずか10年で一括払いしようと申し出たという逸話はカルタゴの戦後復興と繁栄振りを窺わせます。
第三次ポエニ戦争(前149年~前146年)が何故起こったのか、大カトーの有名な言葉を借りれば、何故「カルタゴは滅ぼされなければならなかった」のかについては諸説がありますが、カルタゴの繁栄がローマに危機感を与えたことと、第二次ポエニ戦争を契機としてローマが明確に地中海世界の覇権国家としての道を歩み始めたことが関係していることは確かなようです。
とはいえ、昔も今も大義名分がなければ戦争はなかなか起こせません。ローマにつけいる隙を与えさせたのは、カルタゴの隣国ヌミディアとの交戦でした。第二次ポエニ戦争の後、カルタゴの隣国ヌミディアはカルタゴのアフリカ領を自国に併呑する野心を抱き、カルタゴの属領に侵攻しました。カルタゴはローマに調停を求めますが、ローマは態度を明らかにせず、結果としてこの属領はヌミディアに併呑されることとなってしまいました。この時、カルタゴ政界には「ヌミディアに領土問題で譲歩してもローマとの開戦を回避しよう」という親ヌミディア派が存在していました。しかし、ヌミディアが次にカルタゴのアフリカ領中枢部の領有を主張し始めると、カルタゴ内の対ヌミディア強硬派は親ヌミディア派を追放してしまいます。追放された親ヌミディア派はヌミディアに開戦を勧め、ヌミディア軍はカルタゴの都市を包囲しました。またしてもカルタゴは内部の造反者によって国難を迎えることになったのでした。
ローマとの講和条件を堅持してきたカルタゴでしたが、国の中枢部が侵されるにあたってついに前150年、ヌミディアとの戦争状態に入りました。そしてこれが、ローマに開戦の口実を与えることになったのです。ローマの開戦準備を知ったカルタゴは狼狽し、戦争を回避するためローマとの交渉に入りますが、ローマは応じません。その後も交渉の過程で人質としてカルタゴ貴族の子弟300人を差し出す、あらゆる武器を引き渡すなど、無理難題を耐えローマの寛容に期待しましたが、ローマは武器引渡しが済むやカルタゴへの侵攻を開始したのです。ここでも政治目的の欠如したカルタゴと、明確な政治目的をもって臨むローマとの差は歴然でした。目的のない国家は歴史の必然として消え行く運命にあるのかもしれません。カルタゴはその後3年に及ぶ包囲戦を持ちこたえましたが、ついに前146年力尽き滅亡しました。市街は二度と復興できないよう、7日間に渡り完膚なきまでに破壊しつくされたといいます。
カルタゴはその後、滅亡より102年後にローマの初代皇帝アウグストゥスによって再建され、やがて首都ローマ、アレクサンドリアと並ぶ帝国内で最も繁栄した都市の一つとなりました。「古代カルタゴとローマ展」ではその時の繁栄振りを物語るモザイクなどが展示されています。しかしそれらはあくまで「ローマのカルタゴ」であって、恐らくその当時のカルタゴ市民は、自分たちがポエニのカルタゴ人の子孫であるという自覚すらなかったことでしょう。やはり「地中海の女王」カルタゴは前146年で地上から消滅し、わずかに博物館や遺跡でその痕跡をとどめるのみとなったのです。
 | 通商国家カルタゴ (興亡の世界史)佐藤 育子,栗田 伸子講談社このアイテムの詳細を見る |
繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした

よろしければクリックおねがいします!
↓


















