都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「風俗画と肉筆浮世絵 - 館蔵肉筆画の精華 - 」(後期展示) たばこと塩の博物館
たばこと塩の博物館(渋谷区神南1-16-8)
「風俗画と肉筆浮世絵 - 館蔵肉筆画の精華 - 」(後期展示)
5/24-7/1
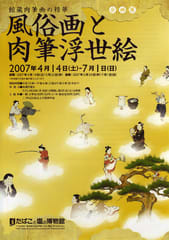
渋谷の繁華街のど真ん中にある博物館です。何度も前を通った記憶がありますが、中へ入ったのは初めてでした。館蔵の風俗画、または肉筆浮世絵が約40点ほど展示されています。入館料は100円です。

端的な博物館名が示すように、コレクションの中核は、たばこと塩に関連する浮世絵でした。ようは、展示品の多くに煙草を嗜む人物が描かれ、または塩を作る人々が登場しているわけなのです。長い煙管を加え、のんびりとしたさまで楽し気にくつろぐ宮川一笑の「色子」などを見ると、何かとその害の叫ばれる現代とは異なり、たばこがある種の文化を築いてきた歴史を思うような気もします。さすがに塩焼きの光景は今でもなかなか見られませんが、総じて肩の張らない、それこそ往時の庶民の息遣いをリアルに感じられるような作品ばかりでした。名の知れた絵師は皆無に近いものがありますが、その分、先入観なしで江戸時代の生活へと想いを馳せることが出来ると思います。
たばこ、塩以外の作品もいくつか出ていましたが、その中で特に印象深かったのは「蝦夷人風俗絵巻」(作者不明)でした。作品の言葉を借りると「蝦夷人」が、鉄砲を片手に、鹿や熊を勇ましく狩っています。また「蝦夷」関連では、この他にも雪好の「蝦夷人風俗図」などが出ていました。これらはやはり、作者が当地へ渡って描いた作品なのでしょうか。「蝦夷」を題材とした作品を見るのは初めてだったもので、とても新鮮な感覚で楽しめました。
久隅守景の「塩焼きの図」も魅力的です。淡彩着色とありましたが、さながら墨絵のような味わいで伸びやかに塩焼きの光景を描いています。たっぷりととられた余白にも美を感じる作品でした。人々が、まるで小人の人形ように可愛らしく表現されています。
会期は迫っていますが、渋谷の喧噪から逃れるにも最適な展覧会だと思います。館内は空いていました。
7月1日までの開催です。(6/23)
「風俗画と肉筆浮世絵 - 館蔵肉筆画の精華 - 」(後期展示)
5/24-7/1
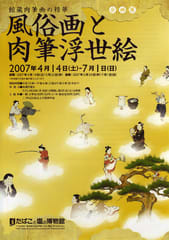
渋谷の繁華街のど真ん中にある博物館です。何度も前を通った記憶がありますが、中へ入ったのは初めてでした。館蔵の風俗画、または肉筆浮世絵が約40点ほど展示されています。入館料は100円です。

端的な博物館名が示すように、コレクションの中核は、たばこと塩に関連する浮世絵でした。ようは、展示品の多くに煙草を嗜む人物が描かれ、または塩を作る人々が登場しているわけなのです。長い煙管を加え、のんびりとしたさまで楽し気にくつろぐ宮川一笑の「色子」などを見ると、何かとその害の叫ばれる現代とは異なり、たばこがある種の文化を築いてきた歴史を思うような気もします。さすがに塩焼きの光景は今でもなかなか見られませんが、総じて肩の張らない、それこそ往時の庶民の息遣いをリアルに感じられるような作品ばかりでした。名の知れた絵師は皆無に近いものがありますが、その分、先入観なしで江戸時代の生活へと想いを馳せることが出来ると思います。
たばこ、塩以外の作品もいくつか出ていましたが、その中で特に印象深かったのは「蝦夷人風俗絵巻」(作者不明)でした。作品の言葉を借りると「蝦夷人」が、鉄砲を片手に、鹿や熊を勇ましく狩っています。また「蝦夷」関連では、この他にも雪好の「蝦夷人風俗図」などが出ていました。これらはやはり、作者が当地へ渡って描いた作品なのでしょうか。「蝦夷」を題材とした作品を見るのは初めてだったもので、とても新鮮な感覚で楽しめました。
久隅守景の「塩焼きの図」も魅力的です。淡彩着色とありましたが、さながら墨絵のような味わいで伸びやかに塩焼きの光景を描いています。たっぷりととられた余白にも美を感じる作品でした。人々が、まるで小人の人形ように可愛らしく表現されています。
会期は迫っていますが、渋谷の喧噪から逃れるにも最適な展覧会だと思います。館内は空いていました。
7月1日までの開催です。(6/23)
コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )









