アドラー心理学に基づく勇気づけの研修(外部研修も)とカウンセリングを行う ヒューマン・ギルド の岩井俊憲です。
今朝は早い時間の新幹線で出かけるので、とても早い時間のブログの更新です。
今日も3つのことについてお伝えします。
1.霞が関の某官庁で【管理者】のための研修
2.致知出版社のメルマガ:『経営者を育てるアドラーの教え』
3.「このブログのフォロワーになってください!」
1.霞が関の某官庁で【管理者】のための研修
昨日の午後は、霞が関で某官庁での管理職研修を100人を対象に行っていました。
会場、オンライン双方のハイブリッド型研修でした。
3つのケースについて討議も交え、私がコメントと講義を加えるかたちの方式でした。
アドラー心理学が新鮮に映ったようです。
来週も同じような形式と規模で行います。
私のサラリーマン生活は、お隣の駅の虎ノ門であったので、この近くがとても懐かしかったです。

2.致知出版社のメルマガ:『経営者を育てるアドラーの教え』
致知出版社のメルマガでドラッカーとカントと並んでアドラーのことが紹介され、拙著『経営者を育てるアドラーの教え』の一部が転載されていました。
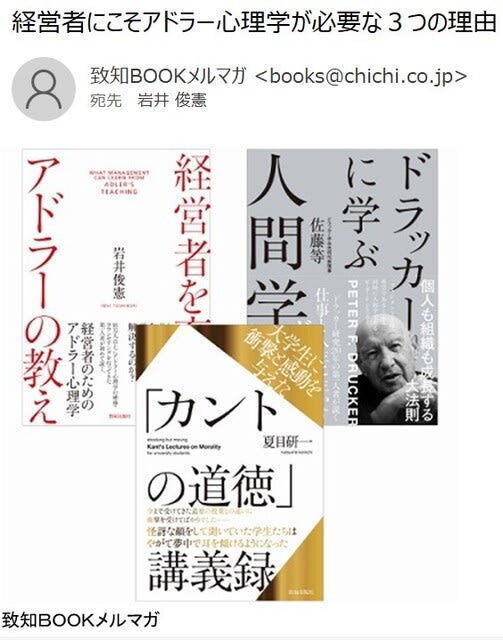
本日は、『経営者を育てるアドラーの教え』の一部をご紹介します。
…………………………………………
経営者にこそアドラー心理学が必要な3つの理由
…………………………………………
私は35歳で会社を退職したあとアドラー心理学を学び始めましたが、学ぶほどに「経営者にこそアドラー心理学が必要だ」という思いに到りました。
なぜアドラー心理学が経営に役立つのでしょうか。
それには大きく三つの理由があります。
第一の理由は、会社にはさまざまな個性を持つ人間が参加しているということです。
会社を成長させるために、経営者はそうした人間の能力を正しく評価し、引き出していかなくてはいけません。
そのためには「人間をどう見るか」という人間観が絶対に欠かせません。
人間を肯定的に見るか否定的に見るかによって、その人の見え方は全く違ってきます。
アドラー心理学では人間を肯定的に見ることを教えます。
そして、そういう人間観に基づいて見れば、人間には無限の可能性があるのです。
経営者がそうした人間観を持つことが会社を成長させるもとになると私は思っています。
第二の理由は、アドラー心理学は、過去の原因は問わず、未来に向けて何ができるかを模索するものだということです。
この考え方は会社の目的・目標を見るということにつながり、非常に未来志向です。
過去の失敗を反省することはもちろん大切ですが、原因追及ばかりでは成長できません。
これは人も会社も同じです。
過去の反省を踏まえ、未来に向けて何ができるかを考える。
それが社員のモチベーションを高め、会社を前進させる力になります。
その点で、未来志向のアドラー心理学は経営に適していると言えるのです。
第三の理由は、アドラー心理学のベースにある「勇気づけ」という考え方が組織を元気にするということです。
実際に、アドラー心理学を学んだ経営者が非常に生き生きとして元気になるという例をたくさん見ています。
経営に自信が持てるようになると同時に、人間の可能性を信じることによって「自分だけがひたすら頑張らなくても自分のチームの中に優れた人材がいる」ことに気づくようになります。
この経営者の気づきが社内全体を活気づけることにつながります。
社内コミュニケーションがよくなり、モチベーションが上がります。
社員が「社長は変わった」と思うようになると、経営者のビジョンも浸透しやすくなるのです。
日本人はネガティブ探しが得意です。
あそこが悪い、ここが悪い、親が悪い、周囲が悪いと欠点ばかり探しています。
でも、意外に見落としているのは自分自身の可能性です。
自分自身を見つめて自分の中にあるリソース(資源)・可能性を探してみると、意外にもたくさん見つかります。「自分は大したことない」と思っている人でも、自分で自分を振り返り、周囲の人に自分のいいところを言ってもらうなどして、それを自分自身にフィードバックすると、いろいろな可能性が見つかってきます。
その結果、「そうか、自分にはこういういい面があるんだな」「今までの生き方は間違っていなかったな」と、自分を肯定的に見ることができるようになるのです。
それが自信となって、可能性が開花していくのです。
ネガティブな面にばかり目を向けていると、そうした可能性を発揮できません。
また、それを相手のニーズと結びつけることもできません。
これは非常にもったいない話です。
先に言ったようにアドラー心理学は人間を肯定的に見ようとしますから、一人ひとりの可能性を引き出すために非常に効果的なのです。
ただし、アドラー心理学が過去の原因を問わないと言っているのは、人間の行動についてです。
経営手法について問題が生じれば、それは原因を探して是正する必要があります。
もっとも原因探しするといくらでも出てきますし、どうでもいいような夾雑物も混じります。
そういう点では、失敗の原因追及ばかり行うのは無意味ですし、とりわけ人間の行動に関してそれをやることは望ましくないのです。
【本書にはこんな内容が掲載されています】
・経営者にこそアドラー心理学が必要な3つの理由
・アドラー心理学を用いた叱り方の2つのポイント
・失敗をした人には必ず敗者復活のチャンスを与える
・信用と信頼はどこが違うのか
・経営者は耳学問の大家になれ
・スタッフが牛耳り始めた会社はおかしくなる
・期待にはハシゴをかけろ
・共感とは、相手の目で見、相手の耳で聴き、相手の心で感じること
・相手を効果的に説得する5つのポイント
・イノベーションの一番の抵抗勢力になるのは、社長自身?
・社員の姿勢が変革のモデルにならなくてはいけない
・困ったときは10のアイデアを出せ
・ネガティブなフィードバックを歓迎する上司は必ず成長する
・感謝の見逃し三振はしてはいけない
・国も会社も人も、あらゆるものはミッションから始まる
・経営者の意識と行動が変われば、会社は変わる
9月から来年の7月まで某中小企業の取締役、執行役員の6名を対象にヒューマン・ギルドで『経営者を育てるアドラーの教え』をサブテキストとして経営者教育を担当しています。
3.「このブログのフォロワーになってください!」
私は、2008年1月からブログを初めて何と17年近くになりますが、あまり宣伝もすることなくほぼ毎日更新しています。
スマホをいじっていて下のところまでググったら「フォローする」という欄を見つけました。
人気ブログにならない理由がわかりました。
23人しかフォロワーがいないのです。

このブログをご覧のあなた、是非私のブログのフォロワーになってください。
Search(検索)欄から入ると、アドラー心理学のコンテンツが誰よりも豊富に詰まっていることが確認できますよ。

(クリックして勇気づけを)
<お目休めコーナー>11月の花(28)

