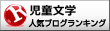太平洋戦争さなかの1944年。アメリカ本土爆撃に必要な気象情報を入手するため、日本軍の特殊部隊がアラスカの森林地帯へと侵入した。10人の日本兵を率いるのは、元オリンピック・メダリストの日高遠三大尉。
しかし、その電波を米軍も察知し、野獣監視人アラン・マックルイアをガイドにアラスカ・スカウトとの合同部隊を編成して森林地帯に部隊を投入するのだが……。
……という、アラスカを部隊にした日本兵とアメリカ人のサバイバルをドイツ人が書いた話。考証的におかしな点が皆無ではないけれど、欺し欺され、追いつ追われのサバイバルゲームにして男たちの戦いは、ささいな点など気にさせません。
「ハワイ諸島は昔からアメリカのものだったか? なぜアメリカはプエルトリコを、グアムを、ウポルを治めているのか? 有色人種の希望でか? テキサスとカルフォルニアにはどうしてやって来たのか? 弱体のメキシコを略奪するためではなかったか! ネヴァダ、アリゾナ、ニューメキシコ……(以下略)」
なぜ日本はこんな戦争を始めたかとアランに訊ねられた刀自本少尉が正当防衛だと言い張る返答の一部。狂気の暴論と一蹴されますが、このくだりはけっこう長いので、アメリカ人には書けなかったかも知れません。
後日談も良い感じに締めくくられています。
【アラスカ戦線】【ハンス・オットー・マイスナー】【気象情報】【純白のオオシカ】【巨熊】
しかし、その電波を米軍も察知し、野獣監視人アラン・マックルイアをガイドにアラスカ・スカウトとの合同部隊を編成して森林地帯に部隊を投入するのだが……。
……という、アラスカを部隊にした日本兵とアメリカ人のサバイバルをドイツ人が書いた話。考証的におかしな点が皆無ではないけれど、欺し欺され、追いつ追われのサバイバルゲームにして男たちの戦いは、ささいな点など気にさせません。
「ハワイ諸島は昔からアメリカのものだったか? なぜアメリカはプエルトリコを、グアムを、ウポルを治めているのか? 有色人種の希望でか? テキサスとカルフォルニアにはどうしてやって来たのか? 弱体のメキシコを略奪するためではなかったか! ネヴァダ、アリゾナ、ニューメキシコ……(以下略)」
なぜ日本はこんな戦争を始めたかとアランに訊ねられた刀自本少尉が正当防衛だと言い張る返答の一部。狂気の暴論と一蹴されますが、このくだりはけっこう長いので、アメリカ人には書けなかったかも知れません。
後日談も良い感じに締めくくられています。
【アラスカ戦線】【ハンス・オットー・マイスナー】【気象情報】【純白のオオシカ】【巨熊】