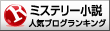書庫の整理をしていて発掘。
書庫の整理をしていて発掘。大学の時の日本的経営論のテキストかなと思ったけれど、開いたら見返しに著者からゼミの恩師への一筆が添えられた謹呈の書。あっ、形見分けでもらったやつかしら。これは自分の代では処分できんなー。
江戸時代から戦前・戦後までの日本の組織における構造を分析し、藩のように企業内の身分が出身大学という出自によって地位も給与も定まってしまった戦前に対し、戦後はラグビーチームのようなスポーツチームに近くなったと評した。ただ、これはあくまで年功序列と企業への一体感があることが前提だった。
日本企業は「終身雇用と年功序列」のシステムであり、欧米の「能力主義・業績主義」と対比される存在だった。
しかし、長期の景況予測は外れることがあっても、人口統計は外れない。戦争や疫病でもなければ特定の世代の人口が急激に減ることはないし、逆に大量の移民でもなければ人口が急増することもないというのは自明の理なのだ。人口停滞と高齢化による人口ピラミッドの逆転によっていずれ「終身雇用と年功序列」が崩壊することはシステム上の必然だった。年功序列で地位や給与が上がることが期待できなくなれば、終身雇用のメリットもなくなるからだ。
ならば、日本企業が「能力主義・業績主義」に変化できるかというと、著者は悲観的だ。「能力主義・業績主義」は雇用の段階で求められるものが明確になっているからこそ成立するものであり、日本の企業が導入しようとしても能力や業績の評価が主観が介在する抽象的で曖昧なものにならざるをえないから、どうしても貢献意欲や一体感が失われていくだけとなる。今は過渡期だから誤魔化せているだけだ。
これはバブル景気以前の1982年の刊行。
先見の明には敬服するけれど、著者が心配していたのは「中高年の失業」。まさか、若年層が正規雇用されなくなり、非正規雇用がごく普通になるとは予想もできなかったのだ。『約束の国』で中高年を大事にしすぎて若者に未来を見せられない国家は滅びると言われていたけれど、まさにそんな時代になろうとはねえ……。
【日本社会と日本的経営】【西田耕三】【文眞堂】