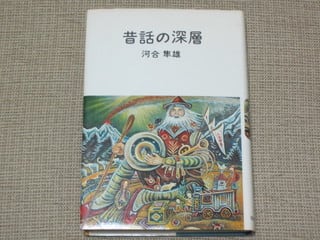河合隼雄 1977年 福音館書店
去年9月に買った古本、著者名から心理学関係だろうなとは思ったけど、昔話ってのがそこんとこどうなってるのか気になったもんで。
(諸星大二郎ファンなものだから、伝説とか民俗文化とかってのはけっこう興味ある。)
ユングの心理学なんてまったく知らないんだけど、たとえば鬼退治とか物語の詳細はなんでもいいが、洋の東西を問わず、成人をしのぐ活躍をする昔話があれこれあることは、「人類はこのような超人的な子どもの話を好む」「全人類に共通に、このような超能力をそなえた子どもという表象を産出する可能性が無意識内に存在する」(p.16)って解説されちゃうと、そうか集合的無意識ってそういうこと、と初めてわかった気がした。
あるところに二人の兄弟がおりました、で始まり、二人の性格や行動の対比で進められる昔話は世界中にあって、古い例では紀元前1300年頃のエジプトに既にあったというんだが、それって「このようなテーマがいかに人間の心の在り方と深く結びついているかを示すものである(p.93)」と言われちゃうと、そうか人の心理のなかには普遍性のあるものあるんだと納得せざるをえない。
主にグリムに題材をとっているんだが、なんとなく通り過ぎていた昔話に秘められている意味を明るみにされちゃうと、そこまで深読みできるものだったんだと驚く。
たとえば、昔々あるところに王様と三人の息子がいて、王様は死にあたって息子のなかで最もものぐさな者に王位を継承させようとしました、なんて話について、まず王妃が登場しない男性ばかりの世界であることに注目。
>自分に対してふりかかってくる運命に対して積極的に戦ってゆくこと、これは男性の原理である。これに対して、運命を受け容れること、これは女性原理である。(略)おそらく理想としては、この両立し難い原理が一人の人格のなかに統合的に存在することであろう。
>ところで、この話のなかで王さまが死に瀕しているが、これはなにを意味するのだろうか。これは男性の原理のみによって成立していたこの王国の規範性が、今やひとつの危険に臨んでいること示している。(略)(p.82-83「怠けと創造」)
という具合で、意識と無意識とのバランスの乱れみたいなことを指摘するんだが、そこでなんで怠けが評価されるかっていうと、
>常識の世界に忙しく働いている人は、天の声を聞くことができない。怠け者の耳は天啓に対して開かれている。このように言うと、私の心には現代の多くの「仕事に向かって逃避」している人たちのことが思い浮かんでくる。これらの人は仕事を熱心にし、忙しくするという口実のものに、自分の内面の声を聞くことを拒否しているのである。(p.85)
ってことで、意識的な努力の評価に対するアンチテーゼとしての無為の重要性だってことで、現代人の心理療法にまで結び付けられちゃう。
(どうでもいいけど、運命に対する男性原理と女性原理の立ち位置のちがいは、ホリイ氏の『恋するディズニー 別れるディズニー」で学んだのと同じことだ。)
ほかにも、白雪姫の母親とか、いばら姫の悪い魔法使いとかってのは「母性の否定的な面を表わすことは明らか」ということで。
母親に否定的なコンプレックスをもつと、娘は自らの女性性を否定しようとして、現代の臨床像としてそれは思春期拒食症になるとか、ガラスの棺にはいった乙女の像は離人症の症状を連想させるとかって見解を披露されて、
>このように、女性の思春期の発達と関連づけてみると、いばら姫は案外すべての正常な女性の心理的発達の過程を描いているのかも知れぬと思われる。(p.128-129「思春期」)
だなんて想像もしたこともなかったとこに着地させてくれる。
父性原理と母性原理というのはポイントになる考え方らしくて、
>母なるものの、すべてのものを区別することなく包みこむ機能と、父なるものの善悪などを区別する機能との間に適切なバランスが保たれてこそ、人間の生活が円滑に行われる(p159「父と息子」)
という観点から、王と息子とか、王と姫とか、物語におけるいろんな対立の場面を、これはこういう状態を反映しているみたいに意味解説してくれるんで、なかなかおもしろい。
“昔々あるところに王がいて、庭のりんごの木の実の数は毎日数えさせていましたが、あくる朝になると実がひとつずつ無くなっていることが報告されました”で始まる物語があるんだけど、これって、りんごの数を数えてるのは規範性の尊重を示すものなんだという。
で、りんごが盗まれるのは、規範に対する挑戦で、規範性の体現者としての王は何らかの意味で危機に陥っていて、規範を改善し危機を救うものとして、新たな男性性の動きが必要とされると、例えば王の息子たちがりんごの見張り役として登場してくることになるってのが物語のつくりだそうだ。
>りんごが盗まれるということは、意識から無意識への心的エネルギーの流れが生じたことを意味すると述べた。それが王の知らぬ間に盗まれるとは、自我のあずかり知らぬ間に退行が生じていることを示す。これは一種のノイローゼ的な状態である。(p.168「父と息子」)
という調子で、まさか黄金の鳥がりんごをついばみに来る昔話が、ひとのノイローゼのことを表しているとは想像したこともなかった。
そのへんとても刺激的で、けっこうおもしろく読めた本だった。うーむ、グリム童話いっぺんちゃんと読んでみようかなと思わされている。
章立ては以下のとおり。諸星ファンとしては、いきなり登場したのが「トルーデさん」ってのは気になるところ。
第一章 昔話と心の構造
第二章 グレートマザー(太母) トルーデさん
第三章 母からの自立 ヘンゼルとグレーテル
第四章 怠けと創造 ものぐさ三人息子
第五章 影の自覚 二人兄弟
第六章 思春期 いばら姫
第七章 トリックスターのはたらき 忠臣ヨハネス
第八章 父と息子 黄金の鳥
第九章 男性の心の中の女性 なぞ
第十章 女性の心の中の男性 つぐみの髯の王さま
第十一章 自己実現の過程 三枚の鳥の羽
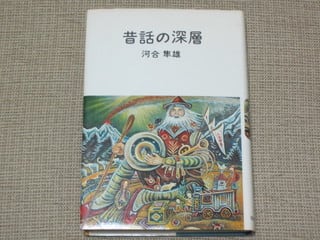
去年9月に買った古本、著者名から心理学関係だろうなとは思ったけど、昔話ってのがそこんとこどうなってるのか気になったもんで。
(諸星大二郎ファンなものだから、伝説とか民俗文化とかってのはけっこう興味ある。)
ユングの心理学なんてまったく知らないんだけど、たとえば鬼退治とか物語の詳細はなんでもいいが、洋の東西を問わず、成人をしのぐ活躍をする昔話があれこれあることは、「人類はこのような超人的な子どもの話を好む」「全人類に共通に、このような超能力をそなえた子どもという表象を産出する可能性が無意識内に存在する」(p.16)って解説されちゃうと、そうか集合的無意識ってそういうこと、と初めてわかった気がした。
あるところに二人の兄弟がおりました、で始まり、二人の性格や行動の対比で進められる昔話は世界中にあって、古い例では紀元前1300年頃のエジプトに既にあったというんだが、それって「このようなテーマがいかに人間の心の在り方と深く結びついているかを示すものである(p.93)」と言われちゃうと、そうか人の心理のなかには普遍性のあるものあるんだと納得せざるをえない。
主にグリムに題材をとっているんだが、なんとなく通り過ぎていた昔話に秘められている意味を明るみにされちゃうと、そこまで深読みできるものだったんだと驚く。
たとえば、昔々あるところに王様と三人の息子がいて、王様は死にあたって息子のなかで最もものぐさな者に王位を継承させようとしました、なんて話について、まず王妃が登場しない男性ばかりの世界であることに注目。
>自分に対してふりかかってくる運命に対して積極的に戦ってゆくこと、これは男性の原理である。これに対して、運命を受け容れること、これは女性原理である。(略)おそらく理想としては、この両立し難い原理が一人の人格のなかに統合的に存在することであろう。
>ところで、この話のなかで王さまが死に瀕しているが、これはなにを意味するのだろうか。これは男性の原理のみによって成立していたこの王国の規範性が、今やひとつの危険に臨んでいること示している。(略)(p.82-83「怠けと創造」)
という具合で、意識と無意識とのバランスの乱れみたいなことを指摘するんだが、そこでなんで怠けが評価されるかっていうと、
>常識の世界に忙しく働いている人は、天の声を聞くことができない。怠け者の耳は天啓に対して開かれている。このように言うと、私の心には現代の多くの「仕事に向かって逃避」している人たちのことが思い浮かんでくる。これらの人は仕事を熱心にし、忙しくするという口実のものに、自分の内面の声を聞くことを拒否しているのである。(p.85)
ってことで、意識的な努力の評価に対するアンチテーゼとしての無為の重要性だってことで、現代人の心理療法にまで結び付けられちゃう。
(どうでもいいけど、運命に対する男性原理と女性原理の立ち位置のちがいは、ホリイ氏の『恋するディズニー 別れるディズニー」で学んだのと同じことだ。)
ほかにも、白雪姫の母親とか、いばら姫の悪い魔法使いとかってのは「母性の否定的な面を表わすことは明らか」ということで。
母親に否定的なコンプレックスをもつと、娘は自らの女性性を否定しようとして、現代の臨床像としてそれは思春期拒食症になるとか、ガラスの棺にはいった乙女の像は離人症の症状を連想させるとかって見解を披露されて、
>このように、女性の思春期の発達と関連づけてみると、いばら姫は案外すべての正常な女性の心理的発達の過程を描いているのかも知れぬと思われる。(p.128-129「思春期」)
だなんて想像もしたこともなかったとこに着地させてくれる。
父性原理と母性原理というのはポイントになる考え方らしくて、
>母なるものの、すべてのものを区別することなく包みこむ機能と、父なるものの善悪などを区別する機能との間に適切なバランスが保たれてこそ、人間の生活が円滑に行われる(p159「父と息子」)
という観点から、王と息子とか、王と姫とか、物語におけるいろんな対立の場面を、これはこういう状態を反映しているみたいに意味解説してくれるんで、なかなかおもしろい。
“昔々あるところに王がいて、庭のりんごの木の実の数は毎日数えさせていましたが、あくる朝になると実がひとつずつ無くなっていることが報告されました”で始まる物語があるんだけど、これって、りんごの数を数えてるのは規範性の尊重を示すものなんだという。
で、りんごが盗まれるのは、規範に対する挑戦で、規範性の体現者としての王は何らかの意味で危機に陥っていて、規範を改善し危機を救うものとして、新たな男性性の動きが必要とされると、例えば王の息子たちがりんごの見張り役として登場してくることになるってのが物語のつくりだそうだ。
>りんごが盗まれるということは、意識から無意識への心的エネルギーの流れが生じたことを意味すると述べた。それが王の知らぬ間に盗まれるとは、自我のあずかり知らぬ間に退行が生じていることを示す。これは一種のノイローゼ的な状態である。(p.168「父と息子」)
という調子で、まさか黄金の鳥がりんごをついばみに来る昔話が、ひとのノイローゼのことを表しているとは想像したこともなかった。
そのへんとても刺激的で、けっこうおもしろく読めた本だった。うーむ、グリム童話いっぺんちゃんと読んでみようかなと思わされている。
章立ては以下のとおり。諸星ファンとしては、いきなり登場したのが「トルーデさん」ってのは気になるところ。
第一章 昔話と心の構造
第二章 グレートマザー(太母) トルーデさん
第三章 母からの自立 ヘンゼルとグレーテル
第四章 怠けと創造 ものぐさ三人息子
第五章 影の自覚 二人兄弟
第六章 思春期 いばら姫
第七章 トリックスターのはたらき 忠臣ヨハネス
第八章 父と息子 黄金の鳥
第九章 男性の心の中の女性 なぞ
第十章 女性の心の中の男性 つぐみの髯の王さま
第十一章 自己実現の過程 三枚の鳥の羽