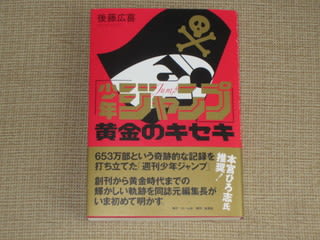後藤広喜 2018年3月 集英社
むかしのこと振り返りついでに、もうひとつ、元編集長が書いたジャンプの歴史。
6月に2刷を重ねたあとに見つけておもしろそうだからと買ったのは7月。
著者は前年10月に週刊になったジャンプ編集部に昭和45年入社して配属された生え抜きで、以降ジャンプの歴史をずっと現場で経験してて。
そのひとが、
>「少年ジャンプ」が一番おもしろかったのはいつか? と聞かれたら、わたしはこの飛躍期だと答えるようにしている。(p.70)
って言ってる時期を、実際にリアルタイムで読んでたものとしては、同感だと思うし、幸せだとまで感じる。
飛躍期ってのは、100万部を超えた翌年である昭和46年から210万部までいった昭和52年まで。
前半戦は厳密には私は参戦してないが、当時の連載作品の名前を並べられると、嗚呼と思うものばかり。
ジャンルが豊富で、新しいマンガ家も出てきて、たしかに勢いがあったんだろうなと思う、読んでるときはそんなこと考えずに面白いってだけでページ繰ってたんだけど。
でも、そんななかで『アストロ球団』画いてるあいだに、作者が頭にコブができて手が腫れた心因性の病気になってしまうって出来事があって、それは担当者だった本書の著者が追いつめたからだみたいな話はけっこうショッキング。
>おもしろい漫画を作ろうという意気込みのせいとはいえ、夜討ち朝駆けのネームチェック、打合せは異常といえば異常、狂気の域に踏み込んだような感じだった。(p.82)
なんて認めてますが、そのくらいの情熱がなきゃ、あのころのエネルギーあふれる週刊マンガ誌はできなかったのねと納得するような感じもある。
後発のマンガ誌であるジャンプは、自らの手で新人を発掘して育てなければならなかったみたいなことは、これまでも聞いたことあるけど、新人漫画賞の設定・募集を少年マンガ誌で初めてやったのがジャンプだってのまでは知らなかった。
で、ストーリーマンガ部門は「手塚賞」の名前で、私が読み始めたころには歴然と存在していたけど、これって初代編集長と手塚治虫のあいだの個人的なつながりでできたもので、正式な契約とか名義料の支払いがなかったってのは、今回初めて知った。
「手塚治虫文化賞」起ち上げのときに、名前を返せと言われかけたんだけど、賞の趣旨ちがうので共存を図り話し合いで解決したってエピソードが書かれてる。
で、週刊ジャンプの発行部数は、平成6年の年末に653万部までいって、これがピークとなったらしいが、そのころには私は読んぢゃいない。
著者が本書の終盤でジャンプの分水嶺と位置づけてとりあげるのは、平成2年12月に連載開始した『幽☆遊☆白書』だけど、これも私は全く読んでない。
なんで、このマンガがターニングポイントとみなされるかというと、
>(略)この作品が雑誌の読者とコミックスの読者との乖離を象徴的に映し出しているからである。(略)
>雑誌の発行部数を誇る時代はすでに終わったのだ。コミックスが売れる漫画を、どれだけ掲載できるかが重要なのだ。(p.264-265)
ということで、メディアミックス戦略も含めた展開をして、単行本が売れるマンガづくりをした結果、コミックスを買うけど雑誌は買わないという客層を相手にすることになり、週刊誌の連載マンガの読まれ方が変わっちゃったらしい。
雑誌が読まれるためには、昭和40年代から50年代にかけてやった、ジャンルが豊富で何だかわかんないがゴチャゴチャいっぱい入ってるってつくりのほうがよかったんだろうけど、いまはコミックスの売り上げやアニメ化を狙った作品のショウウインドにマンガ誌はなっちゃったと。
あと、商売とは別の話で、著者が憂慮しているのは、数として読まれているわりには、マンガが文化として熟成する環境にないことで、もっと評論活動が活発に行われることを望んでいる。
>わたしが恐れるのは、漫画をマニアのもの、「個」の趣味のレベルに閉じ込めてしまうことである。的確な言い方が見つからないが、もっと外に開かれた、社会的、普遍的な価値づけをしていく必要があると思っている。(p.261)
ってのは、いい意見だ。
章立ては以下のとおり。連載マンガの年表がついてるのは、なんかうれしい。
第1章 「少年ジャンプ」の編集方針は創刊時にすべて決まっていた
第2章 創刊誕生期――昭和43年7月11日発売の創刊号から昭和45年末最終号まで――
第3章 飛躍期 マガジンに追いつき追いこせ ――昭和46年年始発売号から昭和52年末最終号まで――
第4章 常勝期 三〇〇万部の壁を越えて四〇〇万部へ ――昭和53年年始発売号から昭和59年末最終号まで――
第5章 黄金期 六五三万部発行を達成するまで ――昭和60年年始発売号から平成6年末最終号まで――
終章 それからのことについて思うこと
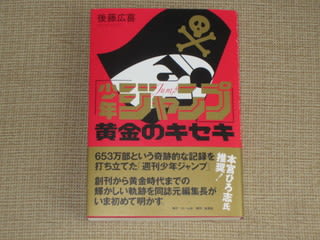
むかしのこと振り返りついでに、もうひとつ、元編集長が書いたジャンプの歴史。
6月に2刷を重ねたあとに見つけておもしろそうだからと買ったのは7月。
著者は前年10月に週刊になったジャンプ編集部に昭和45年入社して配属された生え抜きで、以降ジャンプの歴史をずっと現場で経験してて。
そのひとが、
>「少年ジャンプ」が一番おもしろかったのはいつか? と聞かれたら、わたしはこの飛躍期だと答えるようにしている。(p.70)
って言ってる時期を、実際にリアルタイムで読んでたものとしては、同感だと思うし、幸せだとまで感じる。
飛躍期ってのは、100万部を超えた翌年である昭和46年から210万部までいった昭和52年まで。
前半戦は厳密には私は参戦してないが、当時の連載作品の名前を並べられると、嗚呼と思うものばかり。
ジャンルが豊富で、新しいマンガ家も出てきて、たしかに勢いがあったんだろうなと思う、読んでるときはそんなこと考えずに面白いってだけでページ繰ってたんだけど。
でも、そんななかで『アストロ球団』画いてるあいだに、作者が頭にコブができて手が腫れた心因性の病気になってしまうって出来事があって、それは担当者だった本書の著者が追いつめたからだみたいな話はけっこうショッキング。
>おもしろい漫画を作ろうという意気込みのせいとはいえ、夜討ち朝駆けのネームチェック、打合せは異常といえば異常、狂気の域に踏み込んだような感じだった。(p.82)
なんて認めてますが、そのくらいの情熱がなきゃ、あのころのエネルギーあふれる週刊マンガ誌はできなかったのねと納得するような感じもある。
後発のマンガ誌であるジャンプは、自らの手で新人を発掘して育てなければならなかったみたいなことは、これまでも聞いたことあるけど、新人漫画賞の設定・募集を少年マンガ誌で初めてやったのがジャンプだってのまでは知らなかった。
で、ストーリーマンガ部門は「手塚賞」の名前で、私が読み始めたころには歴然と存在していたけど、これって初代編集長と手塚治虫のあいだの個人的なつながりでできたもので、正式な契約とか名義料の支払いがなかったってのは、今回初めて知った。
「手塚治虫文化賞」起ち上げのときに、名前を返せと言われかけたんだけど、賞の趣旨ちがうので共存を図り話し合いで解決したってエピソードが書かれてる。
で、週刊ジャンプの発行部数は、平成6年の年末に653万部までいって、これがピークとなったらしいが、そのころには私は読んぢゃいない。
著者が本書の終盤でジャンプの分水嶺と位置づけてとりあげるのは、平成2年12月に連載開始した『幽☆遊☆白書』だけど、これも私は全く読んでない。
なんで、このマンガがターニングポイントとみなされるかというと、
>(略)この作品が雑誌の読者とコミックスの読者との乖離を象徴的に映し出しているからである。(略)
>雑誌の発行部数を誇る時代はすでに終わったのだ。コミックスが売れる漫画を、どれだけ掲載できるかが重要なのだ。(p.264-265)
ということで、メディアミックス戦略も含めた展開をして、単行本が売れるマンガづくりをした結果、コミックスを買うけど雑誌は買わないという客層を相手にすることになり、週刊誌の連載マンガの読まれ方が変わっちゃったらしい。
雑誌が読まれるためには、昭和40年代から50年代にかけてやった、ジャンルが豊富で何だかわかんないがゴチャゴチャいっぱい入ってるってつくりのほうがよかったんだろうけど、いまはコミックスの売り上げやアニメ化を狙った作品のショウウインドにマンガ誌はなっちゃったと。
あと、商売とは別の話で、著者が憂慮しているのは、数として読まれているわりには、マンガが文化として熟成する環境にないことで、もっと評論活動が活発に行われることを望んでいる。
>わたしが恐れるのは、漫画をマニアのもの、「個」の趣味のレベルに閉じ込めてしまうことである。的確な言い方が見つからないが、もっと外に開かれた、社会的、普遍的な価値づけをしていく必要があると思っている。(p.261)
ってのは、いい意見だ。
章立ては以下のとおり。連載マンガの年表がついてるのは、なんかうれしい。
第1章 「少年ジャンプ」の編集方針は創刊時にすべて決まっていた
第2章 創刊誕生期――昭和43年7月11日発売の創刊号から昭和45年末最終号まで――
第3章 飛躍期 マガジンに追いつき追いこせ ――昭和46年年始発売号から昭和52年末最終号まで――
第4章 常勝期 三〇〇万部の壁を越えて四〇〇万部へ ――昭和53年年始発売号から昭和59年末最終号まで――
第5章 黄金期 六五三万部発行を達成するまで ――昭和60年年始発売号から平成6年末最終号まで――
終章 それからのことについて思うこと