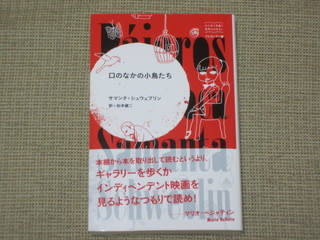村上龍 1989年 集英社文庫版
村上龍の短編集。『愛と幻想のファシズム』好きだったからな当時は、文庫の新刊出たらすぐ買ったんだろう。
で、『ラッフルズホテル』とか『トパーズ』はハードカバーで持ってるけど、どうもあんまりおもしろいと思わなかったらしく、そのあとはリアルタイムで追っかけんのヤメたんだよね、村上龍に関しては、たぶん。
読み返してみた、これも、そんなにいいとまでの感想は持てなかった、当時もいまも、私にはあまり合わないのかなあ。
今回これを持ち出したのは、気もちワルイつながりだ、前回から。なんてえ扱いだ、と自分でも思うけど。
ヌルヌル、ベトベト、血とか汗とかヘドとか何だかわかんない液体とか、そういうのに塗れる描写がいっぱいあるからねえ、作者には。
「ニューヨーク・シティ・マラソン」
ニューヨークの黒人売春婦ナンシーは、正規の(?)料金45ドルをもらう代わりに、マラソンで勝ったら二千ドルやるという客のもちかけた賭けにのる。
どうでもいいけど、ナンシーと同居してる語り手の「僕」の職業も、男娼ときてる。口の中に残る不快な味を消すにはタバスコを二、三滴飲むのが一番速い、とかって描写はさすがだ。
「リオ・デ・ジャネイロ・ゲシュタルト・バイブレイション」
事故で身体半分に大やけどを負ったレーサーのニキが主人公。
リオデジャネイロには静養に来たんだけど、知りあったレダと、カーニバルの熱狂に飲み込まれていく。
「蝶乱舞的夜総会(クレイジー・バタフライ・ダンシング・ナイトクラブ)」
今回、これが、いちばん気もちワルイ。
香港のナイトクラブでピアノを弾いている「僕」と、一緒に住んでいるダンサー志望だがまるでぶきっちょなマーヌという28歳の女。
ふたりは、異常に羽虫が多い夜に、虫の発生してる場所を見つけてガソリンで焼いてやろうと、近所を探しに行く。
そこで得たものから、マーヌはものすごいダンスを踊れるように変身し、国際的にも認められるようになる。
あー、気もちワルイ部分は、引用するのもヤだから、書かない。
「ハカタ・ムーン・ドッグ・ナイト」
博多の山笠の時期に出会った、バンドのプロモーション・営業が仕事で出張できてる男と、地元のクラブではたらくユキの話。
「フロリダ・ハリー・ホップマン・テニス・キャンプ」
ボストンで投資コンサルタントをして巨額の富を築いた「わたし」だが、ある日突然妻から離婚を言い渡された。
フロリダの別荘ですることもなく途方にくれていたときに、近くのスクールに来ていた、雨の日の勝手にプールで泳ぎ始めたテニス選手と出会う。
これは、べつに気持ちわるいところのない話。料理って新しい趣味も見つけられて、仕事も再起して、わりとさわやかな話だ。
「メルボルンの北京ダック」
オーストラリアのメンツィス・アト・リアルトというホテルでドアマンとして勤めている「私」は、全豪オープンに出場している長身のスウェーデン人の若い選手が気になった。
12年前に亡くした息子に似ているような気がしたからだが、その話をすると足を不自由にしてから外出しなくなった妻も、その選手の試合を見てみたいと言い出した。
うん、これもさわやかな話だ。
「コート・ダ・ジュールの雨」
シティの金融界で恐れられるほどの成功を成し遂げた「私」がリヴィエラに静養に来ているときの話。
そこで見かけたドイツ人家族四人だが、そのなかで少年だけが父母と姉の会話にまったく加わろうとせず、様子がおかしい。
「私」がコンコルドのコクピットから、楕円に拡がる地球の光景を見て、通貨や穀物相場のことなんかアタマのなかから吹っ飛んぢゃうとこが印象的。
べつに気持ちわるいとこないな。
「パリのアメリカ人」
パリで働くけどアメリカ英語のできる「オレ」の仕事は、世界中からCF撮影とかで来る客たちの出迎えやら夜の案内。
この夜も、もっと過激なショーをやってるクラブはないのかなんて言う、アメリカ人をあちこち案内してまわる。
「ローマの詐欺師」
ローマ市内で、一人旅の観光客を相手に、自分も困っているツーリストの様を演じて、詐欺をはたらく「わたし」の話。
あるとき、東洋人の女性に(女性はこのテの詐欺には引っ掛からないのに)まちがって声をかけてしまう。
ところが、この女性の語るバイオコンピュータの話のほうが途方もなかった。
…よく見りゃ、全部が全部、気もちワルイ話の集まりってわけでもないな。
まあ、それだけ「蝶乱舞的夜総会」の印象が強烈なんで。
なんせ、虫の残してったものを、脳にダイレクトに注入するんだぜ。あ、言っちゃった。

村上龍の短編集。『愛と幻想のファシズム』好きだったからな当時は、文庫の新刊出たらすぐ買ったんだろう。
で、『ラッフルズホテル』とか『トパーズ』はハードカバーで持ってるけど、どうもあんまりおもしろいと思わなかったらしく、そのあとはリアルタイムで追っかけんのヤメたんだよね、村上龍に関しては、たぶん。
読み返してみた、これも、そんなにいいとまでの感想は持てなかった、当時もいまも、私にはあまり合わないのかなあ。
今回これを持ち出したのは、気もちワルイつながりだ、前回から。なんてえ扱いだ、と自分でも思うけど。
ヌルヌル、ベトベト、血とか汗とかヘドとか何だかわかんない液体とか、そういうのに塗れる描写がいっぱいあるからねえ、作者には。
「ニューヨーク・シティ・マラソン」
ニューヨークの黒人売春婦ナンシーは、正規の(?)料金45ドルをもらう代わりに、マラソンで勝ったら二千ドルやるという客のもちかけた賭けにのる。
どうでもいいけど、ナンシーと同居してる語り手の「僕」の職業も、男娼ときてる。口の中に残る不快な味を消すにはタバスコを二、三滴飲むのが一番速い、とかって描写はさすがだ。
「リオ・デ・ジャネイロ・ゲシュタルト・バイブレイション」
事故で身体半分に大やけどを負ったレーサーのニキが主人公。
リオデジャネイロには静養に来たんだけど、知りあったレダと、カーニバルの熱狂に飲み込まれていく。
「蝶乱舞的夜総会(クレイジー・バタフライ・ダンシング・ナイトクラブ)」
今回、これが、いちばん気もちワルイ。
香港のナイトクラブでピアノを弾いている「僕」と、一緒に住んでいるダンサー志望だがまるでぶきっちょなマーヌという28歳の女。
ふたりは、異常に羽虫が多い夜に、虫の発生してる場所を見つけてガソリンで焼いてやろうと、近所を探しに行く。
そこで得たものから、マーヌはものすごいダンスを踊れるように変身し、国際的にも認められるようになる。
あー、気もちワルイ部分は、引用するのもヤだから、書かない。
「ハカタ・ムーン・ドッグ・ナイト」
博多の山笠の時期に出会った、バンドのプロモーション・営業が仕事で出張できてる男と、地元のクラブではたらくユキの話。
「フロリダ・ハリー・ホップマン・テニス・キャンプ」
ボストンで投資コンサルタントをして巨額の富を築いた「わたし」だが、ある日突然妻から離婚を言い渡された。
フロリダの別荘ですることもなく途方にくれていたときに、近くのスクールに来ていた、雨の日の勝手にプールで泳ぎ始めたテニス選手と出会う。
これは、べつに気持ちわるいところのない話。料理って新しい趣味も見つけられて、仕事も再起して、わりとさわやかな話だ。
「メルボルンの北京ダック」
オーストラリアのメンツィス・アト・リアルトというホテルでドアマンとして勤めている「私」は、全豪オープンに出場している長身のスウェーデン人の若い選手が気になった。
12年前に亡くした息子に似ているような気がしたからだが、その話をすると足を不自由にしてから外出しなくなった妻も、その選手の試合を見てみたいと言い出した。
うん、これもさわやかな話だ。
「コート・ダ・ジュールの雨」
シティの金融界で恐れられるほどの成功を成し遂げた「私」がリヴィエラに静養に来ているときの話。
そこで見かけたドイツ人家族四人だが、そのなかで少年だけが父母と姉の会話にまったく加わろうとせず、様子がおかしい。
「私」がコンコルドのコクピットから、楕円に拡がる地球の光景を見て、通貨や穀物相場のことなんかアタマのなかから吹っ飛んぢゃうとこが印象的。
べつに気持ちわるいとこないな。
「パリのアメリカ人」
パリで働くけどアメリカ英語のできる「オレ」の仕事は、世界中からCF撮影とかで来る客たちの出迎えやら夜の案内。
この夜も、もっと過激なショーをやってるクラブはないのかなんて言う、アメリカ人をあちこち案内してまわる。
「ローマの詐欺師」
ローマ市内で、一人旅の観光客を相手に、自分も困っているツーリストの様を演じて、詐欺をはたらく「わたし」の話。
あるとき、東洋人の女性に(女性はこのテの詐欺には引っ掛からないのに)まちがって声をかけてしまう。
ところが、この女性の語るバイオコンピュータの話のほうが途方もなかった。
…よく見りゃ、全部が全部、気もちワルイ話の集まりってわけでもないな。
まあ、それだけ「蝶乱舞的夜総会」の印象が強烈なんで。
なんせ、虫の残してったものを、脳にダイレクトに注入するんだぜ。あ、言っちゃった。