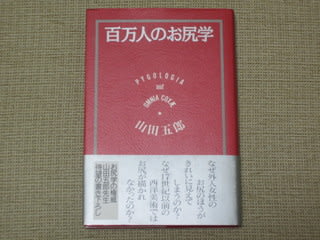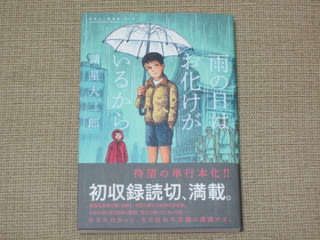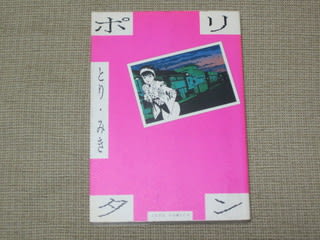山田五郎 1992年 講談社
去年9月に古本まつりで見かけて、なんとなくおもしろそうなんで買ってしまった、読んだの最近。
「お尻学」とは、カバーの内っ側にある紹介にいわく、
>1.お尻というおろそかにされがちな部位を通じて、文学、芸術、風俗など、あらゆる現象を研究する学問。
>2.物語の表面にまどわされず、裏側から真実を追究する懐疑的姿勢。
>3.心理は頭=脳ではなく、お尻=肉体に宿るとし、精神と肉体を再び統一させようとする反近代主義。
ということだそうで、けっこうマジメなんで、勉強になった。
たとえば、日本人の美意識を語るとき、「和尻」と「洋尻」のちがいが大きな問題だという。
ちなみに、和尻とは「薄い・低い・歪つ、ぽっちゃり・すべすべ、触覚的・直感的・個性的、経験論的個性美」が特徴で、かたや洋尻は「厚い・高い・丸い、むっちり・ごわごわ、視覚的・分析的・類型的、観念論的理想美」だという。
そんなことはどうでもいいんだけど、ぢゃあなんで洋尻のかたちのほうがすぐれていると思ってしまうのかというと。
きっちり幾何学的にデザインした人体図でつくられたりする西洋美術なんかのほうが、比較や分析が可能で、分かりやすいという性質をもってるからだと。
>いつでもどこでも誰にでも同じように理解できる、つまり、時間や空間や個人差といった自然の条件に左右されず、理性でコントロールできる普遍的なシステムへの意志――。
>西洋文化にすぐれて特徴的なこの傾向を、ドイツの社会学者マックス・ヴェーバーは『世界の脱呪術化』への意志と呼び、近代資本主義が西洋社会で生まれたのは、プロテスタンティズムの倫理感を通じてこの意志が展開された結果だと説明している。(略)
>いずれにせよ、近代資本主義と民主主義は、いままでに人類が作り出した最も普遍的な文化システムだといってよい。それは、あらゆる「いわくいいがたい」差異を数字に置き換えることで、交換可能な「分かりやすい」価値にしてしまう。(略)
>『洋尻』が世界を席巻する理由はここにある。近代資本主義自体は文化の違いを超えた普遍的なシステムだが、それを取り入れると、西洋人の肉体を基準とした象徴体系と美意識が、もれなくついてきてしまうのだ。(p.32-33)
ということで、中沢新一のカイエ・ソバージュ・シリーズで遅まきながら勉強している、一神教と資本主義の問題に、こんなとこで出くわすとは思わなかったんで、驚いた。
あと、西洋文化史とか美術には私はぜんぜん知識がないんだが、西欧文化とは、古代ギリシャ・ローマ文化、ユダヤ・キリスト教、ケルト・ゲルマン民族という三つの要素の混合性から成るという話が繰り返しあって、そいつは勉強になった。
古代ギリシャは神の似姿である人間の肉体を讃美する、キリスト教は堕落への誘惑として肉体を否定する、ゲルマンは着衣が本来の姿であり裸体は人間の尊厳をはぎ取られた状態という羞恥をもつ、そういうのが入れ代わり立ち代わりしてつくられてきたっていうんで、こんど美術館でも行ったら(まず絶対行かないけど)なんか見る目変わっちゃいそうな気がした。
章立ては以下のとおり。
巻頭に特別寄稿があって、タモリの「お尻の思ひ出」というのはともかく、笠井寛司の「お尻の医学」というほうは骨格と筋肉の説明があっておもしろいと思う。
第1章 尻学原論
第2章 お尻の西洋美術史
第3章 お尻のファッション史
第4章 お尻と写真の変態史
第5章 お尻の戦後史
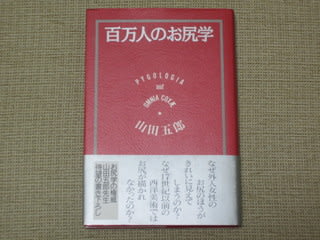
去年9月に古本まつりで見かけて、なんとなくおもしろそうなんで買ってしまった、読んだの最近。
「お尻学」とは、カバーの内っ側にある紹介にいわく、
>1.お尻というおろそかにされがちな部位を通じて、文学、芸術、風俗など、あらゆる現象を研究する学問。
>2.物語の表面にまどわされず、裏側から真実を追究する懐疑的姿勢。
>3.心理は頭=脳ではなく、お尻=肉体に宿るとし、精神と肉体を再び統一させようとする反近代主義。
ということだそうで、けっこうマジメなんで、勉強になった。
たとえば、日本人の美意識を語るとき、「和尻」と「洋尻」のちがいが大きな問題だという。
ちなみに、和尻とは「薄い・低い・歪つ、ぽっちゃり・すべすべ、触覚的・直感的・個性的、経験論的個性美」が特徴で、かたや洋尻は「厚い・高い・丸い、むっちり・ごわごわ、視覚的・分析的・類型的、観念論的理想美」だという。
そんなことはどうでもいいんだけど、ぢゃあなんで洋尻のかたちのほうがすぐれていると思ってしまうのかというと。
きっちり幾何学的にデザインした人体図でつくられたりする西洋美術なんかのほうが、比較や分析が可能で、分かりやすいという性質をもってるからだと。
>いつでもどこでも誰にでも同じように理解できる、つまり、時間や空間や個人差といった自然の条件に左右されず、理性でコントロールできる普遍的なシステムへの意志――。
>西洋文化にすぐれて特徴的なこの傾向を、ドイツの社会学者マックス・ヴェーバーは『世界の脱呪術化』への意志と呼び、近代資本主義が西洋社会で生まれたのは、プロテスタンティズムの倫理感を通じてこの意志が展開された結果だと説明している。(略)
>いずれにせよ、近代資本主義と民主主義は、いままでに人類が作り出した最も普遍的な文化システムだといってよい。それは、あらゆる「いわくいいがたい」差異を数字に置き換えることで、交換可能な「分かりやすい」価値にしてしまう。(略)
>『洋尻』が世界を席巻する理由はここにある。近代資本主義自体は文化の違いを超えた普遍的なシステムだが、それを取り入れると、西洋人の肉体を基準とした象徴体系と美意識が、もれなくついてきてしまうのだ。(p.32-33)
ということで、中沢新一のカイエ・ソバージュ・シリーズで遅まきながら勉強している、一神教と資本主義の問題に、こんなとこで出くわすとは思わなかったんで、驚いた。
あと、西洋文化史とか美術には私はぜんぜん知識がないんだが、西欧文化とは、古代ギリシャ・ローマ文化、ユダヤ・キリスト教、ケルト・ゲルマン民族という三つの要素の混合性から成るという話が繰り返しあって、そいつは勉強になった。
古代ギリシャは神の似姿である人間の肉体を讃美する、キリスト教は堕落への誘惑として肉体を否定する、ゲルマンは着衣が本来の姿であり裸体は人間の尊厳をはぎ取られた状態という羞恥をもつ、そういうのが入れ代わり立ち代わりしてつくられてきたっていうんで、こんど美術館でも行ったら(まず絶対行かないけど)なんか見る目変わっちゃいそうな気がした。
章立ては以下のとおり。
巻頭に特別寄稿があって、タモリの「お尻の思ひ出」というのはともかく、笠井寛司の「お尻の医学」というほうは骨格と筋肉の説明があっておもしろいと思う。
第1章 尻学原論
第2章 お尻の西洋美術史
第3章 お尻のファッション史
第4章 お尻と写真の変態史
第5章 お尻の戦後史