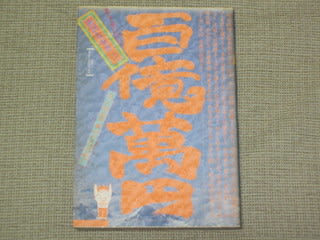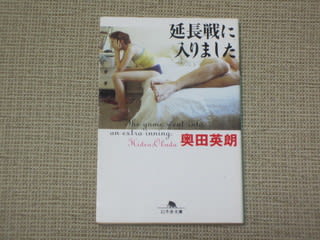唐沢なをき 1992年 扶桑社エクセレント・コミックス
これは、こないだ12月に地元の古本ワゴンセールで見つけたマンガ。
べつに探してたというわけぢゃなく、まったく知らないものだったんだけど、こういうのはここであったが百年目なんで即買うことにした。
「唐沢なをき最新傑作集」ってなってるけど、巻末の初出一覧をみると、だいたい1986年から91年くらいに描かれたもの。
それも著者あとがきにいわく、「なにしろ描き散らし放題だったんで」という状態のを集めたらしい。
唐沢商会の活動ばかりぢゃなくて、なをき個人のマンガも忘れてもらっちゃ困るということで、編んだそうな。
四コマ1ページだけってのもあるし、長くても10ページくらいのギャグマンガいろいろ。
けど私はこういうギャグマンガ、好きだな。
一読してのお気に入りは、「血煙狂四郎無頼剣」、なぜかタイトルの下に「このマンガは企画ページではありません」って入ってる。
最初のページで主人公の侍と悪漢数名を出して時代劇ものかと思わせておいて、2ページめに行くと、主人公はやおら
>その前に一人暮らしの朝食にとっても簡単でおいしい
>「大根とほうれん草のスパイス炒め」を紹介してやろう
とレシピを語りはじめて、フライパンを振るう。なにがおかしいと訊かれても困るが、爆笑してしまった。
「刑事なひとびと」もばかばかしく面白い。
最初4ページも延々とひとりの登場人物がヒンズースクワットをする、92コマも。
で、あとは翌日刑事の仕事の現場で、身体を動かそうとすると筋肉痛で苦しむってだけのことなんだけど、それがムチャクチャおかしい。
コンテンツは以下のとおり。
・目隠し平次捕物帳
・怪しきココロ
・アタックが一番!二人羽織編
・アタックが一番!戦場編
・それゆけ栄光
・恐怖のマヨネーズ女
・刑事な人々
・リクルート事件風刺漫画
・正月漫画
・神の味噌汁
・血煙狂四郎無頼剣
・旗本窒息男
・私的抑圧(プライベートプレッシャー)
・明日はデートだ!
・フェイスハガーアイちゃん
・ホラーくん変身のまき
・赤○○○の女の子
・コカインでGO!
・労働は尊い
・虫喰いミッちゃん
・Let's Go 由佳里ちゃん
・ももんがあの人々
・オクトマン!
・怪奇は踊る
・愛しののーずい
・課長はロボット
・漫画4WDと人類の存亡
・SF大宇宙大銀河大決戦
・SF戦争の猫たち
・SF無重力の使命
・妖怪へそまたぎ
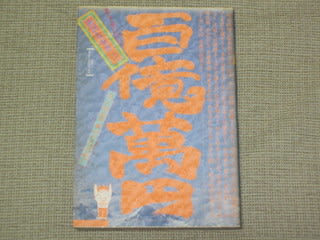
これは、こないだ12月に地元の古本ワゴンセールで見つけたマンガ。
べつに探してたというわけぢゃなく、まったく知らないものだったんだけど、こういうのはここであったが百年目なんで即買うことにした。
「唐沢なをき最新傑作集」ってなってるけど、巻末の初出一覧をみると、だいたい1986年から91年くらいに描かれたもの。
それも著者あとがきにいわく、「なにしろ描き散らし放題だったんで」という状態のを集めたらしい。
唐沢商会の活動ばかりぢゃなくて、なをき個人のマンガも忘れてもらっちゃ困るということで、編んだそうな。
四コマ1ページだけってのもあるし、長くても10ページくらいのギャグマンガいろいろ。
けど私はこういうギャグマンガ、好きだな。
一読してのお気に入りは、「血煙狂四郎無頼剣」、なぜかタイトルの下に「このマンガは企画ページではありません」って入ってる。
最初のページで主人公の侍と悪漢数名を出して時代劇ものかと思わせておいて、2ページめに行くと、主人公はやおら
>その前に一人暮らしの朝食にとっても簡単でおいしい
>「大根とほうれん草のスパイス炒め」を紹介してやろう
とレシピを語りはじめて、フライパンを振るう。なにがおかしいと訊かれても困るが、爆笑してしまった。
「刑事なひとびと」もばかばかしく面白い。
最初4ページも延々とひとりの登場人物がヒンズースクワットをする、92コマも。
で、あとは翌日刑事の仕事の現場で、身体を動かそうとすると筋肉痛で苦しむってだけのことなんだけど、それがムチャクチャおかしい。
コンテンツは以下のとおり。
・目隠し平次捕物帳
・怪しきココロ
・アタックが一番!二人羽織編
・アタックが一番!戦場編
・それゆけ栄光
・恐怖のマヨネーズ女
・刑事な人々
・リクルート事件風刺漫画
・正月漫画
・神の味噌汁
・血煙狂四郎無頼剣
・旗本窒息男
・私的抑圧(プライベートプレッシャー)
・明日はデートだ!
・フェイスハガーアイちゃん
・ホラーくん変身のまき
・赤○○○の女の子
・コカインでGO!
・労働は尊い
・虫喰いミッちゃん
・Let's Go 由佳里ちゃん
・ももんがあの人々
・オクトマン!
・怪奇は踊る
・愛しののーずい
・課長はロボット
・漫画4WDと人類の存亡
・SF大宇宙大銀河大決戦
・SF戦争の猫たち
・SF無重力の使命
・妖怪へそまたぎ