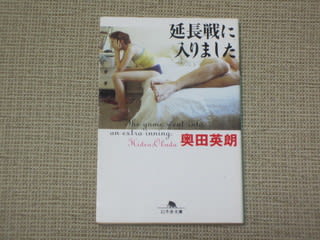奥田英朗 平成15年 幻冬舎文庫版
もうひとつ、スポーツのエッセイ、前に読んだ『どちらとも言えません』がおもしろかったので、期待して買ってみた古本の文庫。
これまた著者あとがきにいわく、「要するに茶々をいれているのである」というスタンスで、まじめなスポーツ談義ではない。
でも、著者のスポーツへの視線がいいんだ、そこがおもしろい。
走り高跳びのベリーロールと背面跳びを比べて、背面跳びは実用性がないので許せないというとか。
2メートルの壁を飛び越えて、仲間のために助けを呼んできてほしい場面で、2メートル40センチ飛べる背面跳びのアスリートは、きっと言う。
>「下はコンクリートじゃないですか。クッションがなければ跳べませんよ」
>こんなひ弱な野郎が表彰台に並んでいいわけがない、と思いませんか?(p.174「ハイジャンプと着地という現実」)
と、きたもんだ、飛べばいいって部門とスタイルを分けて競技種目を設定しろって。
スキーの複合競技にもひと言あって、近代五種なんかに比べたら、ジャンプと距離だけでは、
>2種目で「万能」を名乗るにはやや説得力に欠けるのだ。
>よって、ついでに《フィギュア・スケート》をする。(p.179「万能選手の尊敬と複合競技の醍醐味」)
という提案をする。
そこまではいいのだが、さらに万能を求めて、「空手」と「数学」も加えるべし、
>飛んで、走って、踊って、戦って、知力をしぼる。これぞ人間の理想の姿。(p.180同)
と言う、笑った。
おもしろがってばかりいると、ときどきピシッと鋭いとこもあって油断ならない。
韓国の日本への対抗意識は理屈ぢゃない感情なんだろうけど、日本人も、
>日本人は「白人社会で通用する日本人」が見たいのである。(p.167「野茂の大リーグ挑戦と日本人のナショナル・パスタイム」)
っていう心境になるのが避けられないんで、オリンピックとか、野球やサッカーの選手が外国に移籍すると大騒ぎしちゃうんだというが、正しいだろう。
そこを、へんに批評するんぢゃなくて、ナショナル・パスタイム=国民的ひまつぶしなんだから、しょーがない、みたいな距離感でいるところがいい。
もうひとつ、スポーツ選手が泣くのが嫌いだというスタンスには、共感できる。
>しかし、それでも私は泣くスポーツ選手というものがあまり好きではない。
>だいいち美しくない。(略)
>それに日本人の涙好きは、他人の涙に感動するというより安心したいからだと私には思える。(p.91「スポーツ選手の涙と大衆の期待」)
って、そうそう、って思う。
特に、高校野球の最後のバッターがアウトなのに一塁ヘッドスライディングして、そのまま泣き崩れてるようなのを、自己陶酔だと批判するのは、いいねえ。
>酔ってるなあコイツ、と私は思ってしまう。(略)
>高校野球の記者はハッキリと「泣かなきゃ記事になんねーよ」と言っているくらいである。(略)
>まあ、これが子供なら許せるが、大人のそれもプロがやるとなると私は絶対に許せない。(p.93-94同)
というのは、よくぞ言ってくれたって感じである。
世の中、感動乞食の勢力が増えてて、特に既存のマスコミにはそういう傾向が強いんで、見てて気持ちわるいものが多い、最近。
駅伝の生中継なんて、これアクシデントを期待してるだろってくらいの、水面下の悪意が伝わってくるんで、私は見ないようになった。
気のせいかな、いや、確実にあるよ、ハプニングをライブでレポートしてえなあって感じの底意地のわるさ。
ま、いっか、そーゆーの見たいひともいるんだろ、きっと。
どうでもいいけど、著者は文中でときどき「おぼこい」っていう形容詞を使うんで、あれって思ったら、岐阜県立岐山高校の出身なんだそうである。
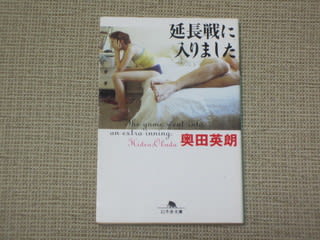
もうひとつ、スポーツのエッセイ、前に読んだ『どちらとも言えません』がおもしろかったので、期待して買ってみた古本の文庫。
これまた著者あとがきにいわく、「要するに茶々をいれているのである」というスタンスで、まじめなスポーツ談義ではない。
でも、著者のスポーツへの視線がいいんだ、そこがおもしろい。
走り高跳びのベリーロールと背面跳びを比べて、背面跳びは実用性がないので許せないというとか。
2メートルの壁を飛び越えて、仲間のために助けを呼んできてほしい場面で、2メートル40センチ飛べる背面跳びのアスリートは、きっと言う。
>「下はコンクリートじゃないですか。クッションがなければ跳べませんよ」
>こんなひ弱な野郎が表彰台に並んでいいわけがない、と思いませんか?(p.174「ハイジャンプと着地という現実」)
と、きたもんだ、飛べばいいって部門とスタイルを分けて競技種目を設定しろって。
スキーの複合競技にもひと言あって、近代五種なんかに比べたら、ジャンプと距離だけでは、
>2種目で「万能」を名乗るにはやや説得力に欠けるのだ。
>よって、ついでに《フィギュア・スケート》をする。(p.179「万能選手の尊敬と複合競技の醍醐味」)
という提案をする。
そこまではいいのだが、さらに万能を求めて、「空手」と「数学」も加えるべし、
>飛んで、走って、踊って、戦って、知力をしぼる。これぞ人間の理想の姿。(p.180同)
と言う、笑った。
おもしろがってばかりいると、ときどきピシッと鋭いとこもあって油断ならない。
韓国の日本への対抗意識は理屈ぢゃない感情なんだろうけど、日本人も、
>日本人は「白人社会で通用する日本人」が見たいのである。(p.167「野茂の大リーグ挑戦と日本人のナショナル・パスタイム」)
っていう心境になるのが避けられないんで、オリンピックとか、野球やサッカーの選手が外国に移籍すると大騒ぎしちゃうんだというが、正しいだろう。
そこを、へんに批評するんぢゃなくて、ナショナル・パスタイム=国民的ひまつぶしなんだから、しょーがない、みたいな距離感でいるところがいい。
もうひとつ、スポーツ選手が泣くのが嫌いだというスタンスには、共感できる。
>しかし、それでも私は泣くスポーツ選手というものがあまり好きではない。
>だいいち美しくない。(略)
>それに日本人の涙好きは、他人の涙に感動するというより安心したいからだと私には思える。(p.91「スポーツ選手の涙と大衆の期待」)
って、そうそう、って思う。
特に、高校野球の最後のバッターがアウトなのに一塁ヘッドスライディングして、そのまま泣き崩れてるようなのを、自己陶酔だと批判するのは、いいねえ。
>酔ってるなあコイツ、と私は思ってしまう。(略)
>高校野球の記者はハッキリと「泣かなきゃ記事になんねーよ」と言っているくらいである。(略)
>まあ、これが子供なら許せるが、大人のそれもプロがやるとなると私は絶対に許せない。(p.93-94同)
というのは、よくぞ言ってくれたって感じである。
世の中、感動乞食の勢力が増えてて、特に既存のマスコミにはそういう傾向が強いんで、見てて気持ちわるいものが多い、最近。
駅伝の生中継なんて、これアクシデントを期待してるだろってくらいの、水面下の悪意が伝わってくるんで、私は見ないようになった。
気のせいかな、いや、確実にあるよ、ハプニングをライブでレポートしてえなあって感じの底意地のわるさ。
ま、いっか、そーゆーの見たいひともいるんだろ、きっと。
どうでもいいけど、著者は文中でときどき「おぼこい」っていう形容詞を使うんで、あれって思ったら、岐阜県立岐山高校の出身なんだそうである。