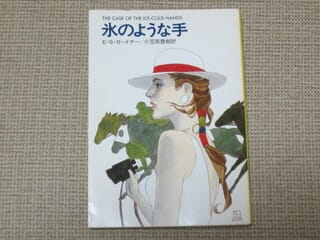フィリップ・ロス/中野好夫・常盤新平=訳 平成二十八年 新潮文庫版
こないだ『本当の翻訳の話をしよう』を読んだら、村上春樹さんが、
>この作品を読んだときの気持ちの昂ぶりは本当に大きかった。彼の中で一番好きな作品です。その頃は僕は小説を書こうなんて思ってもいなかったから、ただ「すごいなあ」と感心しながら夢中になって読んでいました。(『本当の翻訳の話をしよう』p.84)
なんて絶賛してたんで、読んでみたくなって、先月古本屋で手に入れて読んでみた。
原題「THE GREAT AMERICAN NOVEL」は1973年の作品。
『偉大なるアメリカ小説』が、訳題では『素晴らしいアメリカ野球』になったのは、丸谷才一さんの提案だそうだ。
もとの『偉大なるアメリカ小説』っていうのは、「偉大なるアメリカ小説」という概念をからかっているらしいんだけど、それが日本人にはわからないだろうからってことで、そうなったらしい。
「偉大なるアメリカ小説」ってのは確固たる観念であって、新しく作られたこのグレートな国にふさわしいグレートな小説ってことなんだけど。
それはいまだ書かれていないものを指すんであって、「まだ見ぬ偉大なるアメリカ小説」のような感じで、まだ達成されてないけれど存在すべき理想のもの、みたいな概念で、これがそれなんだよってシャアシャアとタイトルにつけたところがふざけてるんだという。
でも、なかみはたしかに野球を題材にしているので、訳題でもあながちハズレてるわけではない、でも、ほんとに素晴らしい野球のことが書いてあるかと期待すると、全然そんなんぢゃないから驚くけど。
第二次大戦前にはあったという、架空の第三のメジャーリーグ「愛国リーグ」の話だ、8チームが加盟している。
主役となる球団は、ルパート・マンディーズ、本拠地はニュージャージー州ポート・ルパート。
かつては1928年からワールドシリーズ三連覇をしたこともあったのだが、オーナーが代替わりすると、有力選手を放出したりして、すっかり弱くなった。
しかも、この戦時下の1943年のシーズンには球場を政府にアメリカ軍の乗船基地として貸し出してしまい、チームは全試合を遠征で戦うことになり、34勝120敗のダントツの最下位となる。
レギュラーのメンツ紹介が第2章であるんだけど、セカンドは14歳の体重92ポンドの坊やだし、サードは52歳で試合中でも居眠りしてるし、ファーストはバクチ逮捕歴のある酒びたりだし、キャッチャーは片脚が木の義足だし、ライトは左腕がないし、といった具合でなんだかとんでもない。
さらに、相手チームには背番号1/4をつけた小人が登場して、代打でフォアボールを選ぶ専門のはたらきをするなんて話になってくると、おいおいスゴイなとしか言いようがない。
まったくもって、全編をとおして、黒人のことはバカにするし、ユダヤ人のことは悪口いうしで、巻頭に「本書には現在の観点からみて差別的と思われる箇所があるが」とあるのももっともで、「復刊」と銘うたれてるのはそれで廃盤だったのかと想像してしまう。
もっとも、史実として黒人はメジャーリーグに入れなかったってこともあるし、著者はユダヤ系だっていうから、これがアメリカだろうがと言い張られちゃったら反論はできないのかも。
どうでもいいけど、グリーンバックスのユダヤ人オーナーの息子アイザックが科学の天才で、7歳のころから野球チームの戦術にも口を出して、「犠牲バントはするな、1シーズンで72得点の損になる」とか、「首位打者には一番を打たせろ、選手は得点生産性の高い順に打つべきだ」とかのセイバーメトリクス理論をふりまわすんだけど、1973年という本書の発表時点ではこれは卓見なのでは。
(『9回裏無死1塁でバントはするな』によれば、ビル・ジェームズの『野球抄1977』という自費出版小冊子で、バントや盗塁の効果を否定する分析が発表された。)
さて、1943年のマンディーズのことがボリュームとしては多いんだけど、それに先立つ第1章では、1933年にグリーンバックスに登場した新人投手が主役になっている。
バビロニアからきた19歳のギル・ガメシュは大男の左腕投手で、時速120マイル(190キロ以上かよ、おい)とも言われる剛速球でシーズン41勝をあげるんだが、審判の判定に不服だと悪態をついて退場になるような奴なんだが、なんとも強烈なキャラクター。
シーズン終盤に、ある事件を起こして球界追放の処分をくらって、行方不明になる、なんでそんなエピソードから始まってたのかとおもうと、1944年にマンディーズの監督として帰ってくるという終盤につながる。
村上春樹さんは、
>僕はこれ、一種のキャラクター小説だと思うんです。(略)整合性なんてどうでもいいんですよね。読んでる方は面白いキャラクターが出てきたり、ここが面白いという部分がいくつかあれば納得して読んでいけちゃうんだよね。それは小説の力だと思う。小説って、何かを五つ書いて、三つが効いていれば、あとの二つは外れてもいいんですよ。力さえあれば。(『本当の翻訳の話をしよう』p.82-83)
と評してる、なるほど、力はあるなー。
荻野目洋子 2006年 ビクターエンタテインメント
きょう12月10日は、私のアイドル・荻野目ちゃんのお誕生日だ、おめでとうございます! と毎年勝手に祝ってる。
さて、なに聴くかな、ここに並べてないもの、まだあったっけって探したら、このミニアルバム。
オリジナルぢゃなくて、カバーですね、荻野目ちゃんがすきなうたをボサノバにうたってる。
当時なんでそんな企画がでてきたのか知らないけど、CDの紙のなかによると、荻野目ちゃんは子供のころ姉の部屋から聴こえてくる音楽を、
>(略)英語の世界はイマジネーションを膨らませ
>意味が理解できない小学生の私にも
>言いようのない高揚感を与えてくれたものです。
と受けとめていたらしいんで、まあそういうのをこんどはご自身で発信しようということだったんでしょう。
で、これがなかなかいいんですね、やっぱ荻野目ちゃん、歌うまいわ。
2006年て何してたかな、俺。北のほうに引っ越した年ではあったな。希望をもってたとは言いがたいが、不安みたいなものはなんも感じたりしてなかったんぢゃないかなという気がする。
1.I Love Your Smile
2.De Do Do Do De Da Da Da
3.Part Time Lover
4.Girls Just Want To Have Fun
5.Conga
6.Merry Jane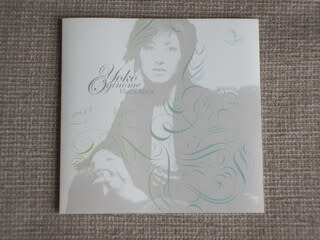
諸星大二郎 2021年11月 講談社モーニングKC
11月22日には発売になってたのを、油断して一週間ほど気づかずにいたが、無事わりと早めに書店で買って読むことができた。
このマンガのつづきを読むことを一番の楽しみに生きているんで、一年に二冊も新刊が出てくれたのはありがたいことである。
さて、物語のほうは、火焔山近くの寧戎城あたりで水が止まったことを発端にして暴動が起きてるんだが、高昌城の兵とかソグド兵まで出てきて鎮圧しようとしてる。
山のなかにいた浮浪児たちも暴徒の仲間入りしてるんだが、暴徒である農夫たちは子供なんかより牛魔王の力を利用しようというのが狙いで。
そもそも暴動のきっかけは魔族たちが妖物を仕掛けたからで、ゾロアスター教寺院から来たアシャイバンダクはその解決を図ろうとするが敵もなかなか手強い。
そんななかで、悟空はついに牛魔王と相まみえるんだが、対峙した瞬間に、こいつを倒さなけりゃという宿命を感じる。
一回で決着はつかないんで、また続巻を待てということになるんだが、次は来年2022年夏という予告もあるので、それまではつまんない感染症にかかったりしないで生き延びたいもんだ。
第八回 悟空 児を捜して寧城に入り 牛王 威を顕して陋巷を震わす(その二)
第九回 刀圭 遊里に胡娘を伴い 行者 陋巷に緑林を知る
第十回 胡娘 酔いて胡旋舞を舞い 心猿 往きて牛魔王に見う
第十一回 両雄 相見えて宿命を知り 怪童女 悟空に再会す
E・S・ガードナー/小笠原豊樹訳 一九八三年 ハヤカワ・ミステリ文庫版
また古いペリイ・メイスンシリーズを読んでみた。
原題「THE CASE OF THE ICE-COLD HANDS」は1963年1962年(※2022年1月9日訂正)の作品。
メイスンの事務所に来たのは、よくある展開で二十代後半の美しい女性、今回はブロンドでも赤毛でもなく「みごとなブリュネット」で、「黒い情熱的なひとみ」の持主。
でも秘書のデラ・ストリートに言わせると、「非常に個性が強くて、いうなれば鉄火の女」というのでひとくせありそう。
依頼内容が変わってて、今日の午後のレースの500ドル分の馬券を持ってきて、買ったときのオッズは50倍だったんだけど、当たってたら払戻金を明日窓口で受け取って、わたしの指示にしたがって手渡してくれというもの。
これは当たってるんだろうなと推測するメイスンたちが、録音の競馬実況放送番組を聞くと、やっぱりその穴馬は勝っていて、翌日受け取るべき現金は14,250ドルと判明。
翌日競馬場に行って、窓口で大金を受け取ってスーツケースに入れてると、神経質そうな五十がらみの男が警察官をつれてやってきて、メイスンのことを逮捕しろとわめく。
男の言うには、その馬券は自分の会社の使用人のロドニー・バンクスが買ったものだ、その賭け金500ドルは自分から横領した金だ、だから自分の金を取り戻すのだ、おまえは共犯だろと。
警察官に聞くと、ロドニー・バンクス自身は前日のレース直後に同じ馬の50ドルの馬券を払い戻しに来たところで逮捕して拘禁中だという。
奴の身柄と50ドル馬券は抑えたが、ほかにも馬券を買ってるに違いないんだ、同じレースの時に奴の姉が100ドル馬券売り場付近にいたのを目撃してるが払い戻しに現れない、おまえはその女のために金とりにきた共犯だろ、というのが相手の言い分。
なんでこんな仕事を依頼されたのかが見えたメイスンだけど、さようでございますかというはずもなく、推論だけの話にはとりあわずその場をやりすごす。
依頼人の女から連絡があり、受け取ったカネのなかから5000ドルを弟の保釈金として払って、残額をいまいるモーテルにもってきてくれという。
乗りかかった船なので保釈手続きまでは済ませたが、やばそうな姉弟なのでこれ以上関わり合いになるのはよそうと思っていると、非常に重大な用件なのでと依頼人からまたメイスンは呼び出される。
モーテルの部屋へ行ってみると彼女は不在で、バスルームで胸を銃で撃たれた死体を見っけちゃう。
そこへ彼女が戻ってくるんだが、彼女の両手は氷のように冷たかった、っていうのがタイトルの由来。
警察が呼ばれて現場検証すると、死体はドライアイス漬けにされてたと判明、物証も出てくる。
具合のわるいことに、メイスンの依頼人は、以前友人たちとの話のなかで、ドライアイス使えば犯行時刻をごまかせるって言ったことがあるし、近くのマスの釣り堀で働いていて持ち帰り用のドライアイスの扱いに慣れているとわかる。
自宅へ戻ってじっとしてろってメイスンの忠告をきかず、依頼人は現場でみつかったドライアイスの容器を処分しようと動いてしまって、警察に殺人容疑でつかまる。
かくして、いつものとおり、圧倒的に不利と思われる状況で事件は裁判に持ち込まれる。
この裁判では、被告の弟が証人として呼び出されるが、別の抜け目ない弁護士がついていて、「わたし自身に不利な証言をすることは拒否します」っていうおなじみの手を使うんだが、検察側が非負罪特権を認めるという声明書が出されるという異例の展開になる。
どっちにしろ、いつもどおり劇的な逆転で裁判はメイスンが勝つのがお約束なんだけど。
裁判シーンより私が気になったのは、横領した金で買った馬券の儲けは誰のものかって議論、メイスンのセリフによれば、
>横領された金の所有権は、依然として元の所有者にある。その金がなにかに投資されて、利益を生んだとすれば、その利潤は元の所有者のものだ(略)
>横領は犯罪だからね(略) 横領者には、金の所有権は生じない。金が横領した人間のものでなければ、その金から生まれた利潤も当然その人間のものじゃないさ(p.71)
っていうんだけど、現在の日本の法律がどうかは知らんが、ガードナーが著作のなかでそう言うんなら当時のカリフォルニアの判例はそれで間違いないんだろうなと思うくらい、シリーズに対する私の信頼は厚い。
どうでもいいけど、日本では横領とかの容疑者が「カネは競馬に使った」とかとんでもないこと言うのは、そう言うもんだと決まりきってるかららしいね。
弁護士がホントにアドバイスするのか、裏社会の都市伝説的な言い伝えなのかは知らんが、なにか高価なモノを買ったとか言っちゃうと、それ売って少しでも返せとか言われちゃうんで、証拠が残らなくて追究されないものとして競馬を持ち出すんだという。
まるで犯罪の動機であるかのように引き合いにだされちゃう、競馬は、何の罪もないはずなのに、イメージがわるくなって、いい迷惑だよね。