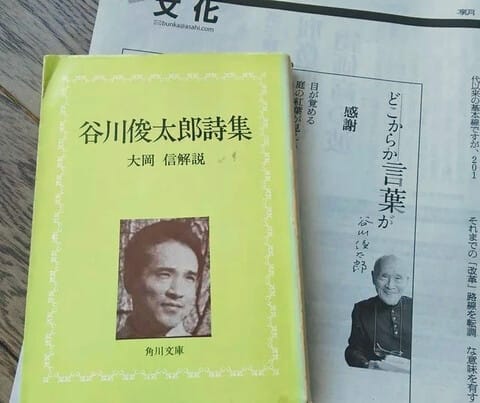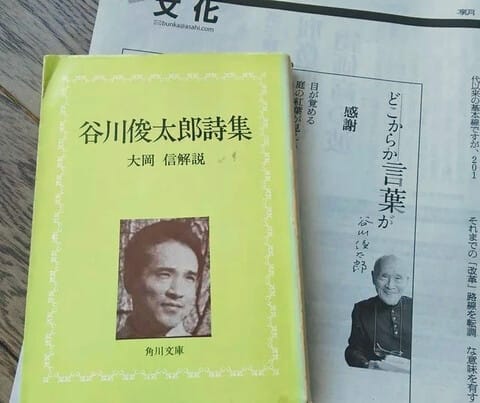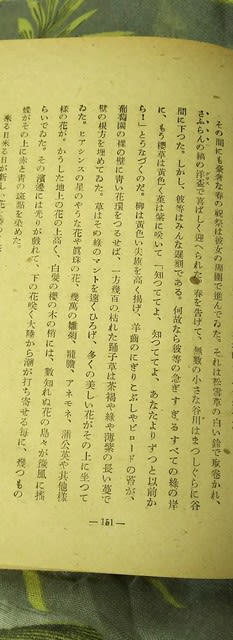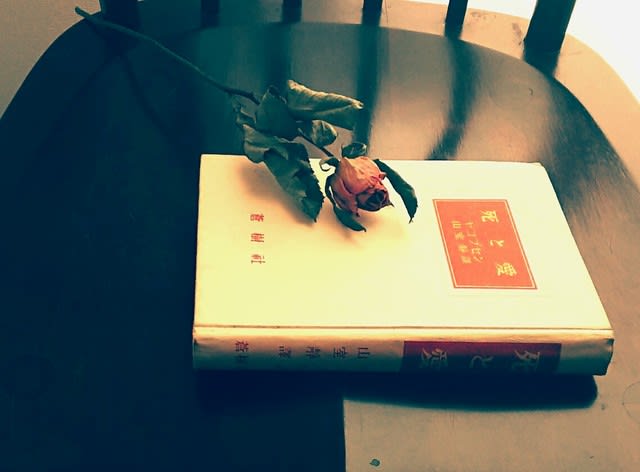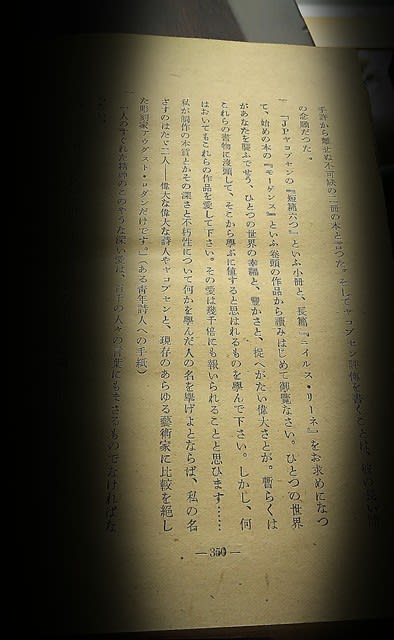マイケル・オンダーチェさんの作品は 作品同士の間でも パッチワークをつくることが可能なのだ、、
と、 先月 『ライオンの皮をまとって』を読み、 新作の『戦下の淡き光』を読んだ後に(
>>)書きました。
マイケル・オンダーチェ著『ライオンの皮をまとって』は初期の作品で、『イギリス人の患者』の前に書いた作品、、 登場人物にも両作品にはつながりがあります。
(今回、再読後に感じたことを書くので 両作品の内容に触れています。ご容赦ください↓)
『イギリス人の患者』の舞台はは第二次大戦終結間近のイタリア。
連合軍が去った後の廃墟の寺院に残った身元不明の大火傷の患者と、 彼を看護するハナ、 そこに地雷除去の工兵キップと、 ハナを良く知る元泥棒の兵士カラヴァッジョが加わり、 四人の不思議な共同生活がはじまる。 患者の口から断片的に語られる 戦前そして戦時中の砂漠探検の記憶や愛の物語、、 見知らぬ者同士だったハナ、キップそれぞれの戦争中の記憶、、 それらが散文詩のように織り成され、 国籍も来し方も異なる彼らの過去や 戦争によって失ったものの哀しみがすこしずつ明らかになっていく。
けれども、 最初に読んだ二十数年前には、 その詩的な文章がもたらす映像的なイメージに酔いしれるのが精一杯。。 患者が語る人妻キャサリンとの愛の物語や、 看護婦ハナと地雷除去の工兵キップが互いに惹かれ合っていく過程に心をうばわれ、、 彼らがそもそもなぜこのイタリアの戦地にいるのか、 ハナがどこの国から来たのかすら殆んど考えていませんでした。 前作にあたる『ライオンの皮をまとって』と、 第二次大戦後の英国を描いた『戦下の淡き光』を読んでやっとそのことに気づいたのです。
重複になりますが、、
「、、 でも、 『戦下の淡き光』を読んで、 『イギリス人の患者』を二十数年ぶりに読んで、 その前提となっている『ライオンの皮をまとって』をまたまた読み返しているところですが(共通するのはふたつの大戦にまたがる時代だということ)、、
『イギリス人の患者』には《イギリス人》など何処にも出てこなかった事… ハナも、ハナの父親のパトリックやカラヴァッジョもカナダから何をしに戦争に加わってイタリアにいたのか、、 (恋におちる相手の)人妻のキャサリンはなぜ砂漠へ来たのか、、」
(前回 『戦場のアリス』実在した英国諜報部の女性スパイ小説の読書記より
>>)
『イギリス人の患者』の中で 看護婦ハナの身の上についてはわずかの情報しか書かれていませんが カナダ人であること、 母はアリス、 継母はクララ、 父パトリックは大戦に参戦しフランスで死亡し、 父の長年の友人が元泥棒のカラヴァッジョでハナを探し出してこの寺院に現れる。
彼らの前半生の物語が『ライオンの皮をまとって』です。 ハナが生まれる以前の、 パトリックとアリスが出会う話や、 後に継母になるクララとの関わり、 そして泥棒としてのカラヴァッジョの経歴。
『イギリス人の患者』と『ライオンの皮をまとって』は別々の独立した小説ですが、 これら共通する登場人物にはマイケル・オンダーチェさんのそれなりの《意図》がたぶんあるのでしょう、、 カナダへの移民たちの物語、 その家族の物語、 人と人が出会い結ばれ 別れ 時代が移り変わっていく歴史… だから、『イギリス人の患者』を再読するときに、 なぜハナが、 カラヴァッジョが、 カナダを遠く離れたイタリアの戦場にいるのかを考えてみる意味はあると思うのです。 《イギリス人の患者》も英国人ではないし、 イギリスの戦争をインドの工兵キップが戦い、 カナダ人のハナの父がフランスで戦死し、 ハナとカラヴァッジョは今イタリアにいる。。
『ライオンの皮をまとって』のネタバレになりますが、 ハナは母アリスと、プロレタリアートの活動家カートウとの子で カートウはハナが生まれる前に殺されました。 ハナが父と呼んでいるパトリックは育ての父です。 そして母アリスはハナが11歳のとき爆死しました。
《爆弾》というのは『イギリス人の患者』の中でとても大きな意味を持っているものです。 ハナが恋心を抱く工兵キップは爆弾処理の工兵。 書かれていないけれども、 ハナの父パトリックも元々建設現場のダイナマイト爆薬のプロでした。
カナダの国づくりの為に使われたダイナマイト、 そして資本家の権力に抵抗する闘争の爆弾、、 大戦下では敵を斃す爆撃や地雷になり、 それから無差別に大量に人類を破壊する原爆へ、、
ハナは『イギリス人の患者』のなかで自分の過去や家族についていっさい語りません。 養父パトリックの戦死も頭から締め出して、 取り憑かれたように患者の看護に身を捧げます。 が、活動家の実父の死、 その闘争活動にも関わった母の爆死、 養父パトリックの戦死、、 ハナの心の闇の深さは底知れないはず… 前作では養父パトリックと暮らすようになるハナは16歳、、 もしかしたらパトリックを父というよりかけがえのない人、愛する人として見ていたのかも、と思う。 全身にやけどを負って生死をさまよう患者を憑かれたように看護するハナは 自分の闇、自分の喪失を患者に投影して必死にその命を引きとどめようとしているのかもしれない。 ハナは《イギリス人患者》を「愛している」とカラヴァッジョに語る。。
そのハナが 《爆薬》の専門家、地雷除去の工兵キップに惹かれていくのは ここにもなにか意味があるのだろう…
深読みすれば ハナの養父パトリック(戦時には40代のはず)が従軍するとしたら、 爆破や火薬の知識を請われて、ではないだろうか… 元泥棒のカラヴァッジョが諜報活動に利用されていたことが書かれているのだから、 そう考えられる。 かつてパトリックとカラヴァッジョは資本家を狙って犯罪を犯した服役者だった。 大戦の兵士に迎え入れるとしたら、 彼らの技術を軍が利用する為と考えるのが妥当かと思う。。
爆死した母をもつハナにとってのこの戦争、、 移民としてまたプロレタリアートとして連合軍に参加している(させられている?)カナダ人のパトリックやカラヴァッジョにとっての戦争、 キップの戦争、、 英国人の出てこない英国軍の戦争という意味。。、
『ライオンの皮をまとって』を読んだ上で『イギリス人の患者』を読み直すと、 インド人工兵キップの英国軍参戦への想いや、 クライマックスでヒロシマへの原爆投下を知ったときのキップの白人憎悪という急展開の違和感が 少し違った意味でわかる気がしてきます。
カナダで白人の国づくりの為に移民が過酷な労働を強いられ、命を奪われ、搾取され、、 という『ライオンの皮をまとって』からのつながりで見れば、 非白人兵士キップに原爆の怒りを体現させたオンダーチェさんの想いもなんとなく感じることはできる。
、、 白人憎悪というよりも、 《爆薬》を終わりの無い争いの手段へ、、殺戮の手段へと変えてしまった者への憎悪。
《爆弾》《爆薬》というキーワードは 『戦下の淡き光』にも繋がっていくこともまた 考える必要があるけれども 新作についてはここではやめておきましょう。。
***
《イギリス人の患者》=アルマシー伯爵はハンガリー人の貴族の考古学者・探検家でした。 そのことは後半のほうで カラヴァッジョが患者にアヘンを投与し、 語り合う過程で明らかにされます。 カラヴァッジョは英国諜報部の命を受けたスパイなのでしょう、、 アルマシーが愛した人妻キャサリンと夫のクリフトンも諜報活動に関わっていたことをカラヴァッジョは告げます。 サハラ砂漠の詳細な地図作成をし、 その土地や部族の知識を持つハンガリー人アルマシーの情報を得る為にクリフトン夫妻が送られた、ということです。
キャサリンがアルマシーに 読むものがなくなったから本を貸して、という場面があります。 肌身離さず持ち歩き、さまざまな備忘録を書き留めてある手帳がわりのヘロドトス『歴史』を、キャサリンはアルマシーから一週間借り受けます。 小説の中ではたったこれだけですが、 このことを別の意味にとらえることもできるでしょう。。
小説の中では アルマシーはキャサリンの遺体を隠した洞窟へたどり着く為 三年後に砂漠へ戻ったことが語られます。 カラヴァッジョは、 アルマシーがドイツ軍のスパイとなり、 ロンメル将軍率いるドイツ軍の「サラーム作戦」にアルマシーが関与し、 諜報員エプラーをカイロへ導く役割をアルマシーがしたことを追求します。 このことは史実だそうですが、 ドイツ軍の手引きをしたアルマシーという解釈や、 その情報を得たカラヴァッジョが諜報員としてその後どうしたか、 アルマシーをどう扱ったか、については 物語には出てきません。 キャサリンを純粋に愛しただけのアルマシーの行動か、、それともスパイか…
意味は読者の解釈にゆだねられます。
正直、、 最初に読んだ二十数年前には、 ロンメル将軍や「サラーム作戦」のことなど何一つ知りませんでしたし、読んだ記憶も残っていません。 アルマシーが実在の人物だというのも知りませんでした。
マイケル・オンダーチェさんの作品は、 たった1行を読み飛ばすと とてつもなく大事なキーワードや伏線を忘れることになる、、と今回気づきました。 ただ、 そこに気づかせるのがオンダーチェさんの主眼なのか、 それとも 詩的で映像的な断片的記憶のつぎはぎの中を読者に自由にさまよわせるのが それが作者の望む読まれ方なのか、、 それもよくわかりません。。
人それぞれで良いのだと思います。
アルマシー伯爵を検索していたら、 オーストリア政府観光局のこんなサイトをみつけました。 アルマシーが暮らした城に現在宿泊できるのだそうです。 実在のアルマシーはイタリアでは死ななかったのですね…⤵
ベルシュタイン城
László Almásy Wiki ラースロー・アルマシー伯爵について
***
『ライオンの皮をまとって』の中にも描かれていない謎がいっぱいです。。
ハナを生んだ母アリスはなぜ若いころ尼僧だったのか… やがて愛し合いハナを身籠ることになる相手の活動家カートウについても詳細はなにも描かれません…
尼僧だったアリスの命を助けた男ニコラス・テメルコフは、 パトリックが服役していた間 両親のいないハナを5年間育てた大事な人です。 そのニコラス・テメルコフについても、 とても重要な人物なのに、、(尼僧アリスとのエピソードもものすごくロマンティックなものだったのに) テメルコフの生き様についてはほんの少ししか書かれません。
マイケル・オンダーチェさんの断片的な物語の手法、、 空白の物語がもたらす余韻や想像の世界、、 その深さ、広さ、、はかなさ、、 ゆえに その物語が愛おしくてたまらないのだと思います。 でも 彼等はきっとどこかに生身の肉体を持って 歴史のなかで生きていたのだろうし(実在しなくてもそう思わせる背景を持ち) オンダーチェさんの作品世界のどこかと別の本のどこかで多くの存在が互いに響き合っているのだろうと思います。
きっと どこかに カートウの物語や、 ニコラス・テメルコフの物語や、 若き尼僧の物語が隠れているのかもしれないし、 これから書かれることもあるのかもしれない…
新作『戦下の淡き光』にも似たような想いがあります。。 新作ではラストにひとつの《種明かし》をオンダーチェさんはめずらしく描いて下さったけれど、 「娥」の物語や 「屋根から落ちた少年」の物語や、、 読後も想いはいつまでもひろがります…
、、 個人的には 『イギリス人の患者』のハナと、 『戦下の淡き光』のぼくが、、 このあと出会うこともあるのかもしれない、、 などと考えてしまいました。 親を喪失した子供時代という過去を持つ二人が…
たんなる想像 ですが…
、、 オンダーチェさんの残りの作品や 『ディビザデロ通り』もまた再読したくなってきました、、 エンドレスになっちゃう…
秋の日よ 暮れないで…
よい読書を。 よい週末を。。