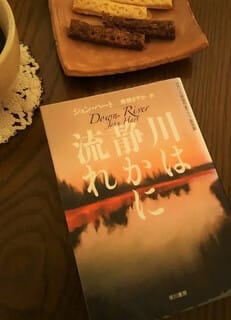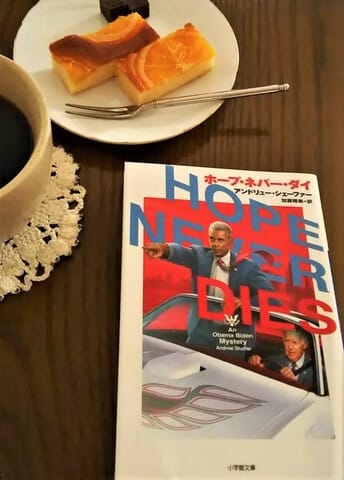4月になりました。 桜、咲きました。
予想に反して開花は遅くなりましたが、 冬枯れの色彩だった街に、ふわっと淡く桜色が浮かびあがるのはうれしいものです。
・・・ ちょっと個人的なことで…。。 先月病院に行ったところ 心臓の検査結果がとっても悪くて、、すこ~し落ち込みました。 これまでじりじりと悪くはなっていたものの 境界領域にとどまっていたのが とうとう悪い領域にはいりこんでしまって、、
そんなに苦しい想いはしてないんだけどな…。。 でも避けられない道のり。。 決してよくはならないから。 これからは毎日が終活の日々… どこまでつづくかは身体次第ね。。 長い長いながーい終活になればいい、、 その日々をちゃんと生きてく。 思い患うことなかれ…
***
春はミステリーの季節。 と勝手に決めているのはワタシです。 目まぐるしい変化の春、 これから毎月コンサートのお出かけもあるし、、 今しばらくは純文学を離れ ミステリー読書の季節がつづきます。
これまでにも沢山書いてきたラーシュ・ケプレル夫妻のヨーナ・リンナ警部シリーズ 第9作が3月に出版されたことも存じております。 でも読みませ~ん、まだ。。
、、前作が肩透かしだったとはいえ、 今度の新刊はサーガが主役になりそうな気配はわかっているので もしももしも余りに恐怖な展開になって最終作へ、、 なんてことになったら、 最終作までまともな気持ちで生きていけ無さそう…(そこまでのこと?) 、、そんな不安(ファンでもある…) 、、なもので、 最終作の出版が決まる頃に満を持して読みたいと思ってます。。
、、 勝手な、ほんとに勝手な願望としては、 ヨーナはサーガに斃されて欲しい… 或はその逆か…(悲痛だけど)。。 お互い以外の、どうでもいいような(←語弊)殺人鬼の手にかかって終える最期なんて許せない… ヨーナも。 サーガも。。
(…と、 サーガのこと考えるとおかしくなるのでここでやめます…)
***
ところで、、
いつから読書の評価に、 「読みやすい」という基準が出てきたんでしょう…
しばしば目にするようになった 「とっても読みやすかったです」 「これは読みやすい本ですか?」 という言葉。。 「読みやすい」って何… ストーリーが単純? 登場人物が少ない? 漢字が少ない? すいすいあっという間に読めるのが良い本? 、、最近よく悩まされています。。
、、まぁ 忙しい時代、 読書などにかける時間も限られ、 読んでみて失敗だったとがっかりするようなムダは極力避けたい気持ちも解らなくは無いですが… 読みやすい、読みにくい、って感想がよくわからない……(ほかに、音楽が 聴きやすい、とか言われるともっと理解不能…)
、、今回の本は おそらく「読みにくい」本、と見なされるのかな。。 ですが 私には楽しめた読書でした。 構成も、文体も、とても面白いと思って読んだし、 友人にも勧めたら、 やはり 「面白かった」と返って来ました。
作者はオーストラリアの作家、 ピーター・テンプル。 残念ながら2018年にすでに他界されています。
『壊れた海辺』 ピーター・テンプル著 土屋晃・訳 ランダムハウス講談社文庫 2008年 原著は2005年

舞台はオーストラリア 南端のヴィクトリア州マンローという、海辺のとても小さな町。 主人公は、署員が3人くらいの警察署の署長キャシン。
・・・と、 簡単に紹介文を書いてしまってはこの小説の良さが損なわれてしまいます。 この小説の好いところは なんにも説明がないところ。
キャシンは身体に過去の大きな怪我の後遺症を抱えている刑事。 生まれ故郷に帰り、 廃屋みたいなかつての我が家に暮らしている。 でもその過去がどんなだったのか殆んど説明がない。 登場人物たちも、 いきなり固有名詞が会話に出てくるのだけれど、 それが人の名前なのか 村の名前なのか、 なにか先住民の~~族などの名称なのか、なかなかわからない。 訳注でもあれば、、と思うのだけど、 その説明のなさが作者の個性だろうから注も無い。
読者にとってはまったく不親切な書き方ですすめられる物語ではあるけれども、 読んでいくうちに キャシンの持つ心の寂寞さや、 その土地に住む人々の 何世代にもわたる込み入った人間関係などが見えてくる。
そして ひょんなことからキャシンの家に泊めることになった渡り職人の男と、 なんだかよくわからないけれども キャシンとの間に誠にぶっきらぼうな、でもどこか人間味のある関係が育ってくる。
事件の謎とともに、 この土地の(この土地にあらわれる)人々の謎も一緒に味わいつつ (少しだけロマンスもあり)、、 ラストは少し意外な事件の急展開があって、、 と、 読みにくい割には読後感は 正統派なハードボイルドとして楽しめました。 孤独なもの同士のそっけない会話も時に胸に刺さるものあり…
あとから思うと、 脇役のひとびとの描写はほんの少しずつなのに、 それぞれで別の物語が作れそうな余韻のある背景を備えている、、 そういう描き方ができるところがこの作家さんの力量なのだと思います。
この作品は 2007年の英国推理作家協会賞や 2008年のネッドケリー賞などを受賞しています。
***
『シューティング・スター』 ピーター・テンプル著 圭初幸恵・訳 柏艪舎 2012年 原著は1999年

先に『壊れた海辺』を読み、 同じ作家さんのものを、と探したらこちらが見つかりました。 札幌にある出版社さんからの本。
こちらの主人公フランクは (こちらも)過去に何らかのいきさつがあって警察を追われた元刑事で、 その前には軍人としてアフガニスタンにいたという経歴の男。 現在は「交渉人」という問題解決の仕事をなりわいとしている。(が、なぜか園芸コースの学校にも行っている…)
今回の仕事は、 ある巨大同族企業の15歳の孫娘が誘拐され、 その身代金の受け渡しをするためにフランクが雇われたというもの。 一族の長老は、今回の事件を警察にゆだねる気はなく、 身代金とひきかえに孫娘の解放だけを望んでいる。 それだけなら 指定場所へ身代金をはこんで行くだけでフランクの仕事は終わる、、 のだったが…
『壊れた海辺』と比べると、 『シューティング・スター』のほうがスリリングな冒頭に感じられます。 とうぜんのこと、身代金を渡してそれで解決、、 にはならないのですが、、 そこさから先がまた別の意味で読みにくい小説で、、
この巨大同族企業の家族たちがいろいろ登場してくるのですが、 名前がトムとかマークとかパットとか、、 その妻がクリスティーンとかステファニーとか、、 誰が誰やら。。 長男とか、次男とか、、 ん~~ どうでもいいや、と思って読み進めていくと後でまったくわからなくなります。。
今回、 主人公の交渉人フランクの相棒に、 軍人時代の友が出てくるのですが、 二人のやさぐれた会話が面白くてそちらに気を取られてしまい、 (一族の名前のことも作者の企みに違いないと思うのですが) 最後のほんの数ページで急展開、急直下の結末に 眼がテン。。
え…? どういうことだったの…? ほんとうに悪いのは誰…? と、、 すべての伏線を拾っておかないと結局おいてきぼりになります。。(私、いまだにわかっていない部分が…)
願わくば、、 本の作りを一考していただけるともうちょっと読みやすくなると思うのですが、、 頁が開きにくかったり、 何度も前を読んだりいったりきたりしたいのに、それをすると本がバラバラになりそう。。 (できれば一族の家系図もあったらいいな)
でも、こちらも面白いハードボイルド小説でした。 フランクとその相棒のコンビで続編も出来そうなそんな終わり方だったし、 今回のちょっとしたロマンスのお相手も別の物語が書けそうななかなか魅力的なひとだったし、、 でも、すぱっと今作だけ、という潔い作家さんなのですね。 書かれていない余白は読者のイマジネーションに。。
今作も2000年のネッドケリー賞受賞作です。
***
きょうの2作品は昨年末と年初に読んでいた本。。 いまはまたべつのミステリを読んでいます。
、、 読みやすい 、、 わかりやすい
、、 聴きやすい
、、 生きやすい
べつにそうでなくても いい… と思うよ
予想に反して開花は遅くなりましたが、 冬枯れの色彩だった街に、ふわっと淡く桜色が浮かびあがるのはうれしいものです。
・・・ ちょっと個人的なことで…。。 先月病院に行ったところ 心臓の検査結果がとっても悪くて、、すこ~し落ち込みました。 これまでじりじりと悪くはなっていたものの 境界領域にとどまっていたのが とうとう悪い領域にはいりこんでしまって、、
そんなに苦しい想いはしてないんだけどな…。。 でも避けられない道のり。。 決してよくはならないから。 これからは毎日が終活の日々… どこまでつづくかは身体次第ね。。 長い長いながーい終活になればいい、、 その日々をちゃんと生きてく。 思い患うことなかれ…
***
春はミステリーの季節。 と勝手に決めているのはワタシです。 目まぐるしい変化の春、 これから毎月コンサートのお出かけもあるし、、 今しばらくは純文学を離れ ミステリー読書の季節がつづきます。
これまでにも沢山書いてきたラーシュ・ケプレル夫妻のヨーナ・リンナ警部シリーズ 第9作が3月に出版されたことも存じております。 でも読みませ~ん、まだ。。
、、前作が肩透かしだったとはいえ、 今度の新刊はサーガが主役になりそうな気配はわかっているので もしももしも余りに恐怖な展開になって最終作へ、、 なんてことになったら、 最終作までまともな気持ちで生きていけ無さそう…(そこまでのこと?) 、、そんな不安(ファンでもある…) 、、なもので、 最終作の出版が決まる頃に満を持して読みたいと思ってます。。
、、 勝手な、ほんとに勝手な願望としては、 ヨーナはサーガに斃されて欲しい… 或はその逆か…(悲痛だけど)。。 お互い以外の、どうでもいいような(←語弊)殺人鬼の手にかかって終える最期なんて許せない… ヨーナも。 サーガも。。
(…と、 サーガのこと考えるとおかしくなるのでここでやめます…)
***
ところで、、
いつから読書の評価に、 「読みやすい」という基準が出てきたんでしょう…
しばしば目にするようになった 「とっても読みやすかったです」 「これは読みやすい本ですか?」 という言葉。。 「読みやすい」って何… ストーリーが単純? 登場人物が少ない? 漢字が少ない? すいすいあっという間に読めるのが良い本? 、、最近よく悩まされています。。
、、まぁ 忙しい時代、 読書などにかける時間も限られ、 読んでみて失敗だったとがっかりするようなムダは極力避けたい気持ちも解らなくは無いですが… 読みやすい、読みにくい、って感想がよくわからない……(ほかに、音楽が 聴きやすい、とか言われるともっと理解不能…)
、、今回の本は おそらく「読みにくい」本、と見なされるのかな。。 ですが 私には楽しめた読書でした。 構成も、文体も、とても面白いと思って読んだし、 友人にも勧めたら、 やはり 「面白かった」と返って来ました。
作者はオーストラリアの作家、 ピーター・テンプル。 残念ながら2018年にすでに他界されています。
『壊れた海辺』 ピーター・テンプル著 土屋晃・訳 ランダムハウス講談社文庫 2008年 原著は2005年

舞台はオーストラリア 南端のヴィクトリア州マンローという、海辺のとても小さな町。 主人公は、署員が3人くらいの警察署の署長キャシン。
・・・と、 簡単に紹介文を書いてしまってはこの小説の良さが損なわれてしまいます。 この小説の好いところは なんにも説明がないところ。
キャシンは身体に過去の大きな怪我の後遺症を抱えている刑事。 生まれ故郷に帰り、 廃屋みたいなかつての我が家に暮らしている。 でもその過去がどんなだったのか殆んど説明がない。 登場人物たちも、 いきなり固有名詞が会話に出てくるのだけれど、 それが人の名前なのか 村の名前なのか、 なにか先住民の~~族などの名称なのか、なかなかわからない。 訳注でもあれば、、と思うのだけど、 その説明のなさが作者の個性だろうから注も無い。
読者にとってはまったく不親切な書き方ですすめられる物語ではあるけれども、 読んでいくうちに キャシンの持つ心の寂寞さや、 その土地に住む人々の 何世代にもわたる込み入った人間関係などが見えてくる。
そして ひょんなことからキャシンの家に泊めることになった渡り職人の男と、 なんだかよくわからないけれども キャシンとの間に誠にぶっきらぼうな、でもどこか人間味のある関係が育ってくる。
事件の謎とともに、 この土地の(この土地にあらわれる)人々の謎も一緒に味わいつつ (少しだけロマンスもあり)、、 ラストは少し意外な事件の急展開があって、、 と、 読みにくい割には読後感は 正統派なハードボイルドとして楽しめました。 孤独なもの同士のそっけない会話も時に胸に刺さるものあり…
あとから思うと、 脇役のひとびとの描写はほんの少しずつなのに、 それぞれで別の物語が作れそうな余韻のある背景を備えている、、 そういう描き方ができるところがこの作家さんの力量なのだと思います。
この作品は 2007年の英国推理作家協会賞や 2008年のネッドケリー賞などを受賞しています。
***
『シューティング・スター』 ピーター・テンプル著 圭初幸恵・訳 柏艪舎 2012年 原著は1999年

先に『壊れた海辺』を読み、 同じ作家さんのものを、と探したらこちらが見つかりました。 札幌にある出版社さんからの本。
こちらの主人公フランクは (こちらも)過去に何らかのいきさつがあって警察を追われた元刑事で、 その前には軍人としてアフガニスタンにいたという経歴の男。 現在は「交渉人」という問題解決の仕事をなりわいとしている。(が、なぜか園芸コースの学校にも行っている…)
今回の仕事は、 ある巨大同族企業の15歳の孫娘が誘拐され、 その身代金の受け渡しをするためにフランクが雇われたというもの。 一族の長老は、今回の事件を警察にゆだねる気はなく、 身代金とひきかえに孫娘の解放だけを望んでいる。 それだけなら 指定場所へ身代金をはこんで行くだけでフランクの仕事は終わる、、 のだったが…
『壊れた海辺』と比べると、 『シューティング・スター』のほうがスリリングな冒頭に感じられます。 とうぜんのこと、身代金を渡してそれで解決、、 にはならないのですが、、 そこさから先がまた別の意味で読みにくい小説で、、
この巨大同族企業の家族たちがいろいろ登場してくるのですが、 名前がトムとかマークとかパットとか、、 その妻がクリスティーンとかステファニーとか、、 誰が誰やら。。 長男とか、次男とか、、 ん~~ どうでもいいや、と思って読み進めていくと後でまったくわからなくなります。。
今回、 主人公の交渉人フランクの相棒に、 軍人時代の友が出てくるのですが、 二人のやさぐれた会話が面白くてそちらに気を取られてしまい、 (一族の名前のことも作者の企みに違いないと思うのですが) 最後のほんの数ページで急展開、急直下の結末に 眼がテン。。
え…? どういうことだったの…? ほんとうに悪いのは誰…? と、、 すべての伏線を拾っておかないと結局おいてきぼりになります。。(私、いまだにわかっていない部分が…)
願わくば、、 本の作りを一考していただけるともうちょっと読みやすくなると思うのですが、、 頁が開きにくかったり、 何度も前を読んだりいったりきたりしたいのに、それをすると本がバラバラになりそう。。 (できれば一族の家系図もあったらいいな)
でも、こちらも面白いハードボイルド小説でした。 フランクとその相棒のコンビで続編も出来そうなそんな終わり方だったし、 今回のちょっとしたロマンスのお相手も別の物語が書けそうななかなか魅力的なひとだったし、、 でも、すぱっと今作だけ、という潔い作家さんなのですね。 書かれていない余白は読者のイマジネーションに。。
今作も2000年のネッドケリー賞受賞作です。
***
きょうの2作品は昨年末と年初に読んでいた本。。 いまはまたべつのミステリを読んでいます。
、、 読みやすい 、、 わかりやすい
、、 聴きやすい
、、 生きやすい
べつにそうでなくても いい… と思うよ