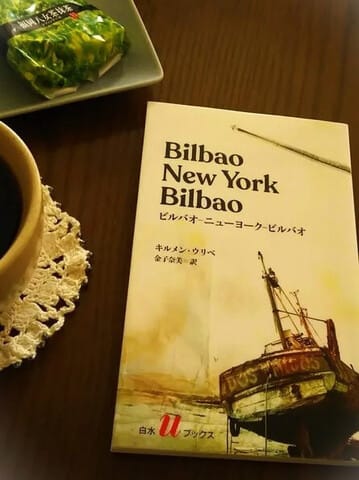・・・ 年末のお掃除、 水回り終了~。。
ひとやすみ… 今日はここまで。 無理しない… 疲れを残すとかならず後でダウンするから・・・
***

エコール・ド・パリの時代の藤田嗣治のエッセイを読んでいます。 大正2年、 27歳でフジタはパリに渡ります。 翌年、 第一次世界大戦が始まりますが 帰国せずに絵を描きつづけて、、 その頃の思い出…
このころのフジタの文章はとても饒舌で 立て板に水の如く言葉があふれ出ているようです。 アーティストらしく 自己演出にも長けた人なのでしょう、、 パリの思い出は苦労話も 女性の話も どこか短篇小説のような演出というか、 盛ってあるような語りに思えます、、 読んでいてそれが楽しいのですけど…笑
「春の女」というエッセイから…
ベルリン生れのこの娘は、巴里を憧れて、自転車で北から南へと、野に寝、山に宿って只白い路をフラリフラリと何日も何日も小鳥の様に、子羊の様に、春の野を、春の畑を、花の香を吸い、空の雲を追って巴里のカッフェに飄然と現れたのであった。・・略・・
(『腕一本 巴里の横顔』藤田嗣治 講談社文芸文庫)
自転車ひとつでドイツから旅して来たこの娘は すぐにカフェで評判になり、 つぎつぎに画家たちのモデルとなって 「秋のサロンを占領してしまった」とあります。
今から百年余り昔に 自転車と身ひとつで欧州を縦断して女の子がパリにやってくるなんて…(年は21歳と…) ほんとうにそんな子がいたのかしら・・・
以前に読んだアンネマリー・シュヴァルツェンバッハの本の肖像が ちょっと頭を掠めました。。 でも時代も年齢もちがいます、 ベルリンでの生活や自転車で事故死したというアンネマリーの記述に ただ連想してしまっただけで…
フジタの語るベルリンから来た娘が、 サロン出品のたくさんの絵にどう描かれたのか、 名前もなく記述もなく 誰の絵ともわかりません。 本当にそんな娘がいたのかさえも… でもフジタの「春の女」は まるで短篇小説のように美しく儚いエッセイでした。 フジタは乳白色の女性の絵を描くとおなじ気持ちでエッセイも書いたのでしょう…
***
このエッセイを読んで、 この小鳥のような春の娘がすこし羨ましく思えました。。 こんな風に身ひとつで生きて旅して 身ひとつの糧を得ていけることに…。 たとえどんな若さに戻れたとしても、 そこらじゅう手術の痕だらけの身では画家のモデルにはなれませんもの、、笑
身ひとつを頼りに、 まさに微動もしないまま数世紀のちの世にまで残る芸術作品になれるなんて、 それはなんとすばらしい才能であり 羨ましいひとつの生き方かと… そんな百年前の巴里の女性たちを、 フジタは言葉でもみずみずしく残してくれています。。
同じ本の 華やいだ巴里の記述のすこし後には、、 帰国した藤田嗣治が帝国海軍委嘱の戦争画家となる従軍記に変わるのです。。 が、それは今日は止します 気持ちが乱れてしまいますから…
***
今年のブログは 年内これでラストになると思います。 このあとの年末年始の日々は、 無理せず 楽しく(←ラクとも読めます)
私と私の周囲のみんなが 心地良く愉しく、 それだけを願ってはたらきます。。
以前、、 パリの読書記で 「どう? 君の幸せが見つかった?」 という言葉を引用しましたね(>>) あの言葉をこのところよく思い出すのです 日々の暮らしのなかで…。 美味しいチョコをみつけた、、 ひさしぶりの友からの連絡が元気そうだった、、 頭痛のない日々が一カ月以上つづいている、、 新年の予報までずーっと晴れ、、 家族の誰も風邪ひかない、、
「どう? 君の幸せが見つかった?」
あなたが愉しそうにしてること、、
君の歓びは わたしの幸せ
どうぞ素敵な日々を…
ひとやすみ… 今日はここまで。 無理しない… 疲れを残すとかならず後でダウンするから・・・
***

エコール・ド・パリの時代の藤田嗣治のエッセイを読んでいます。 大正2年、 27歳でフジタはパリに渡ります。 翌年、 第一次世界大戦が始まりますが 帰国せずに絵を描きつづけて、、 その頃の思い出…
このころのフジタの文章はとても饒舌で 立て板に水の如く言葉があふれ出ているようです。 アーティストらしく 自己演出にも長けた人なのでしょう、、 パリの思い出は苦労話も 女性の話も どこか短篇小説のような演出というか、 盛ってあるような語りに思えます、、 読んでいてそれが楽しいのですけど…笑
「春の女」というエッセイから…
ベルリン生れのこの娘は、巴里を憧れて、自転車で北から南へと、野に寝、山に宿って只白い路をフラリフラリと何日も何日も小鳥の様に、子羊の様に、春の野を、春の畑を、花の香を吸い、空の雲を追って巴里のカッフェに飄然と現れたのであった。・・略・・
(『腕一本 巴里の横顔』藤田嗣治 講談社文芸文庫)
自転車ひとつでドイツから旅して来たこの娘は すぐにカフェで評判になり、 つぎつぎに画家たちのモデルとなって 「秋のサロンを占領してしまった」とあります。
今から百年余り昔に 自転車と身ひとつで欧州を縦断して女の子がパリにやってくるなんて…(年は21歳と…) ほんとうにそんな子がいたのかしら・・・
以前に読んだアンネマリー・シュヴァルツェンバッハの本の肖像が ちょっと頭を掠めました。。 でも時代も年齢もちがいます、 ベルリンでの生活や自転車で事故死したというアンネマリーの記述に ただ連想してしまっただけで…
フジタの語るベルリンから来た娘が、 サロン出品のたくさんの絵にどう描かれたのか、 名前もなく記述もなく 誰の絵ともわかりません。 本当にそんな娘がいたのかさえも… でもフジタの「春の女」は まるで短篇小説のように美しく儚いエッセイでした。 フジタは乳白色の女性の絵を描くとおなじ気持ちでエッセイも書いたのでしょう…
***
このエッセイを読んで、 この小鳥のような春の娘がすこし羨ましく思えました。。 こんな風に身ひとつで生きて旅して 身ひとつの糧を得ていけることに…。 たとえどんな若さに戻れたとしても、 そこらじゅう手術の痕だらけの身では画家のモデルにはなれませんもの、、笑
身ひとつを頼りに、 まさに微動もしないまま数世紀のちの世にまで残る芸術作品になれるなんて、 それはなんとすばらしい才能であり 羨ましいひとつの生き方かと… そんな百年前の巴里の女性たちを、 フジタは言葉でもみずみずしく残してくれています。。
同じ本の 華やいだ巴里の記述のすこし後には、、 帰国した藤田嗣治が帝国海軍委嘱の戦争画家となる従軍記に変わるのです。。 が、それは今日は止します 気持ちが乱れてしまいますから…
***
今年のブログは 年内これでラストになると思います。 このあとの年末年始の日々は、 無理せず 楽しく(←ラクとも読めます)
私と私の周囲のみんなが 心地良く愉しく、 それだけを願ってはたらきます。。
以前、、 パリの読書記で 「どう? 君の幸せが見つかった?」 という言葉を引用しましたね(>>) あの言葉をこのところよく思い出すのです 日々の暮らしのなかで…。 美味しいチョコをみつけた、、 ひさしぶりの友からの連絡が元気そうだった、、 頭痛のない日々が一カ月以上つづいている、、 新年の予報までずーっと晴れ、、 家族の誰も風邪ひかない、、
「どう? 君の幸せが見つかった?」
あなたが愉しそうにしてること、、
君の歓びは わたしの幸せ
どうぞ素敵な日々を…