

佐野洋子さんといえば、『神も仏もありませぬ』で
小林秀雄賞を受けた作家で、軽妙なエッセイがもち味。
が、この本では、母との関係、母への愛憎、娘としての思いが、簡潔かつ率直に、
だけど、淡々と、にはほど遠い言葉で、連綿と書き連ねてある。
乳がんを再発した著者が、このことを書かなければ死ぬに死ねない、
という思いがあふれている本、といったほうがよいだろう。
母が命にかかわる病気になり、わたしにとっても、
母との関係、母への愛憎、娘としての思いを考えることの多かった日々、
あらためて母と向き合い、「わたしは母を愛している」と確認する日々だった。
すべての、「母を持つ娘」に読んで欲しい本。
先週の「よみうり堂」に書評が載っていた。
 『シズコさん』佐野洋子著 新潮社1400円 母と娘のねじくれた絆 『シズコさん』佐野洋子著 新潮社1400円 母と娘のねじくれた絆 母親との関係をテーマに、30~40代の女性にインタビューしたことがある。一人一人が、これほどたくさんの矛盾する言葉を口にした取材は後にも先にもこの時だけだ。愛と嫌悪、尊敬と恨み、感謝と怒り――。 自分の母のようになるのがイヤだから子供を産みたくないと、強い口調で言った人がいる。同じ人が、インタビューが終わる頃には、母のように完璧(かんぺき)な子育てをする自信がないと洩(も)らした。 夫より子供より母の方が好きだったという主婦は、母が死んだ時、遺体にすがって「私もお棺に入る!」と叫んだ。しかしその後、気がつくと生前の母が嫌がったことをすべてやっていたという。車の運転を習い、ミニスカートをはき、専業主婦をやめて職についた。「母という重しがとれ、自分でもとまどうほどの解放感がありました」 母を憎んでいる人も、愛している人も、みんな母が重たいのだった。 『シズコさん』は、70歳になる佐野洋子が、みずからの母親について綴(つづ)ったエッセイである。母という存在の重たさを、ここまで正直に、魂を削るようにして書いた人を、私は他に知らない。 著者の母・シズコさんは、90歳を過ぎて老人介護施設で暮らしている。この母親のことを一度も好きだったことがないと著者は書く。見栄を張って学歴をごまかし、障害者の弟妹に冷たく、決してごめんなさいとありがとうを言わなかった母。 4歳の時、手をつなごうとして邪険に振り払われてから、著者は一度も母にふれたことがない。母親が嫌いで、顔を見ると首を絞めたくなるという友人の話を聞いて思う。<この人の方がましだ。素手で首をしめられるのだ。私は素手で母の首にさわるなんて嫌だ> 一方で、母がいたから現在の自分があるのだということもわかっている。母は31歳で敗戦を迎えて一家で北京から引き揚げ、42歳で未亡人になった。7人の子供を産んで3人を亡くし、女手ひとつで4人の子供を全員大学に入れた。愚痴をこぼし、人の悪口も言ったが、しょぼくれた姿を子供たちに一度も見せなかった。 母を好きになれないことに娘は自責の念を持ち続け、高価な介護施設に入れたことを<金で母を捨てたのだ>と思う。その施設で呆(ぼ)けが進んだ母は、別人のように柔和で優しくなっていった。 ある日、著者は母の靴下を脱がせようとして、〈途中でやめた纏足(てんそく)みたいに小さく〉なった冷たい足を、思わず手でさする。やっと母にさわることができたのだ。 〈「私悪い子だったね、ごめんね」 母さんは、正気に戻ったのだろうか。 「私の方こそごめんなさい。あんたが悪いんじゃないのよ」〉 50年以上の歳月をかけて、母娘がたどり着いた場所。そこに立ち会う時、読者もまた自分自身の母への愛憎に向き合うことになる。私の女友達は皆この場面で泣いたという(私も泣いた)が、それはきっと、ひとりひとり違う涙だったろう。 それにしても、娘にとって、母親とのねじくれた絆(きずな)をほどき、結び直すことは、なんと大変な作業であることか。それはもしかすると、結婚や仕事や子育てよりも困難な、人生の大仕事なのかもしれない。 <私とあなたの間には、いることも、いらないこともあったわねェ> 呆けたシズコさんが著者に言う言葉だ。そう、すべての母と娘の間には、ないほうがよかった出来事がたくさんある。でも、なかったことにはできない。そのまま、まるごと、許し合うしかないのである。 ◇さの・ようこ=1938年、北京生まれ。絵本作家、エッセイスト。代表作に『100万回生きたねこ』『わたしのぼうし』など。最新エッセーに『役にたたない日々』。 新潮社 1400円 評・梯 久美子(かけはし・くみこ) 1961年、熊本県生まれ。ノンフィクション作家。『散るぞ悲しき』で第37回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。 (2008年6月2日 読売新聞) |

応援クリック
 してね
してね 



昨日読んでいたのが、三浦雅士さんの『漱石 母に愛されなかった子 』。
若いころ漱石がすきで、特に『心』に惹かれて何度も読んだわたしにとって、
「目からウロコ」のめちゃおもしろい評論だった。
あらためて、漱石を読み直したくなった。
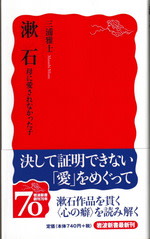
『漱石 母に愛されなかった子 』
(三浦 雅士著/岩波書店 /2008/04)
----------------------------------------------
決して証明できない「愛」をめぐって
母の愛を疑い、その疑いを覆い隠す。……どうもそれは、人間というものの仕組みに深くかかわっているように思えます。漱石を手がかりにそのことを考えてみたい。あるいは、そのことを手がかりに漱石について考えてみたい。漱石という作家は、本人が意識していたかどうかはともかく、そのことについて集中的に考えていたと思われるからです。(本文より)
■内容紹介 漱石が生涯抱え続けた苦悩。それは母の愛を疑うという、ありふれた、しかし人間にとって根源的な苦悩であった。『吾輩は猫である』『坊っちゃん』等の初期作品からまさに圧巻の『明暗』まで、この「心の癖」との格闘に貫かれた漱石作品は、今なお自己への、人間への鮮烈な問いとして我々の前にある。
現代を代表する文芸評論家が、批評の新たな地平をしめす一書。
-----------------------------------------------------
今朝の毎日新聞にも書評が載っていたので紹介します。
 今週の本棚:鹿島茂・評 『漱石 母に愛されなかった子』=三浦雅士・著(岩波新書・777円) 今週の本棚:鹿島茂・評 『漱石 母に愛されなかった子』=三浦雅士・著(岩波新書・777円) ◇「欠如ゆえの過剰防衛」の秘密 以前、夏目漱石がフランス文学をどう評価しているか気になって調べたことがある。総じて点が辛い中、モーパッサンの『ピエールとジャン』だけは例外的に激賛されていた。『ピエールとジャン』とはこんな物語だ。母親の愛が弟のジャンに片寄っているため偏屈な性格になった兄のピエールは美しい未亡人に恋しているが、未亡人はジャンを愛しているので嫉妬(しっと)に苦しむ。あるときジャンに未知の男から莫大(ばくだい)な遺産がころがりこんだことから、ピエールは弟が母親の不義の子である事実をつきとめ、自分が愛されなかった理由を知る。母親への愛と憎しみ、弟への嫉妬、そして、それらを克服できない自分への嫌悪感。こうした感情に悩み抜いたピエールは太平洋航路の船医になって家庭を去っていく。 フランス文学畑の人間からみると『ピエールとジャン』は佳作だが、漱石の言うほどの大傑作ではない。ために、どうして漱石がそれほどこの作品にほれ込んだのかいまひとつ理由がわからなかったが、本書を一読して疑問は氷解した。ピエールとは漱石自身であり、「母に愛されなかった子」ピエールの懊悩(おうのう)は漱石の懊悩そのものだったのである。 著者によれば「母に愛されなかった子」漱石というテーゼを証明するには『坊っちゃん』一つで足りるという。げんに坊っちゃんは、おやじはちっともおれを可愛がってくれなかった、母は兄ばかりを贔屓(ひいき)にしていたと語る。坊っちゃんに仮託した漱石の母親への心の屈折が明らかになるのはその死に際してのエピソードである。母が病気で死ぬ二、三日前、坊っちゃんは台所で宙返りして肋骨(ろっこつ)を打ち、母から叱(しか)られ、おまえのようなものの顔は見たくないと言われる。母親の言葉は怒りの強さを示すレトリックなのだが、坊っちゃんはこれを字義どおりに受け取り、じゃあ、消えてやるよと、親戚(しんせき)の家に泊まりにいって親の死に目に会えずに終わる。 こうした、愛する相手がこちらの要求するレベルで愛に応えてくれないと、「なら、いい!」とふて腐れ、捨て鉢な態度に出て、それによって余計傷つき、人も傷つけるという愛情表現の空回りのドラマこそが漱石文学の根幹を成すと著者は考える。「母親に愛されていないのではないかと疑い、疑ったことを後ろめたく思い、その後ろめたさを打ち消すために、これだったら愛されないに違いないという証拠を自分から作っていく、そうして疑いを正当化する」。坊っちゃんの態度は漱石自身に巣くう愛情乞食(こじき)の投影なのだ。 こうした欠如ゆえの過剰防衛的性格は、母親が登場しない『草枕』や『虞美人草』、さらには『三四郎』『それから』『門』の前期三部作でも、また晩年の作品でも男女関係に転位され、大きなライトモチーフとなっている。このあたりの分析は見事というほかないが、ひとつだけ挙げるなら『それから』で三千代が代助に「なぜ捨ててしまったんです」と問い詰めるクライマックスの解釈だろう。「なぜ捨ててしまったのか、というのは、幼い漱石が、母に対して投げかけたかった問いにほかならなかった。投げかけたかったけれども、投げかけずに終わってしまった問い、そうして、捨てられるくらいなら、こっちから捨ててやるという論理にしがみつき、そういう煩悶(はんもん)から超然とすべく漢籍に走り、表現者への道を選んだ、そのきっかけになった問いにほかならなかった」 親と子の、そして男と女の永遠に終わらない愛の齟齬(そご)。漱石の現代性を改めて浮き彫りにした傑作評論である。 (毎日新聞 2008年6月8日) |

(2008.6.8 読売新聞)
母との葛藤をえがいた『シズコさん』のテーマの関連では、
信田さよ子さんの『母が重くてたまらない―墓守娘の嘆き』、
母と向き合い理解するための上野千鶴子さん編の
『今、親に聞いておくべきこと』もおもしろい。

『母が重くてたまらない―墓守娘の嘆き』
(信田さよ子/春秋社 /2008/04)

『今、親に聞いておくべきこと』
(上野千鶴子編著, 藤原 ゆきえ著), 田島 安江著/法研/2005)
写真をクリックすると拡大。その右下のマークをクリックするとさらに拡大
人気ブログランキング(エッセイ)に参加中

応援クリック
 してね
してね 





















