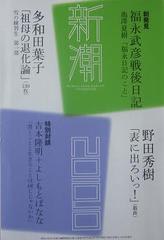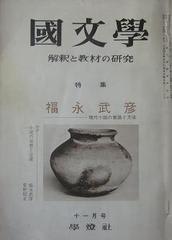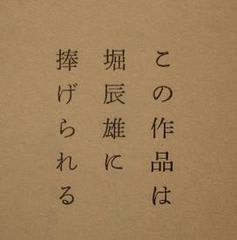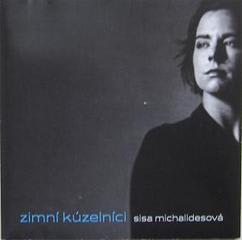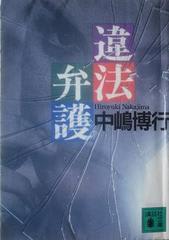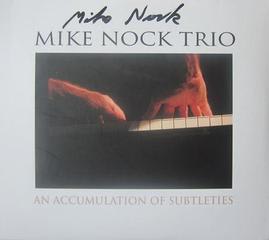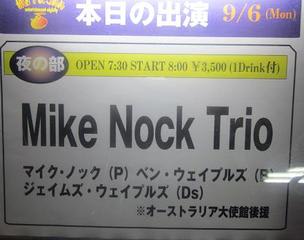キース・ジャレットのコンサートに来日のたびに行っています。
今回スタンダード・トリオでの演奏は、いつこのトリオ編成が終わってしまうのかの心配もあって、という言うようり、絶大ファンなので必ず見るようにしています。
追っかけでないので、来日のたび1回の公演を選びます。
そのチケットが私のお守りみたいになっています。気がついたら、持っているものは5枚になりました。

さて今度のスタンダード・トリオですが、ずっと心配しているベースのピーコックの力強さが一番の心配、これが最後かといつも気を引き締めて聴くコンサートなのです。
会場Bunkamuraの前には有名な(最近ですが)パン屋さんで軽くいただけるのでそこで6時までいただいてから会場に移りました。


久しぶりのキースの会場は、いつものように緊張感が段々と増していきます。
普段よりも長く待った感じで、出てきたオレンジ色のシャツのキースは、椅子に坐るとすっと弾き始めました。
鯉沼さんに申し込んで決まる席はいつも随分前のほうなのですが、今回は残念ながら後ろのほう、生音は伝わらないし、なんとも切れの悪い音が聴こえてきます。
1曲目“Solor”でしょが音がはっきり伝わってきません。サウンド・チョックのしっかりしたキースとしてはめずらしい、なんだこれはの1曲目で始まりました。
1曲目、ミキシングに坐っている人を見たら、一人だけ、2曲目で少しだけ音は改善しました。
3曲目でしょか、とてもゆったりとした曲、1曲目後の刺激少ない音に、夢の中にはいてしまいました。この曲いい感じでした。
“サム・ディ・マイ・プリンス”が流れた時には、これが何曲目か解らないうつろ、でもそこで目がさめて、キースのゴスペル調オリジナル“G-Bluse"で1部は終わりました。
2nd
1 Django
大好きなジャンゴからの始まりに驚きました。音が2ndここらからしっかりと伝わるようになった感じです。という事で1stはミキシングに問題有と思います。
ここでのピアノは、ジョン・ルイスのサウンドにとても似ているように聴こえるのです。
これ、キースがそのリズム運びを捉えながら演奏しているからなのでしょう。
2 My Ship
実はこのコンサート、どうも納得できないのがデジョウネットのドラムスで、ただただメロディにあわせているだけのようなリズム、どうしたくとでしょう。
それに引き換え、ベースのピーコックはフレージングも生き生きしていて、安心したのです。
3 Sandu
グルーヴィーな展開から繋がる曲で、ここら変に集中力が高まりました。
ここで終わってアンコール2曲、2曲目に“When I Fall In Love"が流れた時に今日のアンコールはこれで終わりだと思いました。
初日の今回は残念ながら、過去に並べたチケットよりも驚きは少ないコンサートになりました。
ドラムス(デジョネット)がトリオの創造をおろそかにしてはいけません。
これからいくつかの、日本公演のコンサートがあるでしょう。
このグループ、テンション上がれば凄いことになるので、私の聴かないところで、きっと良い演奏するでしょう。
今回スタンダード・トリオでの演奏は、いつこのトリオ編成が終わってしまうのかの心配もあって、という言うようり、絶大ファンなので必ず見るようにしています。
追っかけでないので、来日のたび1回の公演を選びます。
そのチケットが私のお守りみたいになっています。気がついたら、持っているものは5枚になりました。

さて今度のスタンダード・トリオですが、ずっと心配しているベースのピーコックの力強さが一番の心配、これが最後かといつも気を引き締めて聴くコンサートなのです。
会場Bunkamuraの前には有名な(最近ですが)パン屋さんで軽くいただけるのでそこで6時までいただいてから会場に移りました。


久しぶりのキースの会場は、いつものように緊張感が段々と増していきます。
普段よりも長く待った感じで、出てきたオレンジ色のシャツのキースは、椅子に坐るとすっと弾き始めました。
鯉沼さんに申し込んで決まる席はいつも随分前のほうなのですが、今回は残念ながら後ろのほう、生音は伝わらないし、なんとも切れの悪い音が聴こえてきます。
1曲目“Solor”でしょが音がはっきり伝わってきません。サウンド・チョックのしっかりしたキースとしてはめずらしい、なんだこれはの1曲目で始まりました。
1曲目、ミキシングに坐っている人を見たら、一人だけ、2曲目で少しだけ音は改善しました。
3曲目でしょか、とてもゆったりとした曲、1曲目後の刺激少ない音に、夢の中にはいてしまいました。この曲いい感じでした。
“サム・ディ・マイ・プリンス”が流れた時には、これが何曲目か解らないうつろ、でもそこで目がさめて、キースのゴスペル調オリジナル“G-Bluse"で1部は終わりました。
2nd
1 Django
大好きなジャンゴからの始まりに驚きました。音が2ndここらからしっかりと伝わるようになった感じです。という事で1stはミキシングに問題有と思います。
ここでのピアノは、ジョン・ルイスのサウンドにとても似ているように聴こえるのです。
これ、キースがそのリズム運びを捉えながら演奏しているからなのでしょう。
2 My Ship
実はこのコンサート、どうも納得できないのがデジョウネットのドラムスで、ただただメロディにあわせているだけのようなリズム、どうしたくとでしょう。
それに引き換え、ベースのピーコックはフレージングも生き生きしていて、安心したのです。
3 Sandu
グルーヴィーな展開から繋がる曲で、ここら変に集中力が高まりました。
ここで終わってアンコール2曲、2曲目に“When I Fall In Love"が流れた時に今日のアンコールはこれで終わりだと思いました。
初日の今回は残念ながら、過去に並べたチケットよりも驚きは少ないコンサートになりました。
ドラムス(デジョネット)がトリオの創造をおろそかにしてはいけません。
これからいくつかの、日本公演のコンサートがあるでしょう。
このグループ、テンション上がれば凄いことになるので、私の聴かないところで、きっと良い演奏するでしょう。