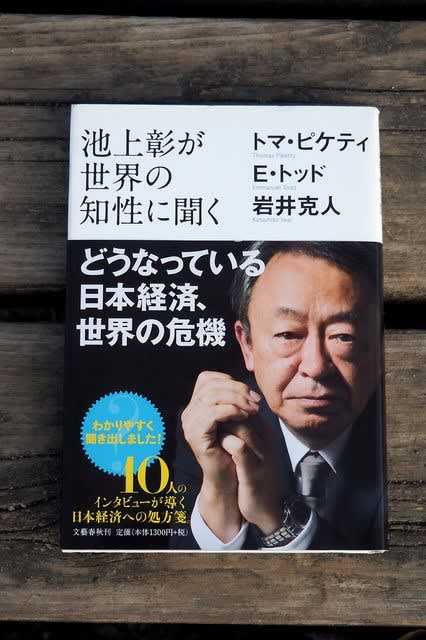
■本日の朝日新聞
何気なく拡げた本日の朝日新聞に、めずらしく瞠目させられた。
一つは書籍の広告。
1.塩野七生さんの「ギリシア人の物語」第3巻の刊行予告が、ふたたび掲載されていた。
塩野七生最後の歴史長編「アレキサンダー大王伝」は、サブタイトル「新しき力」となるようである。
12月15日発売開始。愉しみたのしみ・・・期待で胸をふくらませているファンが、いったいどのくらいいるのか? 価格は高いだろうけど、むろんそれだけの価値ある一冊となるだろう。

2.新聞の日曜版には、さまざまなジャンルにわたって、書評が掲載され、読書人にとっては気になるページ。
そこに大川周明の「日本二千六百年史」(新書版)という広告が!!
たちまち10刷、ベストセラー第1位のキャッチが躍っている。
大川周明にこんな著書があったのは知らなかったぞ(*-ω-*)
おまけに、不敬罪削除37カ所を復原とある。出版は「毎日ワンズ」だそうである。知らんなあ、そんな会社。
戦前はむろん、戦後もGHQが「危険」のレッテルを貼って発禁にした。したがって、「幻の書」というわけである。
これはぜひとも、書店で詳細チェックの要ありだ´д`。
肝心の書評欄には、たいしておもしろそうな記事はなかった。「遺言」を刊行した養老孟司さんへのインタビューだけだな、関心をそそられたのは。

3.「ニュータウン 夢見た先に」
この特集記事も、見逃すことができないおもしろさをもっている。
東京を中心に、地方の大都市とその周辺には、高度成長期に、巨大なニュータウンが建てられた。所帯1千戸以上のいわゆる“ニュータウン”は、全国2千カ所にのぼるという。
それが現在、危機的状況に陥っている。
《ニュータウンの住民は多くが核家族で、住み始めた時期や年齢、収入が似ている。町並みは均一的でプライバシー性も極めて高い。子が独立し、夫婦のいずれかが他界すると、待っているのは孤立だ。
いまニュータウンで起きている現象は今後多くの住宅街で起こる。(中略)近年都心回帰で人気のタワーマンションはそもそも地域と遮断された造りで、高齢となると孤立しやすい。》(神戸大学平山洋介教授)
大いなる時代のうねりを見通すことができず、「はてさて、どうしたものか」と、もがいているのだ。
持続可能性のない“町並み”や“商店街”。
事態は年々きびしさを増しているけど、これを解決するための秘策はいまのところ見つかっていない。
日本の“衰退”。それを阻止できないなら、せめてソフトランディングさせようと、日本中が頭をしぼっている(^^;)
タワーマンションも、このままでは巨大な墓標・棺桶となっていく危険がある。
つぎは、いま読んでいる本の感想をひとくさり♪
■「どうなっている日本経済、世界の危機」インタビュアー池上彰(文藝春秋社刊)。
現在TVなどマスコミで大活躍の池上彰さん、書名も「池上彰が世界の知性に聞く」とまるで二階建ての建物みたいになっている。
またしても池上流の“啓蒙、啓発の書”かなと予想していたが、そうではなかった。
<世界の知性に聞く>
1.経済学者・トマ・ピケティ
2.歴史人口学者・エマニュエル・トッド
3.経済学者・岩井克人
<日本経済の歩みを知る>
4.元総理大臣・中曽根康弘
5.元通商産業事務次官・小長啓一
6.新日本製鉄名誉会長・今井啓
7.元大蔵財務官・大場智満
8.元セゾングループ代表・堤清二
9.元新生銀行社長・八城政基
10. 元財務大臣・塩川正十郎
第一部<世界の知性に聞く>はさしたることがなく、期待はずれ。
準備不足なのか、池上さんの踏み込みがたりず、体よくかわされてしまった感が強い。
「公式インタビュー」みたいなもので、もっとガツンと、しつこく食い下がってほしかった。
とくにピケティ、トッドには、わたしは近ごろ絶大な関心を寄せるようになっている。
著書も数冊買ったばかり。
ところが後半のいわば第二部<日本経済の歩みを知る>は、内容のかなり濃いインタビューとなっている。
中曽根元総理をはじめ、日本の一時代を背負って立った人たちばかり。
勉強不足のわたしは、しばし眩暈に襲われた。
中曽根さんには「日本経済はどこで間違えたと思いますか?」、大場さんへは「プラザ合意と円高不況はアメリカの罠ですか?」、堤さんには「百貨店はなぜ消費者に見捨てられたのですか?」
・・・といったように、相手の急所を衝く質問を、ズバリと投げかけている。
昨夜は堤清二へのインタビューを読みながら、「大いなる時代のうねり」なるものを、ひしひしと感じ、目頭が何というか・・・熱くなって、しきりと過ぎ去りし時代が思い出された。
第二部に登場する人びとは、政界、産業界、財界のトップに君臨したことがあるような有名人ばかり。
堤さんはセゾングループの創始者として、一世を風靡し、また文学活動をするという二足の草鞋を履いた人物。
ここでインタビューに答えている堤さんは「敗軍の将」なのである。
時代のうねりにのみこまれ、凋落していく。
最後には債権者たる銀行に、自宅までとられてしまったと語っている。
そういう男が、世の中には数多く存在する。「敗軍の将」というのは、昔は首を刎ねられたものだが、現在は大抵、老後を生きながらえることができる。
わたしの知人にも、ついこのあいだ、会社を倒産させて、苦境にあえいでいる人がいる。
堤清二という人物は、それを大規模にやり遂げ、頂点に立ったあと、時代の大いなるうねりに抗戦もむなしく没落していった。
時代の繁栄と衰退を、一心に体現したのが、この人であるだろう。
これまではほとんど関心はなかったが、このインタビューをきっかけに、わたしの大切なキーワードの一つに「堤清二(ペンネームは辻井喬)」が加わった。
この人と、その周辺を調べることによって、わたしはわたしが生きてきた時代が、どういったものであったか、追究できそうだ・・・という気分になっている。
政治家としては中曽根康弘または田中角栄、実業家では西武流通グループ、パルコなどを率いた堤清二、これらの人びとの仕事にわたしの半生もまた収斂されるのだろう。
何気なく拡げた本日の朝日新聞に、めずらしく瞠目させられた。
一つは書籍の広告。
1.塩野七生さんの「ギリシア人の物語」第3巻の刊行予告が、ふたたび掲載されていた。
塩野七生最後の歴史長編「アレキサンダー大王伝」は、サブタイトル「新しき力」となるようである。
12月15日発売開始。愉しみたのしみ・・・期待で胸をふくらませているファンが、いったいどのくらいいるのか? 価格は高いだろうけど、むろんそれだけの価値ある一冊となるだろう。

2.新聞の日曜版には、さまざまなジャンルにわたって、書評が掲載され、読書人にとっては気になるページ。
そこに大川周明の「日本二千六百年史」(新書版)という広告が!!
たちまち10刷、ベストセラー第1位のキャッチが躍っている。
大川周明にこんな著書があったのは知らなかったぞ(*-ω-*)
おまけに、不敬罪削除37カ所を復原とある。出版は「毎日ワンズ」だそうである。知らんなあ、そんな会社。
戦前はむろん、戦後もGHQが「危険」のレッテルを貼って発禁にした。したがって、「幻の書」というわけである。
これはぜひとも、書店で詳細チェックの要ありだ´д`。
肝心の書評欄には、たいしておもしろそうな記事はなかった。「遺言」を刊行した養老孟司さんへのインタビューだけだな、関心をそそられたのは。

3.「ニュータウン 夢見た先に」
この特集記事も、見逃すことができないおもしろさをもっている。
東京を中心に、地方の大都市とその周辺には、高度成長期に、巨大なニュータウンが建てられた。所帯1千戸以上のいわゆる“ニュータウン”は、全国2千カ所にのぼるという。
それが現在、危機的状況に陥っている。
《ニュータウンの住民は多くが核家族で、住み始めた時期や年齢、収入が似ている。町並みは均一的でプライバシー性も極めて高い。子が独立し、夫婦のいずれかが他界すると、待っているのは孤立だ。
いまニュータウンで起きている現象は今後多くの住宅街で起こる。(中略)近年都心回帰で人気のタワーマンションはそもそも地域と遮断された造りで、高齢となると孤立しやすい。》(神戸大学平山洋介教授)
大いなる時代のうねりを見通すことができず、「はてさて、どうしたものか」と、もがいているのだ。
持続可能性のない“町並み”や“商店街”。
事態は年々きびしさを増しているけど、これを解決するための秘策はいまのところ見つかっていない。
日本の“衰退”。それを阻止できないなら、せめてソフトランディングさせようと、日本中が頭をしぼっている(^^;)
タワーマンションも、このままでは巨大な墓標・棺桶となっていく危険がある。
つぎは、いま読んでいる本の感想をひとくさり♪
■「どうなっている日本経済、世界の危機」インタビュアー池上彰(文藝春秋社刊)。
現在TVなどマスコミで大活躍の池上彰さん、書名も「池上彰が世界の知性に聞く」とまるで二階建ての建物みたいになっている。
またしても池上流の“啓蒙、啓発の書”かなと予想していたが、そうではなかった。
<世界の知性に聞く>
1.経済学者・トマ・ピケティ
2.歴史人口学者・エマニュエル・トッド
3.経済学者・岩井克人
<日本経済の歩みを知る>
4.元総理大臣・中曽根康弘
5.元通商産業事務次官・小長啓一
6.新日本製鉄名誉会長・今井啓
7.元大蔵財務官・大場智満
8.元セゾングループ代表・堤清二
9.元新生銀行社長・八城政基
10. 元財務大臣・塩川正十郎
第一部<世界の知性に聞く>はさしたることがなく、期待はずれ。
準備不足なのか、池上さんの踏み込みがたりず、体よくかわされてしまった感が強い。
「公式インタビュー」みたいなもので、もっとガツンと、しつこく食い下がってほしかった。
とくにピケティ、トッドには、わたしは近ごろ絶大な関心を寄せるようになっている。
著書も数冊買ったばかり。
ところが後半のいわば第二部<日本経済の歩みを知る>は、内容のかなり濃いインタビューとなっている。
中曽根元総理をはじめ、日本の一時代を背負って立った人たちばかり。
勉強不足のわたしは、しばし眩暈に襲われた。
中曽根さんには「日本経済はどこで間違えたと思いますか?」、大場さんへは「プラザ合意と円高不況はアメリカの罠ですか?」、堤さんには「百貨店はなぜ消費者に見捨てられたのですか?」
・・・といったように、相手の急所を衝く質問を、ズバリと投げかけている。
昨夜は堤清二へのインタビューを読みながら、「大いなる時代のうねり」なるものを、ひしひしと感じ、目頭が何というか・・・熱くなって、しきりと過ぎ去りし時代が思い出された。
第二部に登場する人びとは、政界、産業界、財界のトップに君臨したことがあるような有名人ばかり。
堤さんはセゾングループの創始者として、一世を風靡し、また文学活動をするという二足の草鞋を履いた人物。
ここでインタビューに答えている堤さんは「敗軍の将」なのである。
時代のうねりにのみこまれ、凋落していく。
最後には債権者たる銀行に、自宅までとられてしまったと語っている。
そういう男が、世の中には数多く存在する。「敗軍の将」というのは、昔は首を刎ねられたものだが、現在は大抵、老後を生きながらえることができる。
わたしの知人にも、ついこのあいだ、会社を倒産させて、苦境にあえいでいる人がいる。
堤清二という人物は、それを大規模にやり遂げ、頂点に立ったあと、時代の大いなるうねりに抗戦もむなしく没落していった。
時代の繁栄と衰退を、一心に体現したのが、この人であるだろう。
これまではほとんど関心はなかったが、このインタビューをきっかけに、わたしの大切なキーワードの一つに「堤清二(ペンネームは辻井喬)」が加わった。
この人と、その周辺を調べることによって、わたしはわたしが生きてきた時代が、どういったものであったか、追究できそうだ・・・という気分になっている。
政治家としては中曽根康弘または田中角栄、実業家では西武流通グループ、パルコなどを率いた堤清二、これらの人びとの仕事にわたしの半生もまた収斂されるのだろう。


























