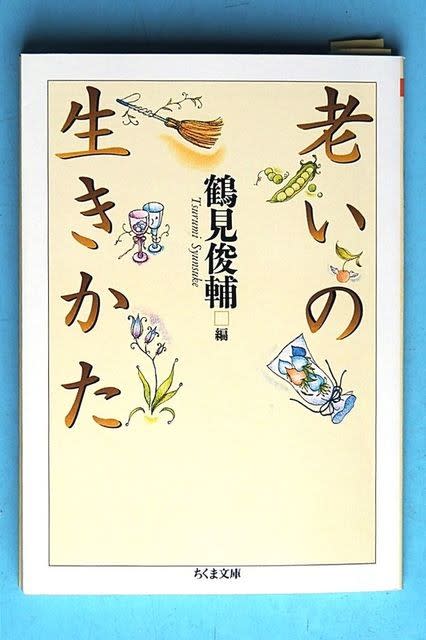
■「老いの生き方」鶴見俊輔編(ちくま文庫 1997年刊) 収録作品覚書をふくめ201ページ
新刊書店をぶらぶら散歩していて、ふと見つけた。たまに、こういうことがある。何かおもしろい本はないかなとアンテナを張り巡らしているから。
新刊なのに、定価560円と良心的な値がついている。2021年に再刊されたものだろう。
《この本は、老いについての文章をあつめた。どのように老い、どのように終るかは、人それぞれでちがうから、当然にこの本は老いについての相反した観察をふくんでいる。限られた時間のなかで、いかに充実した人生を過ごすか。来たるべき日にむけて、考えるヒントになるエッセイ集。》筑摩書房のホームページより引用
鶴見俊輔さんといえば「思想の科学」である。われわれ世代では、愛読者が周辺にそうとういた・・・という感じがする。わたしは読まなかったが。
鶴見さんはプラグマティズムの人・・・アメリカ流儀の合理主義者だと思っていた。そこからさきは、わたしはあまり考えずにやってきた(;^ω^)
べ兵連の小田実さんに近い存在。したがって行動力あり、と。
こういうアンソロジーを読んでみると、そんなに単純なものではなく、世界観は一気に遠くまで見通せるものではないようである。
まずJ・P・サルトルのことばからから引用させてもらおう。
《右眼の方は三つのときに事実上視力を失ってしまったので、この左眼が残る唯一の眼なんだ。それでいまでは物の形はまだおぼろげに見え、光や色も見えるのだけれど、物とか顔とかもうはっきりとは見えない。
したがってもう書くことも読むこともできないでいる。より正確に言えば、書くことはできる。つまり、手で言葉を形作ることはできるし、現在まあ適当なやり方で実際そうしているのだけれど、自分の書くものは見えない。
それに、本を読むことがまったくできない。行とか文字のあいだの空間は眼に入るが、文字それ自体を見わけることはもうできない。読み書きの能力を奪われてしまったわけで、こうなるともう作家として仕事に励むということがまったく不可能だ。作家としてのわたしの仕事は完全に終わりだね。》118ページ(引用者により改行あり)
《ある意味では、そのためにわたしの存在理由はまったく失われている。かつて存在したが、もう存在していない、と言ったらよいかな。だが、がっくりしてあたりまえなのだろうが、どういうわけか落ち着いていられる。失ったもののことを考えて悲嘆にくれたり、憂鬱になったりすることはまったくないな。》120ページ
「七十歳の自画像」と題されたこの談話は、「シチュアシオン X」に収められた長時間インタヴューの冒頭の一部だそうである。
吉本隆明さんのときにも思ったことだが、思想界や文学界に生きた人間が晩年というか、最晩年にみずからの「老い」について語るのは、まことに興味津々たるものがある。
サルトルは75歳、吉本隆明は89歳。
二人とも大きな仕事をたくさん残して、惜しまれつつ逝去した。
「かつて存在したが、もう存在していない、と言ったらよいかな。だが、がっくりしてあたりまえなのだろうが、どういうわけか落ち着いていられる。」と、サルトルは語る。
しかし、ボ―ヴォワールその他の支援者がいたから強気なことがいえたのであろう。
本書には鶴見俊輔はじめ、中勘助、鮎川信夫、富士正晴など19人のエッセイ・断片のような文章が収録されている。すべて「老い」について語ったエッセイである。
昔と違って人生百年時代の開幕・・・などとマスコミがこの現象を煽っている。
皆が皆、百年近く生きられるわけではない。
サルトルの75歳、吉本隆明の89歳は、時代背景を考慮すると、山田風太郎の「人間臨終図鑑」ではないが、“よく生きた”人物といっていいだろう。
ちなみにわたしは現在72歳になるが、72歳というと、
孔子、阿部仲麻呂、西行、沢庵、文学者では徳田秋声、佐藤春夫等が挙げられている。
もう一つ、鮎川信夫が斎藤茂吉について語ったエッセイを引用させていただく。
《茂吉の最晩期の歌は、すべてが自然で、順運のまま生涯の収束にむかって流れていっているようにみえる。
いつしかも日がしづみゆきうつせみのわれもおのづからきはまるらしも
強固な自我と個性による自然詠の果てに、自然そのものと化したのであり、とりもなおさずそれが茂吉の歌の本願だったのである。》64ページ
鮎川さんは茂吉最後の「つきかげ」から数篇選びだしている。
斎藤茂吉70歳。鮎川信夫66歳、といっても、本人にとっては関係ないこと。「おれは長生きしたぞ」と、自慢できるわけではないのだから。
いうまでもないことですが、老いたものには、こういうアンソロジーはなかなか読み応えがあるものです。
新刊書店をぶらぶら散歩していて、ふと見つけた。たまに、こういうことがある。何かおもしろい本はないかなとアンテナを張り巡らしているから。
新刊なのに、定価560円と良心的な値がついている。2021年に再刊されたものだろう。
《この本は、老いについての文章をあつめた。どのように老い、どのように終るかは、人それぞれでちがうから、当然にこの本は老いについての相反した観察をふくんでいる。限られた時間のなかで、いかに充実した人生を過ごすか。来たるべき日にむけて、考えるヒントになるエッセイ集。》筑摩書房のホームページより引用
鶴見俊輔さんといえば「思想の科学」である。われわれ世代では、愛読者が周辺にそうとういた・・・という感じがする。わたしは読まなかったが。
鶴見さんはプラグマティズムの人・・・アメリカ流儀の合理主義者だと思っていた。そこからさきは、わたしはあまり考えずにやってきた(;^ω^)
べ兵連の小田実さんに近い存在。したがって行動力あり、と。
こういうアンソロジーを読んでみると、そんなに単純なものではなく、世界観は一気に遠くまで見通せるものではないようである。
まずJ・P・サルトルのことばからから引用させてもらおう。
《右眼の方は三つのときに事実上視力を失ってしまったので、この左眼が残る唯一の眼なんだ。それでいまでは物の形はまだおぼろげに見え、光や色も見えるのだけれど、物とか顔とかもうはっきりとは見えない。
したがってもう書くことも読むこともできないでいる。より正確に言えば、書くことはできる。つまり、手で言葉を形作ることはできるし、現在まあ適当なやり方で実際そうしているのだけれど、自分の書くものは見えない。
それに、本を読むことがまったくできない。行とか文字のあいだの空間は眼に入るが、文字それ自体を見わけることはもうできない。読み書きの能力を奪われてしまったわけで、こうなるともう作家として仕事に励むということがまったく不可能だ。作家としてのわたしの仕事は完全に終わりだね。》118ページ(引用者により改行あり)
《ある意味では、そのためにわたしの存在理由はまったく失われている。かつて存在したが、もう存在していない、と言ったらよいかな。だが、がっくりしてあたりまえなのだろうが、どういうわけか落ち着いていられる。失ったもののことを考えて悲嘆にくれたり、憂鬱になったりすることはまったくないな。》120ページ
「七十歳の自画像」と題されたこの談話は、「シチュアシオン X」に収められた長時間インタヴューの冒頭の一部だそうである。
吉本隆明さんのときにも思ったことだが、思想界や文学界に生きた人間が晩年というか、最晩年にみずからの「老い」について語るのは、まことに興味津々たるものがある。
サルトルは75歳、吉本隆明は89歳。
二人とも大きな仕事をたくさん残して、惜しまれつつ逝去した。
「かつて存在したが、もう存在していない、と言ったらよいかな。だが、がっくりしてあたりまえなのだろうが、どういうわけか落ち着いていられる。」と、サルトルは語る。
しかし、ボ―ヴォワールその他の支援者がいたから強気なことがいえたのであろう。
本書には鶴見俊輔はじめ、中勘助、鮎川信夫、富士正晴など19人のエッセイ・断片のような文章が収録されている。すべて「老い」について語ったエッセイである。
昔と違って人生百年時代の開幕・・・などとマスコミがこの現象を煽っている。
皆が皆、百年近く生きられるわけではない。
サルトルの75歳、吉本隆明の89歳は、時代背景を考慮すると、山田風太郎の「人間臨終図鑑」ではないが、“よく生きた”人物といっていいだろう。
ちなみにわたしは現在72歳になるが、72歳というと、
孔子、阿部仲麻呂、西行、沢庵、文学者では徳田秋声、佐藤春夫等が挙げられている。
もう一つ、鮎川信夫が斎藤茂吉について語ったエッセイを引用させていただく。
《茂吉の最晩期の歌は、すべてが自然で、順運のまま生涯の収束にむかって流れていっているようにみえる。
いつしかも日がしづみゆきうつせみのわれもおのづからきはまるらしも
強固な自我と個性による自然詠の果てに、自然そのものと化したのであり、とりもなおさずそれが茂吉の歌の本願だったのである。》64ページ
鮎川さんは茂吉最後の「つきかげ」から数篇選びだしている。
斎藤茂吉70歳。鮎川信夫66歳、といっても、本人にとっては関係ないこと。「おれは長生きしたぞ」と、自慢できるわけではないのだから。
いうまでもないことですが、老いたものには、こういうアンソロジーはなかなか読み応えがあるものです。


























