
用事があったので、銀行へ。
西高東低の気圧配置だとかで、北風がびゅーと吹いている。
真っ青な空には、白い雲が、気持ちよさそうにぷかり、ぷかり。
銀行の駐車場はガラガラで用事はまたたくまに完了した(^_^)/~
ふと向こうを見ると、真ん丸な街灯に、豆粒のような人の影がある。
「ああ、おれだな」
そう思いながら腰にぶらさげてあるコンデジでパチリ(;´-`)
豆粒のように・・・と書いたけれど、一億数千万分の一の“わたし”は、
じっさいは豆粒より小さな存在だな。
気障ないい方に聞こえるかも知れないけれど、ナルシシズムで撮るのではなく、いわば「自己認識」の手段として撮る。
セルフポートレイトは昨今の流行になりつつある。デジカメの「自分撮り」機能が進化したからだろう。
過去の巨匠たちもセルフポートレイトを残している人が多いが、その中ではなんといっても、リー・フリードランダーの写真集にとどめをさす。
彼を知っているか、知らないかで、写真の品位が変わってくる・・・とわたしなどは考えている。
日本では荒木経惟さんが有名。私写真の大家といえば、まず荒木さんを連想するのは、わたしばかりではないだろう。品位には欠けるけれど、ラディカルさでは他を圧倒している。
ま、わたしは妻陽子さんを亡くしてからは、荒木さんからは離れてしまったな。しかし、また見たくなるときがくるだろう。写真集は12-3冊か、もっと書庫に置いてあるし...?^^);

mixiをはじめる前は、塩野七生さんの「ローマ人の物語」を、読んで過ごすことがよくあった。「パクス・ロマーナ」まではハードカバーで読み、さらに文庫本でも読んでいる。そのあたりで、読者として力尽きた。・・・というか、興味が他へ移ってしまい、昆虫写真などに夢中になったのだ。
それが「ローマ亡き後の地中海世界」で、塩野さんへの関心がもどった。
はじめ「終わりのはじまり」から文庫で読み返そうとおもっていたが、「すべての道はローマに通ず」に変更。文庫だと第27巻から、ということになる。
いましばらくは、塩野ワールドを遊覧する。
「海の都の物語」に、すっかり魅了されたため、塩野さんの未読本が、書棚にかなりふえている。
「すべての道はローマに通ず」は、ローマ人の物語の中にあって、異色の一冊。
ローマのインフラ整備について、かなり詳細に記述されてある。これによって、ある意味、わたしは土木工学に対する蒙をひらかれた、いまだ記憶も鮮やかな一冊だけれど、忘れてしまったところ、十分読み取れなかったところがたくさんある/_・)/_・)
二度読みどころか、三度読みすら必要かなあ。

これは中央公論社から刊行されている世界の歴史・第20巻「近代イスラームの挑戦」である。
著者は山内昌之さんで、執筆当時(1996年)東大の教授で、過去に一冊だけだが、その著作を読んだ覚えがある。
8. 「イスラーム世界の興隆」佐藤次高
11.「ビザンツとスラヴ」井上浩一、栗生澤猛夫
15.「オスマン帝国とイラン」永田雄三、羽田正
16.「ルネサンスと地中海」樺山紘一
20.「近代イスラームの挑戦」山内昌之
中公の新編世界の歴史は、全30巻の構成となっているが、塩野さんにインスパイアされ、いまのところ、こういった領域に好奇心が向かっている。
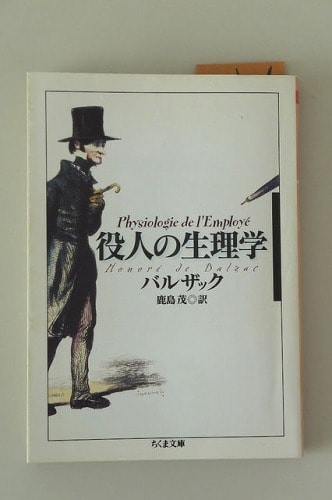
さらにおまけの一冊。
「役人の生理学」バルザック(ちくま文庫)。
これはBOOK OFFの108円の棚にあった。訳者の鹿島茂さんには、過去に非常にお世話になっている。(本を通じて)。
彼の編集にかかると、当時の挿絵を豊富に見ることができる。復元されたそれらの挿絵を眺めているだけでも心が浮き立ってくる*(^-^*)
ささいなきっかけで、一冊の本に、深く・・・ふかくのめり込む。
バルザックの真のおもしろさ、ひいては19世紀文学に深入りしたのは、なんといっても、鹿島茂さんの著作によるところが大きい。
写真と読書。
うっかりしていると、どちらか一方にシーソーが傾いてしまう。
豆粒よりも小さな“わたし”が、空いた時間を、本に使うか、撮影に使うか、悩んでいる。
※要点だけしるすつもりが、つい長~くなってしまった。ヒマだからかな(笑)。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
西高東低の気圧配置だとかで、北風がびゅーと吹いている。
真っ青な空には、白い雲が、気持ちよさそうにぷかり、ぷかり。
銀行の駐車場はガラガラで用事はまたたくまに完了した(^_^)/~
ふと向こうを見ると、真ん丸な街灯に、豆粒のような人の影がある。
「ああ、おれだな」
そう思いながら腰にぶらさげてあるコンデジでパチリ(;´-`)
豆粒のように・・・と書いたけれど、一億数千万分の一の“わたし”は、
じっさいは豆粒より小さな存在だな。
気障ないい方に聞こえるかも知れないけれど、ナルシシズムで撮るのではなく、いわば「自己認識」の手段として撮る。
セルフポートレイトは昨今の流行になりつつある。デジカメの「自分撮り」機能が進化したからだろう。
過去の巨匠たちもセルフポートレイトを残している人が多いが、その中ではなんといっても、リー・フリードランダーの写真集にとどめをさす。
彼を知っているか、知らないかで、写真の品位が変わってくる・・・とわたしなどは考えている。
日本では荒木経惟さんが有名。私写真の大家といえば、まず荒木さんを連想するのは、わたしばかりではないだろう。品位には欠けるけれど、ラディカルさでは他を圧倒している。
ま、わたしは妻陽子さんを亡くしてからは、荒木さんからは離れてしまったな。しかし、また見たくなるときがくるだろう。写真集は12-3冊か、もっと書庫に置いてあるし...?^^);

mixiをはじめる前は、塩野七生さんの「ローマ人の物語」を、読んで過ごすことがよくあった。「パクス・ロマーナ」まではハードカバーで読み、さらに文庫本でも読んでいる。そのあたりで、読者として力尽きた。・・・というか、興味が他へ移ってしまい、昆虫写真などに夢中になったのだ。
それが「ローマ亡き後の地中海世界」で、塩野さんへの関心がもどった。
はじめ「終わりのはじまり」から文庫で読み返そうとおもっていたが、「すべての道はローマに通ず」に変更。文庫だと第27巻から、ということになる。
いましばらくは、塩野ワールドを遊覧する。
「海の都の物語」に、すっかり魅了されたため、塩野さんの未読本が、書棚にかなりふえている。
「すべての道はローマに通ず」は、ローマ人の物語の中にあって、異色の一冊。
ローマのインフラ整備について、かなり詳細に記述されてある。これによって、ある意味、わたしは土木工学に対する蒙をひらかれた、いまだ記憶も鮮やかな一冊だけれど、忘れてしまったところ、十分読み取れなかったところがたくさんある/_・)/_・)
二度読みどころか、三度読みすら必要かなあ。

これは中央公論社から刊行されている世界の歴史・第20巻「近代イスラームの挑戦」である。
著者は山内昌之さんで、執筆当時(1996年)東大の教授で、過去に一冊だけだが、その著作を読んだ覚えがある。
8. 「イスラーム世界の興隆」佐藤次高
11.「ビザンツとスラヴ」井上浩一、栗生澤猛夫
15.「オスマン帝国とイラン」永田雄三、羽田正
16.「ルネサンスと地中海」樺山紘一
20.「近代イスラームの挑戦」山内昌之
中公の新編世界の歴史は、全30巻の構成となっているが、塩野さんにインスパイアされ、いまのところ、こういった領域に好奇心が向かっている。
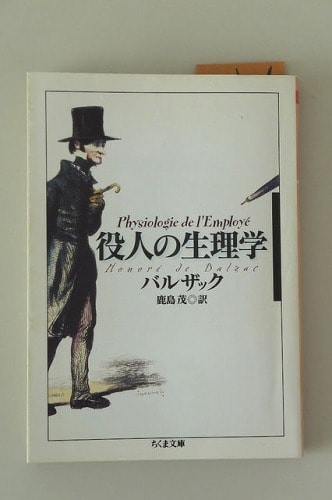
さらにおまけの一冊。
「役人の生理学」バルザック(ちくま文庫)。
これはBOOK OFFの108円の棚にあった。訳者の鹿島茂さんには、過去に非常にお世話になっている。(本を通じて)。
彼の編集にかかると、当時の挿絵を豊富に見ることができる。復元されたそれらの挿絵を眺めているだけでも心が浮き立ってくる*(^-^*)
ささいなきっかけで、一冊の本に、深く・・・ふかくのめり込む。
バルザックの真のおもしろさ、ひいては19世紀文学に深入りしたのは、なんといっても、鹿島茂さんの著作によるところが大きい。
写真と読書。
うっかりしていると、どちらか一方にシーソーが傾いてしまう。
豆粒よりも小さな“わたし”が、空いた時間を、本に使うか、撮影に使うか、悩んでいる。
※要点だけしるすつもりが、つい長~くなってしまった。ヒマだからかな(笑)。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。


























