
■高濱虚子「高濱虚子集」現代俳句の世界1 深川正一郎選(朝日文庫 昭和59年刊)
ほかの俳句の文庫本といっしょに、書棚からこぼれてきた。何気なく手にとって、澁澤龍彦の「物の世界にあそぶ」という序文を読みはじめたら、これにいささか圧倒された。
何だって?
高濱虚子に澁澤龍彦をぶつけただけで、不甲斐ないが「おっ♪」と唸ってしまった。
略年譜を齋藤愼爾さんが編集しておられるので、齋藤さんが仕掛けたのかも知れない。読みはじめたら、中身も凄かった。それほど売れたとは思われないが(^ε^)
澁澤さん、一番“のり”がよかった時代ではなかったか?
めちゃくちゃ西洋派の論客として評論をお書きになっている人物を、「客観写生」「花鳥諷詠」によって主導した「ホトトギス」の領袖にぶつける。そうして、結果として、それが成功を収めているのだ。
いままで正岡子規が偉大だと思い過ぎたため、高濱虚子の存在が目に入らなかった。読もうとかんがえれば、手許に本はいろいろあった。それがこの“朝日文庫”に及ばなかった、わたしにとっては。
解説じゃなく、序文として書かれているため、衝撃が大きくなる。3-4年前に100円かそこいらで、古本屋で買ってきた・・・のだと記憶している。
あるいは、中途半端な位置にとどまれず、わたし的にはど~んと遠くへ飛んで、自由律の種田山頭火、尾崎放哉になる。

(63歳の像。半眼のこの眼が凄みを持っている。本書のとびら)
《あくせくした近代主義から目を転ずるとき、物の世界に悠々とあそぶ虚子のマ二エリスティックな精神は、思いもかけぬ無限の可能性をもって見えてくるにちがいない。古いものは新しく、新しいものは古いのである。表現の世界では、そういうパラドックスがつねに起こっているのだということを料簡する必要があろう。》11ページ
短いエッセイである。あっさり書いているのも好感度UP(´Д`)
・石ころも露けきものの一つかな
・流れ行く大根の葉の早さかな
澁澤さんは、この2つで虚子の風韻を理解していた・・・といっている。
そこから、虚子の写生句の世界へと分け入っていくのである。
《虚子の世界はひろく、まことに茫洋としてつかみどころがないが、その一句一句の分かりやすく曖昧さのみじんもない点は、きわだった特徴をなしているといえる。》8ページ
それから虚子の奥深い世界へと入っていくのだが、わたしにとっては、これらが高濱虚子初体験といえるだろう( -ω-)
・鴨の中の一つの鴨を見てゐたり
・青き葉の火となりて行く焚火かな
・蝶々のもの食う音の静かさよ
・我汗の流るゝ音の聞こゆなり
・水打てば夏蝶そこに生れけり
・風花は黒板塀に生まれつゝ
・鬼灯はまことしやかに赤らみぬ
・タンポゝの黄が目に残り障子に黄
・白牡丹といえども紅ほのか
・襟巻の狐の顔は別に在り
・わだつみに物の命のくらげかな
・大寺を包みてわめく木の芽かな
こういった句から、澁澤さんはカントがいうような“物自体”を遥かに連想している。虚子の句は、ある意味、唐突で、暴力的なものを潜めているのだ。
「物の世界にあそぶ」という序文はわずか4ページ(文庫本で)。
切れ味がいいから、一句一句よせ反す大波のように、説得力が大きい。夜半に読んでいて、おもわず立ち上がりたくなった。
“暴く”とはいえ、もちろんスキャンダルの類ではない。
そうだ。食わず嫌いをやめ、高濱虚子をまるまる一冊読んでみようっと。
はたしてこれが、「客観写生」「花鳥諷詠」を主導した「ホトトギス」の句だろうか!
我慢して、二百句三百句から一句を掬い上げる努力が必要かも知れないけど、澁澤さんが入口の在りどころを、つまり虚子へと至る道をしめしている(;^ω^)タハハ
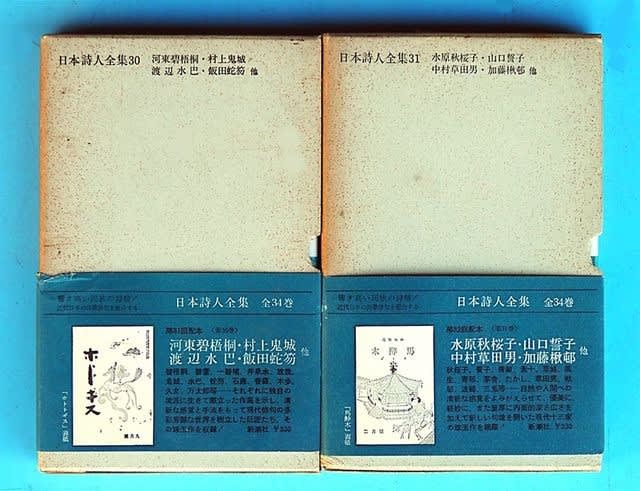
(新潮社の日本詩人全集31巻 水原秋櫻子、中村草田男、山口誓子、加藤楸邨などはこれでざっと読んだ気がするが)
ほかの俳句の文庫本といっしょに、書棚からこぼれてきた。何気なく手にとって、澁澤龍彦の「物の世界にあそぶ」という序文を読みはじめたら、これにいささか圧倒された。
何だって?
高濱虚子に澁澤龍彦をぶつけただけで、不甲斐ないが「おっ♪」と唸ってしまった。
略年譜を齋藤愼爾さんが編集しておられるので、齋藤さんが仕掛けたのかも知れない。読みはじめたら、中身も凄かった。それほど売れたとは思われないが(^ε^)
澁澤さん、一番“のり”がよかった時代ではなかったか?
めちゃくちゃ西洋派の論客として評論をお書きになっている人物を、「客観写生」「花鳥諷詠」によって主導した「ホトトギス」の領袖にぶつける。そうして、結果として、それが成功を収めているのだ。
いままで正岡子規が偉大だと思い過ぎたため、高濱虚子の存在が目に入らなかった。読もうとかんがえれば、手許に本はいろいろあった。それがこの“朝日文庫”に及ばなかった、わたしにとっては。
解説じゃなく、序文として書かれているため、衝撃が大きくなる。3-4年前に100円かそこいらで、古本屋で買ってきた・・・のだと記憶している。
あるいは、中途半端な位置にとどまれず、わたし的にはど~んと遠くへ飛んで、自由律の種田山頭火、尾崎放哉になる。

(63歳の像。半眼のこの眼が凄みを持っている。本書のとびら)
《あくせくした近代主義から目を転ずるとき、物の世界に悠々とあそぶ虚子のマ二エリスティックな精神は、思いもかけぬ無限の可能性をもって見えてくるにちがいない。古いものは新しく、新しいものは古いのである。表現の世界では、そういうパラドックスがつねに起こっているのだということを料簡する必要があろう。》11ページ
短いエッセイである。あっさり書いているのも好感度UP(´Д`)
・石ころも露けきものの一つかな
・流れ行く大根の葉の早さかな
澁澤さんは、この2つで虚子の風韻を理解していた・・・といっている。
そこから、虚子の写生句の世界へと分け入っていくのである。
《虚子の世界はひろく、まことに茫洋としてつかみどころがないが、その一句一句の分かりやすく曖昧さのみじんもない点は、きわだった特徴をなしているといえる。》8ページ
それから虚子の奥深い世界へと入っていくのだが、わたしにとっては、これらが高濱虚子初体験といえるだろう( -ω-)
・鴨の中の一つの鴨を見てゐたり
・青き葉の火となりて行く焚火かな
・蝶々のもの食う音の静かさよ
・我汗の流るゝ音の聞こゆなり
・水打てば夏蝶そこに生れけり
・風花は黒板塀に生まれつゝ
・鬼灯はまことしやかに赤らみぬ
・タンポゝの黄が目に残り障子に黄
・白牡丹といえども紅ほのか
・襟巻の狐の顔は別に在り
・わだつみに物の命のくらげかな
・大寺を包みてわめく木の芽かな
こういった句から、澁澤さんはカントがいうような“物自体”を遥かに連想している。虚子の句は、ある意味、唐突で、暴力的なものを潜めているのだ。
「物の世界にあそぶ」という序文はわずか4ページ(文庫本で)。
切れ味がいいから、一句一句よせ反す大波のように、説得力が大きい。夜半に読んでいて、おもわず立ち上がりたくなった。
“暴く”とはいえ、もちろんスキャンダルの類ではない。
そうだ。食わず嫌いをやめ、高濱虚子をまるまる一冊読んでみようっと。
はたしてこれが、「客観写生」「花鳥諷詠」を主導した「ホトトギス」の句だろうか!
我慢して、二百句三百句から一句を掬い上げる努力が必要かも知れないけど、澁澤さんが入口の在りどころを、つまり虚子へと至る道をしめしている(;^ω^)タハハ
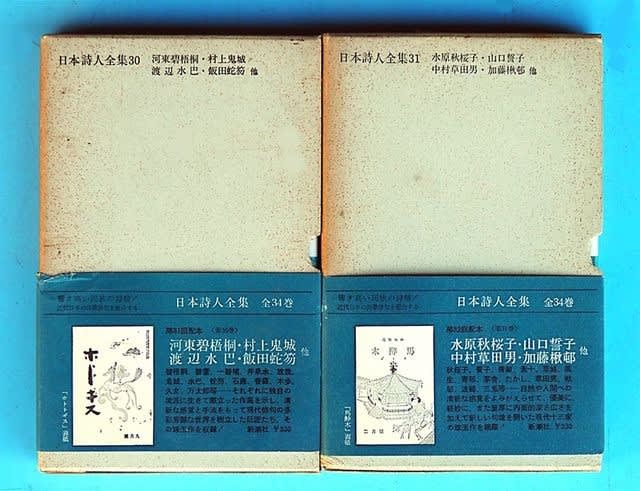
(新潮社の日本詩人全集31巻 水原秋櫻子、中村草田男、山口誓子、加藤楸邨などはこれでざっと読んだ気がするが)


























