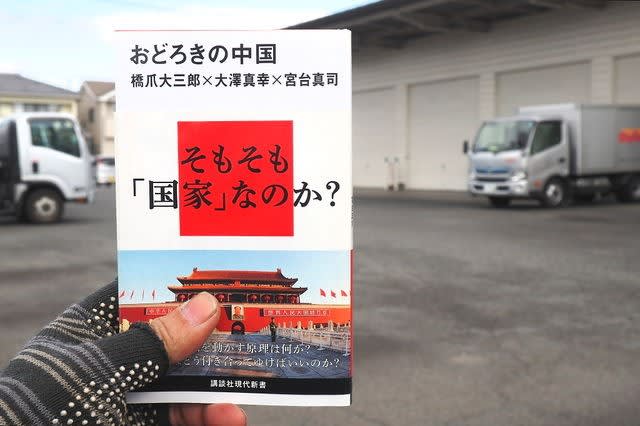
■「おどろきの中国」橋爪大三郎、大澤真幸、宮台真司(講談社現代新書 2013年刊)レビュー
すぐそこの超大国、中国をどう理解したらいいのか(・_・?)
これはたいへん大きな、大きな問題なので、こういうカテゴリーの中で、何かおもしろい本はないものだろうかと、何年も前から探していた。その「読みたかった本」にぶつかったのだ。
知的な興奮をたっぷりと味わうことができる。三人の現代日本を代表する社会学者が、白熱の論議を展開している。
橋爪さんと大澤さんのコンビでおやりになった本は「ふしぎなキリスト教」を最近読んだけど、それ以上の深みがある。奥様が中国人という橋爪大三郎さんを中心に、「中国ってどんな国?」という素朴な、だけどラディカル極まりない論点を、なかなか緻密に検討している。中国の“発祥”にまでさかのぼり、現代にいたるまでの射程がその視野にすっぽり収まっている。
対談、鼎談はどうしても肌理が粗くなるのはやむをえないが、本書「おどろきの中国」には、そういった欠点をカバーする知性の刺激と興奮がてんこ盛り(*゚。゚)
古代や唐・宋の中世中国は、これまで“歴史学” “中国史”のレベルではそれなりの知識があるが、近・現代史にはわたしは疎かった。
全体は以下の4部に分かれている。
第1部 中国とはそもそも何か
第2部 近代中国と毛沢東の謎
第3部 日中の歴史問題をどう考えるか
第4部 中国のいま・日本のこれから
あとがきをふくめ381ページ、途中でだれることなく、読み応え十分であった。
歴史学の本ではなく、社会学の本・・・というのが、本書をおもしろくしている。
しかも、この鼎談をおこなうにあたって、橋爪さんの奥様(張静華さん)をガイド役に、著者3人が、前もって現代の中国を旅しているというのだから徹底している(。・_・)
思い付きでものをいっているのではなく、準備万端ととのえたうえで、この鼎談がおこなわれたわけだ。
《橋爪: ・・・いまみたいなアメリカ一極体制が、あと十年か二十年。そのあとは、つっかえ棒がたくさんあるアメリカ覇権体制になると思う。中国は、覇権国家にならない。
大澤: なるほど、みんながアメリカを応援しますよ、となるわけですね。
橋爪: そうそう。で、これに乗って、アメリカを筆頭とするキリスト教文明圏側にくっついていくというのが、あるべき日本の基本戦略になる。》(本書338ページ)
《橋爪: まず、日本の選択いかんで、日米関係や日中関係がどうこうできると思わないほうがいいと思う。
どうしてかと言うと、中国は、日本よりアメリカを重視しているし、アメリカも、日本より中国を重視しているわけだから、日本のことは後から決まるんです。まず、アメリカが対中関係をどうするか。これが基本で、最初に決まる。それを日本は、適切に予測しなくちゃならない。予測にも、いくつかシナリオがあるでしょう、そのそれぞれに対して、日本がどう行動するかを考える、というのが順番ですね。》(本書340ページ)
社会学者らしい鋭利な洞察が、現実をきわどく抉っている。
むろん、反中、反米の立場からではなく、ニュートラルな立場に立って、日・米・中の国際関係の在りようを分析しているのだ。好き嫌いといった感情のうえに組み立てられた、反米の本、反中の本は腐るほどある。本書はそういった論考とは一線を画す視点から話し合われている。
豊富な知識と体験が、橋爪さんの意見をがっしりと支えているから、説得力がある。
「毛沢東をどう評価すべきか」という問題についても、わたしはようやく納得できる回答を得られた気分。
まさに目から鱗、思索の地平線から、隣国の巨大国家中国の姿が浮上する。中国が巨鯨なら、日本は水槽に入った金魚・・・かもしれない(^^ゞ
よくもまあ、ここまで踏み込んだ議論がなされたものだ。橋爪さんはまちがいなく“理解魔”(大岡信を評した谷川俊太郎のことば)である。
この人の理解のプロセスには、学ばねばならない柔軟な姿勢がある。
話はちょっと飛ぶようだが、本書を読んでいて非常に気になってきたのは、近ごろ喧しい沖縄における米軍基地返還問題。
本書の中でもいくらかふれられてはいるが、アメリカの沖縄における基地は台湾有事、朝鮮半島有事を睨んでいるのだ。
日本が必死になっている“尖閣諸島の帰属”問題など、両大国にとっては屁のようなもの。
台湾にせよ、朝鮮半島にせよ、現在の“コールド・ウォー”がいつ “ホット・ウォー”に変わるかわからない。
日米の防衛問題は、水面下では台湾有事・朝鮮半島有事を想定して協議が続けられている。
沖縄は、沖縄人がそう願っていることとは関係なく、大国間の国益問題に直結している。地政学上、沖縄の占める位置は、まことに重要なので、日本の意向などアメリカはかまってはいられないのである。沖縄が仮に日本から独立したとしても、その現実には変化はない。
すべては“日米安保条約” “日米地位協定”に基礎を置いているのだ。
第3部「日中の歴史問題をどう考えるか」、第4部「中国のいま・日本のこれから」を読みすすめながら、頭の中を、そういった思念(半分は空想の世界だが)が駆けめぐった。そういう意味で、本書にはまことにスリリングな地雷のようなものが埋め込まれている・・・とわたしは読んだ。
日米関係、日中関係に関心がある方には、とくにおすすめ。2013年の刊行だが、知的な情報レベルでは、まったく古びてはいない。
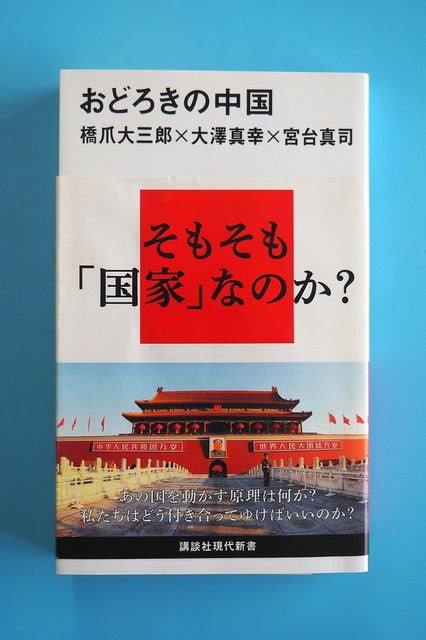
評価:☆☆☆☆☆
すぐそこの超大国、中国をどう理解したらいいのか(・_・?)
これはたいへん大きな、大きな問題なので、こういうカテゴリーの中で、何かおもしろい本はないものだろうかと、何年も前から探していた。その「読みたかった本」にぶつかったのだ。
知的な興奮をたっぷりと味わうことができる。三人の現代日本を代表する社会学者が、白熱の論議を展開している。
橋爪さんと大澤さんのコンビでおやりになった本は「ふしぎなキリスト教」を最近読んだけど、それ以上の深みがある。奥様が中国人という橋爪大三郎さんを中心に、「中国ってどんな国?」という素朴な、だけどラディカル極まりない論点を、なかなか緻密に検討している。中国の“発祥”にまでさかのぼり、現代にいたるまでの射程がその視野にすっぽり収まっている。
対談、鼎談はどうしても肌理が粗くなるのはやむをえないが、本書「おどろきの中国」には、そういった欠点をカバーする知性の刺激と興奮がてんこ盛り(*゚。゚)
古代や唐・宋の中世中国は、これまで“歴史学” “中国史”のレベルではそれなりの知識があるが、近・現代史にはわたしは疎かった。
全体は以下の4部に分かれている。
第1部 中国とはそもそも何か
第2部 近代中国と毛沢東の謎
第3部 日中の歴史問題をどう考えるか
第4部 中国のいま・日本のこれから
あとがきをふくめ381ページ、途中でだれることなく、読み応え十分であった。
歴史学の本ではなく、社会学の本・・・というのが、本書をおもしろくしている。
しかも、この鼎談をおこなうにあたって、橋爪さんの奥様(張静華さん)をガイド役に、著者3人が、前もって現代の中国を旅しているというのだから徹底している(。・_・)
思い付きでものをいっているのではなく、準備万端ととのえたうえで、この鼎談がおこなわれたわけだ。
《橋爪: ・・・いまみたいなアメリカ一極体制が、あと十年か二十年。そのあとは、つっかえ棒がたくさんあるアメリカ覇権体制になると思う。中国は、覇権国家にならない。
大澤: なるほど、みんながアメリカを応援しますよ、となるわけですね。
橋爪: そうそう。で、これに乗って、アメリカを筆頭とするキリスト教文明圏側にくっついていくというのが、あるべき日本の基本戦略になる。》(本書338ページ)
《橋爪: まず、日本の選択いかんで、日米関係や日中関係がどうこうできると思わないほうがいいと思う。
どうしてかと言うと、中国は、日本よりアメリカを重視しているし、アメリカも、日本より中国を重視しているわけだから、日本のことは後から決まるんです。まず、アメリカが対中関係をどうするか。これが基本で、最初に決まる。それを日本は、適切に予測しなくちゃならない。予測にも、いくつかシナリオがあるでしょう、そのそれぞれに対して、日本がどう行動するかを考える、というのが順番ですね。》(本書340ページ)
社会学者らしい鋭利な洞察が、現実をきわどく抉っている。
むろん、反中、反米の立場からではなく、ニュートラルな立場に立って、日・米・中の国際関係の在りようを分析しているのだ。好き嫌いといった感情のうえに組み立てられた、反米の本、反中の本は腐るほどある。本書はそういった論考とは一線を画す視点から話し合われている。
豊富な知識と体験が、橋爪さんの意見をがっしりと支えているから、説得力がある。
「毛沢東をどう評価すべきか」という問題についても、わたしはようやく納得できる回答を得られた気分。
まさに目から鱗、思索の地平線から、隣国の巨大国家中国の姿が浮上する。中国が巨鯨なら、日本は水槽に入った金魚・・・かもしれない(^^ゞ
よくもまあ、ここまで踏み込んだ議論がなされたものだ。橋爪さんはまちがいなく“理解魔”(大岡信を評した谷川俊太郎のことば)である。
この人の理解のプロセスには、学ばねばならない柔軟な姿勢がある。
話はちょっと飛ぶようだが、本書を読んでいて非常に気になってきたのは、近ごろ喧しい沖縄における米軍基地返還問題。
本書の中でもいくらかふれられてはいるが、アメリカの沖縄における基地は台湾有事、朝鮮半島有事を睨んでいるのだ。
日本が必死になっている“尖閣諸島の帰属”問題など、両大国にとっては屁のようなもの。
台湾にせよ、朝鮮半島にせよ、現在の“コールド・ウォー”がいつ “ホット・ウォー”に変わるかわからない。
日米の防衛問題は、水面下では台湾有事・朝鮮半島有事を想定して協議が続けられている。
沖縄は、沖縄人がそう願っていることとは関係なく、大国間の国益問題に直結している。地政学上、沖縄の占める位置は、まことに重要なので、日本の意向などアメリカはかまってはいられないのである。沖縄が仮に日本から独立したとしても、その現実には変化はない。
すべては“日米安保条約” “日米地位協定”に基礎を置いているのだ。
第3部「日中の歴史問題をどう考えるか」、第4部「中国のいま・日本のこれから」を読みすすめながら、頭の中を、そういった思念(半分は空想の世界だが)が駆けめぐった。そういう意味で、本書にはまことにスリリングな地雷のようなものが埋め込まれている・・・とわたしは読んだ。
日米関係、日中関係に関心がある方には、とくにおすすめ。2013年の刊行だが、知的な情報レベルでは、まったく古びてはいない。
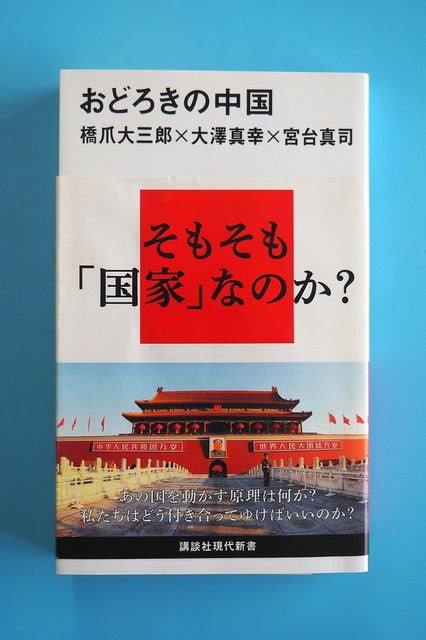
評価:☆☆☆☆☆



























