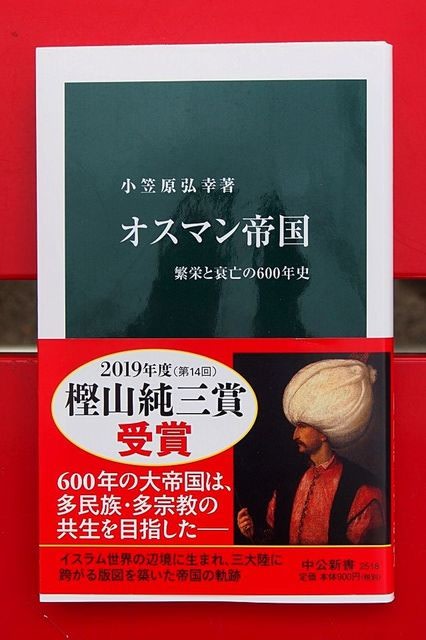
■小笠原弘幸「オスマン帝国 繁栄と興亡の600年史」中公新書(2018年刊)
600年もの歴史を、一息にたどっていく。そういう困難な課題に、真っ向から挑んだ著作。読む側も、心してかからなければならない・・・と思いつつ、ページをはぐっていった。
要はオスマン朝における、権力闘争の歴史である。
メインテーマをそこに絞り込み、初代のオスマン一世から、第三十六代のヴァヒディティンまで、すべてのスルタンについて、その生涯、主な事績を網羅。
内容については、いつものようにネット上のBOOKデータベースを掲げておこう。
《オスマン帝国は1299年頃、イスラム世界の辺境であるアナトリア北西部に誕生した。アジア・アフリカ・ヨーロッパの三大陸に跨がる広大な版図を築くまでに発展し、イスラムの盟主として君臨した帝国は、多民族・多宗教の共生を実現させ、1922年まで命脈を保った。王朝の黎明期から、玉座を巡る王子達の争い、ヨーロッパへの進撃、近代化の苦闘、そして滅亡へと至る600年を描き、空前の大帝国の内幕に迫る。》
権力闘争の歴史叙述と権力構造の分析に、ほとんどのページをついやしている。むろん、イスラムの国家なので、宗教問題は、権力闘争に直結する。しかし、宗教的にというより、政治的なかかわりに主眼がおかれている。
したがって本書を読んだからといって、イスラム教について理解が深まるわけではない(´・ω・)?
以前、鈴木董(ただし)先生の「オスマン帝国―イスラム世界の『柔かい専制』」(講談社現代新書 1992年刊)を読んでおもしろかったので、最新情報にふれるつもりで手に取った。
記述内容が、かなり偏っている。オスマン帝国が具体的にどんな文化をもつ帝国であったのか、その社会的な側面は、ほんのわずかふれられているだけ。
風俗・文化、民衆像といったものの分析・紹介には顧慮されていない。
そもそもすべての皇帝=スルタンについて、一日本人たるわたしが、知る必要があるのか?
著者とはそのあたりの意識にズレがある。鈴木董さんがいう「柔かい専制」について、小笠原弘幸さんの鋭利な分析が聞きたかった。
そういう意味で、やや期待はずれの一冊。戦争や権力抗争のシーソーゲームばかり読まされ、読みすすめるにしたがい、やや退屈になってきた。
三十六人のスルタンのすべての肖像画が引用されているのは、本書が“確信犯”であることを語っている。
旧オスマン帝国の外延にある中小の諸国は、民族自決の美名のもとに分割され、あちらでもこちらでも、紛争がひっきりなしにくり返されている。他国との戦争ばかりでなく、シリアに見られるような内戦もめずらしくはない。
オスマン帝国時代には、民族の融和、宗教上の寛容によって、のどかともいえる微妙な力のバランスが保たれ、人びとは平和を享受できていたのに(。-д-。)
政治史に偏ってはいるが、社会経済史、風俗・文化についてより詳しくしりたければ、ほかの本を読んでくれ・・・というスタンスだと、わたしには見えた。
評価:☆☆☆
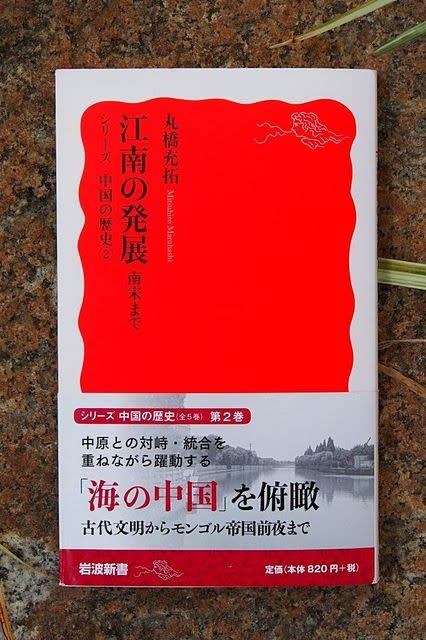
■丸橋充拓(みつひろ)「江南の発展 南宋まで」シリーズ中国の歴史2 岩波新書(2020年刊)
あとがきをふくめ、192ページ(参考文献一覧、略年表、索引等をあわせると210ページ)という薄い新書なので、2日ばかりで読み終えた。
集中して取り組めば、4~5時間で読み終えるだろう。
著者の丸橋さんは、島根大学学術研究院人文社会科学系教授である。
はじめに目次を掲げておく。
・いま、中国史をみつめなおすために(シリーズ中国の歴史の狙い 執筆者一同)
・はじめに
・第一章 「古典国制」の外延 ̶漢以前
・第二章 「古典国制」の継承 ̶六朝から隋唐へ
・第三章 江南経済の起動 ̶唐から宋へ
・第四章 海上帝国への道 ̶南宋
・第五章 「雅」と「俗」のあいだ
・おわりに ふたたび若者の学びのために
・あとがき
「いま、中国史をみつめなおすために」は本シリーズ「中国の歴史」全5巻に付された共通のまえがきとなる。だから“執筆者一同”となるわけである。
「雅」と「俗」というくくりの仕方がややわかりにくいのはこの丸橋先生の独特な語彙だからだが、読んでみると記述はいたって平明。
高校の世界史Bから、中国史へ入門しようとする学生を、読者として想定している。
《ユーラシアを見わたせば、中国は,北は遊牧世界,南は海域世界へと開かれている。第二巻は、長江流域に諸文化が展開する先秦から、モンゴルによる大統一を迎える南宋末までの長いスパンで「海の中国」を通観.中原と対峙・統合を重ねながら、この地域が経済・文化の中心として栄えゆく姿を、社会の重層性にも着目しつつダイナミックに描く。》(本書BOOKデータベースより)
第一章、 第二章は超特急にゆられているよう・・・景色があれよ、あれよと移っていく。
「第三章、江南経済の起動 ̶唐から宋へ」あたりから趣が変わり、落ち着いてきておもしろさがアップする。ここからがまさに本題、はじめは助走といっていいのだ。
中国は基本的には、「規制もするが、保護もする」日本とは違い、「規制もしないが、保護もしない」国家である。
それに対し、一般の庶民、国民は自分たちの生活の拠り所をどこに求めるかというと、それが「幇」という、横のつながりだという。中国という国家の成り立ちが、まことに明快に、一刀両断されている。
ここでいう「幇」(ほう=パン)とは、平たくいえば、友人・知人のこと。国家の組織がいわば縦方向の系列だとすれば、幇とは水平方向のネットワーク。
このあたりは、丸橋さんも章をまたぎ、いろいろな文脈のなかで、十分な説明を尽くしている( -ω-)
長くなるからこれ以上内容に立ち入ることはやめておくが、本書には中国理解のための重要な示唆がふくまれている。
たとえば「胡漢体制と僑漢体制」もはじめて聞く概念である。身を乗り出して耳をすまし、その意味するところを理解し、「ははあ、そうか!」と膝をたたく(^^♪
刊行が2020年、丸橋先生は、留学先の西安で本稿を書き上げたのだそうである。
国内における政治的な混乱・迷走がながらくつづいた中国では、ようやく1990年代にいたって、本格的に歴史研究が始動したのだ。
本書「江南の発展 南宋まで」には、最新の研究成果が盛り込まれている。好奇心旺盛な読者の期待に十分応えてくれるのはまちがいないが、しか~し、新書の形式がこういった論考ではいくらか裏目に出た。
手軽にサクサク読める半面、ボリューム不足なので、4点とさせていただこう。
評価:☆☆☆☆
600年もの歴史を、一息にたどっていく。そういう困難な課題に、真っ向から挑んだ著作。読む側も、心してかからなければならない・・・と思いつつ、ページをはぐっていった。
要はオスマン朝における、権力闘争の歴史である。
メインテーマをそこに絞り込み、初代のオスマン一世から、第三十六代のヴァヒディティンまで、すべてのスルタンについて、その生涯、主な事績を網羅。
内容については、いつものようにネット上のBOOKデータベースを掲げておこう。
《オスマン帝国は1299年頃、イスラム世界の辺境であるアナトリア北西部に誕生した。アジア・アフリカ・ヨーロッパの三大陸に跨がる広大な版図を築くまでに発展し、イスラムの盟主として君臨した帝国は、多民族・多宗教の共生を実現させ、1922年まで命脈を保った。王朝の黎明期から、玉座を巡る王子達の争い、ヨーロッパへの進撃、近代化の苦闘、そして滅亡へと至る600年を描き、空前の大帝国の内幕に迫る。》
権力闘争の歴史叙述と権力構造の分析に、ほとんどのページをついやしている。むろん、イスラムの国家なので、宗教問題は、権力闘争に直結する。しかし、宗教的にというより、政治的なかかわりに主眼がおかれている。
したがって本書を読んだからといって、イスラム教について理解が深まるわけではない(´・ω・)?
以前、鈴木董(ただし)先生の「オスマン帝国―イスラム世界の『柔かい専制』」(講談社現代新書 1992年刊)を読んでおもしろかったので、最新情報にふれるつもりで手に取った。
記述内容が、かなり偏っている。オスマン帝国が具体的にどんな文化をもつ帝国であったのか、その社会的な側面は、ほんのわずかふれられているだけ。
風俗・文化、民衆像といったものの分析・紹介には顧慮されていない。
そもそもすべての皇帝=スルタンについて、一日本人たるわたしが、知る必要があるのか?
著者とはそのあたりの意識にズレがある。鈴木董さんがいう「柔かい専制」について、小笠原弘幸さんの鋭利な分析が聞きたかった。
そういう意味で、やや期待はずれの一冊。戦争や権力抗争のシーソーゲームばかり読まされ、読みすすめるにしたがい、やや退屈になってきた。
三十六人のスルタンのすべての肖像画が引用されているのは、本書が“確信犯”であることを語っている。
旧オスマン帝国の外延にある中小の諸国は、民族自決の美名のもとに分割され、あちらでもこちらでも、紛争がひっきりなしにくり返されている。他国との戦争ばかりでなく、シリアに見られるような内戦もめずらしくはない。
オスマン帝国時代には、民族の融和、宗教上の寛容によって、のどかともいえる微妙な力のバランスが保たれ、人びとは平和を享受できていたのに(。-д-。)
政治史に偏ってはいるが、社会経済史、風俗・文化についてより詳しくしりたければ、ほかの本を読んでくれ・・・というスタンスだと、わたしには見えた。
評価:☆☆☆
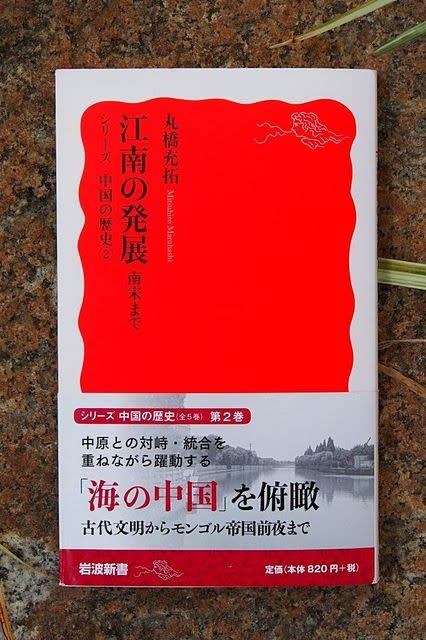
■丸橋充拓(みつひろ)「江南の発展 南宋まで」シリーズ中国の歴史2 岩波新書(2020年刊)
あとがきをふくめ、192ページ(参考文献一覧、略年表、索引等をあわせると210ページ)という薄い新書なので、2日ばかりで読み終えた。
集中して取り組めば、4~5時間で読み終えるだろう。
著者の丸橋さんは、島根大学学術研究院人文社会科学系教授である。
はじめに目次を掲げておく。
・いま、中国史をみつめなおすために(シリーズ中国の歴史の狙い 執筆者一同)
・はじめに
・第一章 「古典国制」の外延 ̶漢以前
・第二章 「古典国制」の継承 ̶六朝から隋唐へ
・第三章 江南経済の起動 ̶唐から宋へ
・第四章 海上帝国への道 ̶南宋
・第五章 「雅」と「俗」のあいだ
・おわりに ふたたび若者の学びのために
・あとがき
「いま、中国史をみつめなおすために」は本シリーズ「中国の歴史」全5巻に付された共通のまえがきとなる。だから“執筆者一同”となるわけである。
「雅」と「俗」というくくりの仕方がややわかりにくいのはこの丸橋先生の独特な語彙だからだが、読んでみると記述はいたって平明。
高校の世界史Bから、中国史へ入門しようとする学生を、読者として想定している。
《ユーラシアを見わたせば、中国は,北は遊牧世界,南は海域世界へと開かれている。第二巻は、長江流域に諸文化が展開する先秦から、モンゴルによる大統一を迎える南宋末までの長いスパンで「海の中国」を通観.中原と対峙・統合を重ねながら、この地域が経済・文化の中心として栄えゆく姿を、社会の重層性にも着目しつつダイナミックに描く。》(本書BOOKデータベースより)
第一章、 第二章は超特急にゆられているよう・・・景色があれよ、あれよと移っていく。
「第三章、江南経済の起動 ̶唐から宋へ」あたりから趣が変わり、落ち着いてきておもしろさがアップする。ここからがまさに本題、はじめは助走といっていいのだ。
中国は基本的には、「規制もするが、保護もする」日本とは違い、「規制もしないが、保護もしない」国家である。
それに対し、一般の庶民、国民は自分たちの生活の拠り所をどこに求めるかというと、それが「幇」という、横のつながりだという。中国という国家の成り立ちが、まことに明快に、一刀両断されている。
ここでいう「幇」(ほう=パン)とは、平たくいえば、友人・知人のこと。国家の組織がいわば縦方向の系列だとすれば、幇とは水平方向のネットワーク。
このあたりは、丸橋さんも章をまたぎ、いろいろな文脈のなかで、十分な説明を尽くしている( -ω-)
長くなるからこれ以上内容に立ち入ることはやめておくが、本書には中国理解のための重要な示唆がふくまれている。
たとえば「胡漢体制と僑漢体制」もはじめて聞く概念である。身を乗り出して耳をすまし、その意味するところを理解し、「ははあ、そうか!」と膝をたたく(^^♪
刊行が2020年、丸橋先生は、留学先の西安で本稿を書き上げたのだそうである。
国内における政治的な混乱・迷走がながらくつづいた中国では、ようやく1990年代にいたって、本格的に歴史研究が始動したのだ。
本書「江南の発展 南宋まで」には、最新の研究成果が盛り込まれている。好奇心旺盛な読者の期待に十分応えてくれるのはまちがいないが、しか~し、新書の形式がこういった論考ではいくらか裏目に出た。
手軽にサクサク読める半面、ボリューム不足なので、4点とさせていただこう。
評価:☆☆☆☆



























