コロナワクチン接種は、ようやくエンジンがかかってきたようで、私の周りにも
少なくとも1回目を終了した人が増えてきました。 6月6日のデータでは、高齢者
(65歳以上)の接種者は 21.8%ですが今後急速に増加するでしょう。
それでも、世界から見れば、日本はかなり遅れていて、人口割合で、カナダ61.6%、
イギリス59.4、アメリカ51.1、ドイツ45.1、イタリア43.1、フランス41.2に対して、
日本は何と10.24%と大きく水をあけられています。(NHK特設サイト6/8)
がんばれ、日本!

先に(12)をアップした時に写したカラのプランターには、今トマトができて
きています。花は、4段目まで来ました。 文末に様子を・・。
前座が長すぎましたが・・不思議な日本語(13)に移ります。
・一蓮托生 もともとは仏語「同じ蓮華に生まれる」の意で、「死後、ともに極楽
に住生して、同一の蓮華(同じ蓮の花)の上に身を託すること」から、「善くても
悪くても行動、運命をともにすること」の意味として用いられます。「一蓮」とは
「一つの蓮の花」を意味し、「託生」とは「身を他のものに任せて生きながらえる
こと」とあります。
つまり、 一蓮托生は、結果はどうであろうと、最後まで行動や運命をともにする
ことを表しています。 元々は「良い行いをした者同士」ということのようでした
が、その後「善悪に関係なく行動や運命をともにする仲間」という意味合いになっ
たそうです。
また、この言葉は江戸時代の心中ものにもよく使われたそうです。 封建時代の
社会の束縛にあって、この世で結ばれぬ恋人同士が、来世こそ添い遂げようと願う
ときなどに使われる言葉であったそうです。
「死なば諸共」も似た意味ですが、こちらは、どこか“やけっぱち”の感じです
ね。 また、「一心同体」というのも似ていますが、こちらは、複数の人が一致
団結して、心身ともに強いきずなで結ばれているようすを表現していて、言わば
「気が合う」「阿吽の呼吸」「調和のとれた関係」を意味しています。「一蓮托生」
には死んだら極楽で再開しようというより強い覚悟があるのですね。
 (ネット画像より)
(ネット画像より)
・さしあたり 意味は、『先のことはともかく、今のところ。今しばらくの間。
当面。』で、「差し当たり必要なものだけを買う」などといいますね。 「差し当
たり(さしあたり)」とは、「将来のことを深く考えずに、今のところは(今しばら
くの間は)」や「先で変わるかもしれないが、今現在に限って対応すること」を意
味している表現です。
似た言葉に「とりあえず」というのがありますが、こちらは、「十分な対応は後
回しにして暫定的な対処をすること」、「他のことをさしおいて、まず第一に対応
すること」で、緊急の場合に使われ、「差し当たり」は将来のことは考慮せずに現
在の一時的な対応をする場合に使われる点が異なります。
また、「当分」というのもありますが、こちらは、「将来のある時期までをばく
ぜんと表す言葉」で、時間的なことだけを言っているのですね。
しかし、同じような意味合いで使う場合もあったり、どちらもOKみたいな場面も
あり、ややこしいところもあるようです。
・ぶっきらぼう というのはどんな棒なんでしょうか。 ぶっ切った、つまり
乱暴に切った木の切れ端のことだそうで、ものの言い方や態度に、愛敬も飾り気も
ない様子を表す言葉なんですね。
「ぶっきり棒」から転じた語であるとありました。「ぶっきり」は「打(っ)切
(り)」で、乱暴に切るという意味で、「打(っ)」は勢いのいい様子を表す接頭
語です。 ぶっ壊す、ぶっ放す、ぶっ飛ばす などがあります。
「ぶつ」が変化して「ぶん」となる場合もあり、こちらでは、ぶん殴る、ぶん回
す・・など。
また、この「ぶっきらぼう」という語は、とくに無愛想な話し方についていうこ
とが多いですが、冷淡な態度が感じられるかどうかというニュアンスまでは含まれ
ないとありました。
・青二才 「青」というのは、未熟であるという意味であることは分かります。
「青春」とくれば、これは若い頃の夢や希望に満ちあふれている時代のことですね。
しかし、この二才というのは、いったい何なのでしょうか? まさか、二才の
子供ということではありません。
日本の古語で、「夫」のことを「背」といっていました。女性から親しい男性の
ことを背、背の君 というのですね。そして、青年のことを「新背(にいせ)」と
いっていたそうで、このことから読み方が変化して「にいせ」⇒「にさい」(二才)
となったとの説なんです。つまり、二才というのは、経験の浅い未熟なという意味
ですね。 この言葉の由来は、まだほかにもありましたがここでは省略しました。
青二才という慣用句は、自分を謙遜したり、相手を叱咤激励したりするときに使
われる言葉ですね。
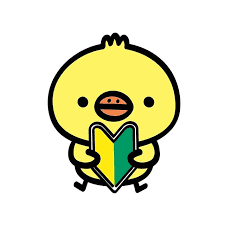 (ネット画像より)
(ネット画像より)
・いまだに goo国語辞書で「未だ」を引くと、いま‐だ【未だ】[副]とあり、
1 今になってもまだ実現していないさま。「未だはっきりしない事故原因」
2 以前のままであるさま。「周囲の山々は未だ冬の装いである」 とあり、否定
の場合も肯定の場合もあります。 で、この「未だ」から、その状態が続いている
さまを「いまだに」という言葉になったのではないかと思われます。
つまり、「未だに」は「今も~している(していない)」というような意味で使
う言葉だとあります。 で、ネットでの論調は、もっぱら「未だに」か「今だに」の
どちらが正しいのか、あるいはどのように使い分ければよいか? というものでした。
この文の流れから見れば、辞書的には「未だに」が正しいということになります
が、最近では「今だに」も結構使われているとありました。 日本語不思議辞典に
よれば、『一般的(世俗的)な使い方としては、肯定的な文章(現在もそれをして
いる)の場合は「今だに」、否定的な文章の場合(現在に至るまでそれが行われて
いない)は「未だに」という使い分けが多いようです。』とありました。

<おまけ> 不思議な日本語(12)の記事アップの時(4月28日)に、ネット
通販で購入したばかりの、プランター2個と用土の作業をした写真を載せましたが、
今回は、あれから1か月ちょっと経ちましたので、その状態をご覧いただこうと思
いました。
ま、どうってことありませんが、1か月とちょっとという時間は、結構な変化を
もたらすのだと・・。
植物の生長に改めてその変化を認識する・・なんて、大げさ!?


(6月8日)
トマト(大玉)をそれぞれの鉢に植えています。いま、花は4段まで来ました。
7段くらいで摘心しますから、もう少しです。このところ真夏のような日差しを浴
びてコロナの心配もなくスクスクと元気そうです。
CZARDAS. V. Monti. Dir.: Enrique G. Asensio. Percusión: Alfredo Anaya & Alberto Román. ConcertBand.

















