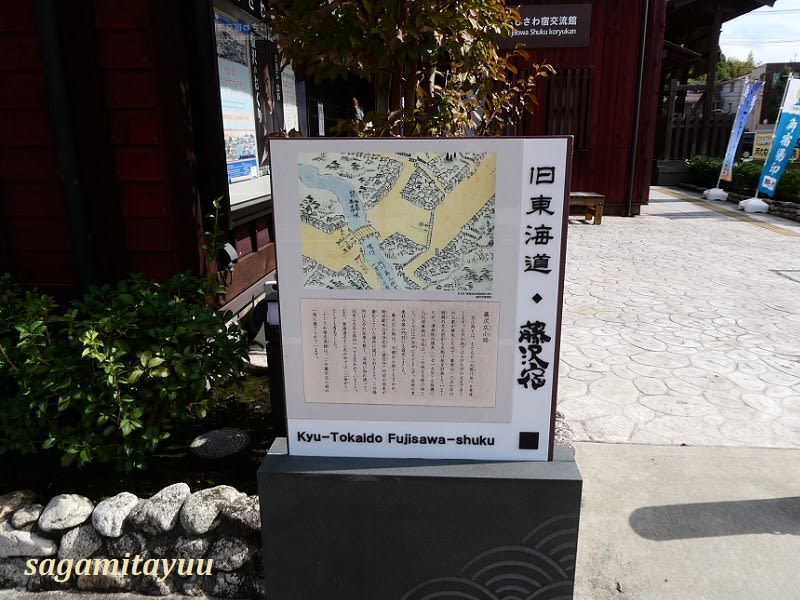相模原市南区大野台3丁目から南区相模台3丁目にかけて総延長5kmに亘って「相模原の道・橋・花ーさがみはら百選ー」の一つ「さがみの仲よし小道」が連なっている。嘗て造られた「相模原台地」に「畑かん水路」緑道となった「仲良し小道」で緑道沿いの随所に花壇が設けられ桜、ハナモモ、藤、アジサイ、ムクゲ、フヨウ、サルスベリなどが植栽され四季の花で彩られる。中間の花壇では生け垣や鉢植えとして栽培されるバラ科の常緑低木の「トキワサンザシ」が赤い実をたわわにつけている。「ピラカンサス」という名前でも呼ばれている。日本には明治時代に導入されたが、葉は濃緑色で光沢があり春には観賞価値が高い白い花が咲き、今の時期の秋には美しい果実がたわわに実る果実が美しい植物でもある。(2411)