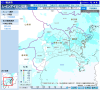この「日出五猿図」(野崎家塩業歴史館蔵)を見た時はびっくりした。縁起物の作品である。初日の出と御縁にかけた五猿という図で、現代ならばさしづめ年賀状の図案として重宝されるであろう。私などはあまりそれこそ縁のない図である。
しかし私がびっくりしたのは猿の描く円がほとんど真円に近くないか、ということと、太陽の円とこの猿の描く円に相似の枝ぶりである。コンパスで描いた円を下敷きにしているように思えた。
凝りに凝った配置である。ひょっとしたら5頭の猿も72度で分割されているのかとも思ったが、それは上部に猿が2頭くっついているのでそうではないことが理解できた。
ここまで細部と配置にこだわるということに私は惹かれる。細部にこだわり、構成にこだわるというのは、細密画の純化のようで、表現意識の喪失につながってしまう恐れがあるが、其一の作品は細密画で終わらない表現意識を感じる。
それは若冲などとも通底するこだわりのように思える。太陽以外は水墨画の技法なのだろうが、枝先にも深い緑色を自然と感ずる。

次の「花菖蒲に蛾図」(メトロポリタン美術館蔵)にも惹かれた。鮮明な色彩の作品が目立つ中、くすんだ色彩におやっと思った。そしてまず目につくのが開いた葉の間から二段に配した勝負の花。これも細かい精緻な描写によるリアリティーが目につくと同時に、細かな描写を避けたくすんだ緑色のグラデーションと濃淡による葉の表現の対比が、奥行きを醸し出していることに気がついた。細かく目を凝らすとくすんだ緑の葉にも色の濃い部分には黄色の葉脈も描いている。
葉と花のこのような描き分けが面白い。その次に私の家の団地でもときどき見かける「オオミズアオ」といわれる大型の蛾。この蛾は大柄だけあって、夜遅く帰宅した時に玄関の付近に止まっているとドキッとする。しかしよく観察するととても美しい羽根と姿態を持っている。なかなか愛すべき蛾である。中国では蛾は美しさの象徴でもあるようだが、日本では概して不当にも嫌われ役である。この蛾の描写は実に的確である。特徴のある触覚や薄緑色の羽根の特徴を描写している。
解説により気がついたが、夜行性の蛾と昼間咲いているらしい花菖蒲の取り合わせは、人工的な取り合わせである。あるいは満月に近い夜の様かと思ったりしたが、月の光だけではここまで蛾の色を鮮明に夜は見ることは出来ない。この奇妙な取り合わせが其一らしいのかもしれない。幻想の美、白昼の夢の世界の演出かもしれない。現実の世界にあるものを使って幻想の世界を描くという、ひょっとしたら現代に通じる技法と美意識なども連想してしまう。
図録を眺めていると後期展示の作品も見たくなる。また前・後期の作品を並べてみるのも面白い作品(藤花図など)もある。風神雷神図襖、夏秋渓流図屏風などの大作、追々取り上げたい。
これだけまとめて其一の作品を眺めることのできるいい機会であった。